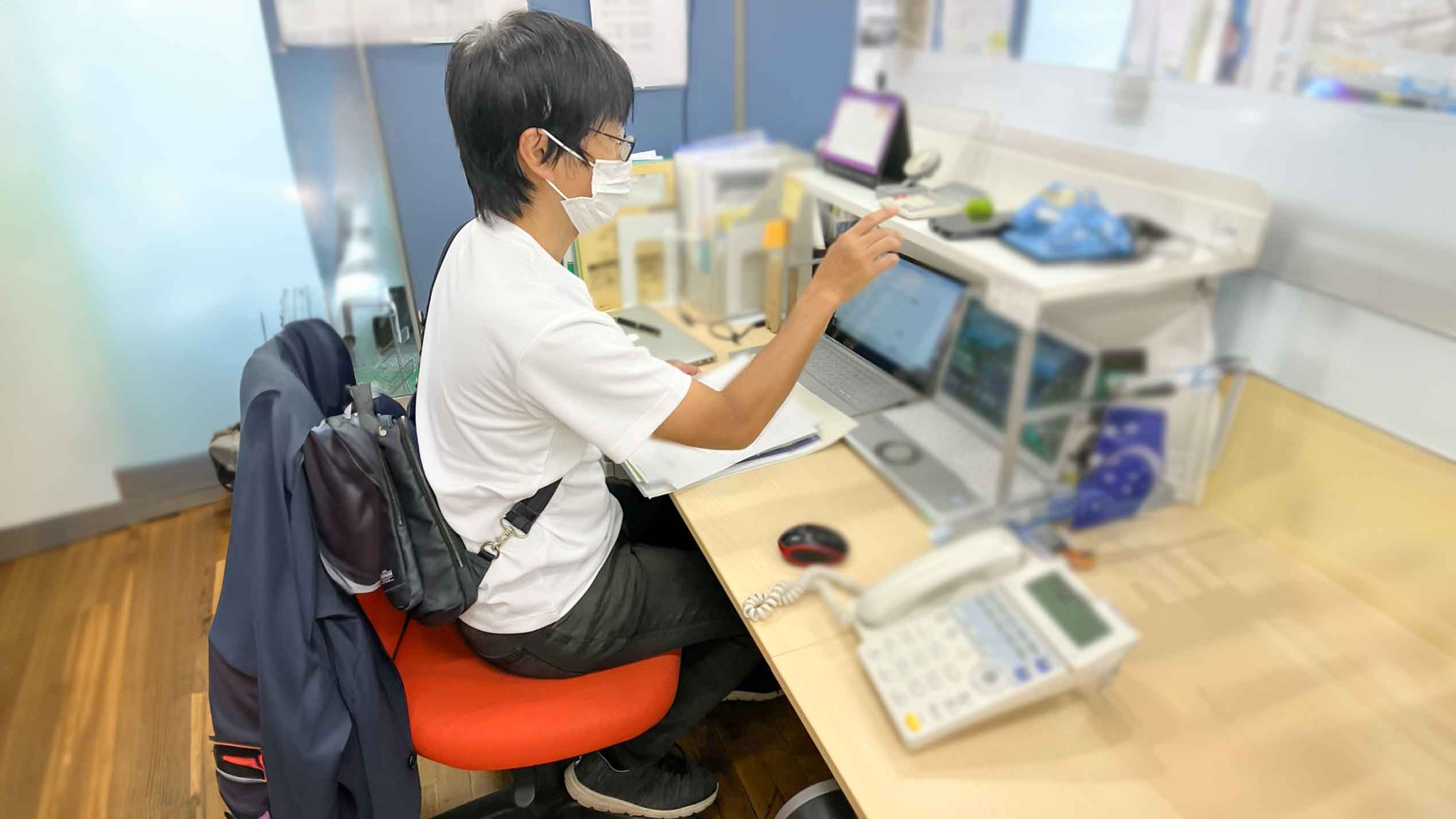―議員として活動していた中で、重松さんはどんな部分を大事にされてきたんでしょうか。
ただ誰かの代弁をするーーということはやめようとは思っていました。
国立には7万5000人ぐらいの人口がいる中で、議員として関われるのはたった20数人なんです。
その中で活動していくのに、他の人と同じことを言ったり、やるのは必要ないなと思って、独自に、かつ自分の信念や考えに沿ったところで、いろんな局面で動くことはかなり意識的にしていました。
―政策や、ご自身の信念として、具体的にどんなものを掲げていたんですか?
どうしても自分の関心に沿ったところになるんですけれども、環境政策と交通政策、
それから行政の仕組みをどう市民により近づけていくかーーという点が自分が進めていた政策や信念の中心にあったと思います。
基本、行政に関わることなので、ほぼ市民生活に関わること全てオールラウンドで判断も求められますし、幸い、私自身、いろんなことに関心を持ちやすい性格でした。
ちょうど2000年に介護保険制度が始まり、障害者自立支援法がより当事者の権利を尊重するものとして障害者総合支援法として改正され、施行されーーという時代を、
議員という行政と市民の中間の立場で伴走できたのは、今から考えるととても貴重な体験でした。
―その後、どんな思いで土屋に入社したのでしょうか?
「(議員を)このまま続けていくのはよくないな」と思って辞めたんですが、「じゃあ、辞めて何をするの?」とは周りからもよく聞かれたんです。
でも自分の中に“辞めて、別の何かをする”っていう明確な何かがあったわけではなくてーー。
“辞める”と決意したら、その日から次の再就職の活動をすればいいものを、その踏ん切りもなかなかつかず、結局、任期いっぱいまでは頭の切り替えもできずに、議員としての任期が過ぎてしまって。
そこからハローワークに行ったり、就職の情報誌を見始めて、ようやく「自分にできることってなんだろう」っていう問いを突きつけられました。
何社か、採用試験を受けたところは落ちたんですよ。
「これができます」「○○が得意です」というわかりやすい経歴のない50歳過ぎの(元議員という)「面倒臭そうな奴を採用したくない」という企業側の思惑もわかります。
その中で、介護職はずっと念頭にあったんですがーーそもそも介護の技術以前に、自分の生活もきちんとできているとは思えない。
そんな自分に「本当に介護ができるのか?」「人の生活に責任が持てるのか?」という問いもありました。
さまざまな問いや思いの中には、学生の頃、大学に入ったばかりでせっかく声をかけてもらったのに、
議員の仕事を全うすることもできずにフェードアウトしてしまったーーそんな後ろめたさも、今もあります。
ただ、結果的に、国立の街で介護の仕事をしている方や障害を持つ方が身近にいらしたので、その方々から声をかけてもらって。
他の施設や介護職にも関わってみた上で、土屋の代表である高浜敏之さんとは以前から知り合いだったということもあって、土屋に入社をしました。
―プランナーズで働き始める前には、「高齢者複合施設のがわ」にも関わられていたそうですね。
そうですね。「11月からの土屋第5期が始まるまでの間、グループホームのがわで受け入れてもらおう」という話をしてくださって、
たった4か月間なんですが、1階の「コミュニティホームのがわ」と、2階の「グループホームのがわ」と両方で介護現場を体験させていただくことができました。
夜勤や入浴介助といったところはベテランのスタッフにお任せして関われないままではあったんですがーー。
介護の仕事も初めてでしたし、正直、「何もできない自分は足手まといなんじゃないか」とは思ってたんですが、私が勤務していた間にコロナのクラスターが発生したり、
スタッフの人的余裕があまりない中では、こんな私でも他のスタッフの方も喜んでくださったんですよね。