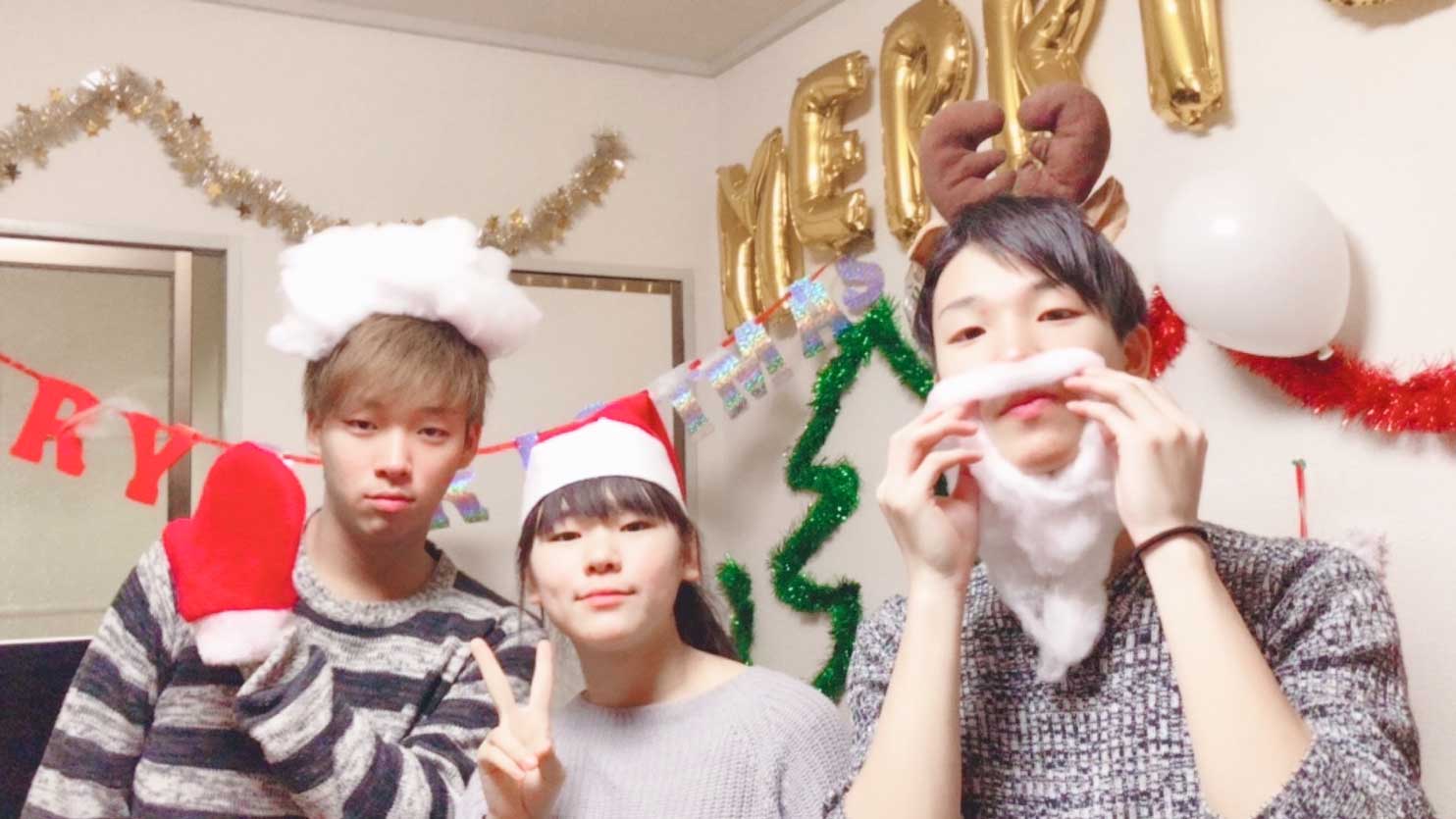―人と関わる時に辻さんが大切にされていることを教えてください。
そうですね。
「自分の価値観を人に押し付けない」っていうことは思ってます。
ものさしを自分でつくったら、そこから何も広がらないなっていうのを勉強したので。
あとは、男であっても女であっても、年も国籍も関係なくーーっていう感覚を常に持ってますね。
―「ものさしを持たない」というのはどんなご経験から?
アテンダントの方とのやり取りから学んだことは大きかったですね。
「自分はこういうふうに思っていて、こうしてほしい」っていうことをアテンダントに伝える時に、以前は「こうあるべきだ」「普通はこうやろ」と思ってたところが私にはありました。
そんな中で、自分が考えていたことを、相手は全くそんなふうに思ってなかったことがあったりーー相手によって受け取り方がそれぞれ違うことに気づいたんですよね。
そういう経験を重ねていった時、「『普通はこうだ』っていう言葉を持つこと自体を、絶対にやめよう」と思うようになって。
「話を聴く側がそういう姿勢でいないと、人の心の扉をひらくことなんてできへんねんな」って思いました。
それはクライアントさんも一緒ですね。
―今のお話とも重なると思うんですが、これまで介護の仕事を長く続けられてきた中でご自身が変わってきた部分はありますか。
初めて働いた施設でも学んだことはたくさんありました。
もちろん施設なので、毎日、同じ流れで進めていかないといけないところもある。
そこは「そういうものなんだな」って。
でも重訪と出会ってからは「介護の中でももっと個別性の高いサービスができる仕事もあるんだ」ということを知りました。
重訪を始めて最初に支援に入ったのが、気管切開をされていた方だったんです。
正直なところ、それまで気管切開をされている方を見たこともなかったし、「大丈夫かな」「怖いな」「何かあったらどうしよう」という思いが先立っていたんです。
重訪の支援時間って1回の支援が10時間と、長いんですよね。
そのクライアントの方はたくさんお話をされる方やったので、いろんなお話をしました。
「なぜ障害を持ったか」という話や、その人の人生とか、背景の話までがっつり伺ったんです。
そういうやり取りが、“見守り”と呼ばれて、重訪のサービス内容として明記されている。
いろいろな方のご自宅に伺ったんですが、「私自身がこんなに人に興味を持って、支援させてもらってる」っていうこと自体が初めてで、結構衝撃的でした。
そこが多分、自分自身が変わっていったところなんだろうな、と思います。
なんか、その人に興味持っちゃうんですね、すぐ。
「どういうふうなことがあって、今ここにいるんやろう」って。
もちろん喋りたくない方もいらっしゃるので、そういう方には伺うことはしませんでしたが、心を許してくださってる方には普通にーー障害を持ってるとか持ってないとか関係なく、無邪気に私の方からいろんなことを聞いてたんじゃないかな、と思います。
今思うと、失礼にあたっていたこともあったかもしれないですが。
―施設で働いていた時とはまた違うご自身が見えてきたんですね。
そうですね。
正直なところ、そこまで人への興味も湧かなかったし、やるべきことがたくさんあって、そんな時間もなかったんですよね。
でも、重訪でこんな長いこと同じひとりの人と関わってると、相手のクライアントさんも私に興味を持ってくださる。
それがいいか悪いかは別として、深く関わるようにはなりましたね。