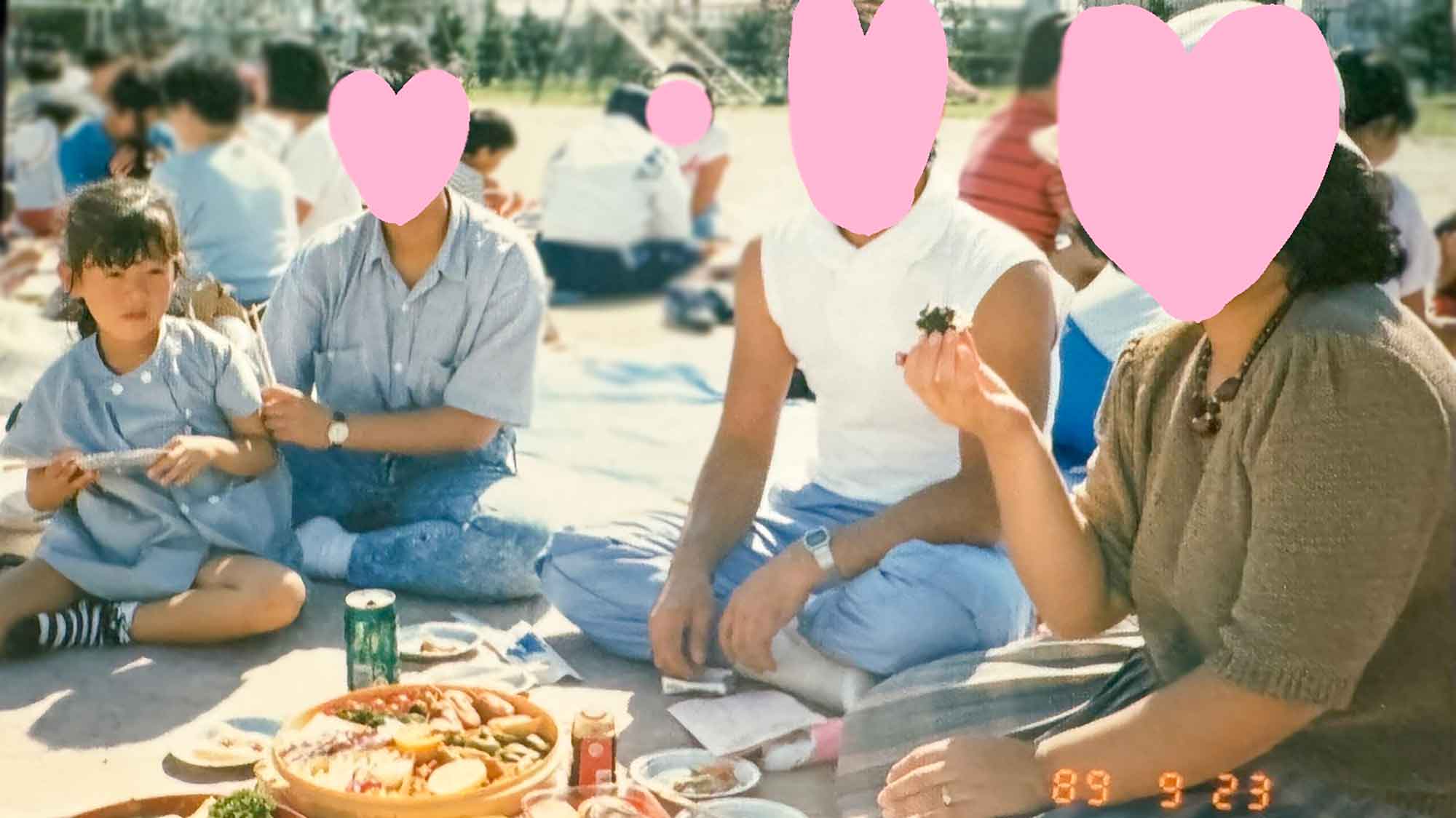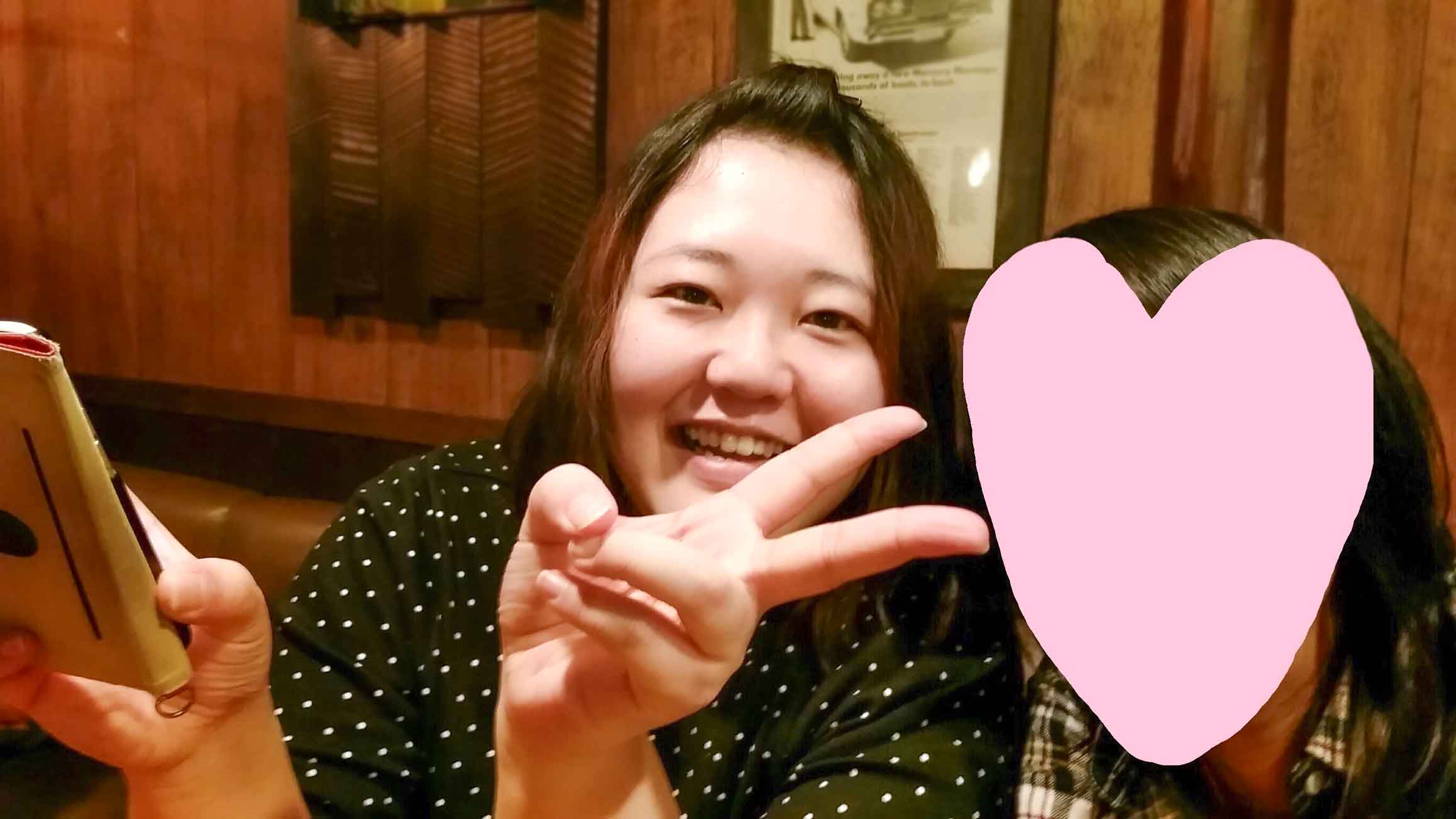―その後は、どんなふうに進まれてきたんでしょうか。
高校を卒業する時に就職をしようと思っていて、学校見学の案内がいっぱいある中で医療事務の仕事に惹かれたんです。
パソコンを使いながら、事務の仕事をすることに憧れを持っていて、医療事務の専門学校に1年だけ通いました。
その学校は珍しく1年制だったんですよ。
1年で資格を取って卒業したんです。
―そこから実際に医療事務のお仕事に就かれたんですか?
それが1回も就かなくて(笑)。
就活をしていたんですが、私の世代では、医療事務職への就職ってものすごく人気で、なかなか採用してくれる会社がなかった。
半年ぐらい頑張ったんですが、決まらなくて結局就きませんでした。
学校を卒業したのが20歳。
その頃、自分では福祉の仕事は全然頭になくてーーただ高校の先生から「福祉の仕事が合ってると思う」って言われたんです。
でも当時の私は「介護は嫌だな、医療事務をやりたい」みたいに返して(笑)。
思い出すのは、私が高校の頃、いとこが白血病で入院をして闘病生活をしていました。
お見舞いに行って、私は彼女の身のまわりのお世話をしていたんですね。
その時にも「福祉とか医療の仕事に就いた方がいいよ」と、いとこから言われたことがずっと頭に残っていてーー。
就活をはじめて、うまくいかなくて、「何をしよう」って思った時に、ふとそのいとこの言葉が頭の中に浮かんできたんですよね。
それで「福祉の資格を取ってみよう」って。
まず学校に行って、ヘルパーの資格(現在の介護職員初任者研修)を取得して、そこからデイサービスで働き始めたのが、福祉の初めての仕事でした。
―実際に働き始めてからはいかがでしたか?
私の父も母も、8人とか、9人兄弟だったんです。
ふたりとも、兄弟の中でも下の方だったので、親戚がご年配の方ばかりで。
小さい頃から年配の方とはよく関わっていたので、すんなり馴染めました(笑)。
ヘルパーの資格を取る時の実習では特別養護老人ホームといった施設系やデイサービス、それから障害福祉、訪問介護も含め、さまざまな事業所を回って研修をしました。
その中でもデイサービスに行った時にーー「楽しいかも」って思ったんです。
利用者の方と喋りながら、コミュニケーションを取りながら仕事をして、一緒に笑ったりするやり取りが「私に合ってるかも」って。
違和感を全然感じなかったんですよね。
―最初に働かれたデイサービスは、長く勤められていたとお聞きしています。その中で印象に残っている入居者の方とのやり取りがあったら教えてください。
認知症の方で、私の名前だけ覚えてくださった方がいました。
新しい記憶を残すのがなかなか難しい中で、毎回、お迎えに行くと私の顔を見て、私の名前をしっかり呼んでくれた方がいたんです。
その方は家に帰ってからも私の話をしてくださったり。
それが嬉しかったですね。
会う度に「誰?」となる利用者の方が多い中で、その方は私を下の名前で呼んで可愛がってくれて。
その方はすーごく印象に残ってます、今でも。
それから、デイサービスは日中はレクリエーション(レク)がメインになってくるんです。
そのレクを私が担当した時に、「あなたがやってくれると楽しいわ」「盛り上げてくれるから、通うのが楽しい」って言ってくださる方がいたり。
そういう言葉を聞くと、「考えてやってよかったなー」って思ってやっていましたね。
利用者の中には、外に出ることに億劫になっている方も多かったので、デイサービスに来て楽しんでくれる時間をつくれたら、それがいちばんいいな、と思っていたので。
実際にみなさんから「楽しい」っていう言葉を言っていただけたのは嬉しかったですね。