《interview 2025.02.03》
定期巡回サービス土屋で関西・東海エリアマネージャーとして働く長谷川伸(はせがわしん)。
福祉を学んだのち、高齢者福祉をメインに介護業界に携わってきた長谷川は2023年、土屋に入社し、定期巡回事業と出会いました。
そこで気づいた、クライアントの“できないこと”から“できること”へ、という視点の転換――定期巡回事業への深い想いと、パイオニアのひとりとして対話をかさねて進む長谷川の今を訪ねます。
定期巡回サービス
関西 東海エリアマネージャー
ひとりでは仕事はできない。同僚、他業種、社会へと広がる「よく見て褒める輪」の大きな可能性。
定期巡回サービス
関西 東海エリアマネージャー
ひとりでは仕事はできない。同僚、他業種、社会へと広がる「よく見て褒める輪」の大きな可能性。
定期巡回サービス土屋で関西・東海エリアマネージャーとして働く長谷川伸(はせがわしん)。
福祉を学んだのち、高齢者福祉をメインに介護業界に携わってきた長谷川は2023年、土屋に入社し、定期巡回事業と出会いました。
そこで気づいた、クライアントの“できないこと”から“できること”へ、という視点の転換――定期巡回事業への深い想いと、パイオニアのひとりとして対話をかさねて進む長谷川の今を訪ねます。
CHAPTER1
「変わり者」と言われた子どもの頃――今も自分が決めたことを突き進んでます。
―ご出身からお聞きしたいんですが――長谷川さんは五島列島のお生まれなんですね。
はい、長崎県五島列島の福江島で生まれました。
―福江島はどんなところなんですか?
私自身は福江の中でも比較的中心のところで生まれ育ちました。
福江島は、隠れキリシタンの教会があったり、自然も豊かなところです。魚釣りですごく有名な土地でもあるので、海の幸も美味しいものが多いですし、五島牛というブランド牛もあります。
五島から福岡に出てきた時に初めて、「食べ物には恵まれてたんだな」ということを感じましたね。
―自然が豊かな中でどんなことして遊ばれていたんですか。
それこそ魚釣りだったり、海で泳いだり。
中学、高校の時はバレーボールをやっていたんですが、部活が終わるとみんなでそのまま海に行って、部活着のまま海に飛び込むこともよくしてましたね(笑)。
―その頃はどんなお子さんでしたか?
そうですね……よく「変わった子だった」と言われてました。
これは後から聞いたエピソードなんですが――親戚の結婚式があって、家族みんなで式に参加するために長崎市に行ったんです。
みんなでホテルに泊まったんですが、夜になって大人はお酒を飲みに外に出て、姉は市内にいる友達に会いに行ってしまって、私はホテルにひとり残されたんです。
そのホテルは鍵がオートロックで――当時、五島ではホテルなんて泊まったことがないので、やり方がわからず、部屋から出たら入れなくなってしまったんですよね。
当時、小学校低学年ぐらいだったと思うんですが、その年齢の子どもであれば、泣いたり、ホテルの人に助けを求めるとは思うんですが、
私の場合、早々と諦めたみたいで――ホテルのロビーにあったマッサージチェアに座って、マッサージを受けながらみんなが戻ってくるのを待っていたらしいです(笑)。
親たちが帰ってきた時にふてぶてしい態度で座っていたらしく、「あいつは変わり者だ」みたいなことをよく言われましたね。
―(笑)。そこは今も変わらないようなところはありますか。
そうですね。自分が決めたことを突き進んでるようなところは今もありますね。

CHAPTER2
「何もできなかった」という思いを、仕事へ――福祉を仕事にする
―福江島にはいつまでいらしたんですか?
高校までですね。
社会福祉士を希望していたので、卒業してからはソーシャルワーク科のある福岡の専門学校に行きました。
―長谷川さんは、「福祉を仕事にする」ことは早いうちから決められていたんでしょうか。
そうですね。福祉に行こうと思ったきっかけが――高校1年生の時に祖父が亡くなったんです。
その時に何もできなかったな、という思いが強くて。その頃から「福祉系の学校に行きたいな」とは考えていました。
それと、時代の流れで介護保険制度ができる時期で、先輩も含め、医療系や介護系を目指す方が多かったのも背景にあるかな、と思います。
―おじいさまはどんな方だったんですか。
もともとは家も近く、小さい時はよく会いに行って、お小遣いをもらったり(笑)。
やさしい祖父でしたね。祖父は人格者で、誰に対してもやさしいし、誰に対しても分け隔てなく接する人でした。
字も綺麗で、本もたくさん読んでいて――そんな祖父だったので、私の父、母もそうですし、親戚も含めて、家族全員からすごく好かれてたんですよね。
私が高校生になった時に祖父が急に体調が悪くなって、家で介護する間もなく、すぐに入院しました。
当時の私は自分のことを優先していて、入院中の祖父にそんなに会いに行けなかったんです。高校生なのであたりまえといえばあたりまえなんですが。
「いよいよだ」と聞いて、慌てて病院にお見舞いに行って――当時はそんな思いでいましたね。
―その後、福祉を学んでからはどんな仕事に就かれたんですか?
卒業後は介護老人保健施設(老健)のデイケアに最初配属をされました。
その後、特別養護老人ホームに移って、デイサービスの相談員として働いていました。学校で社会福祉士を目指していたこともあって、相談員の仕事には興味がありましたね。
その後もほぼ高齢者介護の仕事がメインです。すべて「やりたい」と思って就いた仕事で――もちろん、辞めたくなった時期もあるんですけどね(笑)。
―これまで介護の仕事をされてきた中で、印象に残ってる利用者さんやターニングポイントになった出来事がありましたら教えてください。
就職してまだ1、2年の、デイケアで働いてる頃に出会った方なんですが……
相談員業務を始めて間もなかった頃ですが、ある日、体験利用の方がいらっしゃいました。その方はすごく寡黙な方だったんですね。
デイケアに来ること自体も初めてだったので、すこし警戒もされていたと思います。そんな状況で、私も「1日この人を楽しませなきゃな」と思いながら、いろいろと関わって、その日が終わって――次の日に「いかがですか」という連絡をしたら、実はデイサービスから帰ってきた後に急変してしまっててその日にお亡くなりになっていたんです。
それを聞いた時に、後悔というか、すごく考えることがありました。
自分の中では、「今度来た時に」と思っていたのが、「本当は、今日1日で全部を出さなきゃいけなかったんだな」って――「明日はどうなるかわからない」という感覚を当時はまだ持ってなかったんです。
その時に、高齢者介護に限らず、介護の仕事をする上では、「会ったその瞬間に、自分が持ってるものを出さないと自分が後悔するんだ」「そうじゃないと相手に失礼なんだ」ということを痛感したんです。
それから意識を変えて、「今、会ってるこの時間で自分は何ができるか」を考えるようになりました。その考え方の転換は、仕事の上では大きかったですね。
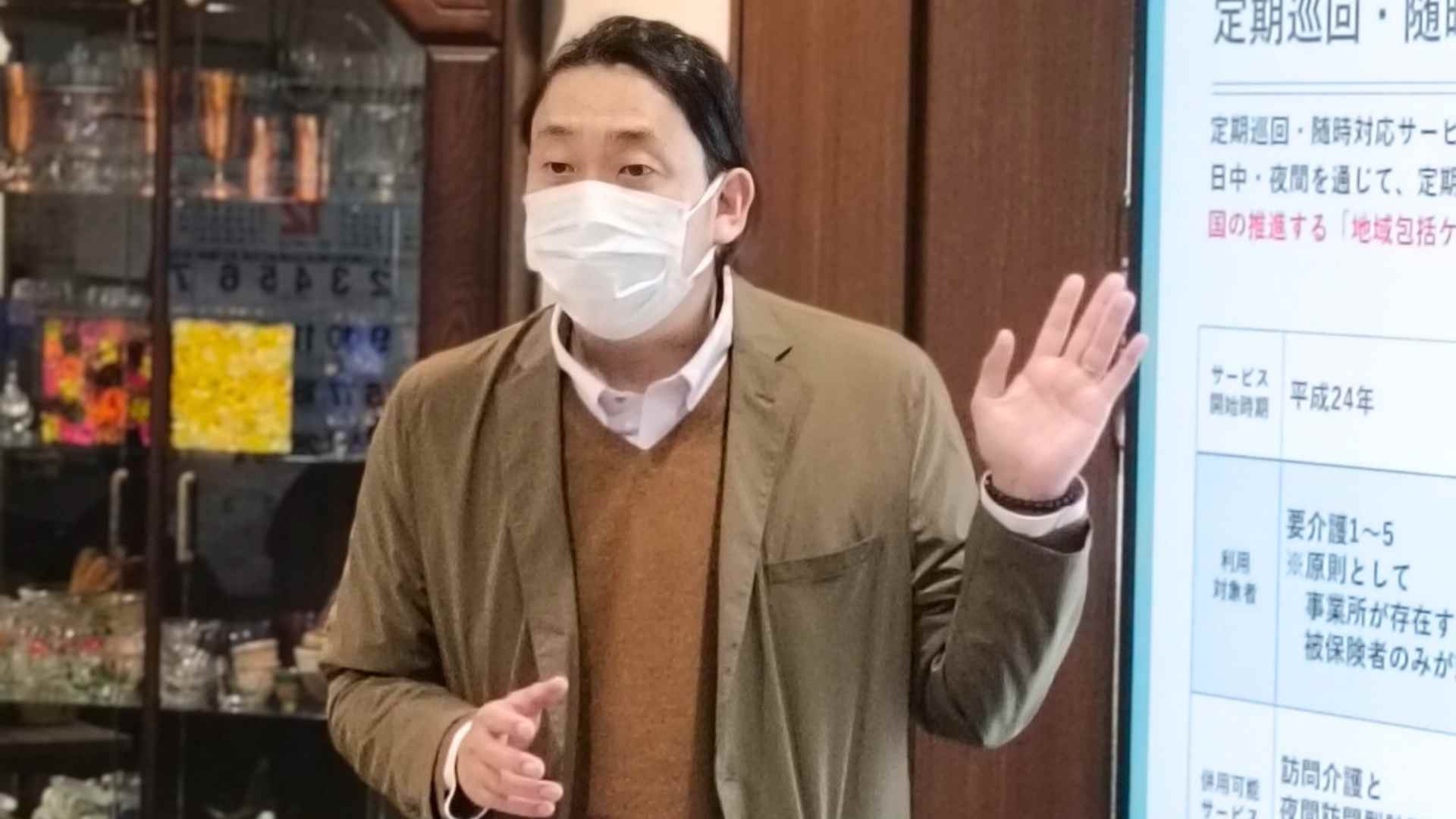
CHAPTER3
これまで培ったもの、やりがい――40歳を過ぎた時、まだ、いや、もっとやりたいことがあった
―さまざまな介護の仕事を経験された後、土屋に入社したのはどんなきっかけだったんでしょうか。
前職の有料老人ホームを退職した後、エージェントさんにお願いしていろいろな仕事を探してもらっていたんです。
その中で、たまたま土屋で働いている方とお話をする機会があって。
私は介護の資格を持っていたので、その時に「仕事を辞めて時間があるなら、アルバイトをしてみたら?」と軽い感じでお誘いをいただいたんですよ。
そこから面接に行った時に、ありがたいことに正社員のお話をいただいて――それがきっかけで入社をしました。
―これは私自身の経験でもあるんですが――40歳前後というのは、自身の立場が変わったり、今までやってきたことに「これでいいんだろうか」と働き方や生き方を見つめ直す時でもあったかな、と思います。長谷川さんはその時、どんな思いで転職をされたんでしょうか?
そうですね。前職は30代前半に入社して、そこで10年ほど働きました。
その10年のあいだに会社が大きくなっていく過程を見ながら、勉強させていただいて。もちろん、今も感謝はあるのですが――最後の頃はこのままでよいのかな?と思うことが増えていきました。
もちろん、その頃はあるポストに収まってもいたので、経済的にもとてもありがたかったし、仕事はやりやすい状況だったんですよ。
でも、40歳を過ぎた時、まだ、いや、もっとやりたいことがある。「もうすこしスキルアップしていきたい」、でも「この会社にいたら、自分はこのまま、一生抜け出せないだろうな」と――。
それで退職をすることにしました。
それまでも転職は多かったんですが、やっぱり年代によって、それぞれ理由が違いますよね。
20代の頃は「お給料の良いところで働きたい」という理由で転職をしてましたし、30代の頃は「介護を辞めようかな」という転機にもなった時期での転職でしたし。
当時は管理者をしてはいたんですが、まだまだマネージメントが下手で――それで退職をしたんですが、介護職そのものは諦めきれずに「純粋に介護だけをしたい」って派遣で働いていたこともありましたし(笑)。
でもそこでいろいろとご縁があって、原点に戻っていくというか――自分が今まで培ったものや仕事のやりがいを考えた時に、「やっぱり自分は介護の仕事が好きなんだな」と思えて介護職に戻ったんです。
CHAPTER4
本人が困ってるところは何か。本当にできないのはどこなのか。それを観察し、みんなで深掘りしていく
―定期巡回サービスは、土屋の中でも現在、新規事業として広がっていってます。数ある介護の仕事の中で、定期巡回の特徴はどんなところにあると思われますか?
定期巡回、私はすごく楽しい事業だと思ってます。
介護保険制度では、“自立支援”という言葉をよく使うんですが――私は訪問介護の経験があるんですが、訪問介護では“自立支援”と言いながら、実際は正反対のことを利用者の方に対してやっているところがあったんですね。
簡単に言うと、介護事業は、企業なので収益を目的にしています。
その収益を得るために、本人はできるかもしれないのに――「この日も支援に入れますよ」「もうちょっと長い時間、入れますよ」って――会社の収益を優先してしまうと本人が必要としてない支援をする方向に流れやすい仕組みになっているんです。
もちろん、そのことが簡単に悪いとも言えませんし、どちらとも大事だとも思います。
でもご本人の立場にとっての“自立支援”には反しているよな、と――。私自身もスタッフの前で「自立支援が大事だよ」と言いながらも、そういう介護保険制度の矛盾をずっと抱えながら働いてきたんです。
でもそれは「しょうがないのかな」と――無理矢理、自分を納得させていました。
でも、この定期巡回に関しては逆で、先に月額の報酬が決まっているんです。極端に言えば、1回しか訪問しなくても10回訪問したとしても、利用者が払う金額は同じ。
そうであれば、回数を減らした方がご本人の自立にとっても、会社の収益にとってもいいんですよね。この“減らす”っていう作業が最初は疑問ではあったんですが――訪問回数を“減らす”ことによって、私たちがいない時間帯に、利用者の方がちゃんとおひとりで生活できているのに気付くことができたんです。
つまり――言葉は悪いんですが――私たち介護者が、勝手に心配をして、勝手に「あなたにはこういうサービスが必要だ」って支援を押し付けていた面が見えてきました。
利用者の“できないところ”を探して、それを支援として収益化する――そういうイメージを、今まで私は介護保険制度に対して持っているところがあった。
でも定期巡回は逆で、“本人ができることを見つけていくため“のサービスなんですよ。
私たち介護者が極端に手を出さずに、本人が本当に困ってるところは何か。
本当にできないのはどこなのか。それをそれぞれが観察し、みんなで深掘りしていく。
アセスメントでは、チームでその作業をするので、私自身が考えている自立支援に近いものでもありますし、最終的には、その人が施設ではなく、ご自宅で住み続けていくために必要な能力を維持していくことにつながるんです。
一人ひとりに合わせた支援ができる個別性もすごく理に適っていますし、今までの介護保険制度にはない面があるので、面白い事業だと思って仕事をさせてもらってます。
―実際にアセスメントは、どのように進んでいくんですか?
例えば、ご家族の方からは「本人があまりわかっていないので、薬の管理は介護者の方にお願いしたい」と最初は言われます。
こちらもクライアントの情報がないので、最初はご家族の仰った通りにするんですが、観察しているとクライアントが必要な時に、ご自身で頓服薬を飲んでる――っていうことは、ご本人はちゃんと理解をされているんですよ。
そういったクライアントの細かな情報を支援者みんなで共有しながら、「○○ができるなら、すぐ変えるのではなく、タイミングを見ながら、次の提案ではこうしてみよう」
「もうすこしご自身でできるんじゃないだろうか」「一方で、それに伴うリスクはなんだろう」とか――意外と誰も知らなかったりもするんですよね。
だからこそそうやって、みんなで意見を交換しながらクライアントのこれからを考えていける。
でもこれは、それぞれが持ってる情報を集めることで考えられるし、介護の計画を立てられるんです。私ひとりでは絶対にできません。
たとえば訪問介護のヘルパーだと伺う回数そのものが少ないので、そこまで深掘りできない部分があります。
でも定期巡回の場合は、ほぼ毎日ご自宅に伺うので、そういった情報量が圧倒的に多いな、とは感じていますね。
―みんなで情報を共有しながら、引き算していくような関わりをされているんですね。
そうですね。引き算できる事業というのは、他の介護保険事業の中でも少ないなと思います。
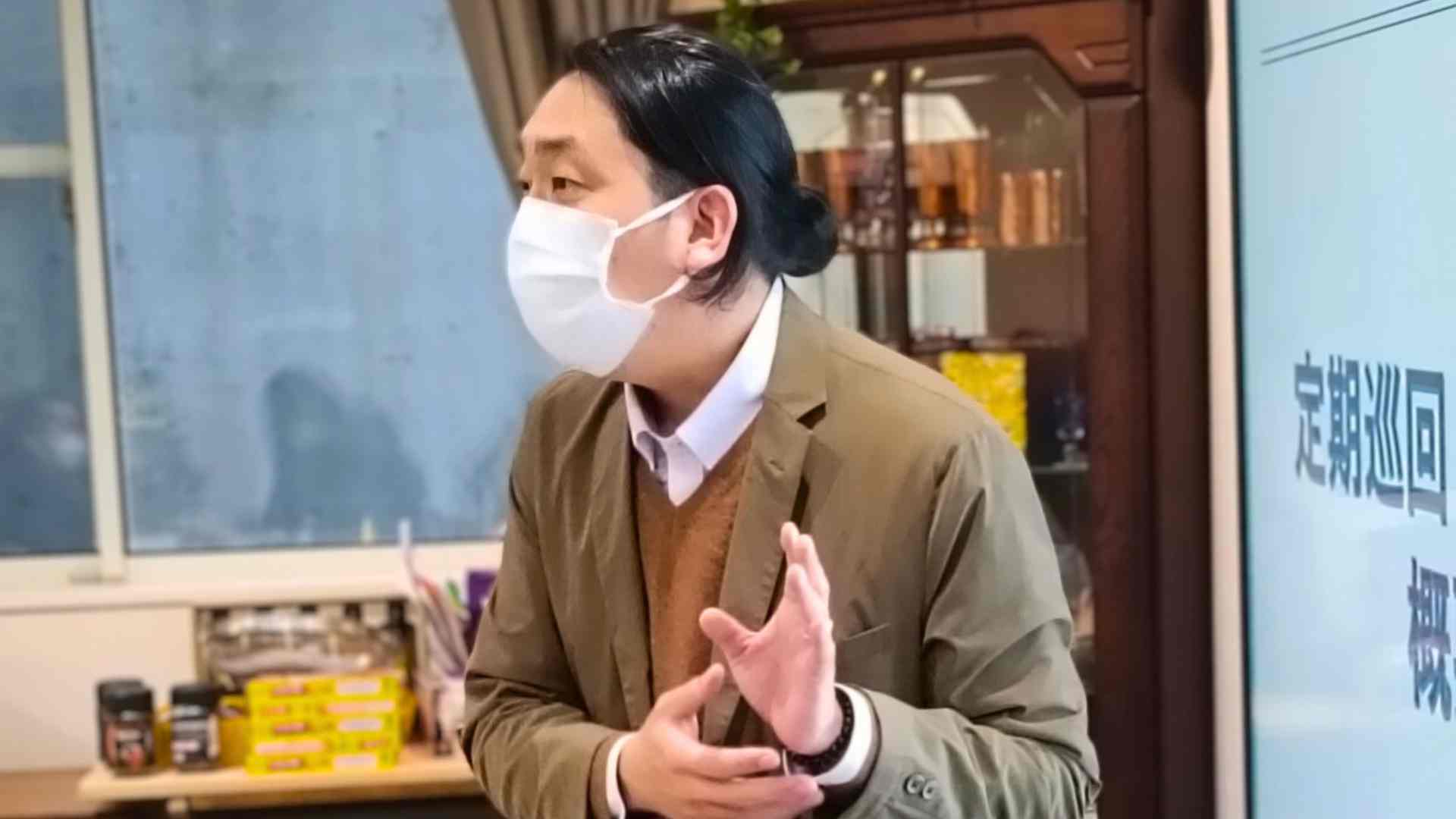
CHAPTER5
ひとりでは何もできない。だからこそ聞き、伝える
―介護の仕事を続けてきた中で、人と関わる時に長谷川さんがどんなところを大切にされているかを教えてください。
そうですね。介護の仕事を経験していく中で、考え方は変わってはきてるんですが、今大事にしてるのは「ひとりで何でも解決しようとしない」っていうことですね。
以前は――「この人を支えるためには自分じゃなきゃいけない」っていう考え方を持っていた時期もありました。介護職では多いのかもしれませんが、それって自分の側から見た話なので、仕事として考えるとちょっと違う。
介護で働く方には気持ちがやさしい方ややってあげたいという思いが強い方も多いのですが、やはり仕事とプライベートは分けなきゃいけないとは思います。
自分の家族に対してだったらできても、クライアントさんとはあくまで仕事で出会い、きっかけをもらってるだけなので――「ひとりでは何もできないな」っていうことを痛感しているので、チーム・マネージメントを意識するようにしてます。
そして、それをできるだけみんなにも伝えていく。
頭の中って見えないので、その人が何を考えてるかはわからない――私も若い頃は、まわりから「何を考えてるかわからない」ってよく言われてましたね(笑)。
言葉にすることもできず、ジレンマもありました。
でも今、ある程度経験を重ねて、実体験や例を挙げながら「自分が考えてることはこういうことなんだよ」と人に話をしていけるようになってきたかな、と。
まだまだなんですけど。
だからこそ、自分の考え方に共感してもらえるような伝え方を今、意識してやってます。私の場合はこれまで事業所の立ち上げを何回か経験していて――「一体、この状況をどうしたらいいんだ」っていう状態から始まって(笑)、もともと要領がいいわけでもないので、当時は人の3倍ぐらい時間がかかって、やってきました。
と同時に、当時は立ち上げや引き継ぎの時に“丸投げ”されるパターンが多かったんですよ。
その頃はまだマネージメントという言葉もそんなに聞かれなかった時代で、人を教えることの難しさも感じていました。
でも、基本的に人って、自分が教わったようにしか人に教えられないんですよね。
それで、「仕事を“丸投げ”される方法では次の世代が育たない」、と。
―そうですね。
なので、できるだけ自分で勉強をしながら、意識してマネージメントという言葉を使ったり、自分の考え方を整理しながら、「次はこういう段階だよね」っていう確認をしていましたね。
私ももう45歳なので、求められる役割として――もちろん事業所を軌道に乗せることや、安定した経営をすることはその中のひとつですが――次の世代を育てていきたい、という考え方になってます。
そこで、私が持ってる知識や経験を、できるだけ次の管理者さんに話をするようにしているんです。
ただ、そこって本人のトライ&エラーでしか実感できないものでもあるんですよね。なので、私から細かく指示するわけではなく、ヒントを与えながらその人自身で経験をしてもらうことがマネージメントにおいてはすごく大事かなと思ってます。
CHAPTER6
日々の観察を毎日重ねることで、ちいさな変化にも気づきやすくなる
―長谷川さんにとって、今の仕事の中での喜びややりがいはどんなところにありますか?
そうですね、ふたつあるんですが、ひとつは、この定期巡回サービス事業を大きくしていきたいですね。
特に今、定期巡回では事業者数が増えていて、そういった成長期に携わらせてもらってることは個人的にもやりがいになっています。
もうひとつは、定期巡回サービスの関西・東海エリアマネージャーという立場になって――
何か課題があった時に、「じゃあ、今度はこうしてみよう」「○○にチャレンジしてみようか」って、各地の管理者のみなさんと“作戦会議”ができることですね。実際に管理者の方から「○○してみたら、うまくいったんです」って報告をもらえると、自分としてはすごく嬉しいですね。
「そう、それそれ!」って、みんなで一緒になって共感する。
共感の嬉しさを今、感じてます。
―定期巡回事業は、これまでの介護保険サービスとは別の側面の魅力がありますね。
定期巡回はやはり、訪問時間は短いんですが、クライアントとのコミュニケーションそのものは取りやすい。
毎日、伺えるのってすごい武器なんですよ。今は土屋に限らず、定期巡回というサービス自体が魅力的な武器をたくさん持ってるなぁ、と思います。
―毎日、ちいさなコミュニケーションを重ねてく中で、ちょっとずつお互いに、ちょうどいい距離感を見つけていくというか……
そうですね。
クライアントの中には、距離を近くとってほしくない方や、「ひとりの時間がいい」という方もいらっしゃいます。そういう場合も、定期巡回って支援時間が短いので、クライアントにとっても使いやすいんじゃないかと思いますね。
そういう時間を毎日繰り返していくと、「今日はこれを手伝ってほしい」って言ってくださるようになったり、「今日はすごくおしゃべりだな」と感じる日が出てきたり。
そういった日々の観察を毎日重ねることで、ちいさな変化にも気づきやすいので。
アテンダントからの報告を見ていると、「こんなことをお話されたんだ」といった会話の内容や、認知面でも「この間言った○○を覚えてくださっていた」とか――気づき、発見が定期巡回の魅力だなと思います。
そこは、クライアントさんから気づかせてもらったところですね。

CHAPTER7
誰もが気軽に福祉制度を利用できるように。きっとこれからの“20年”で介護業界は変わっていく
―長谷川さんはお休みの日はどんなことして過ごしていますか?
仕事の時はちゃんとしてるんですが――プライベートはすごくだらしないんです(笑)。
趣味があるとすれば、40代前ぐらいからゴルフをやってます。ゴルフは、仕事の延長で、「とりあえずできなくてもいいから来てみたら?」と誘ってもらって始めたんですが、最初はすごく嫌いで。
練習もしなかったし、一向にうまくならなくて。
でも、仲のいい人たちと仕事以外でゴルフに行くようにもなった時に感じたのが――当時は管理者として責任ある立場にもなってましたし、完全にマネージメントする側になってたので、人から褒められることって基本、なかったんですよ。
課せられた課題に対して、「やれてあたりまえ」という仕事が多くて。
でもゴルフって、下手くそでも、遠くからアプローチした球が奇跡的に一発でホールに入ったりする偶然があるんです。その時にみなさん、純粋に喜んでくれるんですよね。
自分もそうですし。偉い人と行った時も、「すごいっすね!」って嬉そうな顔をしてくれる。「ゴルフの魅力ってここにあるのかな」と思って。
仕事とはちょっと違って、偶然でもなんでも、「すごいものはすごい」って素直に言えるところが魅力的だな、と。今は全然できてないんですが。
―これからのところもすこしお聞きできれば、と思います。定期巡回のこれから、と同時に、長谷川さん自身のこれからも合わせて、聞かせてください。
定期巡回については、せっかく今、この土屋に入って、定期巡回事業に携わって、エリアマネージャーという重要なポジションにまでさせていただいて――土屋としても、これだけ今、定期巡回に力を入れていただいてるので、業界全体の定期巡回事業の、パイオニア的な存在になっていきたいですね。
会社をしっかり盛り上げてもいきたいし、もちろん自分個人としては収入を上げていきたいとも思ってます。
それと、やっぱり次を育てていきたい。共感できる仲間をどんどん増やしていきたいですね。
―一人ひとりの生活に関わっていく中で、「10年後、20年後、こんな社会になっていたらいいな」というイメージはありますか?
そうですね、10年後、20年後というと、もう私が介護を受ける側になってるかもしれないですが……(笑)。
土屋に入社して、障害福祉分野のお話を聞く機会も多くなりました。今後は介護保険制度に限らず、障害福祉制度ももっとスマートに受けられるような社会になればいいな、と思います。
今も「人のお世話になるなんて」という方もいらっしゃいますし、そういった抵抗や偏見も社会にはまだまだ根強くあります。
でも私は「介護って楽しいな」と思いながら仕事するようにもしてますし、「そこに共感してほしい」っていうところも持ってるんですね。
もちろん、きついかもしれないし、汚いところもあるかもしれないけど、それも含めて「なんか楽しいよね」って言えるように。
それは、土屋で言う“オールハッピーの社会”っていう理念に近いものかもしれないですね。
すべてを綺麗に、壁を取っ払って、風通しよく――っていうのは、20年後ではおそらくまだ難しいかなとは思うんですが、今よりも気軽に福祉制度を利用することがあたりまえの社会になってくれるといいなーーっていうイメージはありますね。
“20年”っていう時間がすごく大事だなとは思ってるんです。
20年前って、私はまだ20代だったんですが、その頃と今って全然違うじゃないですか。こんなふうにzoomでお話できたり、現金も持たなくていい時代になるなんて思ってもいなかった。
そういう意味では、介護業界もきっとこれからの“20年”で変われるんじゃないかな、って期待をしてますね。
―長谷川さんはなぜ介護や福祉の仕事を続けているのか――そこを最後にお聞きしたいです。
今日働く8時間を一生懸命やるように意識をしてます。
そう考え方を変えた時に、毎日、違うことが起きるんですよ。同じ日って1個もなくて――そのことが私にとっては、この仕事の楽しさという原動力につながってるのかな。
同じクライアントさんでも毎日表情が違うし、話す内容も違う。毎日違うことが起こって、毎日違う話をして笑える仕事なんてあんまりないよな、って。
それが、私にとって介護の仕事が好きな理由なのかな、って思いますね。