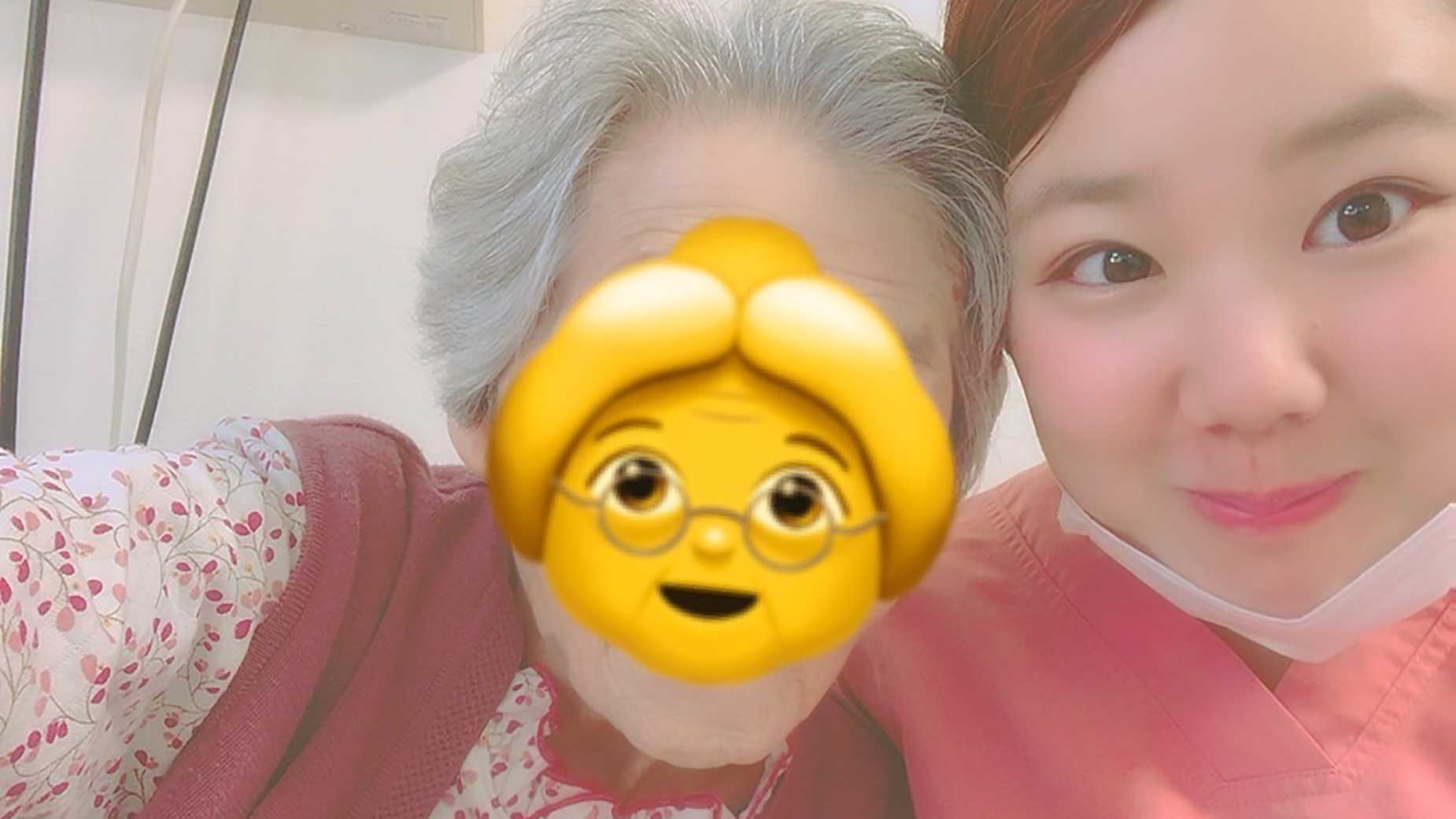―その後の重度訪問介護(重訪)との出会いは、川畑さんにとって大きいものだったのかな、と感じます。土屋に入社されて、実際にクライアントさんの支援に関わるようになって、いかがでしたか。
最初は正直なところ、「無理だー」って思ってしまったんです。
病棟看護師だったので、介護の部分が全くできなくて、本当にきつかった。
注射や採血、検査は得意だったんですが、おむつ交換や移乗、お風呂介助は何もできなくて。
今は違うんですが、その時のホームケア土屋鹿児島は人手が少なかった時期だったのもあって、新人アテンダントには支援の最初の段階で短時間同行した後、割とすぐ独り立ちするような流れだったんです。
もちろん看護師資格もあって、医療的ケアの経験もあったからこそ現場をすぐに任せてもらえたところもあったと思います。
でもコミュニケーションは取れない。
A L S等の難病や障害者の方と関わること自体がそもそも初めてだったので、文字盤の経験もないし、考え方もいまいちよくわからなかった。
それで支援現場で泣いてしまってーーずっと泣きながら、駐車場まで帰りました。
でもそこから、なんでかーー「この会社で働くなら、このままじゃいけないな」と思って(笑)。
もともと看護師時代から、「上にあがりたい」「看護師長になりたい」っていう意欲はあったんですよね。
理由はなく、ただ「やりたい」っていう思いがあった。
当時、ホームケア土屋鹿児島ではコーディネーターが不在だったので、「じゃあ、私がやろう」って。
そこが自分の中で、気持ちがガラッと切り替わった瞬間だったかなって思います。
―「コーディネーターになる」って決めた時。
そうですね。
「もう絶対なってやる」って思いました。
入社当初はーー看護師としての自信があったんでしょうね。
「技術はあるし、まぁ大丈夫でしょう」みたいな気持ちでいたのが、支援現場に入ったら、全部崩れたような気持ちになったんです。
その時、「全然ダメじゃん、自分」って。
それでなんでか「コーディネーターになろう」って思いました(笑)。
そこからはホームケア土屋鹿児島が受けたクライアントの現場は全部入りました。
「私は2回(の支援)で、そのクライアントの支援を全部覚えるんだ」って決めて。
自分で手順書をつくったり、メモったりしてー―「自分が全部の現場に入れるようにして、ちょっとでも次に支援に入るアテンダントのフォローができるまでにならないと」ってなったんですよね。
ーコーディネーターになられてからはどうでしたか。業務が変わってきた時、見えてきたものはありましたか。
そこでも、「まだまだダメなんだな、自分は」って思いましたね。
自分の伝え方の悪さが本当に身に染みたというかーー。
“言葉の知らなさ”があったんだと思います。
本当に経験不足だとは思うんですけど。
2年ほど、鹿児島でコーディネーターをさせていただいたんですが、最初は「なんでこの伝え方がダメなのか」がまずわからなかった。
働いてくださっているアテンダントの方が「自分より目上の方だ」という認識はあったし、
私の中では内容をしっかり伝えてるつもりでも、傍から見ると、すごく失礼な言い方をしていたり。
“私の中で使ってる言葉”が抜けきれないまま、人に伝わりづらい話し方をしていて、まわりからも注意をたくさん受けました。
支援現場に関しては、悩むというよりは「やることをやっていく」っていうふうに進められたんですが、
アテンダントとのやり取りは「私の伝え方ひとつで、こうも結果が変わってくるのか」っていうことをたくさん経験しました。
本当にいろんなことを学ばせてもらったなと思います。
土屋に入社するきっかけをつくってくれた知人がいてーーその人が、誰かのために何かをする喜びとか、覚悟を教えてくれたんですよね。
それまでは、目の前にあるものとか目標に向けて、ただただ進んでいっていたんですが、
「自分がしたいことがあったら、そこに向けて具体的にどういう努力をしたらいいのか」とか、「どんな覚悟を持てばいいのか」を考えさせてもらった。
そういうふうに考えられるようになったのは、その人との出会いがあったからだ、と思ってます。