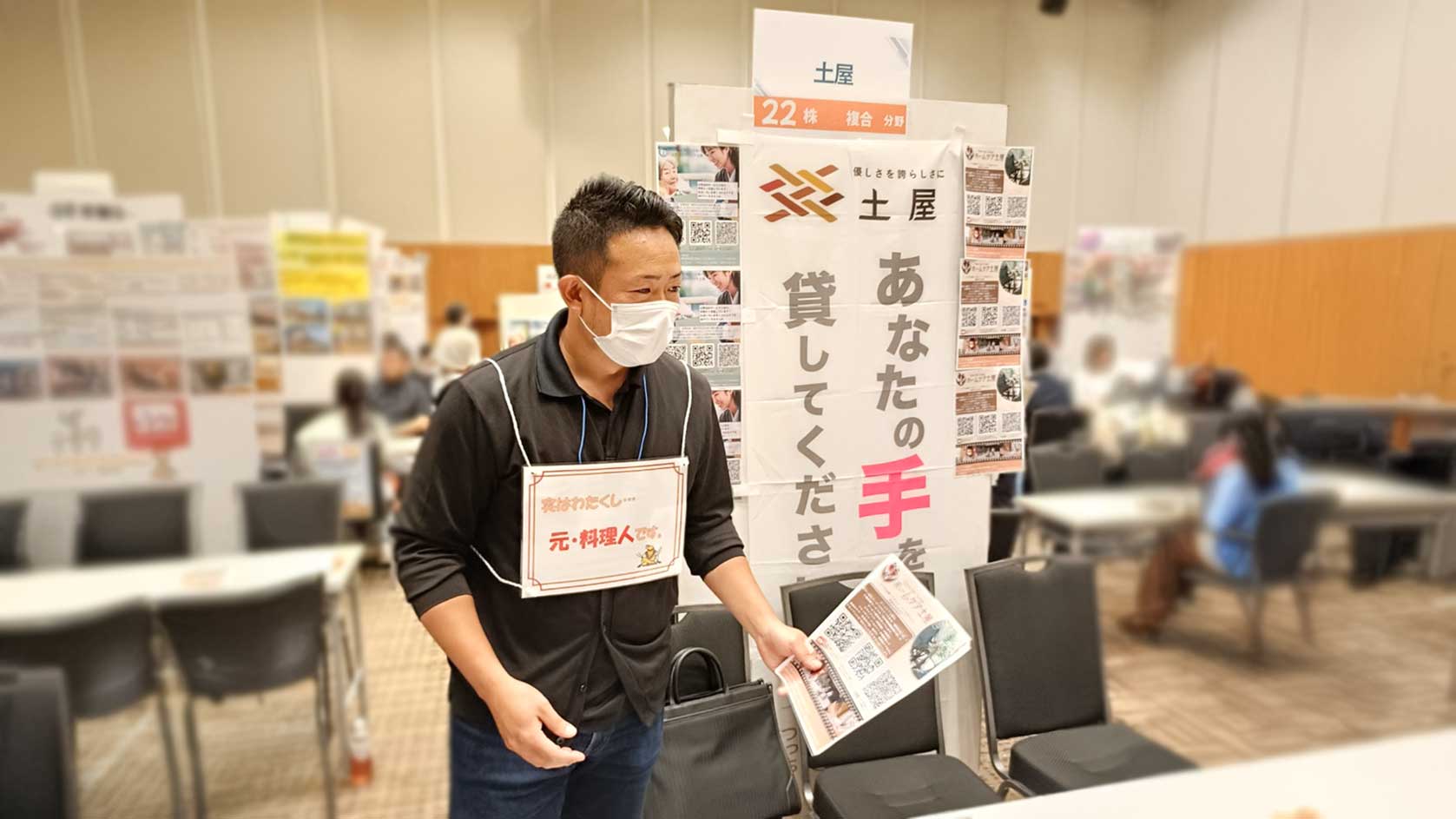―お休みの日はどんな風に過ごされているんでしょうか。
休みの日は――魚釣り一択です(笑)。
今住んでいるところが海にものすごく近いんです。
船での釣りもしますし、船で離島に渡って磯の上でもやります。
でもそれは時間かかるので、普段の週末は海岸や防波堤で釣ってますね。
―魚釣り、どんなところが魅力なんでしょう。
そうですね。
自然相手というところが釣りのいちばんの魅力かなと思います。
あとは魚との駆け引きですね。餌をつけて、海に出れば釣れるわけではないんです。
いかに自然体に餌を泳がせて、魚を釣るか――自分の存在を消すようなイメージで(笑)。
そういったところがすごく楽しいです。
釣りは、保育園の頃から父親と一緒にやってましたね。
小学3年生の時には船に乗って、長崎の五島列島に父親と行って。
夜の真っ暗の海で、畳二畳分ぐらいしかない海上の岩の上に「飛べ」って言われて。釣りもなかなかスパルタでした(笑)。
―これからのこと、そして大野さんがなぜ介護の仕事を続けてこられたのかを聞かせてください。
そうですね。
もうすでに会社としても動いているところではあるんですが、日本で生まれた介護技術――これを海外にも発信をしていけたら、と思います。
いろんな障壁があるかもしれませんが、それでも困った人たちの役に立つならば、頑張っていきたいですね。
なぜ介護の仕事を続けてきたのかといえば――“仕事”というのは、ただの言葉であって、「何のためにしているのか」というところに意味を持たせることで、仕事がやっと活きてくるのかな、と考えています。
自分にとって仕事というのは、やはり人に喜んでもらうことです。
これからももっと広く、あまねく、たくさんの人に喜んでいただけるようにやっていきたいですね。
それは介護に従事している理由とも繋がっているんです。
「もっと喜ばせられるかな」「もっと喜んでいただける方がいるんじゃないかな」――そういう仕事に出会っていくには時間もかかりますし、まだまだ従事していかないといけないな、と思って仕事に取り組んでおります。
一大野さんを仕事に向かわせてくれる原動力は、どんなところにありますか。
そうですね。
これは私事でもあるんですが、介護の仕事に従事させていただいて、「ものすごく誇らしい仕事だな」っていう思いがあるんです。
ひと昔前は“3K”なんて心ない言葉もあったんですが、僕自身はそう感じたことはありません。目の前で人に喜んでもらえる、目の前でありがとうって言ってもらえる。
「こんな楽しい仕事、いい仕事があったのか!」って。
その姿を我が子たちにもメッセージとして伝えてるんですよ。
今の子たちにも、介護職のそういったイメージを培ってもらいたいんですよね。
―最後に、4年ほど、土屋で働かれてきた中で、「こういうところは土屋らしいな」っていうところがあったら、最後に聞かせていただいてもいいですか。
自由、ですね――。
自由っていう言葉だけで聞けば、「開放的」「楽ちん」といったイメージがあるかもしれません。
でも自由っていうのは縛りがない分、逆にきついこともある。
でも自由な環境に置かれる中で――人って「これはダメだ」「こうしなければいけない」と、自分自身でルールをつくっていくと思うんです。
自分で敷いたルールでやっていくことは、実は楽しさがあって、その楽しさが滲み出てる人は人を寄せつけます。
人に喜びを与えますし、楽しさを与えられる人間にもなっていけるんじゃないかなと思うんです。
たとえば、ご自宅で過ごすことが多いクライアントにも、単なる“仕事”として支援をするだけではなくて、土屋がもつ“自由らしさ”を身につけることで楽しい雰囲気も一緒にお届けできるんじゃないか――“自由”という言葉から、そんなことを考えますね。