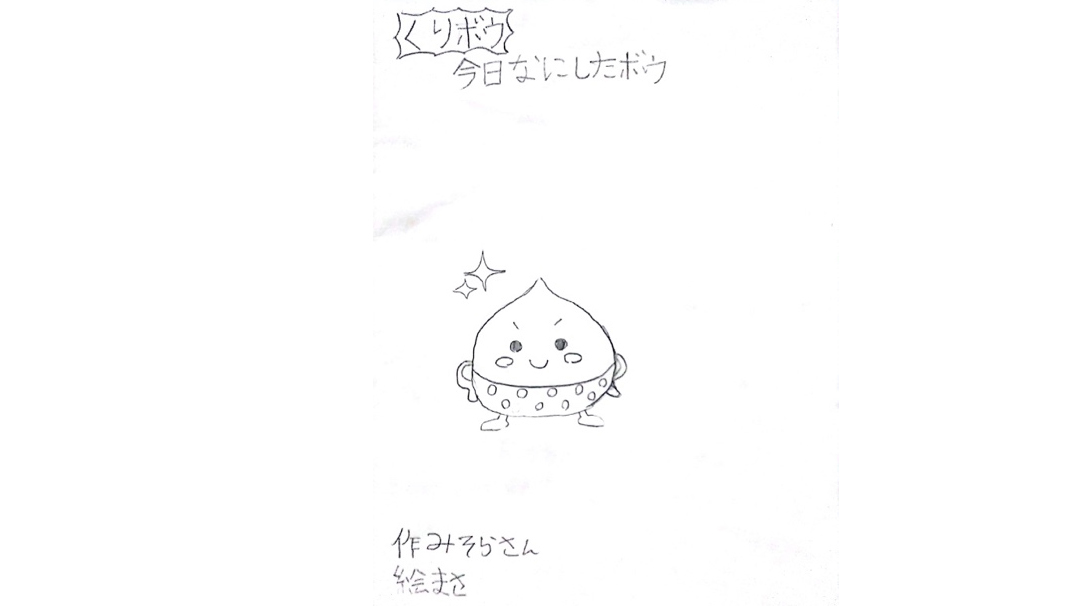―「これからこんなふうに生きていきたい」「土屋でこんなことに関わっていきたい」という思いがあったら聞かせていただけますか。
これから――私は土屋でやりたいことがあるんです。
今、社会的に見ても、美宙さんのお母さんが仰っていた通り、医療的ケアが必要な子たちが利用できる施設やサービスが本当に足りてない状況があります。
実は今度、2歳になる医療的ケア児のお家に支援に入ることになりました。
そのお子さんは普段は入院しているんですが、退院して、1週間自宅に帰ってきた時に「子どもをどうケアしたらいいかわからない。
疲れすぎて夜中まで面倒がみれない。
呼吸器が鳴って、行かなきゃいけないのに体が動かなかった」――先日、親御さんからそんな話を聞きました。
そんな時に私たちヘルパーが支援に行くことで、子どもが自分の家で、親御さんと暮らしていけるんだったら、いくらでも手助けをしていきたい。
子どもが家に帰れる環境を、お母さんの手の温もりで子どもが育つ環境を、つくっていきたいと思うんです。
“子どもを育てる”というだけでもすっごく大変なことですよね。
それが医療的ケアが必要なら、もっと大変になる。
だったら、もっと気軽に人の手を借りていいんじゃないのかな、自分たちでなんとかしようなんて思わなくていいんじゃないかな――。
そうやっていつか、医療的ケア児を持つ親御さんたちのコミュニティができたらいいですよね。
土屋から輪が広がっていけるような地域づくりをこれからしていきたいなと思ってます。
―そのような思いを持たれたのは、美宙さんとの出会いが大きいですか?
そうですね。でもどちらかというと、美宙さんのお母さんのお話が大きかったですね。
―佐藤さんご自身の、“母”としての経験のところで重なったんでしょうか。
私自身も子どもを4人育ててきたので、いろんなことがありました。
有老で働いていた頃は、30分の距離に勤務先があったのに、近くの保育園に入れなくて、毎朝、民間の保育園を3か所回って子どもを預けて、1時間半かけて通勤してたとか――。
もちろん、医療的ケア児のいるご家庭との経験と比べられるものではないんですが。
周りからも“サーカス乗り”なんて言われてましたよ(笑)。
子どもを4人乗せて、ひとりで自転車漕いで、保育園を回って、そこからの介護の仕事――もう、涙流した時期もあったんです。
「今だったら絶対できないだろうな」ってことが、なぜかあの時はできた。子育てって、そういうがむしゃらな時期があるんですよね。
でも――これは医療的ケア児のいる別の親御さんから聞いた話ですが、「ちょっと目を離しただけで呼吸が止まってしまう。だから子どもから片時も目が離せない」
――それは親御さんにとって常に心身が休まらない状況ですよね。
私も子どもが小さかった時、家の中でほんの少し目離した隙に、末っ子が勝手に外に出て、踏切を渡っていたことがあったんです。
「え?玄関開けられた?!」「あれ、踏み切りわたってる?!」って――ベランダで洗濯物を干している間に、末っ子がいなくなっていた。
もちろん、医療的ケア児のいる親御さんの「目が離せない」とは全く状況が違います。
でも、その子の命に関わること。
「子どもから目を離すなんて、誰でもありますよ」「むしろ、目を離したい時ってありますよ」「だからこそ、目が離せないって大変ですよね」って――。
多分、親ってみんなどこかでそんな思いを抱えながら子どもを育てていると思うんです。
だからこそ少しでもお母さんやお父さんたちが休めて、安らぎのある生活ができたらいいな――って。
―そこは、社会の側が変わらないといけない部分ですね。
もともと医療的ケア児やその親御さんにとって行きやすいコミュニティーが少ないこともありますが、「医療的ケアが必要」というだけで、
たくさんの“できないこと”を強いられるような今の社会があるんだ――とも思います。
「医療的ケアが必要ない子はいろんな遊びができるのに、医療的ケアが必要な子は別のグループにいなきゃいけない?じっとしてないといけない?」――それっておかしい。
どんな子にも、その子が望んでいることをやらせてあげたいじゃないですか。
先ほど話をした、これから支援に入る2歳のクライアントのお家では、今度、赤ちゃんが生まれるんだそうです。
その子はお兄ちゃんになる。
そのお家にはお姉ちゃんがいるので、今度、親御さんは、赤ちゃんとお兄ちゃん、お姉ちゃんの3人を育てていく。
でも「医療的ケア児のいるお家は、第2子は考えられない」なんて話を聞くこともあるんです――「そりゃないよな」って思いませんか?
誰だって安心して、親御さんや家族が望むなら、兄弟・姉妹をつくれるような環境をつくっていけたらいいなって、私はやっぱり思うんです。
私たちがみんなで知識を出し合って、手の足りないご家庭を支えていって、子どもたちが在宅で、安心して過ごしていける環境づくりを手伝えたらいいな、って。
そんなあたたかな社会をつくっていきたい、と私は思います。