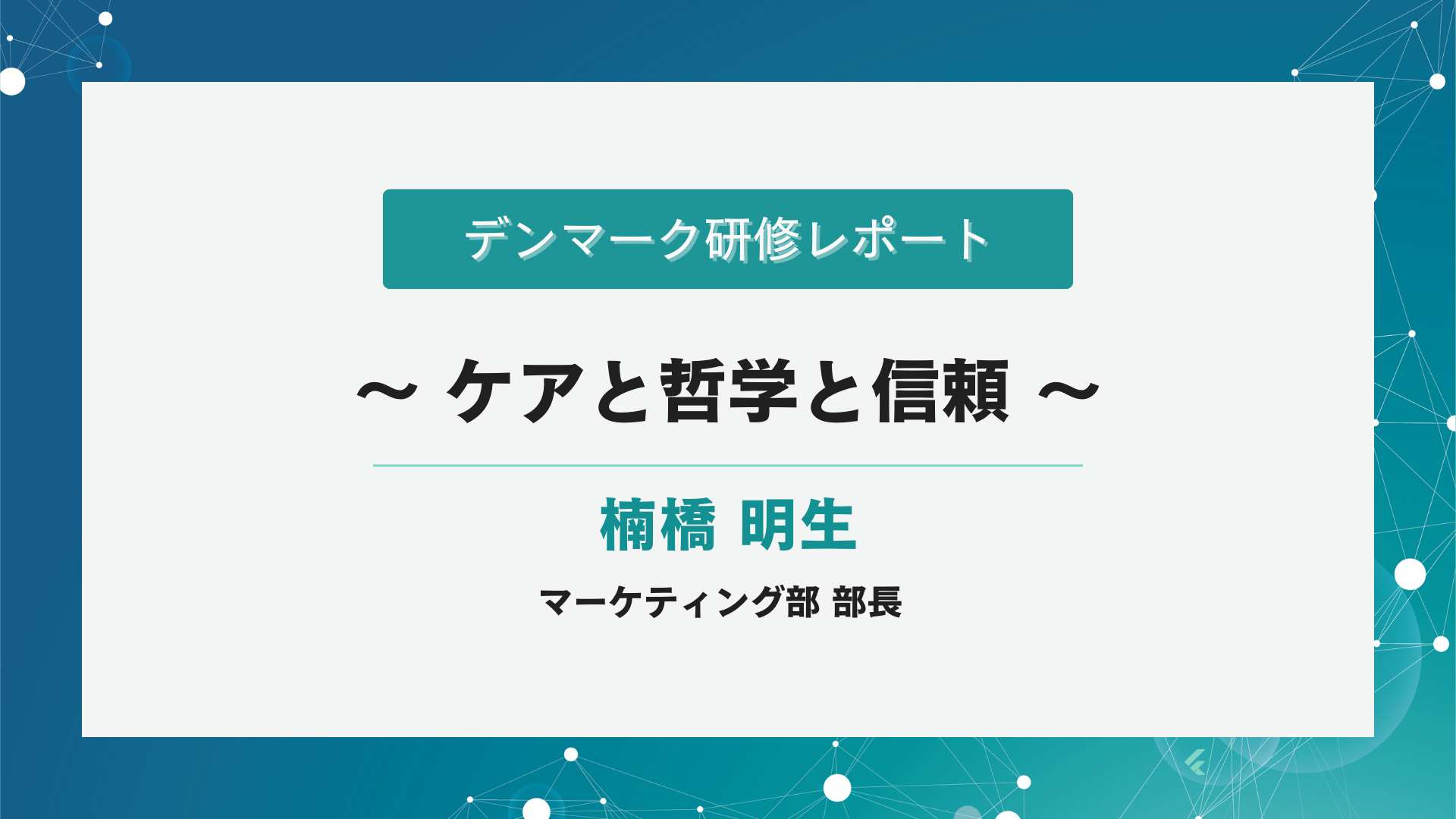
『ケアと哲学と信頼』楠橋明生(マーケティング部 部長)
今回の研修については、大きく3つの観点からレポートをまとめます。
滞在期間は1週間と限られていましたので、すべての側面に深く切り込むことは難しかったかもしれませんが、非常に濃密な学びの時間となりました。
その内容を以下に記します。
今回の研修では、デンマーク・ノーフュンス・フォルケホイスコーレに1週間滞在し、同校副校長であるMomoyo氏による講義を受講しました。
Momoyo氏には、現地視察時の通訳も随所で担当いただき、デンマークの制度や価値観について多角的な理解を深めることができました。
恥ずかしながら、最初に研修プランについて聞いた時はノーフュンス・フォルケホイスコーレの存在を知りませんでした。
しかし、デンマークのプランについて日本の友人と話をしていると「以前から行ってみたかった」「羨ましい」といった声を多くいただき、非常に価値ある場所で時間を過ごせたことを実感しています。
現地では、日本を含む欧州各国から集まった若者たちと交流し、寮生活を通じて日常的なコミュニケーションが自然と生まれました。
学校の周囲には商業施設が少なく、コンビニ等もないため、そのぶん散歩や卓球、ボクシングといった活動や自由な時間を通じて、年齢や肩書きに関係なく心から楽しむことができました。
この学校の魅力を語り始めると際限がありませんので、詳細についてはここまでに留めておきますが、フォルケホイスコーレという制度が若者に与える影響の大きさと深さについては、ぜひ多くの人に知っていただきたいと感じました。
様々な現場を訪問して
ノーフュンス・フォルケホイスコーレ以外にも、研修中には多様な施設を訪問しました。
就労支援施設や在宅ケアの現場、行政の障害福祉担当部署、地元の小学校など、さまざまな立場からデンマークの社会システムに触れることができました。
特に印象に残ったのは、現場の職員たちの発言です。
「私たちには理論(theory)がある」「哲学(philosophy)がある」「だからこそ最適な判断ができる」と、誰もが自信をもって語っていたのです。
これは大きな驚きでした。
ビジネスの現場では、同じ理論やフレームワークを使っても、実行者の力量によって成果や運用方法に差が出ることがよく指摘されています。
しかし彼らの話からはフレームワークの正しい使い方やアウトプットの違いが出てくることはなく、理論や哲学がただのツールではなく、自らの判断や行動、プロとしてのあり方の確かな裏付けとして機能していることがよく伝わってきました。
そして哲学や理論をアセットとしてケアや医療に自信と誇りをもって取り組むだけではなく、誰もが専門職やプロフェッショナルとしての矜持を持ち、言葉だけでなく実際の行動においても、互いを専門職として尊重し合っていることが見て取れました。
この点は非常に徹底されており、働き手にとっては非常にいいシステムが構築されているように思います。
医療職と介護士の関係一つを取っても、日本で行われがちなコミュニケーションではなく、それぞれの職能領域における専門性に対して、相互に耳を傾け、お互いの意思決定を尊重しあう文化が築かれています。
デンマークでは、介護士になるには数年にわたる専門的な訓練を要し、その分、役割と責任も明確に位置づけられています。
福祉と哲学の根幹
デンマークが「福祉国家」として国際的に評価されている背景には、制度の整備だけでなく、その根底にある明確な思想と哲学の存在が大きく影響していると感じました。
人口は日本の約20分の1と小規模ながら、社会保障、医療、教育といった仕組みは、国民の高い納税意識と行政への信頼によって支えられています。
とりわけ注目すべきは、医療や福祉の分野に従事する多くの人々が公務員であり、その人件費が税金によってまかなわれている点です。
この構造により、制度の透明性が確保されると同時に、運用の効率性も求められる環境が整っています。
デンマーク国民は、高い税を納めるからこそ、それに見合った公共サービスの提供がなされているかを厳しく見極め、行政に対しても強い説明責任を求めています。
実際、障害者支援制度について行政の上層部に「財政的理由で、正当な申請が却下されることはあるのか」と尋ねたところ、「そんなことをすれば、私の立場が危うくなる」と即座に返答されました。
このエピソードからも、高負担・高福祉を支える文化の中で、透明性と説明責任が深く根付いていることがわかります。
さらに、そうした信頼と透明性が制度に反映されている事例として、個人情報の扱いが挙げられます。
デンマークでは、一定の条件下で税務署が国民の所得、資産、取引履歴などを自動的に把握する仕組みがあります。
その他医療に関する個人情報なども多くの人がプライバシーに関わる情報を含め、政府にデータを委ねることに抵抗を感じていません。
「政府はこの情報を公正かつ効率的に使ってくれる」という信頼があるためです。
一見すると、こうした仕組みは日本やアメリカなどの自由を重視する民主主義国にとって、プライバシーの侵害とも映りかねませんが、デンマークでは透明性と説明責任が制度を支える前提として成立しており、人々はそれを信頼によって受け入れているのです。
私自身、EUではCookieなどの個人情報の取り扱いにも厳しい規制があることから、「すべての個人情報の利用が厳しく制限されている」と思っていました。
しかし、実際にはビッグテック企業の情報利用が不透明であることに対する不信が主な問題であり、信頼できる主体による情報管理には寛容であるという実態を知ることができました。
透明性と相互監視の仕組み
デンマークでは国民全体に高い納税意識があり、それが社会制度の透明性を支える大きな基盤となっています。
「税を納めるからには納得できるサービスを受けるべきだ」という考えのもと、公共政策の運用に対して常に厳しい目が向けられています。
この姿勢は制度運営にも反映されています。
公共部門で不正や非効率な運用が明るみに出た場合、関係者には速やかに責任が問われ、場合によっては即座に更迭されることもあります。
こうした仕組みが、政策の健全な運営と改善につながっているのです。
同時に、人と人との間に深い信頼も根づいています。
たとえば、デンマークの鉄道では、ICカードをかざす場所がありながら、改札そのものは存在せず、やろうと思えばお金を払わなくてもそのまま乗車できてしまいます。
首都コペンハーゲンを含む全国でこの仕組みが採用されています。
それでも不正乗車が少ない背景には、「信頼を裏切る行為は社会的に恥ずべきことだ」という共通の倫理観があります。
私がアメリカで暮らしていた時、自動改札を楽しそうにすり抜ける乗客を何度も見かけましたが、デンマークではそのような光景に出会うことはありませんでした。
「小さな国だからズルはすぐバレる」という構造的な側面もあるかもしれませんが、それ以上に社会全体が信頼と誇りによって秩序を保っているように感じました。
無賃乗車などの違反が発覚した場合は、その場または後日、監視スタッフに対して日本円でおよそ15,000円相当の罰金を支払う必要があります。
信頼が前提となっているからこそ、違反時のペナルティは明確で厳しく、それもまたデンマークらしい特徴だと感じました。
教育と進路支援
滞在中に訪れた小学校では、子ども一人ひとりに「進路プランナー」が割り当てられているという話を伺いました。
これは非常に印象的でした。
デンマークでは、日本の中学3年生に相当する年齢になると、プランナーとともに将来の進路について具体的に話し合い、方向性を定めていくのが一般的だそうです。
もちろん、決定した進路に必ず従わなければならないわけではありませんが、社会全体としてリソースの最適配分を図るという観点から、このような取り組みが行われているようです。
また、本人の適性に応じて、プランナーが進路の選択肢をある程度絞ることもあるとのことです。
これは人によっては「自由への介入」と捉えられるかもしれませんが、デンマークではそれが「親切」であり「プロとして当然のあり方」そして「効率的な支援」として受け入れられているように思いました。
このように、プランナーには制度上の権限と専門性が与えられており、その立場を背景にして堂々と支援を行うことが可能です。
専門職としての役割が明確に定義されていることが、制度の機能性を高めていると感じました。
自由と制約のジレンマ
この研修を通じて、「自由とは何か」「制約とは何か」というテーマについて深く考えさせられました。
特に印象に残っているのは、帰国後に読んだフリードリッヒ・ハイエクの一節です。
自由の価値は、それが予見も予測もできない動きに与える機会に依存しているため、個別の自由の制限で何を失ったかは、ほとんどわからない。
そういった制限、一般規則の施行ではないあらゆる強制は、何らかの予測可能な特定の結果の達成を目論んでいるが、それが何を阻止したかは通常わからない。
(中略)よって、それぞれの問題を個別のメリットと思われるものだけに従って決定するとき、私たちは常に中央集権的な方針決定の利点を過大評価することになる。
つまり、自由が奪われることで実現されなかった可能性、たとえば創造的なアイデアや行動は、私たちには見えません。
そのため、強制や統制によって明確な成果が得られたとしても、同時に失われたかもしれない未知の価値には気づきにくいのです。
そして実現されなかった可能性については、そもそも議論の対象になりにくいため、結果として「自由を制限することで得られた社会的メリット」にばかり注目が集まってしまいます。
とはいえ、制約があるからこそ生まれる創造性も確かに存在します。
たとえばクリエイティブの分野では、「自由すぎると良いアイデアが出にくく、むしろ制約があるからこそ優れた発想が生まれる」とよく言われます。
ただし、クリエイティブ上の自由と、人間にとっての本質的な自由とでは、その重みは異なるはずです。
こうした点からも、日本のように多くの「自由」が確保されている社会の良さを、改めて実感する機会となりました。
そのうえで、今の時代は、自由や制約をどう捉え、どのように活かすかが問われているとも感じました。
特に会社という単位では、国のレベルより柔軟に制度を設計・運用できる点が多くあるため、こうした視点を今後、土屋における議論にも取り入れてみたいと考えています。
少し余談になりますが、デンマークをはじめとする北欧諸国では「democratic(民主的で、みんなのために開かれている)」という言葉が日常的によく使われています。
IKEAの掲げるスタンスである「Democratic Design」をはじめ「democratic eyewear(みんなのためのメガネ)」や「democratic coffee(みんなのためのコーヒー)」といったお店も存在しており、そうした価値観が社会の隅々にまで根付いている印象を受けました。
一方で、「みんなのための」という理想が利他や団結の精神を育むと同時に「”みんなのために”こうでなければならない」といった強い同調圧力にもつながっているように感じられました。
このあたりは非常に繊細で難しいテーマだと思います。
また、デンマークの社会構造にもその哲学が表れています。
現地では、専業主婦というライフスタイルはほとんど存在せず、結婚後も共働きが一般的です。
これは「選択肢があって、個々が自由に選んでいる」というよりも、人口規模や社会保障の仕組み、価値観の前提から、そもそも「専業主婦」という選択肢自体が現実的に成立しにくい社会的背景があるようでした。
つまり、自由な選択が可能に見える中でも、実際には社会構造によってある程度その方向性が決定づけられている。
そうした意味でも、自由と制約のバランスは、社会の設計思想と深く関わっているのだと実感しました。
締め
もちろん、デンマークと日本では社会的背景や制度の成り立ちが異なります。
しかし、だからといってデンマークの考え方や仕組みから学べることが何もないわけではありません。
たとえば、土屋は大きな会社ですが、デンマーク全体の人口(約500万人)と比べれば、より小回りが利く存在です。
また、国の政策決定に比べれば、企業内での意思決定にははるかに迅速性があります。
もちろん、複雑に絡み合いながら構築されているデンマークの福祉制度そのものを、土屋にそのまま取り入れることは現実的ではありません。
ただ、その根底にある“哲学”を軸とした介護職の地位の確立という考え方は、私たちにとって実践可能な第一歩ではないかと感じました。
なぜ私がこの点に注目したのかというと、日本では「哲学」という言葉に対して、どこか重々しく、堅苦しい印象が根強く残っているように思うからです。私自身もそうした印象を持っていました。
日本では、哲学が「専門的な学問」として輸入された経緯があるため、「難しそう」「敷居が高い」といったイメージが広く共有されてきました。
さらに、日本で語られる哲学は西洋哲学が前提となっている場合が多く、それに触れることなく企業や個人の哲学について語るのは、少し難易度が高いとも感じています。
実際、誰もが何らかの「自分の哲学」や「会社の哲学」を持っているはずですが、体系的に哲学に触れていないと、それを言語化し共有するのは容易ではありません。
一方、ヨーロッパでは、古代ギリシャから始まり、デカルト、ロック、スピノザ、カント、ヘーゲル、ショーペンハウアー、そしてデンマーク出身のキルケゴールといった多くの哲学者が、人々にとってより身近な存在です。
哲学のもつ力が、生活の中に自然と浸透しているように感じました。
もちろん、こうした文化的背景があるからこそ、ヨーロッパでは哲学が自然に機能している側面もありますが、日本でも、東洋思想を含めた様々な土台があります。
これらの土台をうまく活かすことで医療や介護の現場に取り入れていける余地があると考えています。
土屋の代表である高浜は、慶應義塾大学文学部哲学科の出身で、西洋哲学の素養も深く、独自の哲学・美学もあります。
社内外への発信も積極的で、インタビューや動画を通じて、日頃から言葉や考え方を広く伝えています。
ただし、どれほど明快な哲学を掲げていても、それを組織に浸透させ、咀嚼するためには、一定の時間と土壌が必要です。
だからこそ、高浜の思想を軸にしながら、社内で哲学を共有し、理解を深める取り組みが重要だと考えています。
それによって、土屋のスタッフ一人ひとりが、自信と誇りをもって医療やケアのサービスを提供し、その姿勢が社内外に受け入れられていくような文化を、私たちから少しずつ築いていけるはずです。
そして、その流れがゆくゆくは日本の介護業界全体にも広がっていけば、非常に意義深いことだと思います。
CMO・PRという立場として、今後も引き続き社内に向けた哲学の発信や、それを体現する土屋のあり方について議論を深めていきたいと考えています。
私個人としても、あらためて哲学を体系的に、実践的に学び直し、学びを現場で活かすことで、会社に貢献していきたいと思っています。
株式会社土屋について
株式会社土屋は、高齢者や障がい者の方々がより良い生活を送るための介護サービスを提供し、また、さまざまな社会的ニーズに応えるための事業を展開するトータルケアカンパニーです。
■会社概要
会社名:株式会社土屋
所在地:岡山県井原市井原町192-2久安セントラルビル2F
代表取締役:高浜敏之
従業員数:2,766名
設立:2020年8月












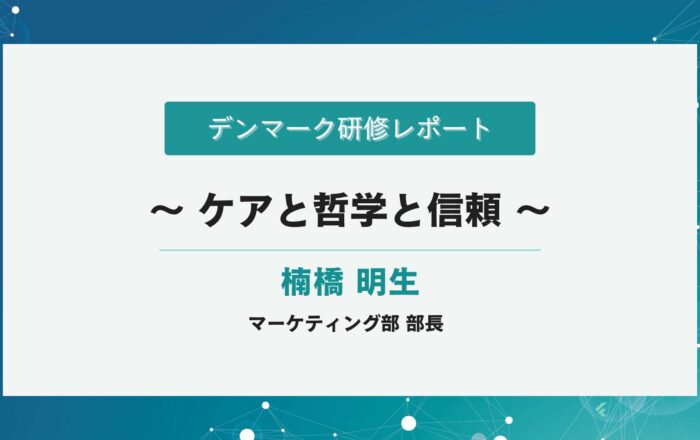

-1.png)




















