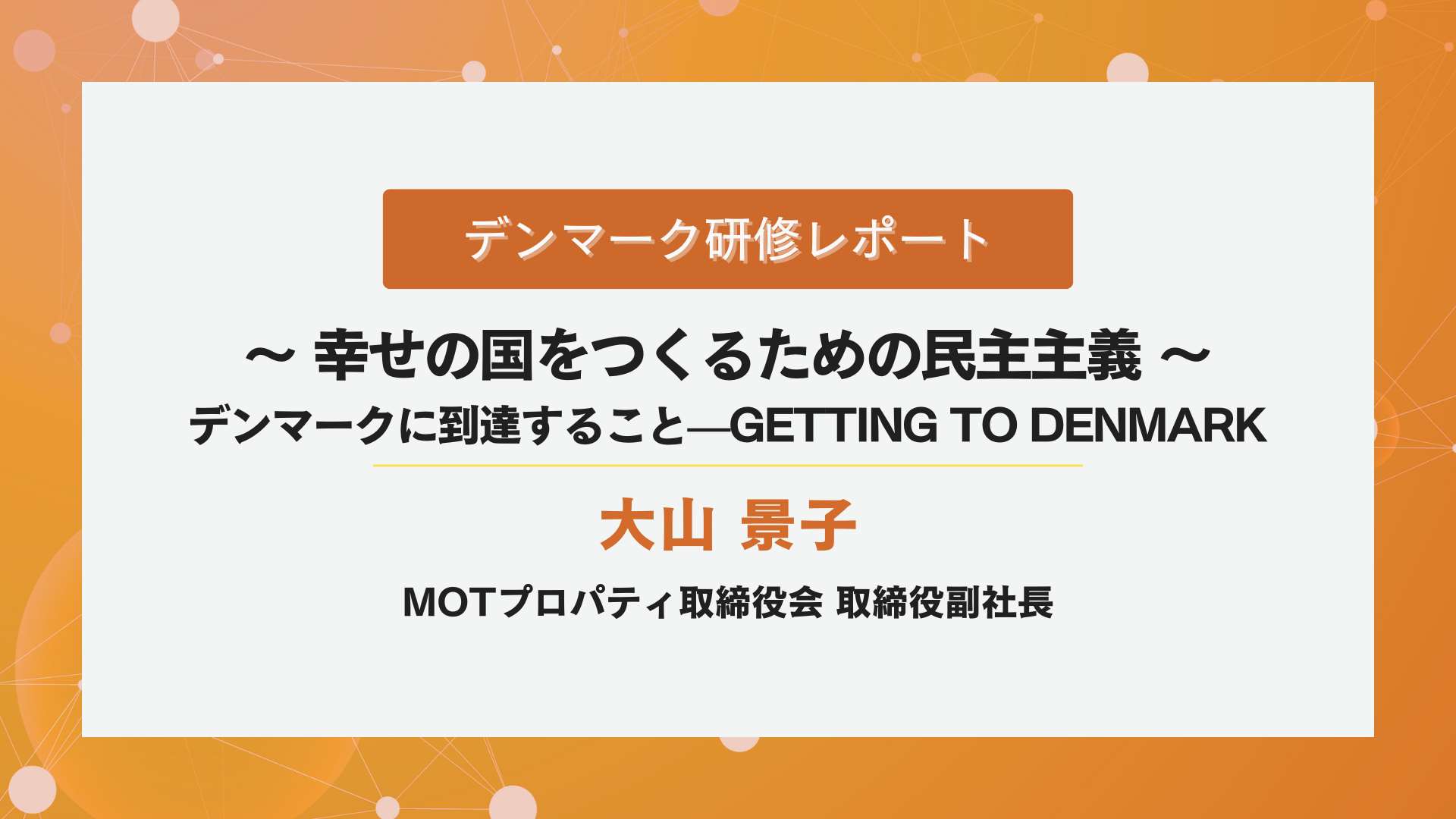
『幸せの国をつくるための民主主義
デンマークに到達すること—Getting to Denmark』大山景子(MOTプロパティ取締役会 取締役副社長)
出発前、はりきって図書館からどっさり本を借りてきた。デンマークはどんな国か予習をしよう。
税率が高く、教育福祉が充実しているらしい。
民主主義が根付き、女性の社会参画が当たり前で、子供たち一人ひとりの個性に応じた教育が、偏差値教育とは全く別の角度で手厚くなされるらしい。
経済格差がなく、人との関わりや、日常的な美が大切にされているらしい—一読したが、ピンとこない。
その在り方自体で日本のいびつな社会をお説教しているみたいな、理想的な社会。
本当にそんな国があるのだろうか?
半分以上信じていなかった。が、デンマークに行ってみたら、それらはうそでないことがよくわかった。
そこには穏やかな、優しい人たちの顔があった。
デンマークは人口600万人(日本の20分の1)、九州くらいの国土だが、グローバル企業も多数あって豊かな国力を持ち、国民一人あたりのGDPは世界トップ10に入っている(9位、日本は34位)。
デンマークに滞在して驚いたのは、とにかく働いている人が優しいこと。
ホテルの受付の人が優しい、空港のお掃除の人が優しい。
にこにこ笑顔で、オープンマインド。
「Yeah!」の、他の国ときっと違う(と思う)、なんとも肯定感のただようイントネーションが印象的。
「Tak(タック、ありがとう)!」にこっとして、気のいい感じでいう仕草がすてきだ。
「どこから来たの?今日はどうしてきたの?楽しんでいってね。」
コペンハーゲンで、レジで前に並んだ人が、まるで古くからの友人のようにお店の人と会話を楽しんでいる。
そのやりとりで、おみやげものを何回か買いそびれたほどだ(いいかんじなのでまったく待たされてイライラするような余地はない)。
デンマークのエレベータは、開くボタンはあるけど、閉じるボタンはない。
なぜなら、閉じるまでの時間、待っていればいいだけの話だから。
いつも焦らされ、きゅうきゅうとした生産性にさらされた日本の日常を思い出した。
2025年の幸福な都市ランキングで、コペンハーゲンは1位に選ばれている(ハッピーシティハブ)。
電線も商品を喧伝する広告看板もない。
戦争や地震などの破壊を潜り抜け、突貫工事された日本のカオティックな街並みと違い、伝統ある自然な街並みはどこをきりとっても美しい。
街を歩く人の数はほどよく、日本の雑踏みたいな風景はない。
福祉施設でも実感したが、人一人当たりにあてがわれる空間が広く、支援が手厚い。
生活大国とはこういうことか、と実感した。
高税率、高福祉の国デンマークは、国家予算の大半が生活に関わる社会保障費にあてられるという。
いくつかの福祉・教育施設をめぐり、幸せや生活の豊かさにむかって社会全体が合理的に設計されているのを実感した。
ジャパン・アズ・ナンバーワンの時代も経験したはずなのに、日本人の生活は豊かな幸せなものにむかっていっているのだろうか。
わたしたちの慣れ親しんだ過剰な競争は何のためのものだろうと、知らないうちにしみついた価値観を問い直される。
デンマーク出身の社会学者、イエスタ・エスピン=アンデルセンは福祉国家の種類を3類型に分類する。
市場経済が中心に据えられる自由主義的なアングロサクソン諸国、階級や職域に基づき、家族が福祉の供給主体となる保守主義的な大陸・ヨーロッパ諸国。
そしてデンマークなどの北欧諸国は社会民主主義的とする。
幸福度の高い北欧諸国は、高水準の福祉を平等かつ普遍的に、個人を単位に、国が主体となって行う。
滞在中、行政や現場の方から、「リソースresource」という言葉を数多く聞いた。
個人のもつ労働力や能力は社会資源として、民主主義によって選ばれ(投票率が高い!)、構成された「大きな政府」によって、幸せな社会構築のためにわりふられ、機能していく。
デンマークでは13歳ごろから専門的な進路指導員が、その人のリソースとむきあった進路指導を手厚くするらしい。
そこにはブルーカラーよりホワイトカラーといった、給与格差に基づく貴賤観念もなさそうだ。
とりわけ、福祉や教育職についた方の誇りや専門性がまぶしく感じられる。
解雇もされるようだが、将来の雇用も生活も保障されているため(フレキュシキリティ)、働く人の顔がいきいきしている。
「ペタゴー」や医療ケアができるヘルパー、相互に専門性を高める会議や、人権を守るための国による監査、組織の立て直しの仕方など、日本の福祉にもアイデアを援用できるのではないかと思えるおもしろいポイントはたくさんあったが、なにより私は「国のかたち」に衝撃を受けた。
かのフランシス・フクヤマは2010年ごろの著作でデンマークを自由民主主義の到達点としてとらえた。
欧米の社会科学者の中で「デンマークに到達すること(Getting to Denmark)」を目指しての議論がなされているという。
日本では1980年代からの新自由主義的な流れが「小さな政府」への政策を推し進めてきた。
戦争に走った全体主義的な政府への不信感から「大きな政府」へのアレルギーがあり、左派もそちらの流れに与してしまうところがあったという。
「民主主義(デモクラシー)」の肌触りの違いも感じた。
デンマークで感じた民主主義は、権力に対して個を主張するといったカウンター的なものでなく、個が全体への責任を社会主義のように慮る、本来的な主体としての創造の重みをもったものだった。
公教育においては、競争よりも対話やプロセスが重視され、民主主義の担い手としての主体が育てられていく。
(余談だが、ふらふらして生きるふうてんの寅さん。寅さんは個人のリソースを持続的に最大限に発揮できているだろうか? デンマークでは、寅さんは女性とのコミュニケーション能力やばななのたたき売りなどの長所を生かし、ちゃんと持続可能な就職をさせられそうだと思った。勝手な曲解かもしれないが、個人がふらふら生きる美学がなりたたない、そのような合理性、義務のシビアさも感じた。)
2000年スタートの介護保険制度で、民間が介護を担う役割が大きくなった。
わたしたちは民間の介護事業者として、公的なサービスを担う責任を負いながら、同時に利益も出す必要性も課されている。
どの制度、システムも万全ではなく、現場から改善の提言を続けていかなくてはならない。
また原点となる介護を担う人のケアの感性は、制度に助けられていたり、反対に障害になっていたりすることはあっても、どの制度下であっても全人格的なものであり、普遍的なものなのだろう。
広井良典氏は、その著書『創造的福祉社会』において、限りない経済成長を追求した時代のあとに来るべきものとして、定常経済システムに基づく福祉社会を構想している。
現在の先進諸国は「生産過剰」が生じており、それが若年層の貧困や失業につながっているという。
逆にケア、コミュニティ、自然といった貨幣に換算されるのが困難であるような領域において、社会起業家の創造的な動きが起きている。
いま環境負荷の少ないケアのような労働を見直すべきであり、高福祉、高負担の社会モデルも、地域レベルで実践できるか議論されるべきとしている。
広井氏は、歴史をひもとき、いままで人類に訪れた経済定常化の時代とは、技術革新のない退屈な時代だったのではなく、ものの考え方がドラスティックに変化していく革命的な文化創造の時代であったという(狩猟採集から農耕へ、農耕から工業化社会へ)。
そうであれば、次に来るべき精神革命はどのようなものだろうか? 地球規模の環境問題、資本主義の課題の噴出、AIの発達とシンギュラリティなど、時代の節目を生きているであろうわたしたちは、その根本に「人」と「幸福」を中心に置きなおす勇気を求められていると思う。
わたしたちは、デンマークで生きることはできないけれども、それぞれがデンマーク的なものを実践・創造していくことはできる。
ケア現場に関わるわたしたちが、システムを創造するために日本のシステムを相対化し、一番大切なものを語る自信と勇気を持つために、今回の研修旅行はとても有意義であった。
滞在中、訪問したデンマークの公立学校の校長先生が、子供と関わる教育現場の人材に必要な要素をあげていた。
「①きらきらしていること ②好奇心があること ③勇気があること」
あすでなく、10年後でなく、いま。
働きながら自分もきらきらすることが、子どもたちをきらきらさせていく先生の条件といえるのかもしれなかった。
きらきらした好奇心と勇気で、未来とむきあっていきたい。
そう思えたデンマークへの旅であった。
【主な参考文献】
- 『幸福のための社会学』豊泉周治著、はるか書房
- 『創造的福祉社会』広井良典著、岩波書店
- 東洋経済「新自由主義の生命力」が日本で根強すぎる理由 佐藤健志
- Newsweek 「脱成長? 生活大国デンマークへの日本人の片思い」河東哲夫
- Forbes 2025年「世界で最も幸せな都市ランキング」
株式会社土屋について
株式会社土屋は、高齢者や障がい者の方々がより良い生活を送るための介護サービスを提供し、また、さまざまな社会的ニーズに応えるための事業を展開するトータルケアカンパニーです。
■会社概要
会社名:株式会社土屋
所在地:岡山県井原市井原町192-2久安セントラルビル2F
代表取締役:高浜敏之
従業員数:2,766名
設立:2020年8月












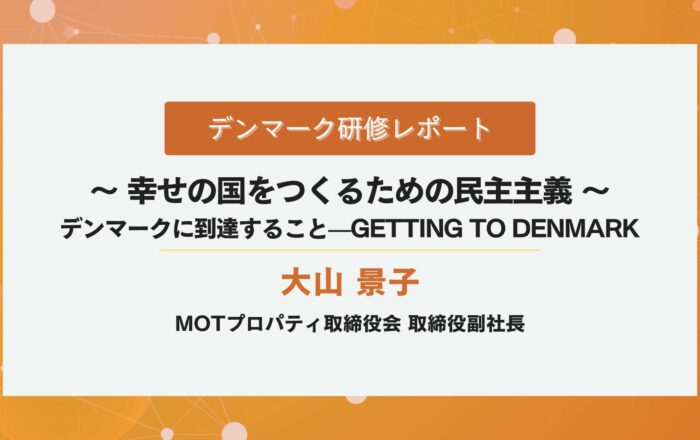

-1.png)




















