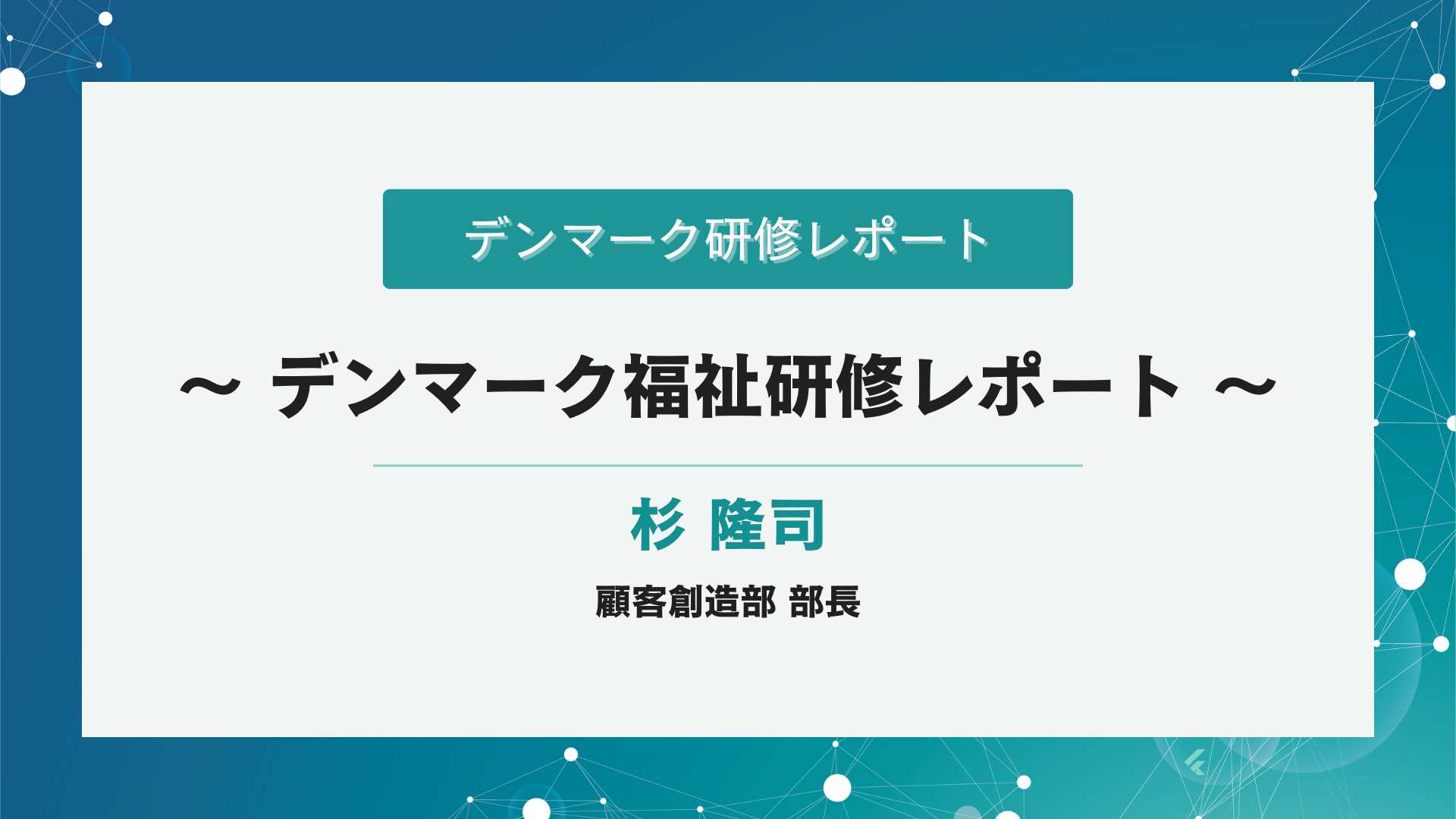
『デンマーク福祉研修レポート』杉隆司(顧客創造部 部長)
研修参加の動機
私の中では北欧・デンマークの福祉制度に対して「憧れ」という感情を持っておりました。
介護職に就く前から、北欧ヨーロッパ諸国は「福祉国家」として世界的に評価されていることは知っておりました。
介護福祉事業に関わるようになってからは、その意識は一層高まり、現場で働く中でも海外の制度や仕組みに対する興味は途切れることがありませんでした。
近年は、顧客創造部として外部向けに重度訪問介護制度や日本の介護制度について説明する機会が増え、「日本と海外の福祉制度はどのように異なるのか?」という素朴な疑問が再び私の中で大きくなっていきました。
ちょうどその時に、デンマーク研修の機会が提示され、迷わず参加を希望したことを今でも鮮明に覚えています。
研修内容と現地での気づき
初日に現地の福祉関係者による講義を受け、デンマークの行政制度や福祉の仕組みについて学びました。医療・教育・介護は「無料」ではなく、税金によって運用されていることへの認識の共有から始まりました。
国民全体が高い税率(所得税最大48%、消費税約23%)を負担したうえで成り立つ制度であり、日本のように老後資金や教育費を個人が準備する必要は少ない一方、デンマーク国民の税金の使い道や政治に対する関心は高く、選挙投票率は90%を超えるそうです。
その概要を聴くだけで、デンマークの制度の単純模倣は難しいとの理解に至りました。
デンマークでは民間の医療機関がほぼ存在せず、地方議員も基本的には無給で、自治に対する熱意がある市民が担っているとのことでした。
介護職は専門職としての色が強く、当然の如く有資格者制度であり、日本よりも取得に期間を要するsosu helper(1年2か月)、sosu assistant(1年8か月)の2段階の資格制度が整備されていました。
また、「ペタゴー」という支援専門職が、要支援者に対する精神的・社会的背景への支援を通じて、看護師や介護士といった専門職の業務負担を軽減する役割を果たしています。
日本のように医師(主治医)が頂点、次に看護師、介護士が続くといったピラミッド型の組織システムではなく、専門職が各々の職務を全うすることで、本人中心のフラットな支援体制が構築されていました。
訪問したオーデンセ州では福祉部門が7課に分かれておりました。
日本のような障害や介護の区分認定制度のようなものはなく、担当課やソーシャルワーカーが申請者の個別ニーズに応じた支援先を促しているそうです。
日本のように家族が第一の支援者とされる文化ではなく、国家全体で支える体制が確立されています。
一方では、労働者の権利保護や労働環境の整備も制度内に組み込まれており、「平等な支援」の概念の広がりを感じました。
研修中には、就労支援施設やグループホームの視察にも参加しました。
障害のある成人を対象にした就労支援施設では、早期年金を受給しつつも少しでも働ける方には労働参加を促す制度が整っており、実際に当事者との会話でも、「自分の出来ることで就労し、国に税金を収めることで私も社会参加をしているんだ」という発言を耳にし、本当の意味での「義務と権利」を果たしていると感じました。
施設内では音楽・清掃・木工・グラフィックデザイン・裁縫、創作活動など、個々の能力に応じた多数の活動が行われていました。
私は日本からのお土産として、自身が事業担当している就労B「あぐり工房」にて製作している「さをり織り」のネコのコースターやクリップを持参しておりました。
同じ創作部門として先方のご利用者に贈答させて頂いたところ、あぐり工房のスタッフが機転を利かせてデンマーク語でのメッセージカードを作成し同封しており、このカードに非常に喜んでくれました。
「機会があったら、あぐり工房に行ってみたい」とも話してくれました。
特別支援学校では日本との違いを複数感じました。
クラスの教員に加え、ペタゴーや療法士、介護士も連携して支援をしていました。
また教員とは別に、一人一人の生徒に「コンタクトパーソン」と呼ばれる担当が約3年間就くそうです。
教員以外にも複数の存在で生徒を支援し続け、意思決定も多職種によるチーム会議で行われており、日本に比べて制度的に成熟していると感じました。
しかし、複数の施設を見学する中で、どこの場面でもデンマークでは全てが理想的に運用されているわけではなく、制度的な限界や現場の負担も存在しているとも耳にしました。
私の中では既に出来上がっているシステムであると思い描いていただけに、現地をリアルに体感し現地での課題も知ることが出来たことで、北欧と日本の福祉システムを比較し、日本式の介護の良さへ目を向け直すきっかけとなりました。
まとめ
今回、世界有数の福祉国家と称されるデンマークでの研修に参加することができ、福祉制度の理念と現実、その運用の両面に触れる非常に貴重な体験となりました。
参加前は「北欧=理想的な福祉」という憧れのような感情を持っておりましたが、実際に現地の制度・現場・文化に触れる中で、それだけではない深い学びと気づきがありました。
デンマークでは、国家が主導し、福祉が公として組織的に体系化されているという印象を受けました。
すべてが制度通りに運用されているのではなく、各機関の責任者に一定の裁量と責任が委ねられており、現場ごとに最適な判断が行われていることに驚かされました。
また、労働者、特に介護士に対しては、しっかりと「権利」と「義務」が制度として確立されており、そのバランスの中でのマネジメントは非常に高度であるとも感じました。
福祉施設、行政機関、教育現場など、どこをとっても同様の構造が根づいており、「社会全体で支える福祉」が実践されていました。
一方で、研修を通じてあらためて感じたのは日本の良さでした。
例えば、都市部でも車道はアスファルトで整備されているものの、歩道は石畳が多く、高齢者や車椅子の方にとって必ずしも快適とは言えない環境も存在していました。
「福祉国家」として制度が整っている一方で、インフラ面や生活環境において、日本のほうが配慮が行き届いている場面もあると実感しました。
これは、日本とデンマークの社会構造や文化背景の違いによるものでもあり、制度だけを比較するのではなく、地域ごとの事情や生活者視点を含めた全体理解の重要性を再認識するきっかけとなりました。
またデンマークは縦割りの様相で組織的に動くのに対し、日本においては行政の管轄でありながらも、利用者対応はそれぞれの施設や事業所に委ねられています。
こうした日本らしさでもあり特徴でもある「自由さ」と「曖昧さ」が、実は「柔軟性」として現場で機能しています。
明確なルールに基づいた北欧型の仕組みは安定感がありますが、対応や判断に一定のゆとりがある日本的な支援のあり方にも、独自の優れた価値があると再認識しました。
世界中の多くの国々にとって、デンマークのような国家主導の福祉制度は「そのまま模倣できるもの」ではありません。
制度の設計から運用まで一貫して国家がリードしているからこそ成り立つモデルであり、導入には政治的・文化的な背景が必要不可欠です。
その点において、日本の介護制度は民間主導で発展してきた実績があり、撤退を余儀なくされた事業者も少なくない一方で、日本型の介護はこれから介護の問題が生じる世界各地においては“輸出可能なモデル”になり得るのではないかという可能性も感じました。
また、今回の宿泊先であった「ホイスコーレ」ののどかな環境や、学校で出会った若い生徒たちが福祉に対して強い想いを抱いている姿に触れ、自分の中にこれまで感じてこなかった感情が芽生えました。
それは“もっと介護を広く世界に届けたい”“日本の介護を海外に紹介するような仕事がしたい”という、願望というより「欲望」に近いものでした。
このような感情を抱くのは初めてであり、今後の自分の人生やキャリアを考えるうえで大きな転機になるような気がしています。
そのためにも、まずは今任されている仕事を1つ1つ丁寧にやり切り、語学を含むスキルの習得にも取り組みながら、様々な経験を積んでいきたいと考えています。
今回の研修は、「憧れ」を「現実」へと変える第一歩となりました。
そして「現実」を踏まえた上で、「次に自分はどう動くか」を考えさせられる機会でもありました。
この貴重な体験を糧に、今後は国際的な視点を持ちながら、福祉に関わる一人として何ができるのかを考え、行動していきたいと思います。
株式会社土屋について
株式会社土屋は、高齢者や障がい者の方々がより良い生活を送るための介護サービスを提供し、また、さまざまな社会的ニーズに応えるための事業を展開するトータルケアカンパニーです。
■会社概要
会社名:株式会社土屋
所在地:岡山県井原市井原町192-2久安セントラルビル2F
代表取締役:高浜敏之
従業員数:2,766名
設立:2020年8月












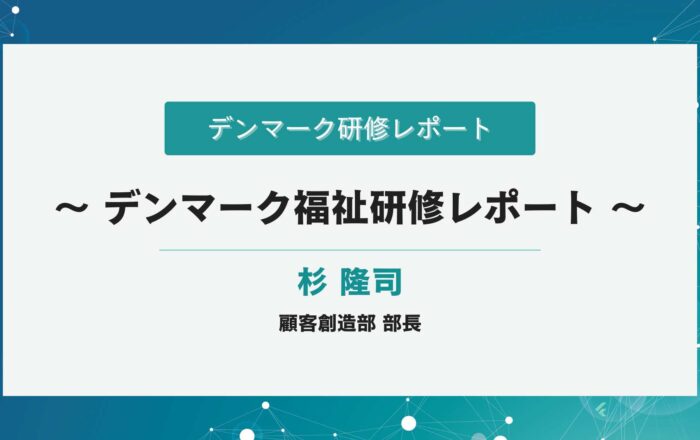

-1.png)




















