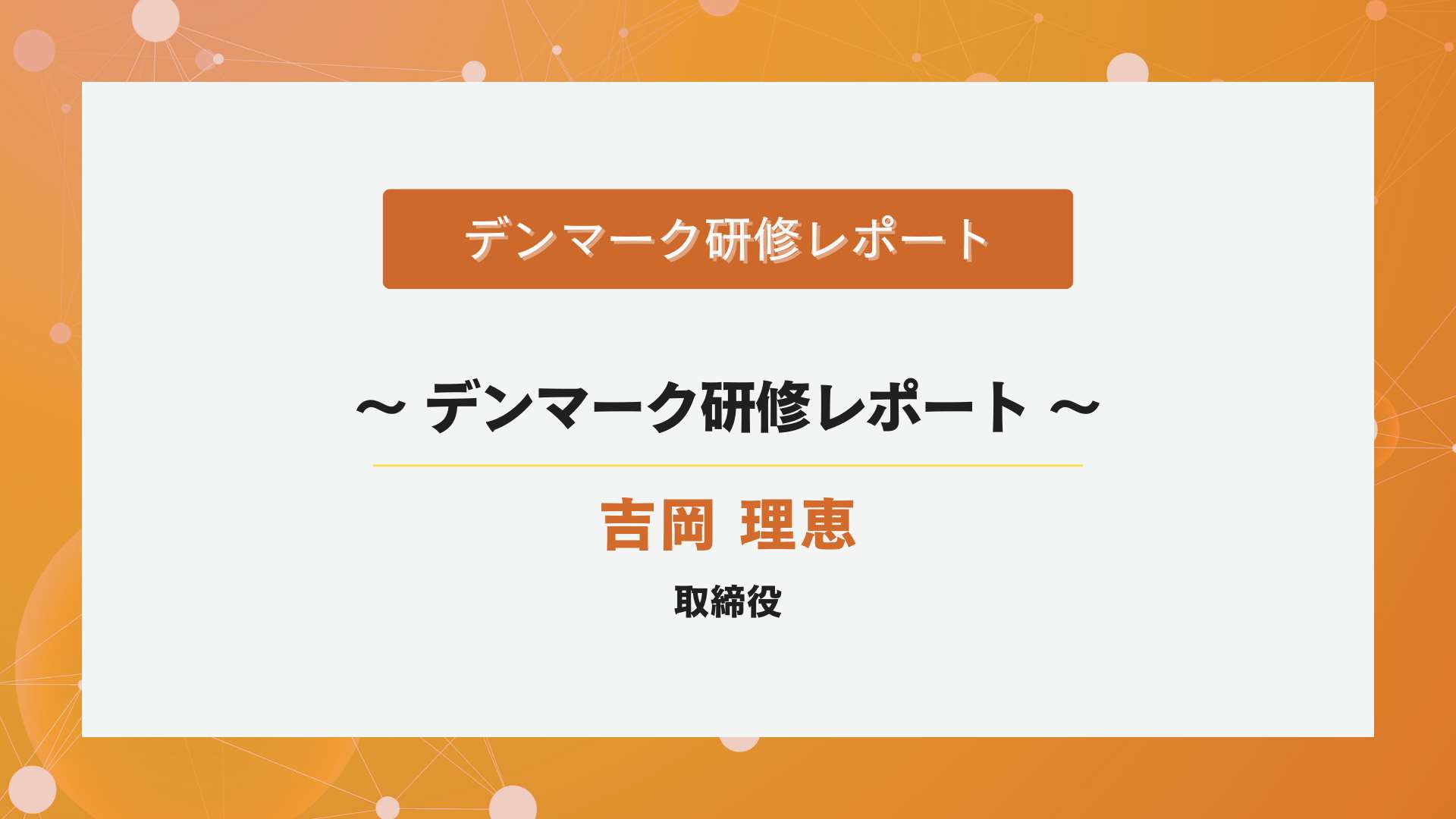
『デンマーク研修レポート』吉岡理恵(取締役)
本研修の話が最初にあったのは昨年の秋でした。
土屋グループを代表して研修のためにデンマークに渡航するということに、嬉しさを上回る戸惑いがあったため、それを払拭するくらいの何かを得てこなければという思いがありました。
そのために何か目的をもってこの研修に参加しようと思い、あれこれ考えた末に、本研修における私個人の目的を、幸福度No.1の国でありかつ土屋の原点でもあるデンマークで土屋グループのCSR活動の方向性を改めて考えること、としました。
これは、デンマークが常に幸福度ランキング1位を争っている国と評されているのを、研修のオリエンテーションに参加するまで知らず、かつ世知辛い日本は55位だということに、この差を生んでいるものは何なのか単純に興味・関心が湧いたのと、
デンマークが土屋の原点であるという点は、土屋グループのメイン事業が重度訪問介護であり、その重度訪問介護は、デンマーク人のバンク・ミケルセン氏が提唱したノーマライゼーションの思想と深い関わりがあるためにそのように思いました。
バンク・ミケルセン氏は第二次世界大戦中にナチスの強制収容所に収容された経験があり、戦後公務員として知的障害者の方々の支援に携わることになったとき、当時の知的障害者の方々の暮らしが、
強制収容所のそれを彷彿させる非人道的なものだったため、障害のある人もない人も平等に暮らせる世界を作るというノーマライゼーションの思想を提起した功績者として知られています。
そしてノーマライゼーションは、日本においては自立生活運動として安積遊歩さんや中西正司さんらによって担われ、また府中療育センターにおける新田勲さんや三井絹子さんらによる抗議運動を経て、
障害を持つ方々が地域で自立して安心・安全な生活を送るためには24時間の見守りを含む介護サービスが提供されるべきだとのことで、重度訪問介護ができたというのが、私がこれまでに学んだことでした。
現在の私の役割は土屋グループのCSRの取組みを推進することであり、グループ全体の所属を問わない組織を作り、ステークホルダーからの信頼を獲得することがその責務となっています。
とはいえ、福祉・介護の株式会社で本業以外の社会貢献活動をどのように実施するかはなかなか悩ましいと感じており、今回の研修に参加することで、その解決方法とまではいかなくとも、何か方向性として目指すものが浮かんでくることをこの研修に期待したいと思いました。
研修の地、デンマークはスウェーデンと海を隔てて接しており、ドイツとは地続きの国境があります。
人口は約600万人で、国土面積は378,000㎢、九州と同じくらいの面積だそうです。
通貨はデンマーククローネ(DKK)で、1クローネが約20~21円の為替レートでした。
主要産業は、海運業、再生可能エネルギー、医薬品などだそうです。
また、自転車文化といった感じで駅には自転車置き場が必ずあり、電車内にも自転車の駐輪区画がありました。
自転車ではなく電動キックボードに乗っている人も目立ちました。
物価は高いと聞いていましたがその通りで、空港をはじめ各地に店舗展開をしていたコンビニエンスストアのセブン・イレブンのカフェラテが38DKK(約760円)でした。
電車は切符を買うこともできますが、専用アプリまたは専用カードにチャージすることで電車賃を払い、駅に日本のようなゲートがないため、時折見回りに来る駅員さんにQRコードや切符を提示して無賃乗車ではないことを示す必要がありました。
デンマークの首都コペンハーゲンは、現在も時折使われているという城や宮殿がいくつかあり、運河にはたくさんの小型船、そして石畳の街並みと煉瓦造りのアパートメントが境目なく並ぶ一方、
地下鉄は自動運転で運転手がいなく、また乗り場へ続くエスカレーターもどこか近未来的な感じがして、街全体が洗練されていてディズニーランドのような風情がありました。
そしてコペンハーゲンから電車で約1時間半のオーデンセというデンマーク第三の都市にある、ノーフュンス・ホイスコーレの短期研修プログラムで1週間の研修が行われました。
ホイスコーレとは、デンマークで約200年の歴史がある全寮制の民間教育機関でデンマーク内に70校弱あるそうです。
成人であれば入学に条件はなく、3か月を1タームとして学生たちが個々のテーマを学んでいるそうです。現在は50名ほどの学生がいて、日本人の学生も10名ほどいました。
研修は、始めにデンマークの社会保障と社会環境を座学で学び、以降はオーデンセの障害福祉課、支援を必要とする方々のグループホーム・就労支援施設・在宅支援施設・特別支援学校、そして地元の小学校を視察させていただき、間に一日隣国ドイツへ観光するスケジュールでした。
全体を通して感じたことは、あくまでも感覚的なものであることを前置きしますが、デンマークは、精神面、物質面、環境面における豊かさのレベルが日本より数段上ではないかということでした。
もちろん日本も豊かであることには間違いがないのですが、全体的な充足度に個人差や格差が著しいのが日本で、最低ラインが高いレベルで保たれているのがデンマークであるといった感覚がありました。
デンマークは医療・教育・福祉介護が公共機関によって担われている国です。
当グループで例えれば、代表取締役も各部門のマネージャーもアテンダント(介護職員)も全員が公務員ということになります。
デンマークの公務員率は約30%だそうですが、この値を日本のそれと比較しようと思いざっと計算したところ、日本の公務員総数に医療・教育・福祉介護従事者の数を足して人口で割ると7%という値となりました。
粗雑な算出と比較にはなりますが、国全体の社会保障に対する投資がデンマークは日本の4倍強といえるかもしれないと思い、ここに両国の差が一部見えるような気がしました。
税金は高く消費税は25%、人によっては給与の半分近くを納税することになるそうです。
それゆえということになるのだと思いますが、国民の政治に対する関心は高く投票率は90%になるとのこと。
市長には報酬が払われているそうですが、議員は無報酬のため、仕事終わりの夜に議会が開催されているそうです。
確かに自分の納めた税金が高いとそれがいかに使われることになるかは関心が大きいでしょうし、中には実際にどのように使うかを自ら決めたいという人も増えるような気がしました。
納税率が高いことで政治への関心と関与が高まり、結果として誰もがよい暮らしができる、というWin-Winの構造ができているようにも思いました。
また、行政機関内での政策実行に対する責務は絶対で、これを実施できなかった場合の責任者への追及は厳しいそうです。
同様のことは各施設の施設長の方々もおっしゃっていて、法律で決められた国民・市民の権利を施設が守れなかった場合は、施設長は進退を問われてしまうそうです。
これらは日本でも同じなのだろうと思いますが、異国の地で聞いたせいか、説得力が違うように感じられました。
そして研修中にいろいろな方とコミュニケーションを取る時間が増える度に、デンマークにおける人間の価値に対する捉え方や権利保障に対する感覚が日本とは違うように感じました。
誰もが平等であり、一人一人には存在する価値があるのだから、その人が一般的な暮らしをする権利は保障されなくてはならない、というフレーズは研修期間中どの視察先の方々からも聞いたことでした。
これは日本でもよく見聞きするのですが、日本で聞くときは、そうはいってもね、という理想と現実の調整弁が含まれているような気がして表層的にも感じてしまうことがあるのですが、今回デンマークで出会った方々のお話を聞く限り、この言葉に対する国と国民の本気度が違う、といった印象を受けました。
この本気度の違いを感じたのは、実はバンク・ミケルセン氏の知名度が思いのほか低かったからでした。
なぜデンマークに来たのか、という問いは何人かの方から受けましたが、ノーマライゼーションを提唱したバンク・ミケルセン氏の母国だから、という返答をしたところ、質問者がバンク・ミケルセン氏を思い出すまで間合いがあり、こちらが拍子抜けしてしまったというところがありました。
在デンマーク35年という通訳兼コーディネーターのモモヨさんによると、ノーマライゼーションという言葉自体が、逆に何がノーマルで何がそうでないかの区別を連想することに繋がるため、この言葉自体に違和感があるとのことでした。
少なくとも戦後には障害者の方々への差別感情もあったはずなのに、そこから発したノーマライゼーション自体が過去の遺産ともいえる扱いとなっていることに、この国の強さを体感したような気持ちになりました。
また、あくまでも私の推察ではありますが、デンマークは一人一人の権利保障を本気で考える一方、権利主張の強い人に対する対処方法も同等に確立させていったのではとも思いました。
権利主張の強くなってしまう人がいる、ということもまた視察先の方々の誰もがおっしゃっていたことであり、この業界あるあるがデンマークでもあるあるだったことにほっとした気持ちを抱きつつも、
そうした事態になったときにどうしているか、またどのようにしたら収拾が早いのかについて先を見据えた対処法も確立されている気がしました。
すべてをキャッチできたわけではありませんが、権利主張の強い人に対する対応方法はざっと次のようなステップを踏んでいるとのことでした。
まずは専門職が参集してクライアントの話を聞きそれぞれの立場から専門的な意見を述べる、簡単に合意形成ができないときは何が着地点なのかの期待値を一致させる、それでも煮詰まったら理念に立ち返って考える。
これも同じようなことは日本でも聞いた覚えはありますが、このステップが確立されていて施設の形態を問わずこれを当たり前のこととしてこなしている、という点が違うと感じました。
本当にこんなことができるのかなとも思いましたが、自然体でお話ししてくださったことに、疑うということが逆に違うような気がしました。
そして実はデンマークには実践的な職業訓練制度があり、これが絶対という社会構成だそうです。
この制度のことは予備知識として渡航前に頭に入っていたのですが、今回の研修での見聞を足すと、この職業訓練の教育プログラムが充実していて、学生は座学と実習を通して専門家としての心構えを徹底して叩き込まれるのでは、と予測しました。
日本では自分が介護の専門家であるかどうかは実は自分が決めているのではと思う節がありますが、デンマークではそれが職業訓練の場で主観的にも客観的にも自覚を持てるように教育されているように感じ、もしそうだとしたら、介護職として働きやすいだろうなと思いました。
また、この職業訓練制度は介護職に限らないため、どの職業に就いたとしても他の職種とフラットな関係が作りやすいように感じ、結果として社会に好循環が生まれるように思いました。
そして研修期間中一番よく聞いたキーワードではないかと思うのが、民主主義(democracy)です。
民主主義とは国民が積極的に政治に参加することを意味する言葉、というイメージを持っていましたので、このワードが出てくるたびに少々違和感があったのですが、デンマークで聞いた民主主義とは、話し合いによる合意形成を得ること、という意味合いが強いものだったのではとこの旅を振り返りながら思いました。
そう思うと、期待値を一致させるという話し合いの平行線を一つの頂点にまとめていく作業も、民主主義と同列になり、私の頭の中の整理に一歩近づくような感じがしました。
さらに、共通理念を掲げているところも圧巻という感じがしました。
特に介護の仕事はサービス業のため、何が正解で何が不正解なのかが時と場合によって180度異なります。
かといって何でも自由にやっていいというわけにもいかないため、常に矛盾に囲まれてしまうという特有の構造があると思っています。
この暗中模索の状況に必要なのが北極星のような役割を果たす共通理念だと思っていたのですが、デンマークにおいてはそれさえも整備済みであり、かつ理念を職員がともに考える会議も定期的に行っているとのことでした。
理念と理念勉強会については、介護分野だけでなく、ホイスコーレにもあるようなので、組織や団体においてはこれらを整備することが当然となっているのかもしれないと思いました。
また、視察先の施設はどこも一人当たりの行動可能なスペースが広いと感じました。
グループホームの1部屋は40~50㎡あり、中庭も広く野ウサギがいたりトランポリンが設置されていたり、棟と棟の間隔もゆとりをもって建てられていました。
オーデンセが郊外の都市だからかもしれませんが、人が生活するうえでの他人との物理的距離間が広く保たれていて、ここにも豊かさを感じました。
山もなく地震もない土地柄のせいか、忘れたときにやってきて何もかも奪っていく自然災害への備えが、常に喫緊の課題ではないということが、どこかこの国の豊かさに幅を持たせているのかなとも思いましたが、これは考えすぎかもしれません。
研修中、視察や意見交換の機会が増えてきたとき、みんなは一人のために、一人はみんなのために、という言葉をふと思い出し、デンマークにおいては、国は国民のために、国民は国のために、と置き換えてもおかしくないような社会になっている感じがしました。
これは双方に強い絆のような信頼関係があると思ったからであり、税金は高いけれどもそれ以上のリターンがある、相互監視体制のようなところもあるけれど決して見捨てられることはない、という安心感があるように感じたからでした。
だから常に幸福度最上位の国なのかと思いつつ、日本の幸福度をどうするということについては何も言及できないものの、土屋グループにおけるステークホルダーの幸福度はもしかしたらデンマークを習うことで上げることができるかもしれないと思いました。
私の渡航目的は、幸福度No.1&ノーマライゼーション発祥の地で土屋のCSRの取組みを再考する、でした。
デンマークは素晴らしい、と思う点は多々ありましたが、信頼関係の構築を表層的な言葉に留めずに地道に目指していくことは土屋グループに還元できることかなと思いました。
そのためにすべきことは、面倒なことを放置しないこと、要請に応えることで変化を感じてもらうこと、これをするためのトレーニングを重ねること、そしていつかできるという希望を持ち続けることではと思っています。
そうすることで、土屋グループとそのステークホルダーとの信頼関係が少しずつ違うものに変わっていく気がしています。
帰国から一日が過ぎるごとに、現実だったデンマークの日々が少しずつ思い出に変化していっている今、あの時学んだことはこれだったと思い出せるようにこのレポートをしたためています。
デンマークはユートピアでもなく、日本がディストピアでもないのですが、今回の研修旅行がなかったら知ることができなかったことは山ほどありました。
また、このレポートに書ききれなかったこともたくさんありますが、この先何かの変化がこれをきっかけだったと振り返れたら、参加した真の価値が生まれるだろうと思います。
最後に、この度は貴重な研修旅行に参加させていただき、誠にありがとうございました。
研修の受入機関であり座学とコーディネートと通訳とマルチに対応してくださったノーフュンス・ホイスコーレ副校長のモモヨ様、研修の企画をしてくださった斎藤様、中野様、そしてスポンサーである当グループの代表に心より感謝申し上げます。
ありがとうございました。
株式会社土屋について
株式会社土屋は、高齢者や障がい者の方々がより良い生活を送るための介護サービスを提供し、また、さまざまな社会的ニーズに応えるための事業を展開するトータルケアカンパニーです。
■会社概要
会社名:株式会社土屋
所在地:岡山県井原市井原町192-2久安セントラルビル2F
代表取締役:高浜敏之
従業員数:2,766名
設立:2020年8月












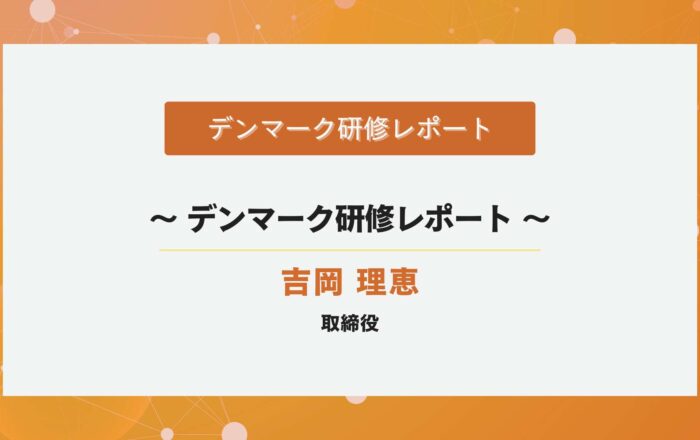

-1.png)




















