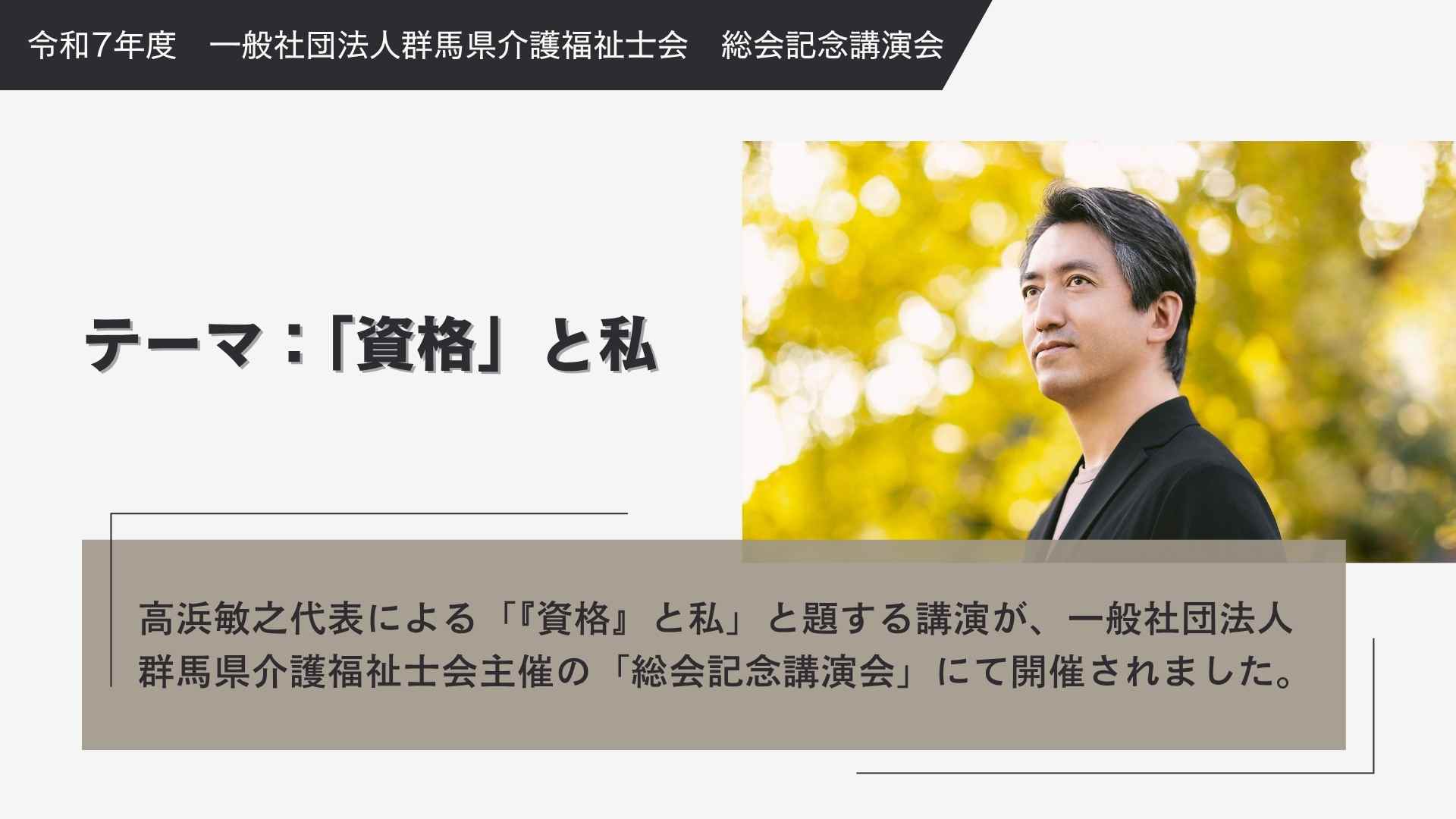
『令和7年度 一般社団法人群馬県介護福祉士会 総会記念講演会』~「資格」と私~
開催レポート
2025年6月21日、高浜敏之代表による「『資格』と私」と題する講演が、一般社団法人群馬県介護福祉士会主催の「総会記念講演会」にて開催されました。
自身の約10年に及ぶケアワーカーとしての立場から、一貫して介護に対するリスペクトに貫かれた本講演は、介護という仕事の価値や意味を十全に感じさせるものとなりました。
またメインテーマとして、土屋グループならびに重度訪問介護の歴史を通して、介護福祉士を始めとする「資格」の必要性やその功罪について語られ、なかでも介護業界における人材不足解消や、介護士の社会的地位の向上への手掛かりが示されるなど、未来の介護に希望を灯す、知見に満ちた講演となりました。

開催概要
■主催:一般社団法人群馬県介護福祉士会
■目的:介護福祉士という資格について考察する
■開催日: 2025年6月21日
■開催場所:群馬県社会福祉総合センター
■対象:介護福祉士会会員/非会員
登壇者
高浜敏之(株式会社土屋 代表取締役CEO最高経営責任者)
<講演内容のピックアップ>
介護業界の人材不足はいかにして解消できるか? ~ 土屋グループの急成長から見る資格要件 ~
当社は創業以来、わずか5年弱で資本金5,000万円、従業員数約2,800名、クライアント数1,500名以上となり、グループ企業もすでに12社となるなど急成長を遂げていますが、その最大の要因として、当社のメイン事業である重度訪問介護の「資格要件の低さ」があります。
医療的ケア(喀痰吸引・経管栄養)の提供に必要な資格要件「重度訪問介護従業者養成研修統合課程」がわずか20時間(2日間)の研修で容易に取得できるため、人材採用の際に「無資格大歓迎」と謳うことができ、多くの応募者の獲得につながっています。
一方で、募集要件を「初任者研修以上」とすると応募数はその10分の1ほどとなり、「介護福祉士募集」となると応募すらありません。
そのため、初任者研修以上の方を採用するには人材採用会社に依頼せざるを得ず、介護報酬の多くが介護士の給与の上乗せではなく、人材採用会社に流れていきます。
このように、経営者の視点で見ると、資格要件の高さと人材採用は反比例します。資格要件が低ければ低いほど従業員を多く抱えることができ、高ければ高いほど難しい。
現在、介護士不足の問題が社会問題化していますが、この問題を解決するのは簡単です。
資格要件を低くするだけで介護士不足問題は解決できますし、資格要件の入り口を緩和すると採用コストも減少するため、処遇改善加算を上げなくても賃上げはできると考えています。
<重度訪問介護の歴史から見る資格要件>
重度訪問介護は主にALSなど難病の方を対象とし、医療的ケアを担うため難易度が非常に高いものとなっています。
一方で、サービス提供に必要な資格要件は低くなっていますが、それは重度訪問介護という制度的な枠組みが成立した背景に関わります。
もともと重度訪問介護は、障害当事者の方々が国や行政に訴えることで制度が作られたというプロセスがあります。
障害を持つ方のご家族からの懇願で1950年代に障害福祉施設が全国に設置されましたが、その環境が非常に劣悪で、障害を持った方たちが「これは人間の生きる場じゃない」という思いを持って施設から飛び出していくという流れが始まりました。
地域に出た方々はボランティアを集めて生活していましたが、ボランティアの方は用事などで休まれることも多く、その際は排泄などにも事欠きます。
そこで、ケアを担う人を労働者にすべく、障害当事者の方々が「ボランティアに給料を」と東京都に訴え、1973年に東京都で重度脳性麻痺者介護人派遣事業が設立されました。
これが日本初の在宅重度障害者に対するホームヘルプサービスであり、現在私たちが提供している重度訪問介護の原型です。
その後、徐々にサービス提供時間数も増え、2000年に介護保険制度が始まった頃には、一部の自治体においてはほぼ1対1で1日10~20時間のサービスを受けられる環境が整うまでになりました。
こうした中、2002年頃に現行の障害者総合支援法の前身である「障害者自立支援法」の案が立ち上がりましたが、そこで最初に出された意見が“介護保険制度と障害福祉制度を統合する”というものであり、これに対して障害当事者から激しい反対運動が起きたわけです。
当時、霞が関に1万5000人前後の障害者が集結し、丸の内線が全てストップする事態にまでなりましたが、なぜ介護保険と統合されてはいけないのか、この理由は次の2つです。
まず一つは訪問介護のフレームです。
介護保険のホームヘルプは、要介護度5の寝たきりの方でも1日1~2時間の訪問となっていますが、すでに重度の障害者は1対1で24時間ケアが受けられるという環境ができており、介護保険と統合されるとその既得権が一気に失われます。
既得権といっても自分の命に関わるものであり、介護保険と統合されると地域で生きていけなくなるということがあります。
もう一つが資格に関わることです。
当時、重度訪問介護は10時間(1日半)の研修で資格を取れましたが、ホームヘルプ事業は初任者研修(旧ヘルパー2級)という130時間の研修が必要になります。
資格要件が厳しくなれば、今まで通りのサービスが受けられなくなる、あるいは受けられるサービスが減ってしまうことになり、これが一本化に反対する大きな理由となりました。
障害当事者が「資格なんてなくていい」と考える背景は、もともと何十年も学生や主婦といったボランティアに支えられていた経験に基づいているもので、これをもってしても障害当時者運動の特性は脱専門家主義であり、脱資格社会と言えます。
資格やゼネラルな知識ではなく、人柄やパーソナリティー、固有の専門性が必要だというのが彼らの主張でもありました。
<資格は必要か、不必要か>
資格には功罪があると思われます。
資格要件を強化して、それを入り口に置くと、人材が集まらずに社会課題は深刻化します。
これが経営者として資格要件の強化に賛成できない理由であり、資格の“罪”の部分ですが、 “功”としては、広く深く様々な事柄を学ぶことを通じて、自分たちの仕事に対して誇りや自信を持てます。
先日、福祉の最先端国家であるデンマークの福祉医療施設を視察してきましたが、デンマークは徹底的な資格社会です。
現地の介護士の誇りと自信、社会的地位の高さも驚くほどでしたが、その根拠となっているのは専門性です。
専門資格を取るためのしっかりとした教育機関があり、それに基づく知識に対する自信と、その専門性に対する社会的信頼もあります。
もっともデンマークでは介護士は公務員であり、社会のフレームが日本とは異なりますが、ケアワーカーの尊厳に取組む上では、デンマークに一つのモデルがあると思います。
このように「資格」と私は、一言で言うとアンビバレントな関係です。
一方では重要であり、一方では社会問題を作る要因にもなっていると思われます。
結論としては、“間口は広く、奥行きは深く”という形で、まず介護保険の訪問介護における初任者研修の資格要件はなくすべきだと考えます。
医療的ケアを必要とするALS患者のケアは20時間の資格要件で可能であるのに対し、自宅に訪問して掃除などをする介護保険の訪問介護に130時間の資格研修は必要ないと感じざるを得ません。
それゆえ、無資格とするのがよいと考えています。
しかし、だからといって資格が全く必要ないとは思いません。
やはり入り口以降はデンマークを見習い、学べば学ぶほどキャリアアップできる知識や技術を獲得できる制度、プロ中のプロを生み出せるような体系を作るべきです。
誰もが入れる一方で、追求すると非常に高いレベルまで到達できるような制度設計にすると、介護業界の人材も増え、希望も持つことができるなど、良いことづくめだと思われます。
株式会社土屋について
株式会社土屋は、高齢者や障がい者の方々がより良い生活を送るための介護サービスを提供し、また、さまざまな社会的ニーズに応えるための事業を展開するトータルケアカンパニーです。
■会社概要
会社名:株式会社土屋
所在地:岡山県井原市井原町192-2久安セントラルビル2F
代表取締役:高浜敏之
従業員数:2,766名
設立:2020年8月












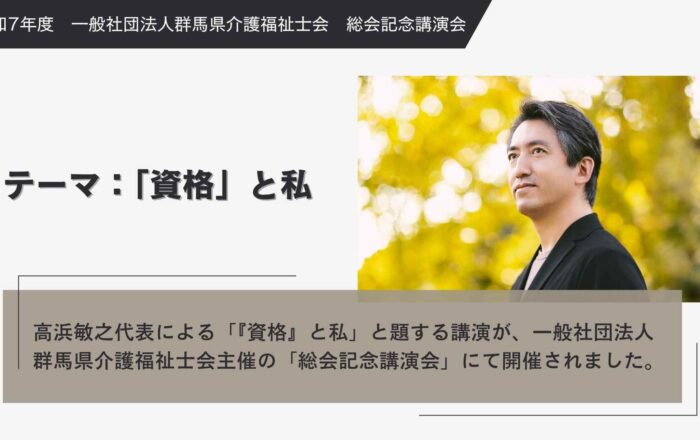

-1.png)




















