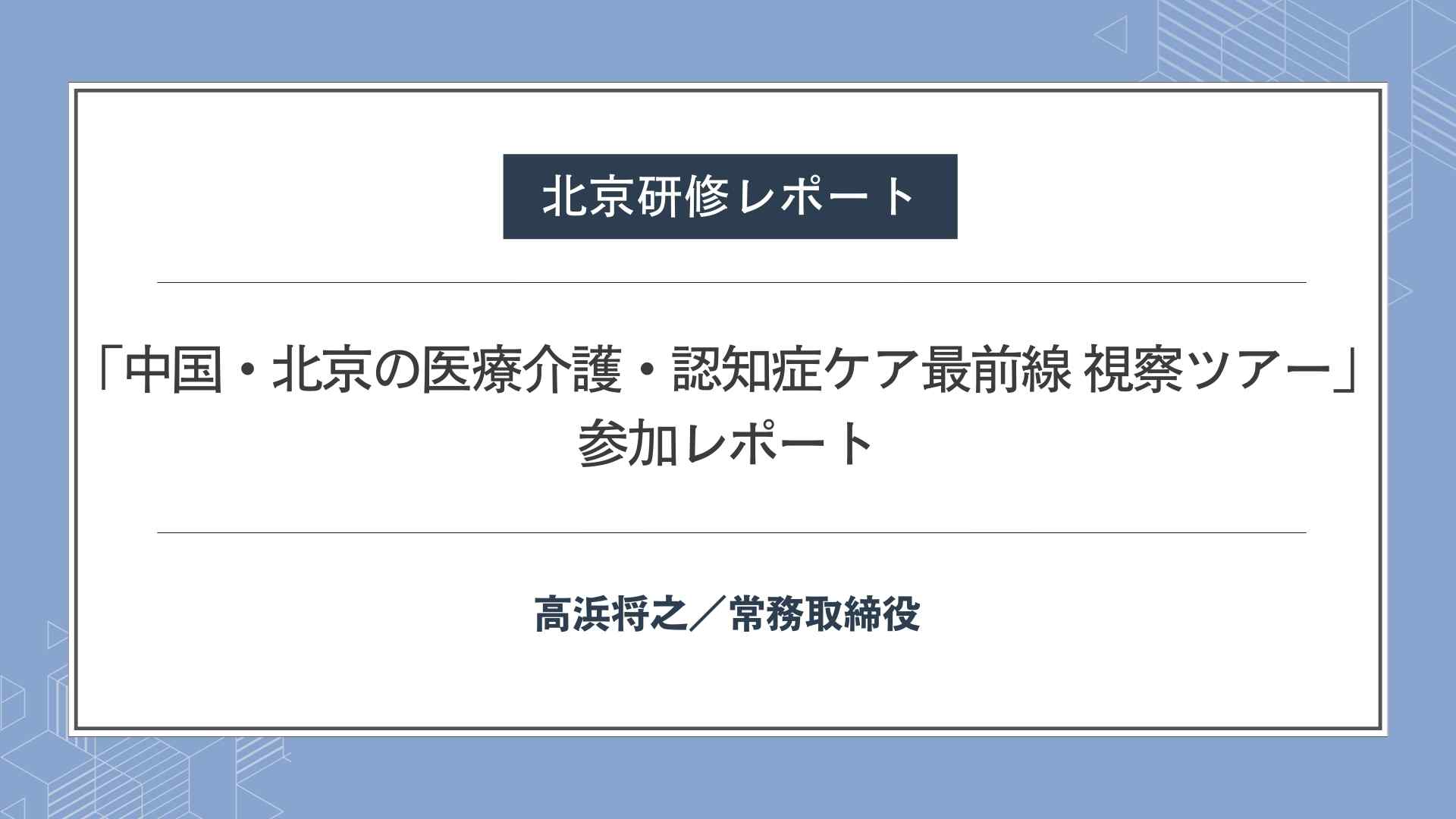
『「中国・北京の医療介護・認知症ケア最前線 視察ツアー」参加レポート』高浜将之/常務取締役
2025年6月24日から27日にかけて実施された「専門家と行く 中国・北京の医療介護・認知症ケア最前線 視察ツアー」に参加させていただきました。
全国から集まった35名の参加者とともに、施設見学や専門家との対話、現地の運営スタッフとの交流を通じて、中国における介護・認知症ケアの実情と、それを支える文化や制度に対する理解を深める、非常に貴重な機会となりました。
1. 中国の介護制度・文化的背景
※以下の内容は視察で直接得たものではなく、報告会参加者の理解を深めるために独自に調査・整理した補足情報です。
中国では急速な高齢化が進んでおり、2025年時点で60歳以上の高齢者人口は約3億人に達すると見込まれています。
政府は「家庭による扶養+地域支援+機関サービス」の三層ケアモデルを提唱していますが、制度整備は依然として過渡期にあり、地域による格差も大きいのが現状です。
以下、日本との比較を含めて主な違いを整理いたします。
| 分類 | 中国の現状 | 日本との違い |
| 年金制度 | 都市と農村で格差あり。 養老保険制度は分断的 | 日本は全国一律の制度 |
| 医療制度 | 基本医療保険あり。 自己負担割合は高め | 日本の方が医療費の 軽減措置が整備されている |
| 介護保険制度 | 一部都市(例:青島市)で パイロット導入中 | 日本は2000年から 全国で制度化 |
| ケアマネ制度 | 制度としては未整備 | 日本では専門職制度として 確立されている |
| プライバシー感覚 | 家族による意思決定が優先され、 情報共有への抵抗感が少ない | 日本では本人の意思と尊厳が 重視される |
このように、中国の制度はまだ発展途上にありますが、超高齢化社会に向けた取り組みが急ピッチで進められている様子が伺えます。
また、文化的な背景に基づく価値観の違いも随所に見られました。
2. 視察を通じて得られた気づき・学び
視察先の施設では、多床室を備えた空間設計が多く見られ、20年前の日本の介護施設を彷彿とさせる印象がありました。
その一方で、認知症ケアに対する職員の姿勢には目覚ましい変化が見られ、「アセスメントを通じて本人のニーズを探し、不安を軽減する・安心を提供する」といった、日本のケアに近いアプローチが現場で取り入れられている様子も印象的でした。
最も強く印象に残ったのは、中国の介護現場において「安全」が絶対的な優先事項として扱われている点です。
施設内の至るところに監視カメラが設置され、居室の入口や衣服には名前や身体状況などの個人情報が掲示されていました。
日本であればプライバシー侵害と捉えられるこれらの対応も、中国ではごく自然なこととして受け入れられているようでした。
この背景には、「本人の安心」よりも「家族の安心」が優先されるという傾向があり、見守りの徹底こそが介護の基本という価値観が強く根付いていると感じました。
また、効率性を重視する社会的・文化的な傾向も影響しているようで、現場職員が業務を確実かつ簡便に遂行するための情報の可視化や監視体制の整備が、合理的な手段と見なされている側面もあるようです。
現地職員からは、「まず100%の安全を確保し、そのうえでQOLを追求すべき」との説明がありました。
この考えに共感できる部分もありますが、私たちは日本の介護実践を通じて、過剰な安全配慮が本人の生活機能や意欲を損なう可能性があることを経験的に学んでおり、違和感を覚える場面も少なくありませんでした。
こうした違いは、単なる介護観の成熟度の差というよりも、そもそも「プライバシー」を個人の権利として尊重する文化が中国社会に根付いていないことが要因であると感じました。
日本では、「尊厳」を守ることがケアの中核的な価値であり、その中に「安全」「プライバシー」「自己決定」がバランスよく位置づけられています。
一方で、中国では「プライバシー」はあまり重視されておらず、介護現場においても「安全と効率」を最優先する価値判断が見受けられました。
「プライバシーとは、何かを隠すことではなく、“自分の情報を誰にどう伝えるかを選べる自由”である」という視点を、今後はより丁寧に説明していく必要があると感じました。
人は“自分が自分でいられる”と感じられるときに安心が生まれます。
監視や情報公開が当たり前という価値観のもとでは、この点を伝える難しさもありますが、だからこそ私たち日本の介護職が「信頼されていることが安心につながる」ということを言語化して伝えられる力を身につける必要があると感じました。
また、利用者に掃除や洗濯物たたみといった「役割」を担ってもらう支援に対し、家族から「それは労働だ。報酬を支払うべきだ」と指摘される場面があるという話も印象に残りました。
これは、日本で一般的な「役割支援=自己実現支援」という捉え方とは異なり、文化的な価値観の違いが反映されている例といえるでしょう。
さらに、視察の終盤には、医療法人社団悠翔会の佐々木淳先生や、あおいけあ代表の加藤忠相さんといった、日本の医療・介護分野を牽引するリーダーたちと直接意見を交わす機会がありました。
視察での気づきをもとに参加者同士が学びを深め、今後の実践へとつながるネットワークが自然に形成されていったことも、本視察ツアーの大きな成果のひとつでした。
3. おわりに
今回の視察を通して、改めて「文化や制度の違いに気づく」ことの意義を実感いたしました。
中国の介護現場は制度面では発展途上であるものの、認知症ケアの質的な進展やAI技術の導入など、日本が学ぶべき点も多く存在していました。
一方で、「安全と自由」「プライバシーと安心」のバランスをどう取るかという課題は、国や制度の枠を超えて、すべての介護職に共通する普遍的なテーマです。
今後も、日本の実践と価値観を踏まえつつ、文化を尊重し、対話を重ねていく姿勢が求められると強く感じました。
最後に、今回の視察を通じて出会った介護業界のオピニオンリーダーやインフルエンサーの方々とのご縁は、非常に大きな財産となりました。
多様な視点を持つ専門家とのつながりを大切にしながら、今後の土屋の事業展開や価値創造にも積極的に活かしていきたいと考えております。
株式会社土屋について
株式会社土屋は、高齢者や障がい者の方々がより良い生活を送るための介護サービスを提供し、また、さまざまな社会的ニーズに応えるための事業を展開するトータルケアカンパニーです。
■会社概要
会社名:株式会社土屋
所在地:岡山県井原市井原町192-2久安セントラルビル2F
代表取締役:高浜敏之
従業員数:2,766名
設立:2020年8月












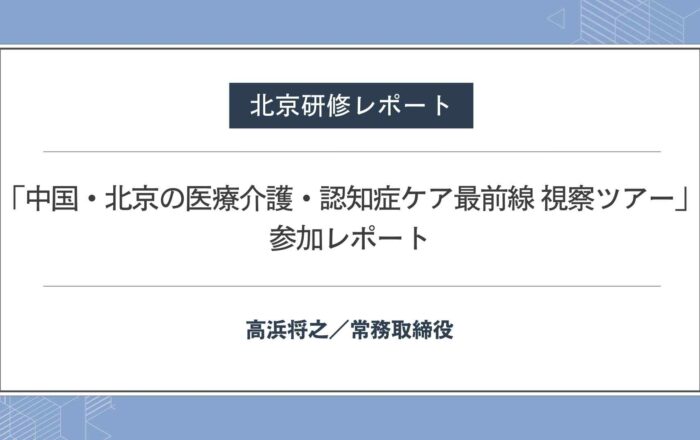

-1.png)




















