【高齢者地域生活推進委員会】定例レポート 2025年3月27日
開催概要
開催日:2025年3月27日
開催場所:オンライン
当日のアジェンダ概要
- 新規グループホームの事業所紹介
- 前回の課題相談等の進捗確認(定期巡回)
- 前回のマネジメントの悩みについての進捗確認
- マネジメントの課題相談
当日の定例レポート
当日の定例ミーティングでは、事業譲渡後のグループホームの取組みが紹介される中で、顧客創造活動の具体的な方法について参加者から貴重なアドバイスが提示されました。
またマネジメントの悩みについても、管理者としての考え方や実践的なコミュニケーション方法など、有益なアドバイスが多く示されました。
1.新規グループホームの事業所紹介
<管理者より事業所紹介>
2025年1月よりM&Aで土屋グループの子会社となり、3月より私が当グループホームのホーム長となりました。
1ユニット9床の事業所ですが、2床のみ埋まっている状況です。
スタッフは、常勤が私を含む3名、非常勤5名、応援スタッフ2名の計10名で稼働しています。
非常勤5名のうち3名は、事業譲渡前には調理の専属スタッフとして稼働していましたが、現在はその方たちの介護職員化を、6月を目指して進めています。
今まではキッチンから出てこれなかった元調理スタッフさんたちですが、今では積極的に介護のケアに参加していただいています。
<現状の課題>
ちらほらと見学や入居希望の面談もありましたが、なかなかタイミングが合わず流れている状況です。
2.アテンダント同士の関係性、チームワーク、コミュニケーションも最優先の課題となっています。
事業譲渡後3か月が経ちましたが、夜勤明けの方と日勤の方がかぶった際に、職場の雰囲気がぴりつく状況がたまに見られます。
アテンダントの高齢者介護に対する考え方が様々なので、統一した理念や目標を共有し、全員が同じ目標に向かって進んでいけるような仕組みを整えたいと思っています。
<現在の取組み>
私自身は顧客創造として、地域にある医療機関や居宅事業所に、とにかくあいさつ回りをしています。
アテンダントによると、地域の中で「あそこのグループホーム、変わったらしいね」という噂がちらほらと回っているとのことですので、それをチャンスに捉えて、当事業所の強みを打ち出していければと考えています。
<事業所の立ち上げに携わった管理者より補足>
事業譲渡の際は、アテンダントのみなさんも戸惑われていましたが、現在は数名の方が我々のケアを見て「今まで諦めていたけど、土屋になって変わるのであれば働き続けてもいい」という気持ちを持ってくれています。
その方たちからは「こうしていこうよ」といった発言も出ていて、それが我々への追い風になっていると思います。
地域住民であるアテンダントさんが、周りの方に「働きやすくなった」「利用者さんが最近すごく最近元気でね」といった話を広げてくれると、少しずつ地域の方たちの認識も変わり、そこから交流が生まれていくことを期待しています。
また、自治会長さんや町おこし協力隊の方たちなど、いろんな方が公的に関わってくださっているので、そういったところからも地域密着型サービスとして、地域の社会資源になっていければと思っています。
<質問による補足>
・職員の育成やモチベーションの維持の取組みに関しては、事業譲渡により周りから「クライアントのADLが向上した」と言われていますので、
アテンダントのみなさんには「私たちの手でここまで変わるんだよ」「こういうケアができるんだよ」など、やりがいや感動・実感を共有しながら、とにかくコミュニケーションに励んでいます。
・3人の調理師の方のうち2人はもともと介護職で、初任者研修を持っています。
ただ、高齢になり、身体介護や長時間勤務が難しくなったことから調理に回っていた方々で、そのお2人は割とすんなり介護職として働けています。
もう1人は無資格ですが、朗らかで明るく、もともと利用者さんと関わるのがすごく好きな方です。
ただ、以前に「調理は厨房に引っ込んでいろ」と怒鳴られた経験があって、そこからあまり利用者さんと関われずにいたという事でした。
現在は前向きに利用者さんとレクリエーションを一緒にしたり、コミュニケーションを取られています。
今後、基礎研修を受けていただく方向です。
この3人の方々には、「調理じゃなくても、あなたたちは介護の仕事をちゃんとやれているよ」とひたすら言い続けています。
・顧客創造活動としては、居宅事業所に伺ってご挨拶をしている形です。
事業所が土屋に変わったことや、当事業の強味、力を入れたいところなどの話をしています。
チラシをお渡ししたり、あとはとにかく愛嬌を振りまいています。
<委員会メンバーよりコメント>
・顧客創造活動に関して、地域とより深くつながるために、地域の医師会や事業者連絡会に足を運んだり、介護事業をしている人の団体に所属したり、デイサービスなどの勉強会に参加するのも良いと思います。
友達になるという感覚でつながると、そこから他の方とも数珠つながりにつながっていけますし、顔が見える関係性を作った後で挨拶や営業に行くと非常に効果があると思います。
2.前回の課題相談等の進捗確認(定期巡回)
<前回の相談内容>
クライアントの臀部に“できもの”ができ、傷口からの出血およびご本人より痛みの訴えがあったことから1日3回、お風呂場でシャワーを流し、臀部の傷口に対して薬を付けています。
その後、かゆみが身体に出始め、ご家族に病院受診をお願いしていますが、ご家族は医療を信用していないこともあり「病院に行かない」の一点張りです。
ご家族に病院受診を受け入れていただくかにはどうすればよいでしょうか。
<前回からの進捗>
クライアントの臀部のできものが増えたので、ご家族にお話しをしたところ、ご家族が病院を受診し、軟膏が処方されました。
現在は、1日1回、就寝前に塗ることができており、出血や乾燥等も改善されてきています。
ただ、ケアマネジャーの方がご家族に訪問診療を提案したところ、契約が面倒とのことで拒否をされています。
何かの場合は当定期巡回に相談するとのことですので、今後も都度ご家族に状態等を報告して、病院受診になるとは思っています。
3.前回のマネジメントの悩みについての進捗確認
<前回の相談内容>
アテンダントのAさんは、強い口調や態度を示される方で、どう対応すればいいか悩んでいます。
上長の面談で、態度を改めてはくれたものの、また緩んできたときには強い口調や態度が出てくると思われます。
毅然とした態度でしっかりと伝えることが大事だということは教わっているのですが、なかなかそれができず、どうマネジメントすればいいのか、苦手分野のマネジメントをどう克服したらいいのかのご相談です。
<前回からの進捗>
現在、週に1度、必ずAさんと2人で話しをするようにしています。
新規のご依頼があった時にはAさんに一番にお伝えし、今後の進め方などをお話ししています。
またその際には「何とか力を貸してほしい」ともお願いしていて、現状はAさんの言い方などが柔らかくなってきていると感じています。
<質問による補足>
・面談は、日勤が一緒だったり、明けでお会いする時に「ちょっといいですか、相談したいことがあります」という形でお伝えしています。
⇒結果的にそれがコミュニケーションの機会になっているということで、参考になりました。
面談と言うとものものしいですが、相手の方を頼っているところがいいと思いました。
4.マネジメントの課題相談
<相談内容①>
現場で介助していた時はコミュニケーションに困ることはほとんどなかったんですが、管理者になってから、現場の要望を聞けたり聞けなかったりすることがあり、スタッフとぎくしゃくするなどコミュニケーションに難しさを感じています。
管理者として、どのようにしていけばいいのか、アドバイスをお願いします。
<委員会メンバーよりアドバイス>
・私も管理者になった当初はなかなか思うことが伝えられず、かなり悩みました。
現在は、ネガティブな言葉を使わないように気を付けています。
ネガティブな言葉自体、誰しも受け取ると嫌な思いがするので、「○○すると“だめ”じゃない」「そんなことしたら“いけない”」「こうして」などの言葉をなるべく使わず、
「こうすると良くなるんじゃない」「こうすると喜ばれると思うよ」など、できるだけポジティブな言葉に置き換えて、押し付けにならずに本人に考えてもらえるよう伝え方を意識しています。
・意見交換が激しくなる場面もたまにはありますが、どちらかがヒートアップしてしまうとダメになるので、必ずこちらは冷静にいることを心がけています。
自分の中で抑えきれそうもないときには、時間を置いてから話したり、コーヒーを飲みながら話したり、テンションがフラットになるように気を付けています。
・人と話すのが大好きですが、以前、ものすごく人に拒絶されてることを知った時に、急に人と話すのが怖くなり、うつ病にもなって人と話せない時期もありました。
ただ、人と話すのが上手な人が「コミュニケーションが上手な人」ではなく、接遇や傾聴は話し好きとは全く関係ないと思います。
むしろ、話すのが苦手の人のほうがきちんと傾聴できていることもあり、そういう人がコミュニケーションが上手だと思います。
<相談内容②>
やる気が低下してきている方に、どうやる気を持って仕事をしてもらえるかが分からず、アドバイスをお願いしたいです。
<委員会メンバーよりアドバイス>
・私がマネジメントする上で大切にしているのが、それが最低限すべきことなのか、あるいはそれを越えてお願いすることなのかの線引きを強く意識することです。
最低限のことは、それをして当たり前というレベルになるので、厳しくお話ししますが、それを越えてお願いするときはコミュニケーションを変えています。
できないことを強制してもできないので、できないことは管理者がフォローしたり、周りの方にも協力を仰いで、その方のできること・できないことをまずは分けた上で、すべきことを常々お話ししています。
やる気で左右されてしまうと、ぶれてしまうかもしれないので、やる気があってもなくても最低限しなければいけないところは、コミュニケーションを取って、それをしてもらえるような環境をまず作ることが必要と感じました。
・方向性を指し示す時には、例えばクライアントさんに最終的にどうなってもらいたいかというゴールや理念を提示するのがいいと思います。
ただ、それが抽象的なものである場合は、それを目指すための目標を明確にして、事業所の目的や目標に向かってコミュニケーションを取るのが良いと思います。
それぞれの人に個々の考えがあるので、「私はこう思う」というのがぶつかった際に、
「事業所としての目的はこうだから、これに対してどういう風にしていくのがいいか」という話をした方が、割とスムーズに受け入れてもらえると思っています。
・やる気のなさの原因が何かということを、いつも視野に入れています。
体調が悪いのか、事情を抱えていて仕事に集中できないのか、職場の人間関係に悩んでいるのか、いろんなことを視野に入れながら、
この人の今の状況でどのあたりまでの仕事を期待してお願いすればいいのかはいつも心がけています。
・もともとモチベーションの低い人を高めるのは難しいですが、モチベーションが高い人が低くなったのであれば、それは何か原因があると思います。
モチベーションを下げた原因が人間関係や家庭環境かもしれないし、それが分からないにせよ、高い所から低くなるのは異常なことので、異常なことは原因があるので治せると思います。
・人間関係とチームワークに関してですが、人間って複数の人が集まれば混乱したり、我を張ったりと、揉めるのが正常だと思います。
落ち着いて何もないのが異常な状態だと思っています。
管理者は、そういった争いやいがみ合い、マウントの取り合いをコントロールして整えていくことをずっと続けていかなくてはならず、
それがマネジメントの大変さですが、そこさえしっかり押さえていくと、みな仕事を回していってくれるので、そこを整えられれば管理者側の仕事が楽になると感じられます。
あと、最近上手くいっていると思ってるのは、上手くいってないことに自分が気づけていないだけということがよくあるので、そこは気を付けています。
・マネジメントを見ていく上で、感情のマネジメントという部分と業務のマネジメントという部分を分けて考える必要性があると思います。
これもその時々や、対象の人物によってバランスの取り方が変わって来るもので、感情ばっかり優先すると業務が置き去りになったり、業務が優先しすぎるとモチベーションに関わって来るので、
そこのバランスを取りながら、感情的な部分と業務の部分の進捗をしっかりと見ていくことが大切だと思います。
時には業務を優先してやっていただかないといけない場面もありますが、業務を優先する上でも感情という部分をしっかり組みとってあげる必要性も出てきます。
このバランスの取り方は、スタッフさんごとに異なったり、事業所の方向性・理念によっても変わってくると思うので、その辺りをしっかりと見極めながらマネジメントができると良いと思います。
【高浜将之委員長による総括】
充実したディスカッションが行われていて嬉しいです。
グループホームの件では、地域の人に「事業所がしっかりやってくれている」と言っていただけるのは、管理者の方々がサポートしながら、アテンダントの皆さんが真摯にケアに向き合ってくれていることだと思うので、
これは事業所のいい事例が地域に広がることでもあり、土屋のブランディングにもつながるので、貴重な事業を引き継いだ流れとして素晴らしい活躍をしてくれていると非常に嬉しく思います。
やる気のない職員さんの話では、私も以前管理者をしていましたが、どうにもうまくいかない時ってあると思うんですね。
ただ、支援が良くなかった、ちゃんと言うことを聞いてくれない、みんなと同じことやってくれないと思っても、極論を言うと戦時状態にいる人に比べると小さなことですし、
そこに自分がフォーカスしすぎると逆に全体を見れなくなる部分があるので、一旦視野を広くもって、そういう別の視点をもつのも一つあると思います。
あとは、そもそも低賃金で、介護の仕事に就いてくれる人もどんどん減ってきている中で、確かにうまくいかないことはあるにせよ、そもそも働いてくれていることに感謝しようと思っていました。
モチベーションの話では、ずっとモチベーション高い人は絶対いないんですね。
絶対、波が起きています。
それに、モチベーションが下がっている時にも、それを自覚している人はゼロに近いくらいで、みんな100%でやってるとどこかで思っているはずです。
逆に言うと、そこで下がっている状態のときはプライベートで悩みを抱えてたり、全力を発揮できない自分がそこにいるということもすごく重要なことで、そこを理解してくれている上長がいて、
仕事ができているかではなく「最近調子悪い?」というように、その人にフォーカスしてあげれば、職員として見れば安心して働ける環境が整うと思います。
それに、一人の人が上手くいかなくても、その人を変えるのは難しいので、その人がどうやったらみんなと同じようにできる仕組みを作れるかというように、人じゃなくてチームにフォーカスするのが関係が壊れないので良いと思います。
みなさん大人ですから、指導されたり、意見されるとプライドが傷つくので、そうではなく、どうすればその人がそこに向かえるのかというようなチームとしての取組みが必要だと思いますし、それをチームの課題にするのもいいと思います。
「これじゃだめだよ」ではなく、「こういう状態良くないから、こうしよう」と全体に語り語り掛けるとかですね。
それでも上手くいかないことは上手くいかないんですが、100%を目指すにしても100%を取り続けることはできないので、波が起きながらも全体としていい方向に向かえるような形で、バランスを取りながらマネジメントすることを気を付けていました。











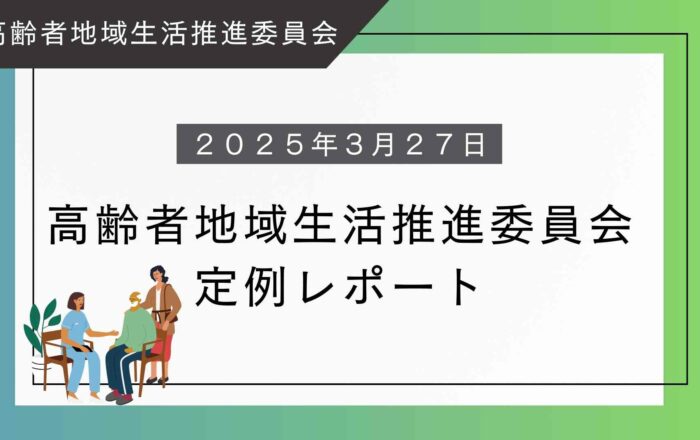
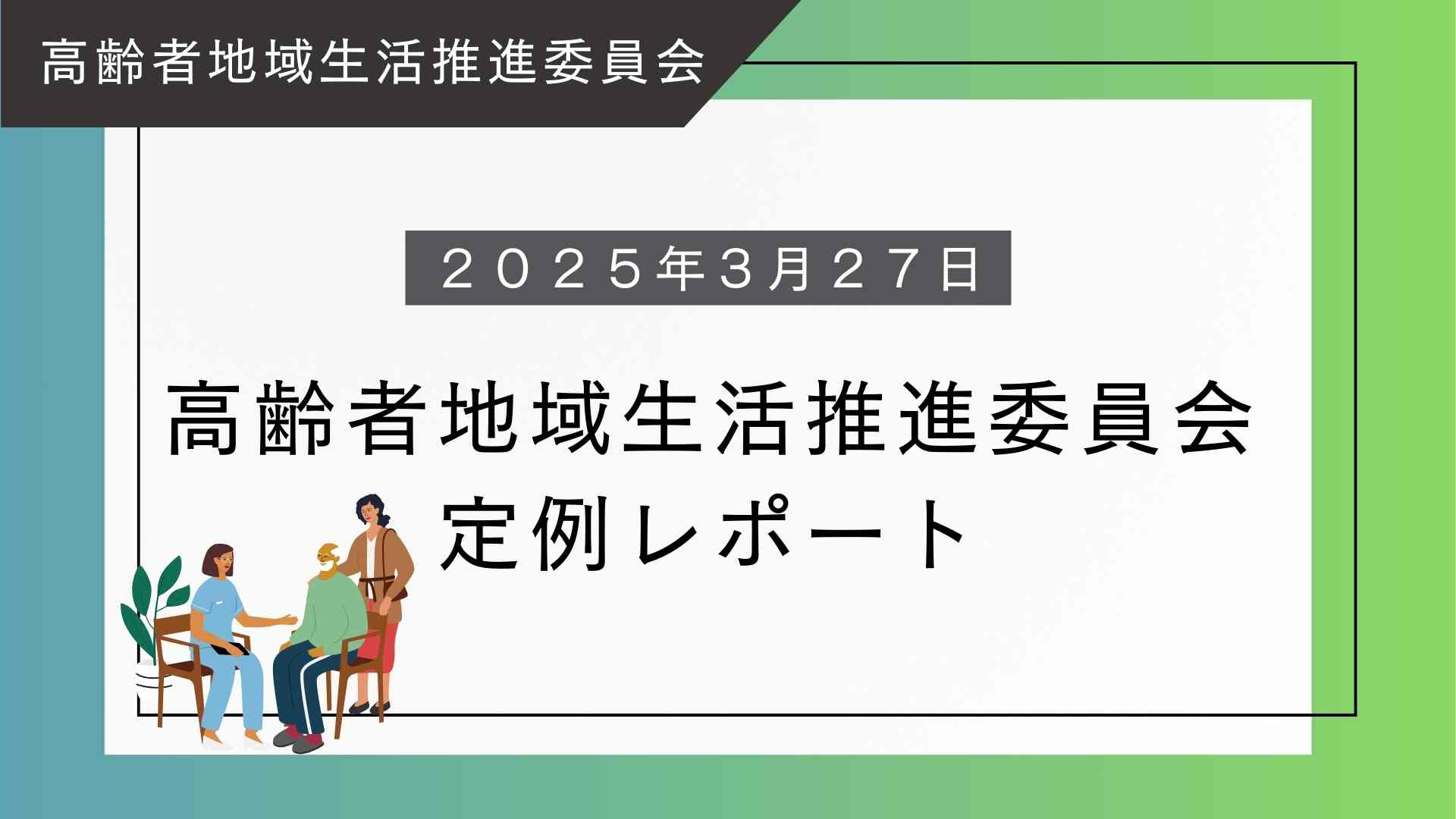

-1.png)




















