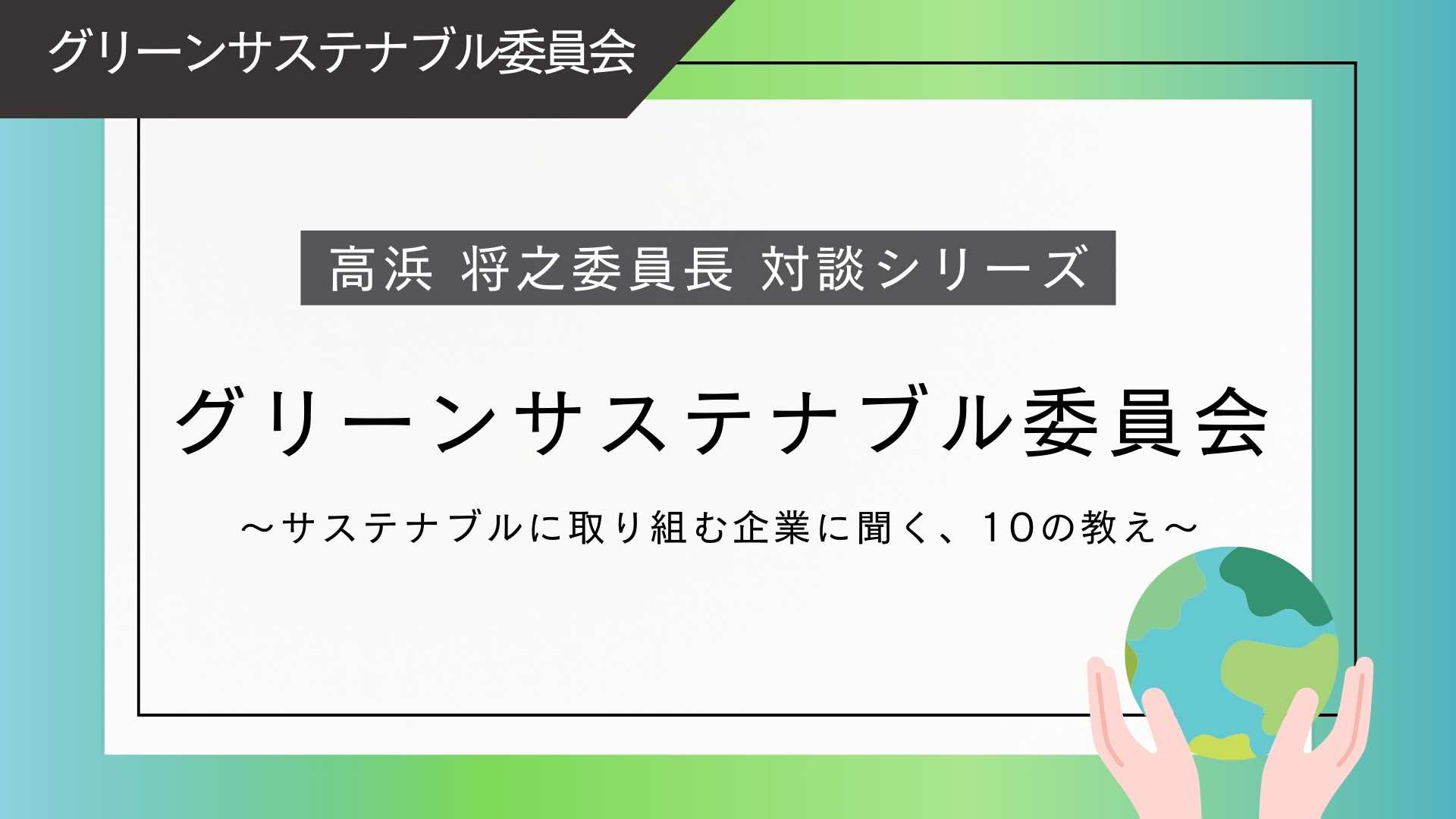
【グリーンサステナブル委員会】高浜将之委員長の対談シリーズ「サステナブルに取り組む企業に聞く、10の教え」
<第1回目ゲスト>
▸阿部哲也氏(IKEUCHI ORGANIC 株式会社 代表取締役)
<会社紹介>
創業73年という歴史を持つ「IKEUCHI ORGANIC 株式会社」(愛媛県今治市)は、オーガニックコットンのみを使用するサステナブルなタオル製造会社として知られており、自社工場でのタオルの生産、自社製品の販売のほか、製造の委託業務も行っています。
代表取締役・阿部哲也氏は当企業の3代目に当たり、「最大限の安全と最小限の環境負荷」という経営理念の下、環境に配慮した良質のタオルを全国各地に届けています。
「環境価値」としてのオーガニック
<高浜>
我々は介護事業者ということもあり、環境に対して大きく負荷をかける事業ではありませんが、社内においてサステナブルに少しずつ取り組む中で、我々にもまだ改善できる余地はあるのではないかと思っています。
そこで、サステナブルな取り組みをしている企業の方々に話を伺い、取り入れられる部分は積極的に取り入れていきたいと考えています。
御社の経営理念は「最大限の安全と最小限の環境負荷」ということですが、これはどのようなことですか?
<阿部>
「最大限の安全」というのは外向きの言葉で、我々が現時点で作り得る製品は、お客様の元に最大限の安全性を担保したものをお届けすべきだということです。
一方、「最小限の環境負荷」というのは内向きの言葉で、製品を現在考え得る最小限の環境負荷でお届けするということです。
当社はこの二軸で運営しています。
<高浜>
タオル業界でオーガニックコットンしか使わない企業というのは聞いたことがないですが、私自身、繊維物を購入する際にはまず表示を見ます。
例えば、ポリエステルが入っていないかなどですね。
ポリエステルが入っていると、洗濯時等にマイクロプラスチックを発生させるからですが、まずここに物を買う時の第一判断基準が入ってきます。
そうした中で、最も環境負荷の低い繊維がオーガニックコットンであり、最も環境負荷の高い繊維が通常のコットンであるという認識は正しいのでしょうか?
<阿部>
正しいとは思いますが、そこにフォーカスが当たると誤解を生じさせることが多くなります。
オーガニックコットンは基本的に「環境価値」しかありません。
物性としては安定せず、ロットごとにぶれ、しかも値段も高い。
消費者が製品の物性だけで考えると、オーガニックでないほうが安定しています。
細番手の糸が引けますし、収穫年次ごとのばらつきもそこまでありません。
それに、単純に製品だけを比較した時に「違い」が分からないんです。
圧倒的な使用感の違いがあれば比較できますが、それもないので、基本的にオーガニックは「環境価値」でしかないんですね。
そのため製品自体で評価した時に「違いが分からないけど高い」という、非常に売りにくい商品だと思います。
▸環境価値って何?
環境価値とは、消費者が直接的に享受できる価値―圧倒的な使い心地や性能―ではなく、未来の人々の暮らしに必要な資源や環境を守るための価値です。
<驚くべきコットンの実態―その持続不可能性―>
オーガニック以外のコットンは、その多くが肥料と農薬のセットで、遺伝子操作された種を用いて栽培されています。
そのため、基本的には肥料・農薬を販売する企業と、種を販売する企業のサプライチェーンの中に自動的に組み込まれることになります。
これにより出費が増えるだけでなく、種自体が遺伝子操作されているため一代種となり、通常のように種を取り、それを植えて育てることのできない仕組みとなっています。
また綿は本来、それほど水を必要とせず、痩せている土地で栽培されることが多くあります。
しかし、栽培で用いられる農薬は毒性が強く、それを洗い流すために水が必要となります。
そのため痩せた土地に灌漑が必要となり、かつ農薬は土の中に堆積していきます。
さらに、収穫時には枯葉剤が使われます。
手摘みのオーガニックとは異なり、コットンの収穫は機械で行われますが、その際に綿花に葉の色が移らないよう、枯葉剤を撒いて葉を枯らします。
枯葉剤は極めて危険な薬物であり、それらが土壌にどんどん蓄積されることで土地と水が死んでしまいます。
そして、それは栽培に従事する人々にも影響を及ぼしています。
綿花は貧しい土地で栽培されることも多く、種なども始めは無料で供給されます。
これは彼らを買収し、そのスパイラルに巻き込むことを意味しますが、実際に栽培に従事する人は教育もあまり受けておらず、農薬の取り扱いも分かっていません。
そのため、防護のための手袋なども使用せず、健康被害も発生しています。
こうしたことから、コットンはその作り方において持続不可能とされています。
<高浜>
経済合理性の面からは、「オーガニックコットンだけしか使わない」という方向に舵を切るというのは、企業として非常に重い決断だと思います。
その背景にあるのが、こうした「持続不可能性」や、生産業が世界中で土地や人々を蹂躙している状況に対するアンチテーゼだと感じますが、御社では「環境価値」という、製品の持つ意味を価値化しているということでしょうか。
<阿部>
そうですね。
綿花はいわゆる超合理的な発想で、無知な人を利用して、土地そのものを損ないながら作っている農産物です。
生産に携わっている人や生産している土壌が被害にあっていますが、これは限定的なことのように見えて、実際はつながっています。
こうしたことを続けていくと、いずれ私たちが住めない地球になってしまう。
経済を回すために、こうした部分は巧みに隠されているとは感じますが、そういうと説教がましくなってしまいますし、実際、タオルの圧倒的な使い心地の差というのは、
タオルの設計や糸の作り方・組み合わせ方にあるので、そこに関しては非常に磨きをかけていて、単純に他のショップと比較された時に、「IKEUCHI ORGANICのタオル」というのが分かりやすいような作り方をしています。
やはり、 “環境負荷の低減”に目的を置くと「我慢消費」になってしまいます。
そうではなく、使った時に「気持ちいい」ということを第一に持ってこないと、きれいごとで終わってしまいます。
だから私たちが一番大事にしているのは「製品の使い心地」と「製品が長持ちするような設計」をすること。
その繊維単体が長持ちすると買い替えの頻度も少なくなるので、それが最も環境負荷が低くなると考えています。
過剰供給社会が生み出す環境負荷
<高浜>
現在、繊維系のアパレルを始め、さまざまな業界が「生産して消費する」ことで業務を成り立たせていますが、そうではなく「タオルの再生」という他にはない取り組みをしているのは非常に特徴・ポリシーがあると思います。
安く作って壊れたら買い替える、要は消費と生産をものすごいスピードで繰り返すことが、環境負荷に対する最大の恒常的課題となるんでしょうか?
<阿部>
タオル業界に関して言えば、綿花栽培を除いては、決定的に環境負荷を助長させるような生産は行っていないと思います。
ただ、繊維産業に広げてみた場合、基本的に供給過剰があり、それで経済を回しているとは感じています。
例えば小売業では、いわゆるプロパー(定価で販売できる期間)がどんどん短くなっていて、セールに回して消化させるというビジネスモデルになってきています。
セールで大量に売るためにセール用の物作りをしたり、大量に商品を積むという形ですが、結局完売しないので、それらは廃棄されることになります。
けれど、こうしたことが続くとは思えません。
小売店も人口に対して必要以上にありますが、どこを見回しても全てにおいて消費する以上の量のもので溢れかえっています。
これで経済が回っているという幻想で我々は今動いていますが、このアプローチや私たちの「豊かさの基準」を変えていかないと世界は変わらないと思います。
<高浜>
つまり、社会の価値観自体に対して問いかけをしているということですね。
現代社会は過剰な供給の中でデフォルトに陥っていますが、アフリカのある街でも服が過剰に供給され余った衣類が不法投棄されている現状があります。
これは、ファストファッションの流行で服の消費サイクルが早くなり、過剰な生産が起きる中で、先進国が必要なくなった服を貧しい国に届けているからですが、アフリカの人たちも昔は良いものが沢山あったので、それを長く着ていたわけです。
けれど、今は質の悪いものが過剰に来て、消費しきれないために砂漠で大量に服を不法に燃やしているようです。
<阿部>
大変なゴミ問題が起こっていますよね。
供給側はCSRに紐づけて「良いことをしている」と言っていますが、向こうは迷惑していると思います。
<高浜>
今の米騒動の根幹も恐らくそうです。
「米がない」と言いながら、コンビニには毎日大量のおにぎりが並んでいます。
その上、コンビニなどは欠品を嫌うので、米自体が一つのエリアで何トンも捨てられている状況です。
<阿部>
おかしいですよね。
これは作り手・使い手双方に誤認があって、作り手は「この原材料や生産工程で物を作り続けたら将来どうなるのか」という視点が欠落しています。
一方で消費者にはもう少し根が深い幻想がある。
「欲しいものが欲しい時に、欲しいだけ手に入るのが豊か」という幻想ですね。
これがゲームだとすると、このゲームに勝った企業が経済的に潤っているわけで、そうやって経済を回していますが、消費者は経済を回すために幻想を信じさせられている。
だから作り手も使い手ももう少し賢くならないと、恐ろしいことになるという思いがあります。
<高浜>
持続可能性とはほど遠い状況ですね。
これだけSDGsが叫ばれていても、いつまで経ってもここから抜け出せないという流れがありますが、実際に今年6月の平均気温も、過去最高だった2020年よりも2.4度高かったということです。
我々も知らない間にこのサイクル、このゲームの中に入り込んでいる。業界内の構造でなく、社会全体の構造に環境問題が非常にリンクしていると改めて感じます。
繊維業の水問題から見える、これからのカタチ
<繊維業における水問題>
タオル生産の工程で環境負荷の高いものが、染色工場で行われる後工程、いわゆる染色整理です。
染色はある程度の温度の水で行うため、重油などの化石燃料が必要となります。
また、そのうち最も環境負荷の高いものが、染色後の排水です。
汚染された水をそのまま海に流すと環境に甚大な影響が出るため、染色した水は浄化施設などで処理した後に海に戻されます。
けれど自社で浄化施設を持っておらず垂れ流しをしたとしても、自治体の高度下水処理施設がすべて処理します。
そのため汚染された水が海へと流れ込むことはほぼありません。ただ、自治体によって状況は異なります。
<高浜>
御社では浄化施設を備えた染色工場を作られたとのことですが、当時の状況はどのようなものだったんでしょうか?
<阿部>
我々が染色工場を建設しようとした時に、まず「今治市内では無理」だと言われたんですね。
今治市は構造的に水が足りず、かつ新しく“水を必要とする染色工場”を建ててはいけないという条例があります。
一方で、同じ愛媛県でも西条市は石鎚山の地下水の恩恵で水が豊かなので、西条市での建設を求められました。
ただその場合、自治体の下水処理施設を使わせてもらえないので、自前で浄化施設を持つ必要が出てきたんです。
ただ、瀬戸内海は当時世界一と言われるほど基準が厳しく、それをクリアするために25メータープールが上下で4面ほど取れるような浄化施設にする必要がありました。
かつ、熱い湯で染めるので、ろ過した水をそのまま流すと周辺の水温に影響し、生態系を破壊してしまいます。
近辺には漁業を生業とする方々もいる中で、基本的には常温にして海に流す必要があり、そのようなプロセスを持つ浄水施設を作らなければいけなかったんです。
これはとても我々一企業だけの投資では不可能で、協同組合を作って浄化施設のある染色会社を建設しました。
現在はそこで染色の後工程をしています。
<高浜>
そのような形の繊維産業というのはほぼない状態ですか?
<阿部>
この貨幣経済界で、工場という生産設備を持つことはどの業界においてもNGで、ほぼファブレスです。
自社で工場を持たず、空いている工場で自社製品を生産する方向に転換しないと“スケールしない”というのが理由だと思われますが、繊維産業もまさにそうです。
そのため海外で生産されることも多いですが、実は今、繊維は日本製にかなり戻ってきています。
円安の影響もあり、今まで委託していた海外の工場での工賃が非常に上がっているためですが、逆に言えば、日本ではまだ縫製などの技術を持っている70代くらい方がかなりいらっしゃるので、そこに生産が返ってきているとしたら、次世代に技術承継ができるかもしれないという期待があります。
<高浜>
それは重要ですね。
私も八ヶ岳に家を建てたのですが、その際に「燃やせないものは使わない」というコンセプトで無垢の木材を使用しました。
やはり家は人生最大の投資なので、「負の遺産を残さないで建てたい」という思いがあったんですが、その家を作ってくださった企業が、“手刻み”などの、いわゆる昔ながらの大工仕事をしているところなんです。
この技術が、今ほぼ消滅しかかっている。
今の大工さんは梱包したものを開ける技術は早いようですが、カットされたものを組み立てることはできても、切って刻んで…という本来の技術がなくなってきているそうです。
この技術を残すために、その企業さんも“手刻み”などをしているということでしたが、そのように家を作ると地震にも強く、耐久性も高く、何百年も家がもとの形のまま続くんですよね。
<阿部>
そうですね。
ちゃんと仕口を作ってという、宮大工さんが持っているようなノウハウですよね。
日本の風土の場合、木目を読まないといけないし、仕口を作って遊びも計算しないといけない。
繊維でも同じような話はたくさんありますね。
タオルが呼び起こす記憶とつながり
<高浜>
オーガニックコットンという環境に優しい商品を作る中で、良かったと思うことはありますか?
<阿部>
そうですね。
面白いことに、タオルの風合いの好き嫌いって、幼少の頃に使ったものにかなり左右されるらしいんです。
例えば、ふわふわしているものが好きだとか、つるつるしているものがいいとか、頭の中で“自分はこれが好きだろう”と思っているものがあって、私たちのお店でタオルを触ってもらうと、その感覚で「これがいいです」と仰るんですね。
ただ、タオルは本来、濡れた手などを拭くものであって、しかも何回も洗濯して同じものを使い続けるので、結局は洗濯した後の製品を濡れた手で使ってみないと評価ができないんです。
私たちの店には何百回も洗濯した後のサンプルも置いてあるので、再度それを濡れた手で触ってもらうと、驚くことに、最初に「いい」と言っていたものと違うものが良いと思う人がほとんどです。
心の感覚、手のひらの感覚が、自分の好きな風合いを覚えているみたいなんです。
そうすると、昔のことが思い出されてきます。
「昔、こんな風合いのタオルケットに寝てたな」といった思い出が甦ってくる。
すると、「実は自分はこんなこだわりがあったんだ」と、好みが明確になるんですね。
そこで自分自身を見つけるんです。これが深くて、面白いですね。
<高浜>
私は認知症介護に長らく携わってきたので、今のお話しはとてもヒントになります。
認知症の方は、昔の記憶はかろうじて保たれていて、しかもそれは手続き記憶なんです。
手の感触、好き嫌いの反応というものが非常に強いので、ケアにも活きるお話しをいただけたと思います。
<阿部>
それがわかると、業界を越えて、色んな人とつながれます。
特にタオルは、お客様のご自宅に行ってからが仕事の始まりで、何百回も洗濯して使われるものなので、ケアの方法によって“もち”も全然変わってしまいます。
それで我々もタオルメンテナンスを始めたんです。
そこにもいろんな方が興味を持ってくれて、そういう切り口からも色々な方とつながれています。
やはり、“だるくて重いこと”って大事だと思うんです。
タオルメンテナンスも環境負荷低減の一環でもありますが、たとえば「工場を持ちましょう」とか「スケールを追求するのはやめましょう」とか、普段は“重い”と感じるんですけど、同じことを考えている企業さんとつながれます。
私たちはそれを「だる重連合」って言ってるんですけど(笑)
<高浜>
確かに、環境問題で「これをしたほうがいい」とか「これはダメだ」と思うことはたくさんありますが、それを言ってしまうと、その方の生活を否定することになりかねないので、私も敢えて言わないようにしています。
説教がましくなるという言葉に共感しますね。
<阿部>
今の生活を楽しめていれば、それが一番いいことだと思います。
だから、そこに疑問を感じない人は別にそのままでいいと思うんです。
でも、「今の生活がなにか嫌だな」と思ったときに、それを改善する手段は沢山ありますよね。
たとえば時短にするとか、経済的にもう少し楽になるようにするとか、当人が問題視している1点だけを考えると、改善できるものは世の中にたくさんあります。
けれど、その1点を改善したからといって根本の満足度は充足されないと思うんですね。
ただ、それを繰り返すことによってでしか、本質的なことに興味を持つことはできないと思うので、その本質的なところに興味が持てるような問いを投げかけていく、そういった施策をやり続けることが必要だと思っています。
さいごに
<高浜>
最後に、これから少しでも環境負荷を減らそうと、サステナブルに取り組んでいる企業に対してメッセージを頂ければと思います。
<阿部>
逆説的な話ですが、環境負荷の低減といったことを考えていくとキリがなくて、病んでしまいます。
突き詰めて考えていくと矛盾がたくさんあって、改善すべきことが山ほど出てきます。
それで「自分は全然できていない」「これをしただけで喜んでいてもだめだ」と、自分自身や自分が属する団体を評価できなくなって、病んでしまう。
でも、病んでしまえば何もできません。
自分ができることの範囲、一企業ができることの範囲は限られているので、とりあえず一つでも取り組んだことを「広げずに続ける」ことが大事だと思っています。
そして何か一つすると、批判する人は必ず出てきますが、その声に負けてしまうと、続かないどころか自分が病んでしまうので、「やれることを等身大でやり続ける」ことに価値があると思っています。
<高浜>
刺さる言葉ですね。
一つでも、少しでも何かに取り組み、それを継続的にやり続けることは、本当に重要だと感じます。
本日はありがとうございました。











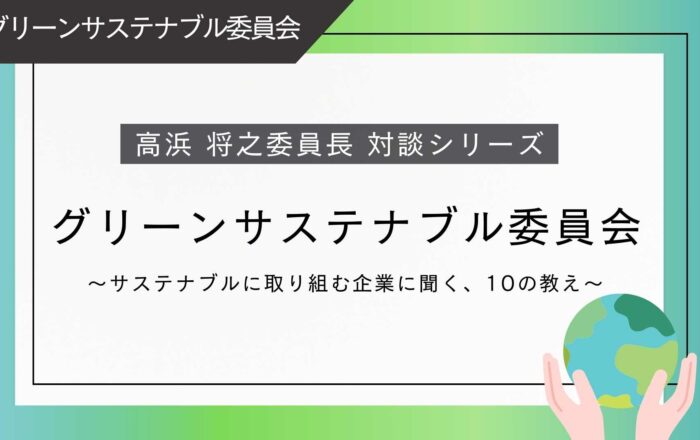

-1.png)




















