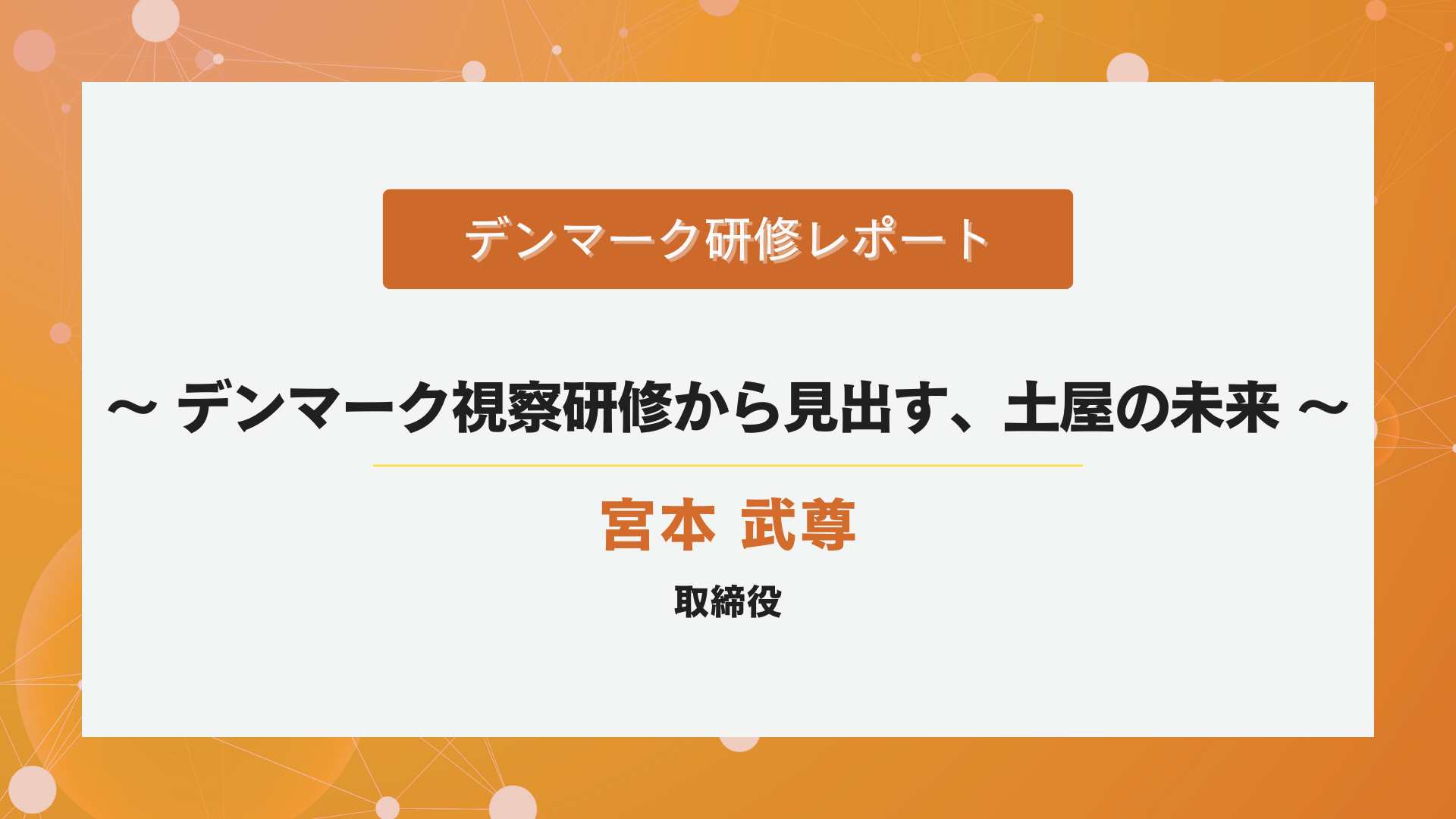
『デンマーク視察研修から見出す、土屋の未来』宮本武尊(取締役)
この度、1週間にわたりデンマークのフォルケホイスコーレにて研修に参加し、デンマークの社会システム、特に福祉と教育の分野における知見を得ることができました。
その中で、彼らが何よりも「対話」を大切にする文化を肌で感じてきました。
株式会社土屋の役員として、そしてCCO(最高文化責任者)、ウェルビーイング委員会長、平和活動委員会長、貧困問題対策委員会長として、この研修で得た学びを日本のウェルフェア、そして当社の社内文化にどのように活かしていくべきか、私の所感をここに述べさせていただきます。
まず今回の研修を通して、デンマークが培ってきた福祉の強みと、日本が長年築き上げてきた福祉の良さを組み合わせた、ハイブリッドな福祉の実現こそが、理想的かつ現実的な未来であると考えました。
研修の1日目、私たちは障害者の就労支援事業所を訪れました。
そこで目にしたのは、様々な程度の障害を持つ方々とペタゴー(デンマーク語で教育者、支援者を指す)たちが共に音楽を奏でる光景でした。
それぞれの異なる世界観が見事に調和し、一つの美しいハーモニーを創り出していることに心底感動しました。
そこには、支援する側とされる側という垣根がなく、誰もがその人らしく存在し、お互いを尊重し合っている姿がありました。
私はこの時、「人間の本来あるべき姿や生き方、社会のあり方とは、まさにこれではないか」と強く感じました。
私たちが目指すべき共生社会の理想が、そこには確かに存在していました。
この交流の根底には、お互いの世界観を理解しようとする深い「対話」があったのです。
その後、オーデンセの障害福祉課を訪問し、トップの方々から税金に関する詳細や、社会システムにおける彼らの役割について伺いました。
デンマークの福祉システムは、高い税負担の上に成り立っていますが、その税金が国民の生活の質を高めるためにどのように活用されているかを明確に理解することができました。
ここでも、国民と行政、そして異なる専門家間のオープンな対話が、システムを支える基盤となっていると感じました。
2日目は特別支援学校を訪れ、障害を持つ方々が創造した数々のアート作品に触れました。
彼らの内側から溢れ出る豊かな感性と表現力は、私たちに大きな感動を与えました。
障害の有無に関わらず、一人ひとりが持つ可能性を最大限に引き出すデンマークの教育・福祉のあり方を垣間見た瞬間でした。
ここでの学びは、個性を引き出すための教師と生徒、そして生徒同士の深い対話の重要性を物語っていました。
3日目には障害者グループホームを見学し、その運営状況についてトップの方から直接お話を伺いました。
利用者一人ひとりの尊厳を重視し、自立を促すためのきめ細やかな支援体制が、いかに実践されているかを学びました。
ここでも、利用者と支援者間の信頼に基づく継続的な対話が、個人の尊厳を支える上で不可欠であることを痛感しました。
4日目は国民の祝日でフォルケホイスコーレは休校だったため、私たちはデンマークがナチスドイツに占領されていた時代の収容所を訪れました。
歴史の悲劇に触れることで、平和の尊さ、そして二度と同じ過ちを繰り返してはならないという強い決意を新たにしました。
歴史から学ぶための対話の場として、このような施設が大切にされていることにも意義を感じました。
その後、ドイツのフレンスブルクを観光し、異文化に触れる機会も得ました。
そして5日目、ボーゲンセの小学校を訪問し、校長先生からデンマークの教育システムと基本的な教育概念についてご教授いただきました。
競争を煽るのではなく、個性を尊重し、自主性を育む教育が、どのように実践されているかを学びました。
子どもたちが生き生きと学び、自ら考える力を養うための環境が、丹念に作り上げられていることに感銘を受けました。
ここでの教育の根幹には、教師と児童、保護者が一体となって対話を重ねることで、子どもたちの成長を多角的にサポートする姿勢がありました。
今回の研修を通して、私はデンマークの社会システム、特に福祉と教育において、日本が学ぶべき多くの側面があると確信しました。
特に、その根底にある「対話」の文化は、日本のウェルフェア、そして当社の未来を考える上で、非常に重要なエッセンスとなります。
同時に、日本がこれまで培ってきた福祉の強みも理解し、両者の良い部分を組み合わせたハイブリッドな福祉モデルを目指すべきだと考えています。
まずデンマークの福祉・教育システムは、徹底して人間中心に設計されています。
障害の有無に関わらず、誰もがその人らしく生き、社会に貢献できるような環境が整えられています。
これは、単なる「支援」という枠を超え、一人ひとりの「存在」そのものを肯定し、尊重する思想に基づいています。
この「共に生きる」思想は、対話を通じて個人のニーズを深く理解し、尊重することから生まれています。
ウェルビーイング委員会長として、この「共に生きる」思想は、まさに私たちが目指すウェルビーイング(心身ともに満たされた状態)の本質であると深く感じました。
そして日本においては、介護保険制度や障害者総合支援法など、社会保障制度が整備され、全国どこでも一定水準の福祉サービスが提供されるという公平性とアクセシビリティの良さがあります。
一方、デンマークのように個々のニーズに深く寄り添い、その人の人生全体を支えるようなきめ細やかな支援という点では、まだ発展の余地があると感じています。
そこで目指したいのは、日本の全国的なサービス提供体制の安定性と、デンマークの個別のニーズに応じた柔軟な支援、そして対話を通じた人間尊重の姿勢を組み合わせたハイブリッド型福祉です。
具体的には、既存の制度の枠組みを活かしつつ、地域コミュニティにおける共生モデルの推進、そして何よりも、福祉・教育に関わる全ての人々が、支援される側・する側という区別なく、対等なパートナーとして尊重され、自身のウェルビーイングも高められる文化を育むことが重要です。
そのためには、日常のあらゆる場面でオープンで建設的な対話を重ね、誰もが安心できる関係性を築くことが不可欠です。
デンマークで「ペタゴー」と呼ばれる専門職は、福祉や教育の現場において極めて重要な役割を担っています。
彼らは単なる介助者や教師ではなく、個々の能力を引き出し、社会参加を促すための専門的な知識と技術を持つプロフェッショナルです。
研修で目にした、ペタゴーと障害を持つ方々が共に音楽を奏でる姿は、彼らが「支援」という一方的な関係ではなく、共に創造し、成長するパートナーであることの証でした。
この協調性も、日常的な対話によって育まれるものです。
平和活動委員会長として、私はこのペタゴーのあり方の中に、平和な共生社会を築くための重要なヒントを見出しました。
異なる背景や能力を持つ人々が、お互いを認め、尊重し合い、それぞれの役割を果たすことで調和が生まれる。
これはまさに、争いのない平和な世界を築く上で不可欠な要素です。
そしてその基礎にあるのは、互いを理解しようとする対話の努力に他なりません。
また、デンマークでは、福祉、医療、教育など、様々な専門家が密接に連携を取り、横断的な支援を提供しています。
この多職種連携は、個々のニーズにきめ細やかに対応し、より質の高いサービスを提供するために不可欠であり、社会全体の安定と調和にも繋がっています。
ここでも、専門職間の円滑なコミュニケーションと対話が、連携を成功させる鍵となっています。
日本においては、訪問介護やデイサービスなど、地域に根差したきめ細やかなサービス提供体制が強みです。
長年培われてきた地域との繋がりや、顔の見える関係性は、日本の福祉の大きな財産です。
土屋として、このデンマークのペタゴーの概念を日本版にローカライズし、福祉従事者の専門性を高めるための研修制度の充実、そして多職種連携を円滑に進めるための仕組みづくりに積極的に取り組むべきだと考えます。
当社の訪問介護事業においても、単に身体介護や生活援助を行うだけでなく、クライアントそれぞれの個性や可能性を引き出すような「ペタゴー的視点」を持った支援を強化していくことで、サービスの質を飛躍的に向上させ、ひいては社会全体の平和に貢献できると考えています。
オーデンセの障害福祉課で伺った税金に関するお話は、非常に印象的でした。
デンマーク国民は、高い税金を負担することに対して、それが社会全体の福祉に還元され、自分たちの生活の質を高めているという明確な理解と納得感を持っています。
これは、単に制度として税金があるだけでなく、その税金がどのように使われ、どのような社会を築いているのかが、国民一人ひとりに深く浸透していることの表れです。
この背景には、行政と国民の間で税金の使途や社会のあり方について、常に透明な対話が行われていることがあります。
貧困問題対策委員会長として、この国民の意識の高さは、貧困問題への根本的なアプローチとして非常に重要だと感じました。
デンマークの充実した福祉制度は、セーフティネットとして機能し、貧困に陥るリスクを軽減しています。
税金が適切に分配され、誰もが安心して暮らせる社会が構築されているからこそ、相対的な貧困も少なく抑えられているのです。
日本においても、生活保護制度など、困窮者に対するセーフティネットは存在しますが、受給へのハードルや、社会的なスティグマなど、改善すべき点も多いのが現状です。
土屋として、そして社会貢献企業として、私たちが提供する福祉サービスが、社会全体のどのような価値に貢献し、ひいては貧困問題の解決にどのように寄与しているのかを、クライアントや地域社会に対して積極的に発信していく必要があります。
そして、それが巡り巡って、私たち自身の生活や未来にどのように良い影響を与えるのかを、具体的に示していくことで、福祉に対する社会全体の理解と意識を高め、貧困の連鎖を断ち切る一助となることができると考えます。
このプロセスにおいても、ステークホルダーとの継続的な対話を通じて、信頼関係を構築し、共通の目標に向かって協力していくことが不可欠です。
デンマーク研修で得た学びは、当社の社内価値観や文化にもポジティブな影響をもたらすものと確信しています。
特に、「対話」を核とした企業文化の醸成は、当社の持続的な成長と社員の幸福に直結すると考えています。
研修で私が最も強く感じたのは、デンマーク社会に深く根付く人間尊重の精神と多様性を受容する文化です。
これは単なる建前ではなく、日常生活のあらゆる場面で実践されています。
障害を持つ方々が当たり前のように社会に参加し、それぞれの個性を発揮している姿は、まさにその象徴でした。
そして、この基盤には、お互いを理解し、受け入れるための丁寧な対話が存在しています。
私はこの「対話」と「多様性受容」こそが、土屋の企業文化の核となるべきだと強く認識しました。
当社の企業理念にも対話や多様性受容について掲げられていますが、これをさらに深く、具体的な行動に落とし込んでいく必要があります。
社員一人ひとりが持つ個性や多様性を積極的に認め、それぞれの強みを活かせるような組織文化を醸成すること。
これは、単に障害を持つ社員に限らず、年齢、性別、国籍、価値観など、あらゆる多様性を持つ社員が、自分らしく働き、能力を最大限に発揮できる環境を意味します。
具体的な取り組みとしては、インクルーシブな職場環境の整備、多様な働き方の推進、そして社員一人ひとりの声に耳を傾け、それを組織運営に反映させる仕組みづくりなどが考えられます。
誰もが安心して発言でき、自身の能力を最大限に発揮できる、対話が活発な空間こそが、創造性と生産性を高め、結果として企業全体の成長に繋がると信じています。
デンマークの教育システムは、子どもたちの自律性を重視し、自ら考え、行動する力を育むことに重点を置いています。
これは、社会全体に根付く「自律と責任」の思想と強く結びついています。
国民一人ひとりが社会の一員としての自覚を持ち、自らの行動に責任を持つことで、社会全体が機能していると感じました。
この自律性を育む上では、一方的な指示ではなく、対話を通じて個人の内発的な動機を引き出すアプローチが重要です。
ウェルビーイング委員会長として、社員一人ひとりの自律性と責任感を高めることは、彼らのウェルビーイング向上に直結すると考えています。
上意下達の指示待ちではなく、自ら課題を発見し、解決策を提案できるような主体性を持った社員を育てることで、仕事へのエンゲージメントが高まり、自己効力感が向上します。
具体的には、権限委譲の推進、チャレンジ精神を奨励する評価制度の導入、そして失敗を恐れずに学びを深めることができるような心理的安全性の高い職場環境の構築が挙げられます。
社員が自身の仕事に意味と価値を見出し、オープンな対話を通じて互いにフィードバックし合い、自律的に業務に取り組むことで、充実感と幸福感を高めることができるでしょう。
フォルケホイスコーレは、生涯学習の場としてデンマーク社会に深く根付いています。
年齢や職業に関わらず、人々が常に新しい知識やスキルを学び続ける姿勢は、私たち企業にとっても非常に重要です。
平和活動委員会長として、この「学び続ける文化」は、社会の課題を理解し、その解決に貢献するための基盤となると考えます。
多様な視点から学びを深めることで、私たちはより広い視野で平和への貢献を考えることができます。
そのためには、異なる意見を持つ人々との対話を通じて、相互理解を深めることが不可欠です。
また、貧困問題対策委員会長として、貧困の原因や現状、そして解決策について常に学び、知識を更新していくことが不可欠です。
社会の変化や利用者のニーズに柔軟に対応していくために、土屋は常に学び続ける組織でなければなりません。
社員のスキルアップを支援するための研修制度の充実、新しい知識や技術を積極的に取り入れるための情報収集の強化、そして社員同士が知識や経験を共有し、共に成長できるような環境づくりを進めていくべきです。
特に、福祉という分野は常に進化しており、最新の知識や支援方法を学び続けることは、質の高いサービスを提供するために不可欠です。
そして、この学びを通じて得た知見を、土屋の社会貢献活動に活かし、対話を通じて人々の共感を呼び、平和で持続可能な社会、貧困のない社会の実現に向けて、具体的な行動を起こしていく所存です。
今回のデンマーク研修は、私にとって多くの感動と示唆を与えてくれました。
デンマークの社会システム、特に福祉と教育における「共に生きる」思想、ペタゴーの役割、そして国民の税金に対する意識の高さに加え、その根底に流れる「対話」の文化は、日本のウェルフェア、そして当社の未来を考える上で、非常に重要なヒントを与えてくれました。
CCO、ウェルビーイング委員会長、平和活動委員会長、貧困問題対策委員会長というそれぞれの立場から、この研修で得た学びを土屋の企業活動に深く組み込んでいく所存です。
デンマークの個々を尊重する手厚い支援と対話の文化、そして日本のきめ細やかな地域密着型サービスや社会保障制度の強みを組み合わせたハイブリッドな福祉モデルを追求することで、私たちはより質の高い福祉サービスを提供できると確信しています。
社員一人ひとりが自分らしく輝き、心身ともに満たされ、自律的に成長できるような「対話」を重んじる企業文化を築き上げ、社会に貢献できる企業として、さらに発展していくことができると考えます。
デンマークで感じた「ヒュゲ」の精神―居心地の良い雰囲気や楽しい交流から生まれる満足感―は、こうした対話文化の賜物であり、私たちの目指す組織のあり方を示唆しています。
この研修で得た熱い想いを胸に、土屋の全社員と共に、より良い未来を創造していくためにこれからも尽力してまいります。
私たちは多様性を尊重し、対話を通じて互いを理解し、共に成長し、そして何よりも、誰もが安心して暮らせる社会の実現に向けて、これからも歩み続けます。
株式会社土屋について
株式会社土屋は、高齢者や障がい者の方々がより良い生活を送るための介護サービスを提供し、また、さまざまな社会的ニーズに応えるための事業を展開するトータルケアカンパニーです。
■会社概要
会社名:株式会社土屋
所在地:岡山県井原市井原町192-2久安セントラルビル2F
代表取締役:高浜敏之
従業員数:2,766名
設立:2020年8月












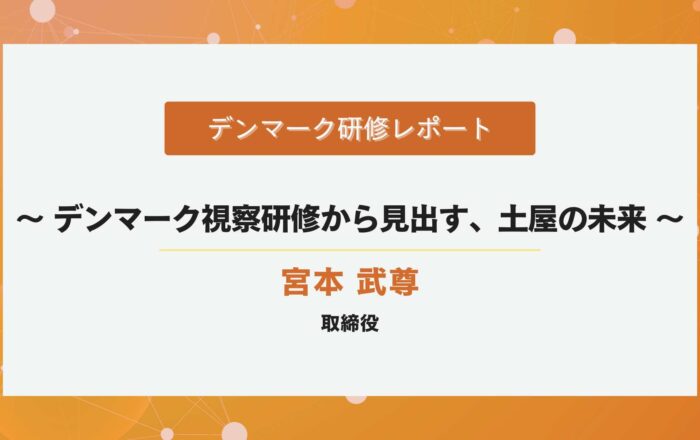

-1.png)




















