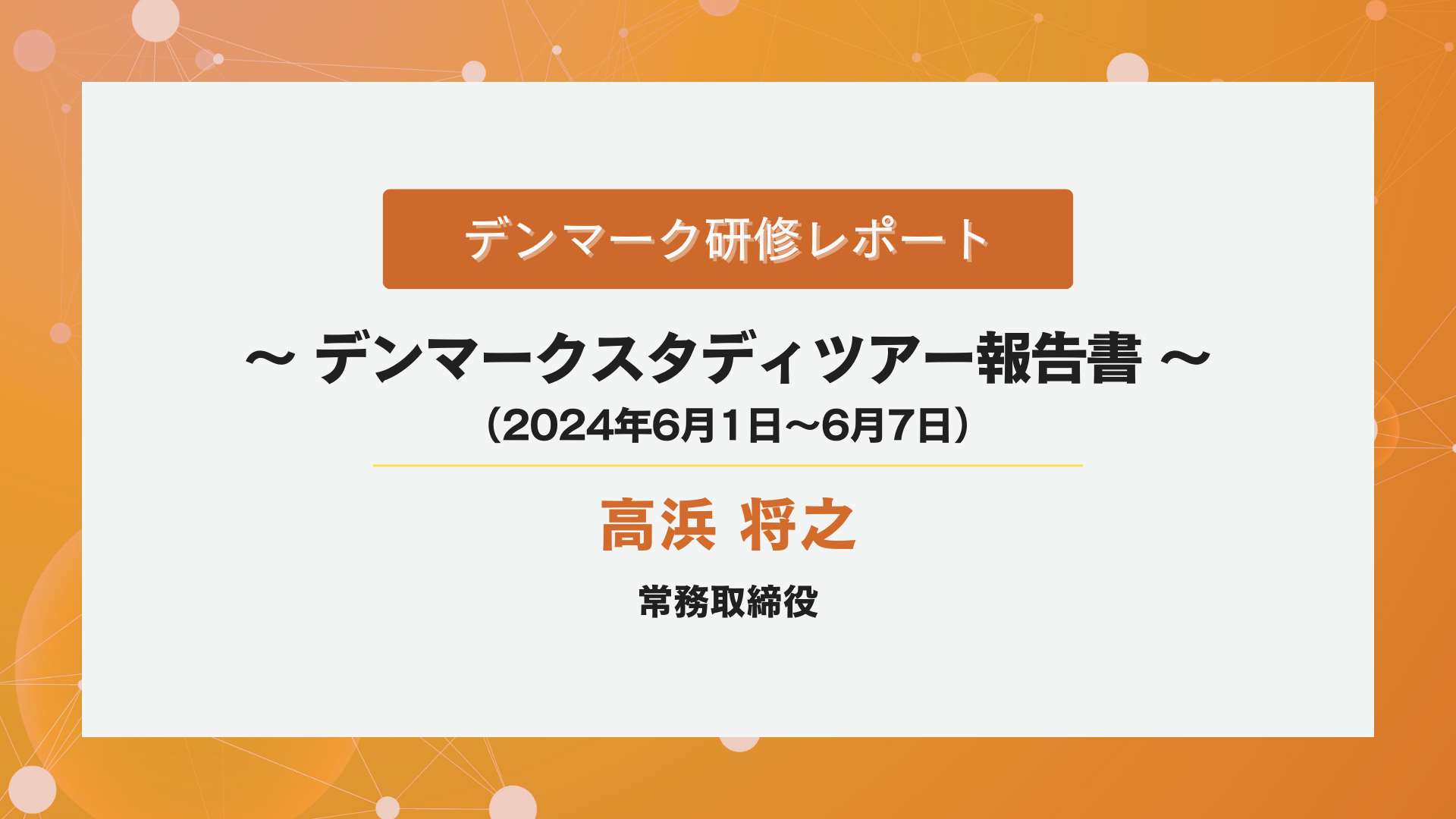
『デンマークスタディツアー報告書(2024年6月1日〜6月7日)』高浜将之(常務取締役)
はじめに
このたび、デンマークスタディツアーに参加する貴重な機会をいただきましたこと、心より感謝申し上げます。
限られた期間ではありましたが、デンマークという国の福祉、社会制度、文化、そして人々の価値観に直接触れることで、これまでの知識や想像とは異なるリアルな姿を体験することができました。
以下に、その気づきと学びを整理してご報告いたします。
1. デンマークという国に対する印象
デンマークに到着して最初に驚いたのは、交通機関における「自己責任」と「信頼」に基づいた運営の仕組みでした。
駅には改札も駅員もおらず、乗客はチケットまたはICカードを使って自己精算。
日本では無賃乗車を防ぐために駅員配置や改札機など多くのコストをかけていますが、デンマークでは「違反する人に高額の罰金を科す」という抑止力によって、人件費を削減し、無駄な税金支出を回避しているという印象を受けました。
また、街中では見知らぬ人同士が気軽に声を掛け合う様子が見られ、公共空間における心理的な距離が非常に近いことに気づかされました。
実際、電車内で向かいに座った女性に「ティッシュ持ってない?」と声をかけられた場面では、異国の地で頼りにされる喜びとともに、日本ではあまり見かけない光景に感銘を受けました。
こうした小さな相互扶助の積み重ねが、「幸福度の高さ」に直結しているのではと感じました。
2. 福祉施設の見学と現地での学び
体調不良の影響で全ての訪問先に同行することはできませんでしたが、参加できた施設では深い学びが得られました。
作業所での音楽活動では、演奏の巧拙に関係なく、参加者全員が「音楽を楽しむ」ことに集中していたのが印象的で、演奏者の表情からは心からの楽しさが伝わってきて、支援者と利用者という立場の違いを感じさせない関係性に、多様性が自然な形で実現できていると感じました。
在宅支援についても、私たちが日本でイメージする「自宅での一人暮らし」とは異なり、グループホームのような共住型の住宅環境で、それぞれに個室が与えられ、自立と支援が調和した空間が整えられていました。
福祉ワーカーとのディスカッションの中で、「専門性の定義とは?」という問いに対して「定義づけるのは難しい。
だからこそ一人ひとりが哲学を持っているべきだ」という答えが返ってきたことは、非常に印象深く、福祉という営みにおいての“意味を持つ”ことが問われていることを実感しました。
3. デンマークの福祉制度と民主主義的な意識
デンマークは「高福祉・高負担」の国として知られていますが、その本質は、税金をどのように効率よく社会に還元するかという「配分主義」にあります。
実際に、滞在中に体調を崩して病院を受診しようとした際、「その程度では医療は受けられない」と案内され、ホテルでの療養を勧められました。
この対応は冷たいものではなく、「限られた医療資源は本当に必要な人に集中させる」という明確な哲学に基づいているようで、日本のように“誰でもすぐ病院へ”という文化とは対照的で、社会全体で「自分の健康は自分で守る」という共通認識が形成されていることに驚きを感じました。
また、ドイツとの国境近くまで足を延ばした際には、移民受け入れを巡る社会構造の違いを体感しました。
ドイツでは街中に移民の姿が多く、多文化共生の様子が見られる一方で、ゴミの多さや雑然とした印象もありました。
これに対し、デンマークは移民政策において非常に選別的で、言語能力・就労経験・文化的な適応力など厳格な基準が存在し、福祉国家を維持するために「統合できる移民のみを選ぶ」というスタンスを取っているようです。
こうした背景には、国民の間に「私たちの税金は、私たちの社会のために使われるべきだ」という共同体意識が強く根付いており、それが制度の安定性と幸福度の高さを支える一方で、ある種の排他性を伴う側面も垣間見えました。
4. 強制収容所跡地訪問とバンク・ミケルセンの思想
ツアーの最終日には、フレズレフにある強制収容所跡地を訪問しました。
この施設は、ノーマライゼーションの理念を提唱したバンク・ミケルセンが第二次世界大戦中に収容されていた場所でもあります。
彼は1944年、ナチス・ドイツに抵抗するレジスタンス活動の一員としてゲシュタポに逮捕され、極限状態の中で「人が人として扱われないこと」の深刻な事態に直面し、
この体験が、後に「障害者があろうがなかろうが、普通の暮らしをするべきである」というノーマライゼーションの思想へと繋がり、世界中の福祉政策に多大な影響を与えることとなり、この訪問は、福祉の原点を見つめ直す極めて貴重な機会となりました。
まとめ
今回のスタディツアーを通して、デンマークという国の制度や文化にじっくりと触れることができました。
福祉の充実や制度への信頼、そして国民一人ひとりの自律的な姿勢。
その背景には、はっきりとした価値観と合理的な考え方があり、それが高い幸福度にもつながっているのだと実感しました。
同時に、そうした仕組みや意識が、時に「自分たちとは異なる他者」を遠ざけてしまう側面もあるのではないか——そんな一抹の緊張感を感じたのも事実です。
それでも、この旅で得た学びや気づきは、これからの日本の福祉や地域のあり方を考える上で、非常に重要なものであったと感じています。
このような貴重な機会をいただけたことに、心から感謝しています。
本当にありがとうございました。
株式会社土屋について
株式会社土屋は、高齢者や障がい者の方々がより良い生活を送るための介護サービスを提供し、また、さまざまな社会的ニーズに応えるための事業を展開するトータルケアカンパニーです。
■会社概要
会社名:株式会社土屋
所在地:岡山県井原市井原町192-2久安セントラルビル2F
代表取締役:高浜敏之
従業員数:2,766名
設立:2020年8月












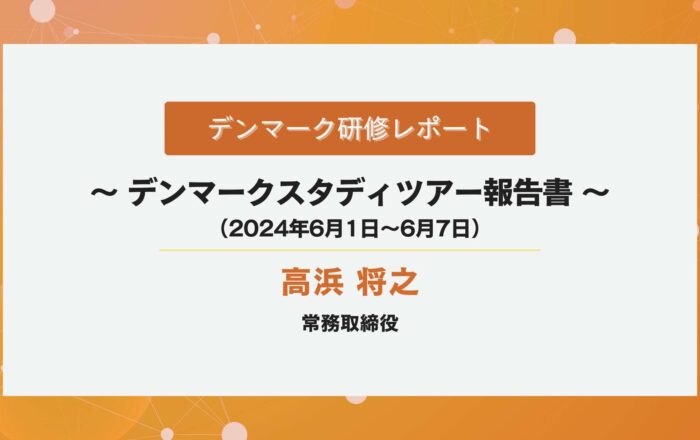

-1.png)




















