【高齢者地域生活推進委員会】定例レポート 2025年2月20日
開催概要
開催日:2025年2月20日
開催場所:オンライン
当日のアジェンダ概要
- 事業所の課題や取り組みの共有(定期巡回)
- マネジメントの悩みについて
当日の定例レポート
当日の定例ミーティングでは、ご家族との介護観のズレにより、管理者が現在抱えている課題が提示されました。
また、事業所内で対応の難しいアテンダントがいることから、マネジメントにおける管理者の悩みについての相談がありました。
双方ともにコミュニケーションの必要性、そして具体的なコミュニケーション方法について、参加者から有益なアドバイスが多く上がりました。
1.事業所の課題や取り組みの共有(定期巡回)
<相談内容>
クライアントの臀部に“できもの”ができ、傷口からの出血およびご本人より痛みの訴えがある。
ご家族からは「陰部の洗浄・清潔保持が一番大事なため、“できもの”がなくなるまで毎日お風呂場でシャワーを流してほしい」という要望を承っている。
当事業所からは、その実施に当たってご家族に病院受診をお願いし、受診・薬の処方を受けていただいた。
現在は、1日3回、お風呂場でシャワーを流し、臀部の傷口に対して薬を付けているが、かゆみが身体に出始めてきた。
当初は乾燥の可能性もあり、ご家族に市販の保湿クリームを塗ることをご提案し、そのようにしているものの、本人は体中がかゆいとのことで、乾燥が原因ではないと思われる。
クライアントが通われているデイサービスに連絡したところ、デイサービスでも身体を傷になるほど掻きむしっているとのことで、
当事業所とデイサービス双方からご家族に病院受診をお願いしているが、ご家族は「病院に行かない」の一点張り。
ただ、ご家族もクライアントを大切にされていて、何とかしたいという思いはあり、薬を使わない対策として行われたのが、お肌にとてもいいシャワーヘッドへの交換。
しかし、かゆみや赤みがももの内側などにも出てきており、ご本人も「すごくかゆい」と掻いており、当事業所としては、婦人科や皮膚科で原因を突き止めてもらって進めるのが良いと考えている。
ご家族に病院受診を受け入れていただくにはどうすればよいか。
<質問による補足>
・訪問看護に医療面からのアセスメントはしてもらっている。
ケアマネは変わったばかりだが、ご家族は当事業所に責められていると感じているのか、ケアマネに「土屋の肩ばかり持たないで」と言われている。
そのため、今後は毎月1回必ずご家族に会いに行き、関係性を作ってから提案などしたいと考えている。
<委員会メンバーよりコメント>
・かゆみには色々原因があり、疥癬など感染するものもある。
ご家族や周りの関係者にも感染する可能性があるので、感染症のリスクを訴えてみるのはどうか。
それが自分ごとになる一つだと感じる。
また、かゆみが内臓から来ていれば、内服でなければ治らないこともあり、受診して原因を確定させるための一つとして、「自分にも影響があるかもしれない」という伝え方もいいと思われる。
・以前、クライアントの顔に“ただれ”が出たものの、同じように「薬が嫌だ」というご家族がいた。
訪看が入ったことにより、少しずつ薬の受け入れができてきて、最終的に病院に行ってくれた。
そこで処方された薬で治ったことから、同じ状態になると薬を塗るようになった。
できものが酷ければ、「ここから介護では厳しい」と、ケアマネを通して訪看に入ってもらい、徐々に訪問診療につなげるなどしないとうまくいかないと思われる。
時間はかかるが、この先も何かあった時は同じことが繰り返されると思うので、介護の目線というより、訪看の介入も一つの方法だと思う。
・レアケースだが、かゆみの訴えがあり、突き詰めると洗濯洗剤や柔軟剤など合成のものにアレルギーがあるのでダメだという方がいた。
ドクターからは「天然成分の石鹸や洗濯洗剤しか使わないように」という指示があったこともあるので、いろんなケースをご家族にお話しし、受診していただくのがいいと思われる。
・以前、ドクターが「人間は継続するとつらいものが3つある。
一つ目が痛み、二つ目が苦しみ、そして最後がかゆみだ。
それがどれだけ人間の精神をむしばむか」と仰っていたが、このご家族も母親のことを思う気持ちは強いので、
「本人にとってはつらいことであり、介護では治せないので受診していただけませんか」という伝え方がいいのではと思う。
・訪看からご家族に病院受診をお願いしてもらうことはまだ試していないとのことで、次のアセスメントを早めて、訪看から受診の声掛けをしてもらうのもよいと思われる。
・心が折れたり、関係性を続けていくことで支援する側が報われなくなり、とてもしんどいと思う。
このご家族はその方なりに母親のことを思っていて、その方なりの守り方があると思うが、残念ながら私たちから見るととてもバランスが偏っている。
ただ、その方がキーパーソンであり、当事者の介護に決定権がある中で、やりきれない気持ちはありながらも相手を変えるのは難しく、
そうしたことから訪問などで関係性を今より良くしていくために頑張るのは大切だと思われる。
訪問した際には、ご家族のニーズをまずは引き出し、ご家族の気になっていること、しんどいこと、こうしたいと思っていることをしっかりと聞き取るのがよいと思う。
そこを一生懸命聞くだけでも関係性は良くなると思うし、今まで思ってもみなかったニーズが分かった時にできることが変わって来るかもしれない。
完全に解決はしなくても、私たちが介入することでとても悪い事態にはならないようにしていく、低め安定というところで、こちら側のモチベーションを保つのが大事だと感じる。
・ご家族は良かれと思ってしていることが、今まで周りから否定されてきた経験もあると思う。
定期的に訪問して信頼関係を作ると、「あなたが言うなら」となることもあるかもしれない。
⇒事業所管理者:ご家族の提案を呑み込んだケースがある。
アテンダントからは否定的な意見もあったが、一度ご家族の言う通りにしてみて、それでダメならまた次の手を考えられるので、アテンダントにもご家族のご提案通りのことをしていただいている。
・起業している方は自分なりの解決策で組み立てていかないと気が済まない面がある。
それで失敗すると納得して、修正していけたりもするので、たとえ間違っていると思っても、その方の納得を得るために横道にそれても我慢して付いていき、
それで身をもって違うと思われた時、本人が求めてきた時にアドバイスするのが最適解だと思われる。
2.マネジメントの悩みについて
<相談内容>
マネジメントがすごく苦手な分野で、強い態度や強い口調、顔に出るなどがあると仕事を振れなくなります。
現在、困っているのがアテンダントのAさんです。
私だけに限らず、他のアテンダントにも強い口調で言われる方で、アテンダントからは「一緒に同行するのが嫌だ」という相談や、
同行後につらかったと泣いた人もあると聞いていて、アテンダントのみなさんも疲弊しています。
私もなかなか強く言えず、耐えてはいましたが、私自身も疲弊してしまって上長に相談したところ、上長が面談してくださり、Aさんも今は態度を改めてはいます。
けれど、また緩んできたときには強い口調や態度が出てくると思っています。
毅然とした態度でちゃんと伝えることが大事だということは上長からも教わっていますが、なかなかそれができないのでどうしたらいいのかと思っています。
また、どんな言い方だったら人に伝わるのかなと。
強い口調の方に対して、また年上で、今まで積んでこられたキャリア・プライドがある方に対して、どうマネジメントしたらいいのか、
苦手分野のマネジメントをどう克服したらいいのか、アドバイスをいただければありがたいです。
<上長からの補足>
当管理者の疲弊がピークになり、どうしてもマネジメントしきれないという相談を受けたので、私と私の上長の2人でAさんと面談を実施し、
実際にアテンダントも疲弊しているし、管理者も仕事を振り切れないというところで、改めていただきたいとお伝えしました。
Aさんからは自分の言動の理由も伺いましたが、職員に求められる言動があり、
行動が伴っていないので改めていただく必要があるというのと、改善しない場合は再度面談させていただくことをお伝えしています。
現在は、Aさんも自身が変わるよう意識してくださっているという報告を受けています。
<質問による補足>
・Aさんとうまくコミュニケーションを取れて、苦手としていない職員がいるかどうかは分からない。
・Aさんは感情を表に出したり、すぐに口に出してしまうなど、我慢が難しい方。
また、自分が思っていることと違うことが起きたなどで強い態度や口調をし、それが全職員に伝わることで、ピリピリした感じとなる。
<委員会メンバーよりコメント>
・Aさんは、人に対して期待しすぎかもしれない。
期待しすぎているから、「どうして私の気にしてるように周りは気にしないんだろう」と、そこにイライラして、勝手にしんどがっているのかもしれない。
周りが自分のイメージ通りに動いてくれないことに対してストレスを感じている可能性がある。
提案としては、Aさんの大変さに共感はしないまでも、「そういうところでAさんはすごくストレスを感じてるんだよね」といったことを話してみるのもよいと思われる。
Aさん自身もベストは尽くそうとしている中で、周りがそれに応えてくれないとか、気づいてほしいことに気付かないことなどに勝手にイライラしていると思われるため、
少なくともそこについては「お察しします」という会話だけでもしてみた上で、Aさんが「そうなんだよね、どうしたらいいのかな」と口にした時に、初めてアドバイスが効く気がする。
アドバイスには攻撃的なところがあるので、本人が求めてもないところにアドバイスするとストレスになることもあり、
まず本人がストレスに感じていることに共感し、少しでも助けを求めてきたときに言ってあげられることがあると思う。
・当管理者の上長が話したことで、Aさんも自分の行動を改めているのは救いだと思う。
性格自体はなかなか変わらないと思うので、鼬ごっこの気もするが、私自身、広域でマネジメントしていると、どうしてもコミュニケーションが希薄になり、苦手な人とはコミュニケーション頻度が減っている。
振り返ると、「そういえば喋りやすい人とばっかり喋ってるな」と感じるが、問題が起こる時はコミュニケーションが希薄だった時で、それが私自身の失敗の中で一番多い。
Aさんは上長が話したことにより改善しているような方なので、例えば月1回でもAさんと話す機会をもってみたり、今までよりも“意識的に”近づくことをした時に、もしかしたら改善するかもしれない。
言いやすくなる環境ができるかは分からないが、ポジティブな方向には向かっていくと思うので、意識的にコミュニケーションの量を増やすのもよいかもしれない。
・女性ならではの“強く言えない”などもあると思う。
私もそういう経験があり、自分一人というわけではなく、上長を頼りながら皆で解決していければと思う。
<委員会メンバーのうち、新管理者の状況>
・私自身、自分を犠牲にして自分でしてしまうこともあったり、介護を始めてまだ2年あまりの中で、周りがベテランばかりなのでやりずらいと思うところもあります。
スタッフの中には、15年ほど管理者をしていて、なかなか管理者の癖が抜けず、まだ管理者の気分でいる人もいて、他のスタッフさんも負担に感じているところがありますが、
私自身、これまで生きてきた中での経験や、介護を始めた後に上司の方々から話しを聞く中で、一番必要なのはコミュニケーションだと感じています。
私自身も周りの上司の方たちを頼っていますが、管理者の立ち位置としてはとにかくコミュニケーションをして、
皆さんから話を聞いて、いろいろな意見が出たとしても、まずは事業所のルール、会社の理念を第一に考えています。
話をするだけで落ち着いたり、話を聞いてくれる人の命令・指示は聞くというタイプの方もいると思うので、
まずはコミュニケーションを取って話を聞いて、マイナス面から入らないことに励んでいます。
・人間関係は難しいと思っています。
私もコミュニケーションを取るのが苦手で、任せたい仕事も多くありますが、任せきれず自分でしてしまっています。
管理者になった当初はお願いすることもあったんですが、嫌そうな反応をされたりすることもあって、それが嫌で、そこからさらに自分でするようになった感じです。
まだ一杯一杯にはなってないんですが、なかなか大変で、なんとか頑張っている状況です。
⇒上長より:彼が悩んでいるのは入社当初から聞いていますが、背景として当該事業所はM&Aで土屋グループとなり、彼はその後に入社し、管理者という形で就任しました。
周りのスタッフはその事業所で10年ほど働いている方たちなので、やりにくい環境がまずありました。
けれどそういう状況下でも、彼は赤字が続いていた事業所を黒字化するなど、結果をしっかり出しているので、
彼が今までやっていることや、これからやろうとしていることは正解だと考えていますし、その話もずっとさせてもらっています。
ただ、スタッフさんを置き去りにしないようにするにはどうしたらいいか、スタッフ個人との関係性をどういうふうに作っていくかについては、
スタッフの性格や特徴を見極めて、一辺倒な対応ではなくて、若干の個別性を出しながら対応したり、しっかり仕事を依頼していただきたいとは思いますが、それがなかなか難しいところだと感じています。
【高浜将之委員長による総括】
悩みを皆で共有できること自体が、この委員会の価値であり、意義のあることだと感じています。
会社として、難しいアテンダントや部下がいる時、その方にどう対応するかがまず一つありますが、同じようなことはまた起きてしまうと思います。
そうした方以外にも同じような方はいらっしゃり、キャリアアップしていく中で一定数がそうなってしまうのも事実です。
今回の件は上長が対応してくれて今のところ改善していますが、ここで改善できることもあるし、これが繰り返されたとき、この方に限らず、
こういう方もマネジメントできるのがマネージャーとして成長していける・キャリアアップしていけることにもつながってくると思いますので、そこの対応方法についてはいろんな形で皆でディスカッションしていければと思います。











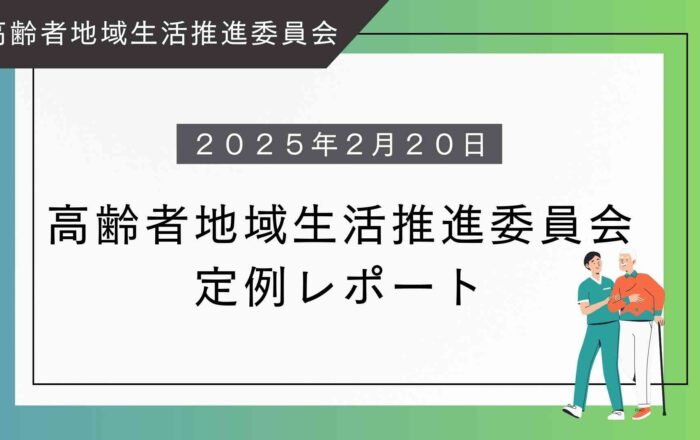
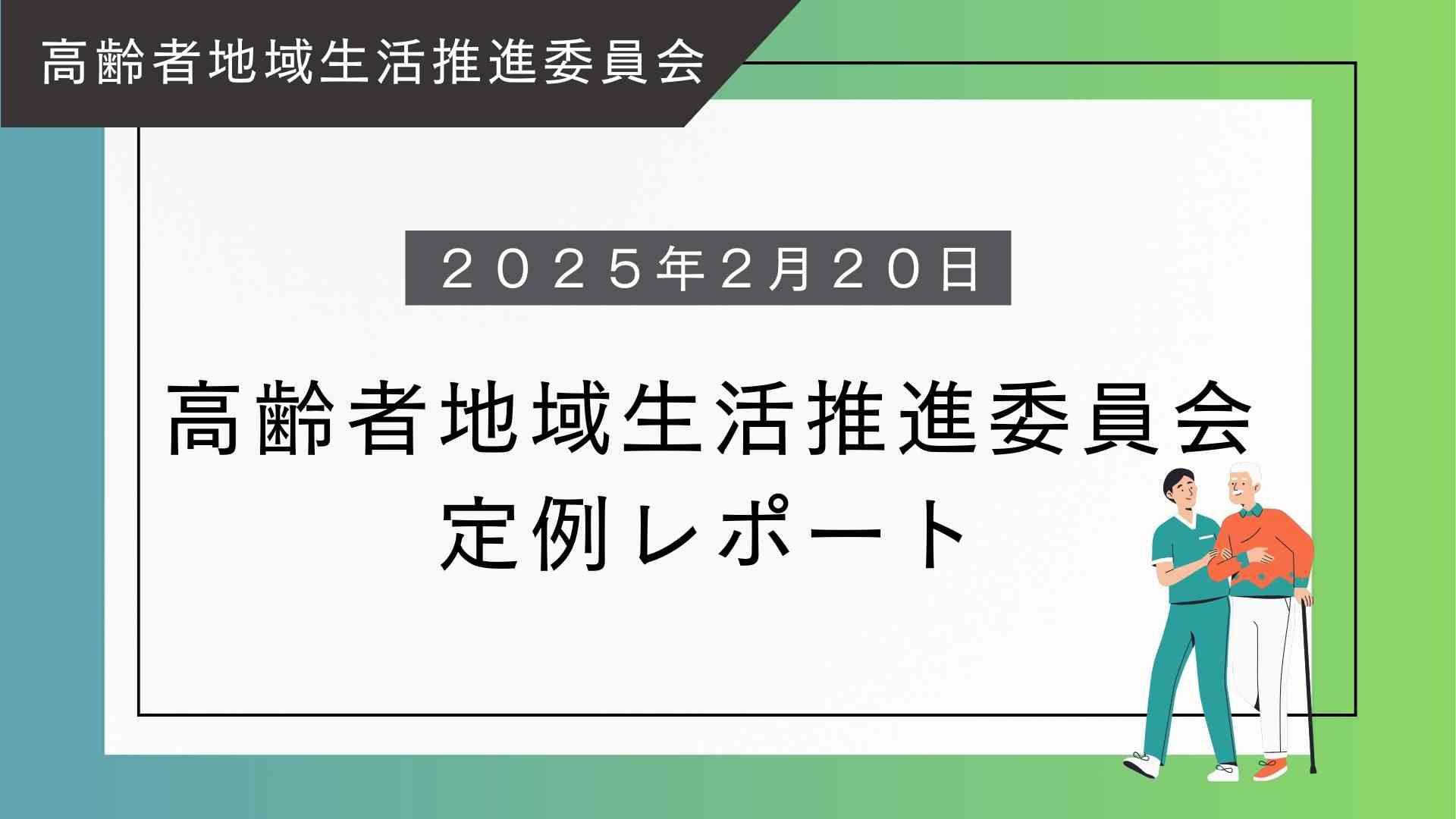

-1.png)




















