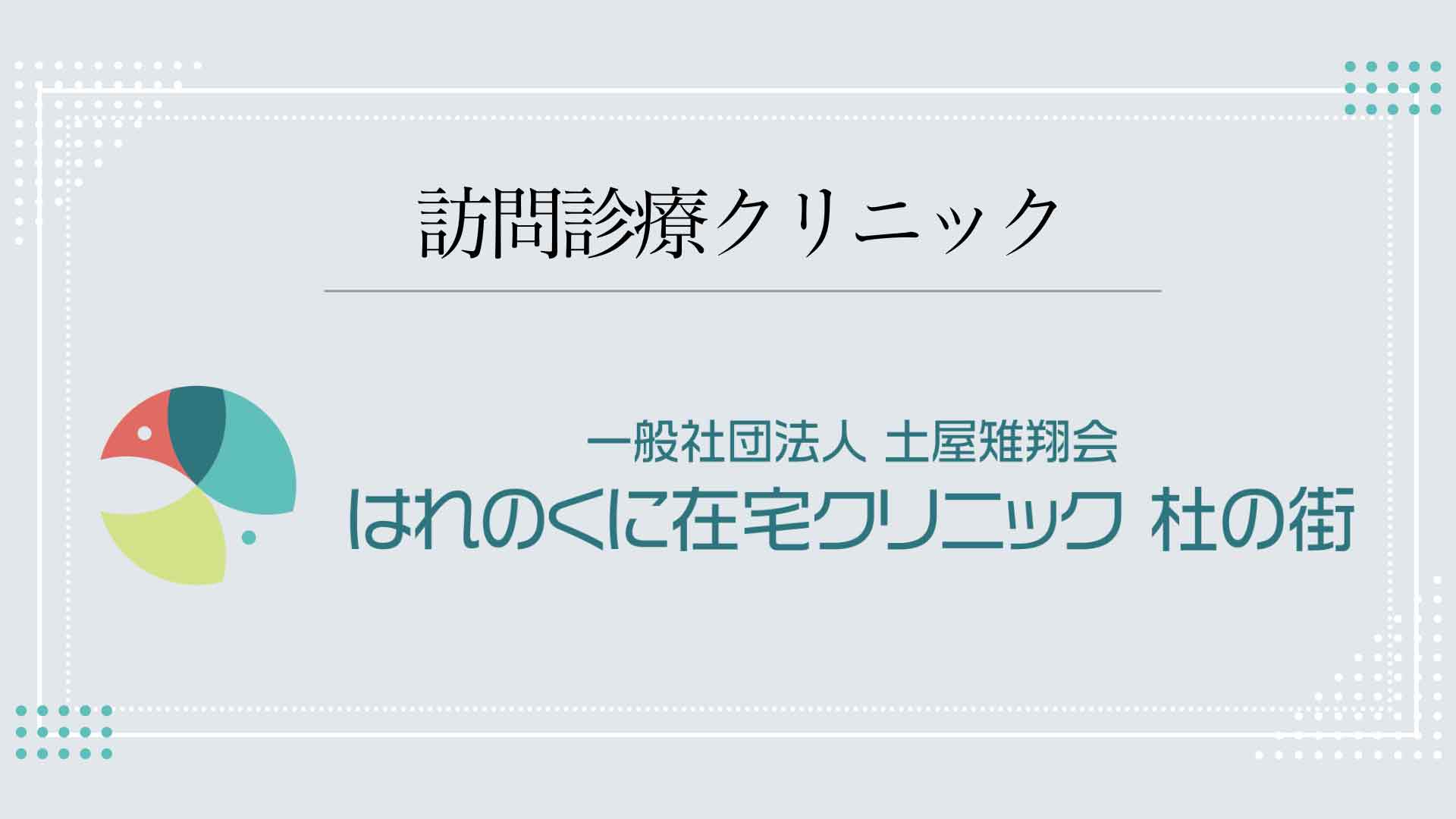土屋ブログ(介護・重度訪問介護・障害福祉サービス)
私は読書家ではない。世の中には、とんでもない読書家がいる。
先ごろ亡くなった立花隆の読書量がすごい。自ら「3万冊の本を読み、100冊書いた」というが、蔵書は10万冊を超える。自宅では収まりきれず、個人事務所(猫ビル)に移したという。立花隆の読書は、本を書くためという明確な目的があってのものである。
同じことが、我が畏友寺島実郎さんにもいえる。寺島さんも自宅にあった何万冊もの本を事務所ビル内の寺島文庫に所蔵している。そこに案内されたことがあるが、まるで図書館のような膨大な量の本が並んでいて圧倒された。寺島さんにも数多くの著書がある。私は寺島さんを勝手に「知の巨人」と呼んでいるが、立花隆は元祖「知の巨人」である。
作家で元外務省主任分析官の佐藤優は月に300冊の本を読むそうだ。そういった多読の有名人は他にもたくさんいらっしゃる。こういったスーパー読書家とは比べるべくもないが、年に300冊読む程度の読者家は、世の中にあふれている。私は最盛期でも年に100冊がやっと。現在は、読書はさっぱりできていない。だから、私は読書家でないと断言できる。別に、こんなことを断言してもしょうがないのだが。
大学で教えている頃、学生にある本を貸してあげた。返してもらった時に、「どうだった」と訊いたら、中身についての感想ではなく、「大学に入って初めて読んだ一冊です」という答えが返ってきた。ゼミの学生の中にも「私は活字が嫌いなんです」と平気で言うのがいた。ここの大学だからではない。若い人が本を読まないのは事実である。読書家ではなかった私、その私の青年時代には、常に何冊かの本が身の回りにあって、ポツポツとではあるが、本を読んでいた。スマホなるものはなかった。今は、時代が違うのだろうか。
読書は義務ではない、権利である。読書は楽しみでもある。「浅野史郎の愉快な人生」も、本がなければ成り立たない。一年に一冊の本を読むか読まないかといった程度の非読書家の若者たちよ、君たちは、本を読む楽しさを味合わないままで人生を終えるつもりか。人生の終わりが近づいている73歳の老人(私のこと)は、こんな余計な心配をしてしまう。
本を読むか読まないかは、育った家庭の環境の影響が大きい。親が本を読むような家庭、部屋中に本がある家庭では、読書好きの子が育つ。私もそうだった。小学生時代、家の書棚に平凡社の世界文学全集、日本文学全集が並んでいた。二人の姉が一巻ずつ取り出して読んでいるのを見ていた史郎少年は、自分も真似して読みたいと思ったのだろう。今でもうっすら覚えているのは、「風とともに去りぬ」、「レ・ミゼラブル」。小学生がどこまで内容を理解して読んでいたかは不明だが、ともかく本人は読んだ気になっていた。
小学校からの帰り道の途中に、田中書店があった。母方の祖母がやっている本屋さんである。そこでしょっちゅう、雑誌「少年」、「少年クラブ」、「野球少年」、「痛快ブック」、「少年画報」を読んでいた。「少年サンデー」、「少年マガジン」の創刊号を読んだのも田中書店の茶の間であった。「少年漫画文学全集」というのもあったなあ。こういうのも、読書というのなら、当時の私はすごい読書家であった。
同じく小学生時代、学校の図書館から借りた本を読んでいた。「十五少年漂流記」(ジュール・ベルヌ)が、血湧き肉躍る面白い本として記憶に残る。題名は忘れたが、ちょっとした濡れ場ごとき場面があって、どきっとした本があった。本の裏表紙に貸出者名が書かれているカードがついている。そこに、ちょっとだけ気になっていた女生徒の名前があるのをみつけて、「あいつもこの場面を読んだんかなあ」とちょっと変な気持ちになったのを覚えている。
◆プロフィール
浅野 史郎(あさの しろう)
1948年仙台市出身 横浜市にて配偶者と二人暮らし
「明日の障害福祉のために」
大学卒業後厚生省入省、39歳で障害福祉課長に就任。1年9ヶ月の課長時代に多くの志ある実践者と出会い、「障害福祉はライフワーク」と思い定める。役人をやめて故郷宮城県の知事となり3期12年務める。知事退任後、慶応大学SFC、神奈川大学で教授業を15年。
2021年、土屋シンクタンクの特別研究員および土屋ケアカレッジの特別講師に就任。近著のタイトルは「明日の障害福祉のために〜優生思想を乗り越えて」。





















-1.png)