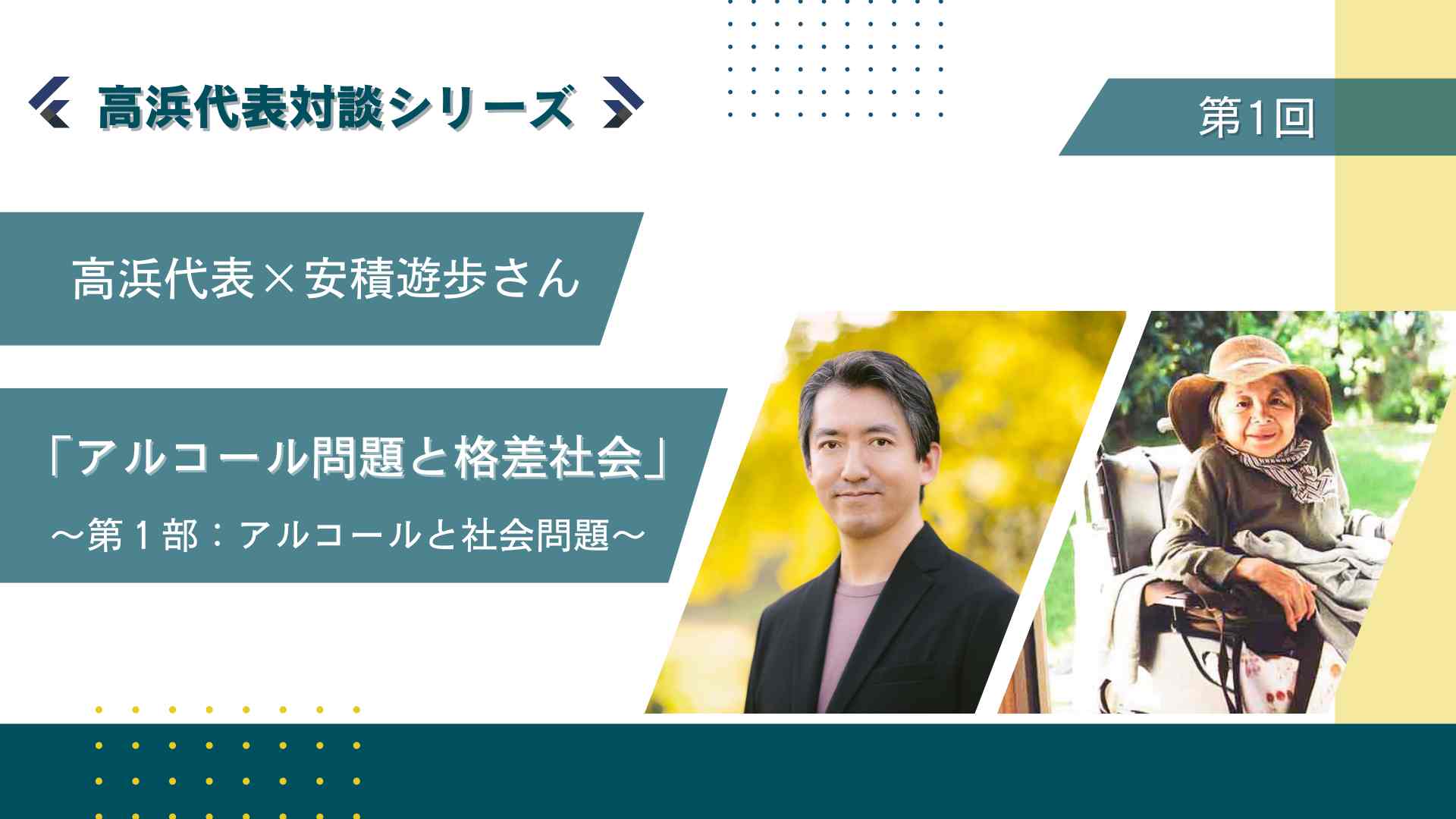
「アルコール問題と格差社会」~第1部:アルコールと社会問題~
対談参加者
安積 遊歩……株式会社土屋 顧問
司会……宮本 武尊/取締役 兼 CCO最高文化責任者
なぜアルコール問題から始めるのか

今回新たに始まりました連続対談シリーズ第1弾として、
お二人は「アルコール問題と格差社会」をオープニングテーマとして取り上げられましたが、
なぜアルコール問題から始めるのかについて、個人的体験も含めてお願いします。

私自身は、障害者差別から逃れるためにアルコールに依存して、
でもアルコール自体がさらに私に追い打ちをかけて依存を促進して、
それでキッチンドランカーになりかけた時に大けがをしたんだよね。
でもそこで命拾いしたことで「アルコールをやめよう」と決断したわけです。
そこからアルコール問題に目を向けていって、はま(高浜代表、以下同)に出会い、
はまにも「やめたほうがいいよ」と、会うたびに言ってた時期があったよね。

はい、そうです。

私も昔はあまりにもつらかったから飲んでたけれど、はまもそうだったよね。
障害者運動の中のアルコール依存というのは、当事者の障害を持つ人も、介助者もとても多かった。
その中で、はまは自分のアルコール依存にすごく取り組んだよね。
それが、この会社ができる大事な要因だったと思うんだよね。
やっぱり、依存症であったからこそ、「ケアの大事さ」に気づいてきたんじゃないかなと思うんですよ。
この会社が、送別会とか色んなときにアルコールなしでイベントをするということもすごくユニークで、
非常にポリシーのある会社だと私は思っているんですよ。
そこに至る経緯はどういったものなの?

これは個人としての視点もあれば、経営者としての視点もあるんですが、
まず経営者としては、正直アルコールに迷惑をかけられている(笑)

(笑)

アルコールを過剰に飲んで問題を起こして、有意な人材が消えていったり、
社内で問題を起こす人の多くが大酒飲みだったり、嫌な言い方かもしれませんが、
経営者として「ほんとにアルコールが迷惑だ」というのが、この問題を取り上げる大きな理由の一つですね。
個人の観点から見た時には、自分自身が大概迷惑な人間だったなと。
私もかつては経営者じゃなくて、どこかの会社に所属してたわけで、ほんとに色んな人に迷惑をかけてきたと思ってるんですよ。
確信があるんですよね。みんなに「ごめんなさい」と謝って回りたいくらいです(笑)

(笑)

ただ、びっくりすることが、アルコールをやめるまで自分が周りにとって迷惑な人間だと全く思ってなかったんですよ。
なんなら周りが「物分かりが悪い」とか「不寛容だ」というように捉えてた。
やっぱりこの自分の認識の変化というか、コペルニクス的転換は驚きすらありますよね。
二人の出会いと依存症との闘い

お二人は長年の付き合いとのことですが、出会いはどのようなものだったんでしょうか?

私は30歳でこの障害福祉の世界に入ったわけです。
そこで、重度全身性障害者介護人派遣事業(現 重度訪問介護)制度を使っての自立生活に初めて触れて、
その自立生活を作ってきた運動というものに触れたんですけど、これは大酒飲みだった私にとっても衝撃と感動があったわけですよね。
「素晴らしいな」と思って、飲みながらその世界に没入していったんですが、
ケアワーカーとして木村英子さん(現 参議院議員)が代表を務める団体で働き始めた数か月後ですね、
その団体みんなで、アドルフ・ラツカというスウェーデンの障害者運動のリーダーの講演を聞きに行ったんです。
その時に初めて遊歩(安積遊歩、以下同)に出会ったんですね。
彼女はパネルディスカッションのパネラーで、その時のトークにびっくりしちゃって、本当に感動したんです。
障害者運動の感動と同時多発的に起きたところもあったわけですが、そこを切り開いた当事者に魅入られて、
本も読んでますます感動して、「何とかこの人とお知り合いになりたい」と。
そしたら、たまたま自分の職場のすぐ近所に遊歩の事業所があって、連絡したら「うちに遊びに来ていい」という。

B&Bやってたからね。

それで景子さん(妻)と一緒に遊びに行ったのが、
遊歩との関係性の出発点だったんですよね。
で、ますますこの人から教えをいただきたいと。
この人が「やれ」っていうことは全部やろうと思ったんです。
その中で、「『再評価カウンセリング』をやりなさい」って言われて、勉強も始めたんですが、
そのテキストに【アルコール厳禁】みたいなことが書いてあって、「それはちょっと守れないな」って(笑)

(笑)

そのカウンセリングのロジック自体はすごく感銘を受けて、そこで学んだ価値観や考え方は、
実はうちの会社でも踏襲している面があるんですけど、アルコール厳禁に関しては、
「他はやるけど、それだけは受け入れがたい」と(笑)カウンセリングで出会ったみんなも結構お酒やめてるんですよ。
でも、そんなの「個人の自由だ」と思って。
その中で、遊歩に会うたびに「酒やめろ」だのなんだの言われて、
「うるさいなあ。うっとうしいな」と思って、ちょっと足が遠のいたんですよ。
それ言われるのがめんどくさいから。
なので、出入りを繰り返してたみたいな感じだったんです。

それでも、アルコールをやめようと思われたんですね。

自分の飲酒量が日増しに増していく中で、一度、依存症診断のスクリーニングテストで自己診断してみたんですよ。
2点以上がアルコール依存症っていうテストなんですけど、20点以上という、めっちゃ高いハイスコアが記録されて、「なんだこれ」って。
その時、遊歩に相談に行って、3か月くらいやめたんですよね。
でも、3か月お酒やめれる人がアルコール依存ってイメージないじゃないですか。
「違うでしょ」って思って、もう1回飲み始めて、反動でたくさん飲んじゃって、
ある時、発作症状みたいなのが起きて、離脱症状が出ちゃったんですよ。
それで精神科のクリニックに行ったら、「正真正銘の病気だ。断酒するしかない」って言われたんですよね。

あの頃は大変だったよね。

はい。ただ、私がちょっと他の人と違うのは、いわゆるアルコール依存の医療が提供する回復システムだけじゃなく、
同時並行的に、遊歩が日本に持ってきた再評価カウンセリングを積極的に使ったんですよね。
これはやっぱり独自の回復プログラムであったわけですけど、病気そのものに対する捉え方も、
他の依存症者とは10%くらい違う視点を持つことができたんです。
一言で言うと、「病を個人の問題に閉じない」ということですね。
その背後にある社会的問題も、同時並行的に見ていくような、複眼的な視点を当事者として持つことができた。
つまり、通常のアルコール依存の治療って、自己認識として、
「自分は加害者だ。だから更生していく必要がある」、その一本で見ていくんですね。
この路線だけなんですけど、私は同時並行的に、自分たちの中にある被害性、
「傷」という言い方もできるかもしれないですけど、自分自身に対してもそういう目で見たし、
共に回復の道を歩む仲間に対しても、そういう視点を持てたっていうのは、遊歩にサポートしてもらったから、
遊歩たちと出会ったからというのは間違いなくあって、やっぱり自分自身、回復の道自体も独特の歩みを進んでいるという感覚はありますね。
他のリカバリープログラムをやってる人たちとはちょっと違うというのは特徴ですね。
個人的、そして社会的問題としてのアルコール

アルコール依存において「病を個人の問題に閉じない」、
つまりアルコール依存の背景には社会的問題があるということですが、障害者運動自体もそうした構造の中にあったんでしょうか。

障害者運動というか、社会運動家に蔓延するアルコール依存症はすごいですよ。

その通り。ピアの活動の中でもすごかったよね。

これは一つの社会問題だって思ってるんですよ。

私もそう思う。
一人一人が生きる世の中が結構つらいし、介護みたいに人間関係がきわめて大事っていう仕事は他にないのに、
障害者の介助も、人間関係っていうよりは「AI、ロボットにさせろ」っていうくらいの社会になってきつつある。
でも、そのしんどさを、アルコールでごまかしたり、個人だけの問題に還元しちゃってたら、アルコール依存症は止まらない。
アルコール問題、アディクションの問題は個人じゃなくて社会全体の問題だとちゃんと捉え直さないと止まらないよね。
さっき、はまは「自分たちが迷惑な存在なんだっていう加害性を自覚していった」みたいなことを言ってたけど、
それはどういうふうにして自覚していったの?

なんとなくはありましたよ。
悪いことしちゃうわけですから。
アルコールって、いわゆる自制力を萎えさせていく薬物なので、周りに迷惑をかければ「悪いな」っていう気持ちになりますけど、
「だからやめよう」ってなるかというと、プツッとリセットされて元に戻っていくような。
場合によっては、罪悪感にずっと捉われてるのは嫌だから、「あいつがこうだから俺はこうしたんだ」みたいな自己正当化を始めたりとか。
だから「俺は悪くない、悪いのはあいつだ。迷惑をかけたのはこっちだけど」っていうようなことを繰り返してた。

個人の問題として見たら、そうなっちゃうよね。

実際、個人の問題ですよ。
治療は基本的には戦略的自責感から始めるというか、他責思考から自責思考に変えないと、
アルコールをやめるということは自分にしかできないので。
「酒造会社が作ってるから悪いんだ」とか言ったところで、酒造会社の製造を止めることはできないので、やめれるのは自分だけだと。
ただ、戦略的自責感から始めるっていうのは変わらないんですけど、自責で終わるのかっていったら、
自分自身はともかくとして、依存症に捉われてきた人たちと何百、何千人と出会ってきた中で、
その人たちの背景を聞く限り、「これはそうならざるを得なかったよね」と思う人があまりにも多かったんですよ。
依存症の回復の業界では、「なったのは本人のせいじゃないけど、治るのは本人の責任だ」という有名な言葉がありますが、実際、その通りだと思いますよ。
高いストレスで、薬物に逃げざるを得ない環境にあった人が多い印象もあるし、
依存症っていう病気は自分にしか治せないっていうのもありますしね。

治すには強烈な自覚が必要だよね。

みんな持ちづらいんですよ。
なぜなら、自分自身の被害性をクローズアップして見ちゃうと、
どうしても「あいつが悪いんだ」みたいな思考にはまっちゃうんで。
「今飲むのは俺のせいじゃない、あいつが俺にストレスを与えるから飲んでるんだ」ってなると、
いつまで経っても自分にしかできない、やめるという行動変異の選択を取ることができないですよね。
ただ、そこで終わると、ちょっと違うんじゃないかと思いますね。
再評価カウンセリングを学んで「それだけじゃないでしょ」って。
じゃあなんで本人はそうならざるを得なかったのか。
ここには明らかに社会問題があって、私の周りの脳性麻痺の人たちも社会運動家も多くがアルコールに依存していたのは、
本人のせいではないようにも見えますよね。

そうそう。
私としては、それを知ってたから、はまに「やめろ、やめろ」って言いながら、
はまの置かれてた、過去から今までのつらさもフォーカスし続けたし、
本人に責任があることだけど、本人だけを責めちゃいけないという視点もすごく大事だと思うよね。
アルコール依存と社会的構造

アルコール依存症の背景に社会問題があるということですが、お二人の経験から見えてきた社会的構造としての問題はどのようなものでしょうか。

貧困問題は依存と相関性があると思いますね。
私は生活保護を受けながら2年半、依存症の回復のために自助グループに散々出ていた中で、
アルコール・ギャンブル・ドラッグへの依存と社会的貧困の相関性が深いと感じています。
貧しい人はやっぱり社会的重圧が深いので、そうしたものに逃げる傾向があるし、そこに逃げれば逃げるほど貧困は深まっていく。
そして貧困が深まると、ますますアルコールやドラッグへの依存が深まるという、ニワトリ・タマゴ問題ですけど、とにかく相関性はあると。
というのも、毎日そういった自助グループに出てたわけですけど、
「ミーティングがやってないな、見つからないな」という時は、山谷とか寿町に行けば、すぐ入れたんですよ。
そこでは24時間とは言わないまでも、1日中どこかでやっている。
やっぱりホームレスの人とか失業者の集まる寄せ場は依存問題の巣窟なんですよね。
一方、六本木や西麻布とかでは、オーナー経営者だけが参加できるアッパークラス用のグループがあって、
覗きに行ったことがあるんですけど2、3人しかいないんですよ。
月に1回なのに。やっぱり貧困層ほどなりやすいんですよ。
で、「これは個人の問題じゃないんじゃないか」と思ったんですね。

日本ではアルコールの消費量は下がっているというデータ(日本人の飲酒傾向 – 依存症対策全国センター)もありますが、
貧困の他に感じる社会問題はありますか。

最近、女性の飲酒がすごく増えてるんだよね。
9%の甘い缶酎ハイの売れ行きがすごいらしいもんね。
あと、若い人のお酒の飲み方も変わってきてるよね。
私はいつでも20代の人との付き合いが多かった。
自分が20代の時から今までずっと20代の人と介助を通しての友達となってきた。
そうやって60代末の今も20代の人との付き合いをしている。
彼らが言うには、お金もないし、お酒を飲んで騒ぐというのはカッコ悪いという認識が広がってきているらしい。
街に出て居酒屋に行くよりも、安いお金で友達の家で飲んでいる感じ。
私やはまの年代の飲み方と、今の若い人たちの飲み方ってだいぶ違うなと思うよ。
いっぱい集まってワイワイ飲むなんて場は、今の20代の人にはあまり聞かないよね。
ただ、心配になる飲み方をしてる。
缶酎ハイとかが甘くて安くて酔いやすいらしい。
この前も、若い女性の学生が意を決したようにね、「どうしたらいいかな。学校帰りに必ず買っちゃうんだよね」みたいに私に聞いてきた。
何人からも聞いてるわけじゃないけど、そういう飲み方自体がものすごいびっくりでね。
「お酒ってそんなふうに飲むんだ」みたいな。病的な飲み方だよね。
彼女は就活の不安で飲んでたみたいなんだけど、就職が上手くいったことによって「もうやめた」って言ってくれた。
嬉しくて、本当に良かったなと思ったよ。
酒造会社も、これは世界的にもだけど、中高年の男性がアルコール問題で健康を害して亡くなってきているから、
若い人や女性にターゲットを移してきていると。
実際、そうだと思うよ。
それが広がるように安い値段で買えたりね。
今は昔みたいにワイワイ飲んで、お金のある人におごってもらったりという関係もできにくいから、
貧しい学生が安いお金でお酒を買って、ひそかにボロボロになっていくことが多いんだろうなという気がします。
若い人たちが経済格差による苦しみからアルコールを使って向き合わないようにしている、いや、向き合えないようにしている社会があるよね。
アルコールの消費量っていうことだけなら、たしかに少なくはなってるけど、
深酒になっているかもしれないなという気はしているね。
孤独の中でね。
だから社会問題なんだよ、これは。
なぜアルコールに依存したのか~依存からの脱却に向けて~

お二人がアルコールに頼られた要因も、そうした社会問題の一つとしてあったものなんでしょうか?
また、そこからどのようにアルコールに頼らなくても良くなられたんですか?

自分がなんで飲んでたのかと考えると、確かにお酒自体が好きだったですけど、
やっぱり主たる目的は「飲みに行こう」と言って友達ができると。
友達作るのが苦手だった自分にも友達ができるようになったという、これがやっぱり大きかったと思うんですよね。
だからよく、「アルコールは治療行為だ」って言いますけど、人間関係に対する治療行為であったというのは、まぎれもない事実だと思います。
でも今は、自分がかつてお酒を飲むことを通じて作ろうとしていた時間とか、
求めていた体験が、ウーロン茶とかコーヒーで得られてるんですよね。
それは、まずはスキルが上がったということがあると思うんです。
人と仲良くなるのが苦手だって言いましたけど、今はあんまりそう思われないわけです。
経営者なので、どんどん仲間を作るのが仕事でもあり、むしろそれが得意だからこの会社もできたって思われますが、昔は絶対違ったんですよ。
でも今は、どっちかというと得意のスキルに入るんですよね、仲間づくりって。
一言で言うと、昔と比べて、コミュニケーション能力が上がったんだと思うんですよね。
じゃあなんで上がったのかと言うと、もしかしたらお酒を飲むことを通じて色んな人と出会って、色んな人とコミュニケーションした結果として、
コミュニケーション能力が上がったから、もうお酒飲まなくても友達ができるようになったと。
だから寂しいとかってないんですよね。
一方で、アルコールは友達もできるんだけど、敵もできるわけであって、なんなら敵のほうが多かったわけで。度が過ぎちゃうと。
「二度と来るな」って言われた店が何軒あったかと(笑)今はウーロン茶飲みながらなんで、敵ができないですよね。

アルコールという手段を使って、危ない橋ではあるんですけど、
ご自身のコミュニケーションスキルを磨いてきたことで変わったわけですね。

もはや飲まなくても友達はできますと。
でもかつては飲まなければできなかった時期もありました。
じゃあ、小さい頃はどうだったかというと、友達すぐできました。
仲間いて寂しいなんかひとつも思ったことなかったです。
これが遊歩から教えてもらったRCメソッドのロジック、「傷」ってやつですよね。
人間関係って嬉しいこともあれば、嫌なこともあるじゃないですか。
嫌な経験をたくさんしていくうちに、だんだん他者と自分を隔てる壁みたいなのが分厚くなっていって、
友達なんか自然にできていたのが、いつの間にかできなくなった時期があったんですよね。
なぜかと言うと、「傷つき経験」だと思うんですよね。
その壁をぶち破るツールとしてはアルコールは明らかに役立ちましたよ。
ただ一番いいのはスパーリングなんか必要ない状態であって、
これは別の治療行為があり得たはずですけど、私は見つからなかったという感じですね。

安積さんは始めに、差別から逃れるためにアルコールに依存したと仰られていましたが、実際、どのような思いがあったんですか?

私は障害を持っているというところで、この社会の権威である地域の中学校の校長から車椅子で来られては迷惑だと言われました。
養護学校に行くべきだと。ひどい差別だよね。
差別で打ちのめしておいて、それを麻痺させるべくアルコールを用意する社会。
これは個人の問題では本当にないよ。
はまはアルコール依存症者の存在自体が迷惑だって言うけど、この社会は動けない身体を持つことが迷惑だと言ってくる。
つまり、言ってこられた私の身体から、障害というか人との違いは絶対になくならないわけだから、
私はやっぱり、「感じたくないし、考えたくない」ということのためにアルコールを使っていったんだろうと思いますね。
もちろん、この社会から排除され、差別されている障害を持った仲間たちとの間には、アルコールがなくてさえ、
すごい共感と、一体の活動があったんだけれども、やっぱりあまりに大変でつらいから、
夜に活動が終わったら、また一杯飲みながら話すという時代があって。

でも、アルコールが飲めない時から、飲んではいけない時から、差別されたことの結果として、
差別されてつらい時にはアルコールに走るというパターンができてたんだよね。
私、14歳で急性アルコール中毒になったことがある。
中学校から「車椅子の子は入ってはいけない」と言われて、
私がつらいっていうのを父親も感じたのか、「もっと飲んでいいぞ」なんて言ってね。
父親はアルコール依存だったから。
それで急性アルコール中毒になりかけて、母親が救急車を呼ぼうかってものすごい焦っているシーンの思い出があるんですよ。
だからキッチンドリンカーになった時には、結婚したかったにもかかわらず、
ものすごい排除とか差別にあって、「殺すぞ」みたいな強迫も受けていたから、それを感じたくない、見たくない、
そこから逃れるためにアルコールを使ったんですよね。
今は結婚制度に全く興味も関心もなくて、これこそ差別制度だなって思ってるくらいで、自由になってきてるんですけど、あの時はしたかった。

あと、どうしてこんなにも戦争が、人を殺すのは良くないってわかってるのに止まないかっていうと、
一つは戦場でアルコールが使われているから。
うちの父親も大日・帝国軍隊の一兵卒として、多分残忍な加害者だった。
その後、シベリアで捕虜となり、そこでは被害者でした。
凄まじい戦争体験者なんですよね。
彼も生き延びるためにアルコールを使いまくっていた。
戦後も毎晩飲んでいた。
飲酒の最初は、祖父がアルコールで破産して満州に逃れてから「自分は絶対飲まないぞ」と決めていたのに、
現地徴収の二日目でベロベロに飲んだし、飲まされたと聞いています。
アフリカや南米の少年兵はアルコールを意識がなくなるまで飲まされ、
親を殺させられた後は、残酷の極みに立つようになると読んだこともあります。
戦争でアルコールが使われている事実をきちんと見ないと、平和は来ないでしょうね。
アルコールには敵、味方という概念を強烈に作り出し強化する暴力性がある。
私も自分の身体に対する暴力をアルコールでふるいまくっていたわけです。

私個人はアルコールで置かれている差別的な状況から逃れたい、逃れられるんじゃないかっていう幻想の中で使い続けてきましたね。
でも、絶対に逃れられないって知ってて、だから、はまが言ってくれてるけど、
ちゃんと「アルコールがなくても聞き合える」っていうことを、その傷も含めて、
そのつらさをお互いに聞き合えるのが大事だろうなと思っていますね。

ありがとうございました。
第1部ではお二人の体験を通して、社会問題としてのアルコール依存についてお伺いしました。
引き続き、第2部に入らせていただきます。












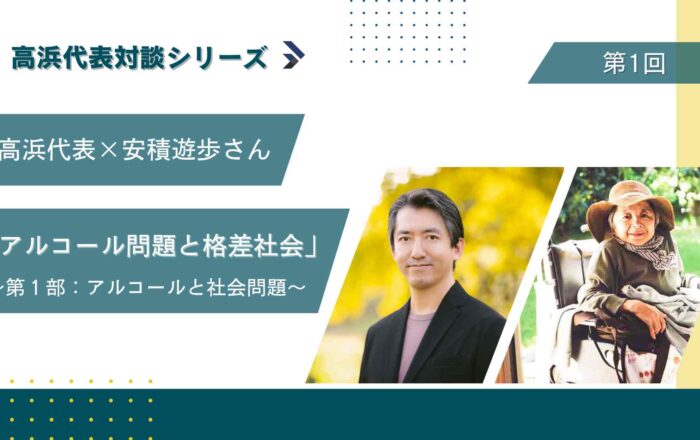







-1.png)




















