2年前の10月7日からのパレスチナに向けたイスラエルの徹底的な虐殺攻撃は、今年の夏の憂鬱をさらにさらに深めるものだ。その上、ありえないと思っていた核兵器に対する肯定的なプロパガンダを口にする政治家が出てきている。
父が生きていたら、この状況をなんと言うだろう。父は10代でアルコール依存の祖父に連れられて、自覚は全くなかっただろうが、満州の植民地主義者となった。それどころか父は、小学校の頃には神社の前を拍手(かしわで)を打たずには通り過ぎることのできない軍国少年でもあったという。
22歳の時に、10年くらい過ごした満州のその地で現地徴収され、天皇の一兵卒となった。その後2年半、その地の人々の命と暮らしとつながりを踏み躙っていった。そこで彼が何をしたのか、彼が直接話してくれたことはない。しかし思い起こせば、父が戦争トラウマを抱えて苦しんでいたことは明白だ。なぜそう思うかといえば、おおまかに言って三つ理由がある。まず一つ目は、彼のアルコールに対する依存は病的なものであったからだ。二つ目は、アルコールを飲んでも飲まなくても、母の料理に対する貶しようは、文句というレベルを超えて、言葉の暴力だった。そして三つ目は、夜驚症である。中国でのことなのか、シベリアでのことなのか、一度も聞けなかったが、急に大声を出して飛び起きることが時々あった。私はしょっちゅう骨折していたので、痛みで眠れない夜、父のその声を聞いて、さらに眠れなくなったものだ。これらの戦争トラウマは、加害者としての2年半と、被害者としての4年半のどちらも関係しているに違いない。
シベリアで捕虜となった父は、戦犯としては告発されなかった。戦犯が裁かれた東京裁判は、米軍と戦った兵隊だけを丁寧に裁いたのだ。父のようにシベリアに抑留された捕虜は、そこでの過酷な労働が懲役刑とみなされたのかもしれない。その刑を終えるために、シベリアの捕虜たちの日本への帰還は遅れた。父もまた、1945年が敗戦であるにも関わらず、1950年代直前の帰還であったという。
ところで今日特に書きたいのは中国のことだ。中国に捕虜となって捕まった日本兵たちへの、中国の政治家・周恩来の処遇のあり方についてである。彼は捕虜に対して、彼らがどんなに行動で極悪非道なことを中国人民にしていたかを強烈に知りつつも、それに報復するということは全くしなかったのである。それどころか捕虜たちに、彼らを監視する中国の人たちよりも良いものを食べさせた。日本の捕虜たちは、特に将校クラスの生活能力が全くないものが多かった。だから自分たちで炊事・洗濯・掃除をやれるように徹底的に指導した。読書や書道、演劇など、暮らしを楽しむための文化活動も奨励した。
唯一の捕虜のタスクは、正直に自分のやったことを書いて、書いて、報告するということだった。ほとんどの捕虜は、正直に書けばどんな罰を受けるかということを恐れて、はじめは少しも正直に書けなかったそうだ。ところが周恩来による捕虜への冷遇や虐待とは真逆の対応に心を開くものがだんだん現れ、最終的にはほとんどの人が、自分のやった行為の残虐さを正直に書くことで、徹底的に反省・謝罪し、少しずつ日本に帰っていった。
周恩来は、彼自身が日本に留学した経験も持っていたので、平和をつくるためには平和な暮らし、自分たちの食べるものを自分で作り、身の回りを整頓しお互いに気配りし合って、生活することなどをきちんと感じる必要があることを知っていたのだ。中国から帰還した兵士たちは「中国帰還者連絡会」という組織を作り、あちこちで戦争の凄まじい現実を講演したり、執筆していった。
私は40代の半ばでこの会の中心メンバーであった湯浅さんと出会った。彼は外科の軍医として中国にわたり、中国の人への生体実験を繰り返し、彼らの命を奪ったのだった。
軍医とは言っても歯医者や眼医者は外科手術がほとんどできなかった。彼は外科医だったので、彼らを鍛えるために中国人を捕まえてきては、ロクな麻酔もせず手足を切り取ったりお腹を切り裂いたりして、外科手術を歯科医や眼科医にさせたのだった。
捕まえられた中国人のなかには、殺されることがすぐにわかり、湯浅さんをリーベンクイズ(日本人は鬼だ)と罵って死んでいった者もいたが、中には軍医に身体を診てもらえると喜んでいる人を無惨に殺したこともあったと話してくれた。
周恩来が作った捕虜収容施設=平和に向けた捕虜更生施設は、今でも撫順というところにあって、私は5年前にそこを訪ねた。湯浅さんとの座談会は、そこを訪ねる前のことだったので、実際に訪ねた時には心から感動した。現実のなかでどうしたら平和な世界を作っていけるのかを徹底的に考え行動した人がいて、その場所があったこと。周恩来の立ち方は、戦犯管理所に働く人間にいつも受け入れられていたとは言えないこともあったと、そこを案内してくれた人が話してくれた。そちらの方が私にとっては納得できる気がしたが、それでも確かに周恩来は日本兵の中の善き人間性にコンタクトすることを諦めず、平和を作ろうと努力し続けたのだ。
私は自分のこの身体が平和の礎であることに微塵の揺らぎもない。父が巨大な暴力・戦争に巻き込まれながらも生きて帰ってきたこと、そこで極貧に近い生活の中ではあったけれど家族内に少しの暴力もなかった母と出会い、私に命をくれたこと。それはこの撫順の戦犯管理所という場所からの平和への取り組みに呼応しているものだとさえ感じている。
戦争はなかなか終わらない。けれども私は決して諦めることなく平和を求めていく。
◆プロフィール
安積 遊歩(あさか ゆうほ)
1956年、福島県福島市 生まれ
骨が弱いという特徴を持って生まれた。22歳の時に、親元から自立。アメリカのバークレー自立生活センターで研修後、ピアカウンセリングを日本に紹介する活動を開始。障害者の自立生活運動をはじめ、現在も様々な分野で当事者として発信を行なっている。
著書には、『癒しのセクシー・トリップーわたしは車イスの私が好き!』(太郎次郎社)、『車イスからの宣戦布告ー私がしあわせであるために私は政治的になる』(太郎次郎社)、『共生する身体ーセクシュアリティを肯定すること』(東京大学出版会)、『いのちに贈る超自立論ーすべてのからだは百点満点』(太郎次郎エディタタス)、『多様性のレッスン』(ミツイパブリッシング)、『自分がきらいなあなたへ』(ミツイパブリッシング)等がある。
2019年7月にはNHKハートネットTVに娘である安積宇宙とともに出演。好評で再放送もされた。

















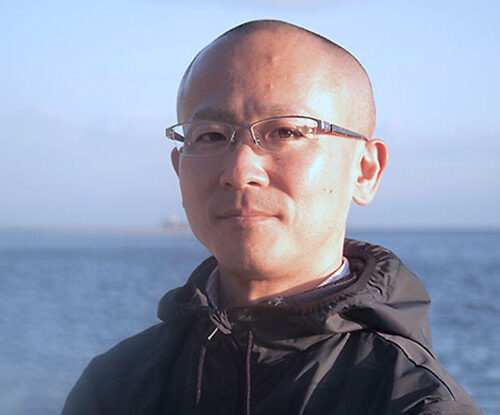
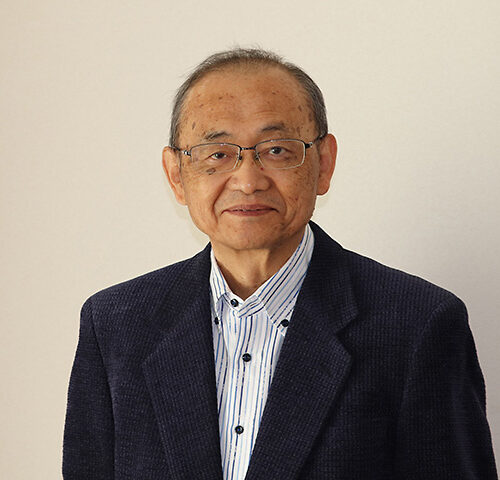

-1.png)




















