土屋ブログ(介護・重度訪問介護・障害福祉サービス)
バスはブレーキの音と共に急に停まり、高いクラクションが二度鳴らされた。乗客たちは何のためにバスが停まったのだろうと耳を済ました。
何も聞こえなかった。
エンジンの低い音が間断なく地響きのように鳴っていた。
冬治もまた座席から身を乗り出して前方を確認したが何も見えなかった。
「なんだろう?」
独り言のようにつぶやくと、隣に座っていた母が、
「動物が飛び出したのかな」
と言った。
しばらくすると低い唸り声をあげて再びバスは走り出した。緩やかな登り坂が続き、紅葉にはまだ早い舗装された山道に入って行った。初秋の黄色味を増した太陽の光で空はいっそう青く感じられた。吸い込まれそうな青々とした空だった。
濃い葡萄色のラインの入った古びたバスが終点に着くと「駅に戻るバスは30分に一本出ている」ことを告げるアナウンスが流れた。
冬治と母親が外に出ると、街とは違う木々の冷たい香りが辺りに漂っていた。
その「展望公園」からは盆地が一望できた。
眼下に、かつてある作家がシルクハットの底と形容した盆地が広がっていた。
家々の屋根が陽の光を反射させてキラキラ光っていた。
盆地の真ん中には大きくうねりながら河が流れており、その河もまた光を反射させてキラキラしていた。
「少し疲れた」と母は言った。
展望台に登りたいと思ったが、それは諦めて眺めのよい芝生の場所を探して家から持ってきたシートを広げた。台風の影響で昨夜まで降っていた雨はすっかり乾いていた。
「このシート懐かしい」母が言って笑う。
保育園の遠足のとき買ったものだと言った。
冬治は靴を脱いでシートに座った。
早速、母は水筒からあたたかい麦茶を注ぎ冬治に渡して、自分の分のお茶を持って隣に座り、そこから一望できる盆地を見て「綺麗だねェ」と声を上げる。
「お日さまを受けて光ってる。ずっと雨だったのに、今日はいいお天気」
母が両手を広げて伸びをする様を冬治はじっと見守っていた。膝に置いた手に妙に力が入っていて、それが不自然なので力を抜きたいと思っても緩めることも怖いのだ。油断はしてはいけない。
切ない秋の風が吹いている。
山の斜面の葡萄畑の葉っぱが揺れていた。
「何年ぶりだろう」
そう言って母はトートバッグからお弁当箱を取り出してシートに並べはじめた。冬治はお弁当箱の蓋を取るのを手伝った。
サンドイッチ、卵焼き、唐揚げ、ちくわ、オリーブ、おかずが綺麗に盛り付けられていて、アルコールのウェットティッシュで手を拭いてから「いただきます」と言ってサンドイッチにまずは手を伸ばした。
母は不安そうな顔で冬治を見つめていたが、冬治が美味しいと言うとホッとした様子で自分もお弁当を食べはじめた。美味しいと言って笑った。
奇跡なのか。
冬治は思った。
これは、夢なのだろうか。
母が朗らかに笑っている。
こんな幸せそうな光景を、本当に自分が体験しているのだろうか。
◇
芝生の広場には子ども連れの家族や若い男女や高齢の夫婦など多数の人間がいて、それぞれにみんな幸せそうだった。その中に自分も入っていることが冬治には信じられない。
グラウンドに白線を引くときに先生が持っている巻尺のような長いリードを付けた小型犬が軽やかに芝生で跳ね回り、飼い主である白い帽子を被った細い女が片手でスマホを操り写真を撮ろうとしていた。
その女の奥に、冬治たちと同じようにシートを広げて若い男女が座っていた。
男は黒いポロシャツに白いジーンズ、女はレモン色のワンピースを着ていてふとももを隠すように膝に薄紫のストールをかけていた。二人とも大学生のようだった。
二人は身を寄せ合って座り、シャボン玉をしていた。
手に持ったピンク色の細いボトルに黄色のストローを入れ、シャボン液をいっぱいつけてどちらが長くたくさんシャボン玉を出せるか競い合うように吹いていた。時折ほっぺたをくっつけてじゃれ合っていた。
その二人が生み出すシャボン玉を見つけて子どもたちが寄ってくる。
子どもたちが寄ってくるのでもっと喜ばせようとして、特に男の方が次から次へとシャボン玉を作ってみせる。
そのシャボン玉が風に乗って冬治たちの方まで流れてくる。ひとつ、ひとつ、ときに連なって、流れてくる。ほとんどは途中で割れてしまうのだが、中に息の長い奴があって割れずに冬治たちの間を通過する。
それが母の頬をかすめる。
冬治はひやひやしていた。
母の顔でシャボン玉が割れたらどうしよう?
不快になり、気分が崩れてこの夢みたいな時間が台無しになってしまうのではないか、と思うと口に運んでいるお弁当も味がしない。
また母の顔をシャボン玉がかすめる。
頭上で割れる。
冬治は母の顔色を伺いながら、シャボン玉を作っている男女の方をチラチラと見ていた。
楽しそうにシャボン玉を追いかけている子どもたちのために先程にも増して大量生産を試みて、一向にやめようとしない。
若い男女二人は自分たちが子どもたちのために善いことをしていると信じて疑っていない。
「シャボン玉を作ることは誰にとっても善なのである」と思い込んでいる。
自分たちの行為は善い行為。
シャボン玉で気を悪くする人などこの世には存在しない、と思っている。
そうだろう。
多くの人はシャボン玉を善とするだろう。
しかし、それは多くの人であって全ての人ではない。
世の中にはシャボン玉のせいで母の気分が崩れないか、それを死活問題として冷や汗をかいている小学校6年生がいることを知ってほしい。
あの二人にはきっと想像できないだろう、と冬治は思う。
知らずに生きてきた幸せ者だ。
冬治は手放しでシャボン玉を楽しい遊びとは思えない。
無邪気に追いかけ回すこともできない。
母親の顔色を伺い、危ういバランスを保って日常が穏便に過ぎていくことだけを願って生きている。
「ちくわ、好きだったでしょ?」母が言った。
「うん、好きだよ」
そんなに好きではないが即答した。
「あんた、小さいときからちくわが大好きで、ずっと握りしめてたもんね」
「そうだったかな」
盆地の家々の屋根が陽の光を跳ねて輝いている。
「こっちにおいで、冬治」
ピクニック懐かしいね、昔はこうやって一緒にきたもんねーと言いながら母は冬治を自分の膝の中に招き入れ、後ろからギュッと抱きしめた。慣れないことだし、後が怖いと思うと体が硬直しリラックスすることなんて絶対にできない。
ただ、あたたかかった。
母の体はあたたかく、やわらかかった。
その熱を背中で受け止めていると何故か涙がこみ上げてくる。泣いては絶対にいけないと唇を噛み締めて我慢する。
「ごめんね、冬治」
冬治の背中に顔を埋めて言った。少し声がかすれていた。
「母さん駄目な母親だよね」
「・・・」
「それはね、分かってるの。母親失格。ごめんね。どうしてだろ。なんで馬鹿なんだろ。どうしてできないんだろ。ごめんね、冬治。ごめんね」
「もういいよ、母さん」
「苦労かけて悪かったね、ごめんね。しちゃいけないって分かってるのに、どうしてしちゃうんだろ」
「もういいんだよ」
これは夢なのだろうか。
母さんの病気がよくなって、これからは楽に生きていけるのだろうか。希望を持ってもよいのだろうか。
そんなことは決してない。
先のことは分からない。
ただ、今、このときはもしかしたら、自分は「幸せ」なのかもしれない。
刹那、「幸せ」かもしれない。
きっと長くは続かないだろう。
手のひらからこぼれ落ちていってしまう。
でも「幸せ」かもしれない。
だから、この景色と、この風の匂いと、この体のあたたかさをずっと忘れずに記憶しておきたい。もう二度と戻ってはこない。
時よ止まれ!
冬治は洋服の袖で涙を拭いた。
しばらくの間、親子は小さく丸まってひとつになっていたのであった。
ふたりを避けてシャボン玉が通過し、割れた。
◇
その日の夜、母親はこれまでの中で最も激しく叫び暴れ、近所からの通報があって冬治は児童相談所に保護されることになった。
【完結編】につづく












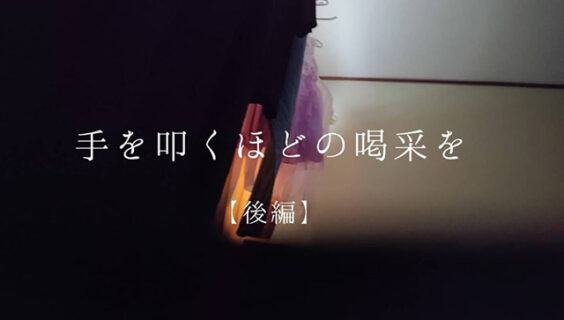


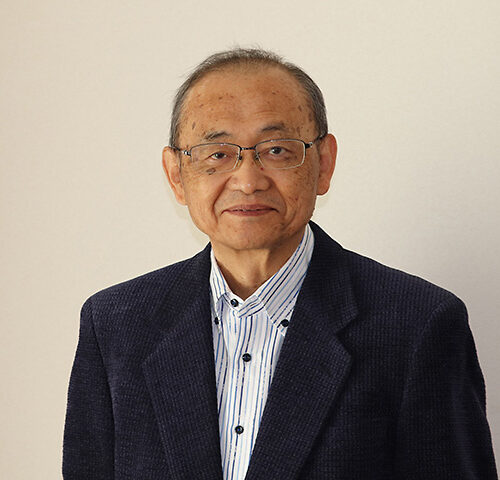




-1.png)




















