土屋ブログ(介護・重度訪問介護・障害福祉サービス)
9 私が出会った障害者運動の先駆者たち①
「木村英子さん その1」
私たちは多様性が尊重されるインクルーシブな社会の実現を追い求めている。私は約20年、様々なスタイルで、様々なチームで、様々な問題意識のなかで、一貫してこのビジョンを追求してきた。これからもこのビジョンの実現に向けた旅路を仲間と共にゆくつもりだ。
そして、この旅の出発点には、障害者運動の先駆者の方々がいた。彼女たち/彼らとの出会いとその際に刻印された衝撃の余韻によって、いまだにこの旅に対する情熱が失われていないといっても過言ではない。これから3回にわたって、その記憶とインパクトについて記述していきたい。
齢30を前にして大学を卒業した。2か所の大学に通わせていただいた。1つ目の大学は法学部、2つ目の大学は文学部。1つ目の大学は中退だった。文学哲学研究者を目指して2つ目の大学に入学したものの、私の能力も環境もそれを許すことはなかった。新聞配達奨学生として大学に通い、途中家庭の事情により休学などを挟みながら、なんとか卒業できた。
さて、どんな仕事をやろうか。
20代は飲食業や営業職やその他もろもろ様々な職種を遍歴しながら生活してきた。まず、ビジネスや商売を仕事にする気は全くなかった。生き難さを出発点として哲学や文学を学んできた自分の臓腑には、生について、死について、他者との関係について、自分なりに真剣に考えてきた痕が残っており、モノやサービスの売り買いというシンプルな世界で生きることをよしとはしなかった。
文学哲学談義をした仲間たちの中に、介護の仕事をしている人たちが何人かいた。実弟もその一人だった。彼らから聞く話に興味がそそられた。特に明確な進路も決めてなかった私は、じゃあ自分も介護でもやろうか、そんな何の気なしの気持ちで、ヘルパー2級、いまでいう初任者研修の資格を取るため学校に通い始めた。
研修で学ぶ内容は、学生時代に学んだ哲学や文学や心理学とも相通じる内容であり、興味深いものだった。資格取得のため学校に通っている期間、収入を得るために引っ越しの日雇いバイトをした。バイト先では例のごとく乱れた言葉と叱責が飛び交っていた。
方向性が決まった今となっては、かつては収入のため生活のためには仕方ないと思えた文化が、耐え難い風景に映るようになってしまった。仕事を終えて、日払いのお給料をもらって、帰り道に駅構内のキオスクで「デイリーアン」というアルバイト雑誌を購入した。早く資格を取って介護の仕事を始めたいなあと思いつつ、山手線のなかで雑誌をペラペラめくってみた。
「地域で生活する障害を持った人たちのサポートをするお仕事。無資格の方も大歓迎!!!」そんな情報が目に入ってきた。介護の仕事をするにはまずヘルパー2級の資格を取らなければならないと思っていたので、軽く驚いた。「電車降りたら電話してみようかな」そう思った。
ヘルパー2級の資格を取るまでまだ3か月くらいかかる。それまで日雇いバイトをするのもウンザリな感じはしていた。電車を降りて、道すがら雑誌を片手に電話してみた。「はい、自立ステーションつばさです。」柔らかな声音がの応答があった。つい2時間まえまで一緒に仕事をしていた日雇いバイトの上司の怒鳴り声とは180度異なる感触だった。
「介護の仕事をしたいと思ってるんですが、ここに資格なくてもオッケーと書いてあるんですけど、ほんとにいいんですか?」
一応聞いてみた。
「もちろんです!」
即答だった。
私の中に軽い歓喜がやってきた。「いまヘルパー2級を取るため学校に通っている最中ではあるんですが、ではぜひ面接していただきたいんです」そう言ってみた。「ぜひ!」そう答えてくださった。喜びが増した。
「東京都の多摩地区にあるんです。面接いらっしゃってください。ただ面接官は障害当事者になりますので、よろしくお願いします。」
そんな声が聞こえた。
「え?」と思ったが「わかりました。ではよろしくお願いします。」そう答えて、電話を切った。軽い不安がやってきた。学生時代にもボランティア活動というものに参加したことは一切なかった。正直いうと全く興味すらなかった。障害者との交流もほとんどなかった。「障害当事者の方々が面接官?サポートを受ける人たちなんでしょ?そんなことできるのかな?ふつうに話できるのかな?」面接日が近づくにつれて、不安が日増しに増した。
面接当日、「自立ステーションつばさ」がある小田急線の永山駅についた。面接時間までまだ3時間ほどある。前もって偵察しておこう。そう思った。駅から歩いて10分くらいで事務所の前についた。車いすに乗られた方々が4~5名いた。その周りには介助者と思われる健常者の方々がやはり同じくらいの人数いた。中には中学生くらいの男の子も混じっていた。
当時パーソナルサポートの介助のお仕事があるということすら知らなかった私には、ボランティアの方々が当事者を慰問しているくらいに受け取られた。まずもって周りにいる方々の佇まいは、私がこれまで見てきた「仕事をしている人」のオーラとはまるで違った。あんなにリラックスして普段着の姿でいる人は、私の中の「仕事をしている人」の定義からは完全にはみ出ていた。
こちらはリラックスどころか緊張と不安がさらに高まった。近所の喫茶店に入り、コーヒーを飲みながら、時間まで待機した。
◆プロフィール
高浜敏之(たかはまとしゆき)
株式会社土屋 代表取締役 兼CEO最高経営責任者
慶応義塾大学文学部哲学科卒 美学美術史学専攻。
大学卒業後、介護福祉社会運動の世界へ。自立障害者の介助者、障害者運動、ホームレス支援活動を経て、介護系ベンチャー企業の立ち上げに参加。デイサービスの管理者、事業統括、新規事業の企画立案、エリア開発などを経験。
2020年8月に株式会社土屋を起業。代表取締役CEOに就任。趣味はボクシング、文学、アート、海辺を散策。

















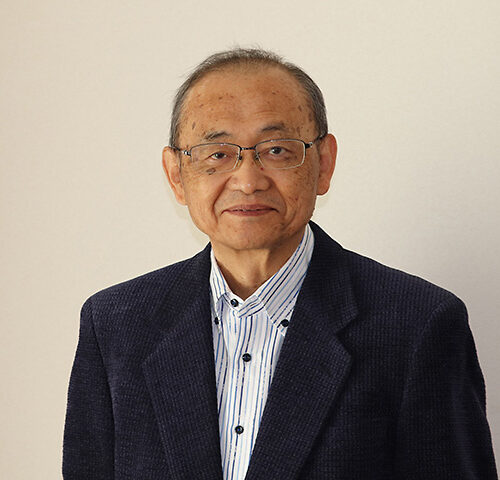


-1.png)




















