
異端の福祉を読んで / 五十嵐優希(人事部労務)
これまで「当たり前」とされていた家族による介護、病院・施設での生活。これはもはや「当たり前」の介護ではなくなっている。
その中でも著者が作り上げた「株式会社土屋」は、重度訪問介護を担っている。人間として、一個人として「当たり前」の生活を提供するのが重度訪問介護だ。しかし、現在は制度そのものの認知不足、事業者不足、財源不足という3つの不足により、障害当事者に対して十分に活用されていないのが現実である。
著者は今まで善意で行われることの多かった介護とはかけ離れた「ビジネス」を取り入れた。そんな「異端の福祉」を突き進める、それが本著の重要なポイントであるといえるだろう。
土屋ではボランティアや清貧を善しとする日本の福祉業界から逆行するように、貪欲に様々な改革を行っている。そこには著者の社会活動家としての経験、それ以前に一個人としての経験が多大に影響している。著者は各年代で様々な「当たり前」を取り巻く問題に立ち向かっていくのである。
第一章後半では介護によって発生してしまった犯罪や事件、そして障害者自身が行動し、世論を、社会を動かしたいくつかの事例が挙げられている。どれも著者が本著、そして現在の土屋でも強く発している「小さな声」を摘み取ったものやそれが集まり「大きな声」になった例であると考える。
そして著者が重度訪問介護の可能性を強く感じた「あるALSのクライアント」の話は、
「声なき小さな声」を拾い上げた、大きな体験だったのだろうと感じた。
私は現在直接クライアントとかかわることがない「人事部」であるが、ラッキーだったのは母が医療従事者であることだと考える。母の職場や、私が預けられた保育所では障害を持つ人々との関りが「当たり前」にあった。だからこそ「声なき小さな声」があることを理解できる環境で成長することができたのである。
ではそれを今の仕事にどう活かすのか、それは「聴く」ことだ。「聴く」ことで得られる「真のケア」は人事部でも共通することである。Weblio和英辞典によると「care」の意味には「気にかけること・細心の注意・配慮」が含まれていた。
これは土屋で働くすべての人に与えられるべきものであり、すべての人が持つべきもの、そう感じたのである。
私はこれを胸に掲げて日々の業務で「当たり前」に「小さな声」を拾い上げる「真のケア」を目指していこうと考えた。
整いつつある国や自治体の制度の中、利益を求める経営陣、クライアントに寄り添いたいアテンダントという二極化していく会社で板挟みにあう著者はアルコール依存症を患っていく。
その時に、自ら障害を負ったことにより障害当事者の気持ちを理解できたような気がした、真の同志になれたように感じた、と著者は語っている。
私自身障害者手帳を持つものとして、思うように仕事ができない日や、そもそも日常生活すら送れない日がある。それでも「生きていきたい」と感じていたし、今も感じている。
土屋に入社して様々な形で障害者に接し、土屋のため、ひいてはクライアントのために働く全ての人と接することでいつかそれが「当たり前」に変わるのではないか、そういった期待を持って働いているのが今の素直な感情である。
著者は土屋を経営する際に「介護難民を支援する」「福祉を夢のある仕事にする」という大きく2つの目標を掲げている。
今まで家庭内で女性が担ってきた仕事は重要であるのにもかかわらず軽視されてきたが、このような人たちの地位を高めることも重要となる。
しかし、善意のみで経営されている介護事業所には限界が訪れている。非営利だけでは成り立たないものがある。営利化することによりスケールメリットが大きくなり、善意だけではない、ビジネスとしての介護を行うことができるのである。
では善意ややりがいは全く不要なのか、それはNOだ。重度訪問介護の中でやりがいを感じられる瞬間は大いに訪れる。クライアントの居宅にいる時間が多いことや、見守りの時間があることで、人間同士の関わりを持つことができるのである。
第四章では、実際に働いている人たちの声がある。その中でも、「プロモーションに力を入れることの重要さ」に共感した。
私自身、うつ病を診断され5年が経つが、自立支援制度の利用や障害者手帳の取得を行ったのは4年目の春のことだった。なぜこんなにも時間が経ってからの取得だったのか、それは「無知」だったからである。
そんな中、私がその制度に気が付いたのは、友人が偶然福祉のことに精通しており、当たり前のように「なんで申請してないの?」と声をかけてくれたことがきっかけだった。
病気になって実感したのは、その病気に向き合うことや治療の大変さ、寛解までの期間を考えることで精一杯で、制度のことや法律のことを考えることができないということであった。
だからこそ、もし自分自身の目につくような形でプロモーションがあれば、実際に認可されるかどうかは別として、「申請」というチャレンジができたのにと感じたからである。
自分の力で生きる、「当たり前」に生きるためには制度や法律の力を借りる必要がある人がいて、でも当事者は周囲に目を向けることができない状況がある。
それを、障害の当事者にならなくても気が付ける、そんな世の中が訪れることを私は願っている。












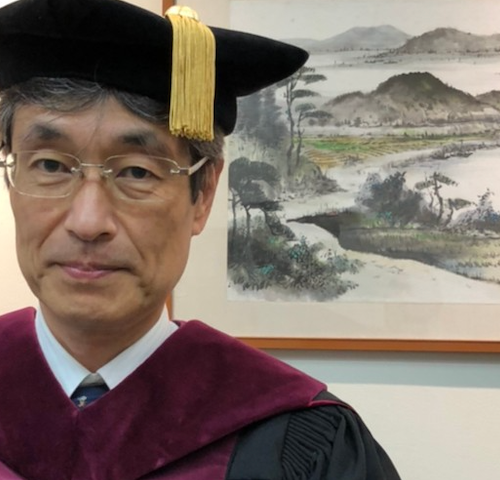






-1.png)




















