土屋ブログ(介護・重度訪問介護・障害福祉サービス)
誕生日会が終わって山咲くんの家を後にし、冬治と仲間数人は帰り道の空き地で遊ぶことになった。
誕生日パーティーに参加していなかった奴らもいつの間にか集まって来ていて、気付けば男の子女の子合わせて10人ぐらいになっていた。
仲間たちは大きな土管のあるその空き地で鬼ごっこをすることになった。
冬治はもっと遊んでいたい気持ちと早く家に帰りたい気持ちの間で揺れたが、なんとなく仲間にさよならを言うタイミングを逃してしまい、30分だけ遊んで帰ろうと思った。
鬼ごっこの途中で友だちの1人が逃げている時にテンションが上がりすぎて激しく転んだ。
右膝を地面に打ち付けてぱっくりと切れてしまい大量の出血があった。単なる切り傷なのだが、子どもたちにとっては恐ろしいくらいの血の溢れ方だった。
転んだ本人は勿論、その出血を目の当たりにした女の子は大泣き。
一緒に遊んでいた仲間もパニックになりウロウロし、中には何かよく分からない言葉を叫び出したり、怒っている奴もいた。
血は次から次へと溢れるように出た。
女の子たちはしゃがみこんで大騒ぎだった。
男の子たちは喚いて大暴れだった。
そんな中、冬治だけが冷静だった。
一切動揺しなかった。一ミリも揺れず、大騒ぎする連中を静かな目で見つめていた。
脈拍の乱れもなかった。
このくらいの状況は騒ぐようなことではない。
普段から激しく揺さぶられているのに慣れている冬治にとっては泣くようなことでもないし、感情を乱すような出来事でもなんでもないのだ。
冬治はゆっくりと転んだ子に近付き、カバンからハンカチを取り出すと血が溢れる傷に当てて「しっかり押さえててね」と言った。
「大丈夫だよ」顔を上げて転んだ子やその周りで大騒ぎしている子を落ち着かせるために呼び掛けた。
ゆっくりと立ち上がり適当な家を探してその家の呼び鈴を押した。
そして出てきてくれたおばさんに事情を話し、電話を貸してもらった。
そこまで流れるように行動を進めた。
「大丈夫、大丈夫」
みんなに呼び掛け続けた。
息は乱れていない。
感情も揺れていない。
みんながパニックになり、怒鳴り、大泣きしている情況は全然たいしたことない。
慣れている情況だ。
親しみのある情況だ。
「これが僕が住んでいる世界だ」
と、冬治は思った。
「山咲君の幸福そうな誕生日パーティーの世界に僕の居場所はなかったけれど、ここには僕の居場所がある」
怪我して泣いている子から自宅の電話番号を聞き出し、冬治が電話を掛けて事情を説明した。
15分後にその子のお母さんが迎えにきた。
お母さんの表情は血の気が引いていた。慌てて来たのだろう、髪の毛もまとまっていなかった。
「君が電話をくれたの?」
お母さんは冬治の手を取りお礼を言ってから、
「冬治君でしょ?」と名前を呼んでくれた。
「はい」
「ありがとうね。うちのは落ち着きがないから」
「………」
「お母さまは元気?」
そう聞かれて一瞬ドキッとしたが
「ええ、あまり変わりありません」と言った。
「そう…」
お母さんは憐れみのような優しさと悲しさが混じった目を冬治に向けた。
「またお母さまのキッシュが食べたいわ」
「そう伝えておきます」
「よろしくね」
これから病院にそのまま行くと言って自転車の後部座席にその子は乗せられた。既に泣くのはやめていたが肩を落としてうつむき、そして恥ずかしそうだった。
帰りながら、後部座席から振り返って「因果やな~」とその子は最後に心弱く言った。
それでその日はおひらきとなった。
◇
一人になって冬治は誕生日会で経験したことをもう一度思い返しながら家に向かった。
夕暮れが近付いていた。
冷えた大気に雑木林の匂いが混じっていた。
東の空にはすでに青黒い闇があった。
冬治は夕暮れの茜色に染まる西の空よりも青暗い闇をたたえた東の空が好きだった。
夕焼けの美しさよりも好きだった。
冬治の家は坂の上にあり、学校から帰るときは坂を登って帰らなければならなかった。
自転車の場合は立ちこぎをして長い坂をずっと登っていかなければならなかった。
中腹で坂は二股に別れ一方は青いトタン屋根の鉄工所へ続く道になり、一方は冬治の家のある住宅街に続いていた。
いつもこの二股に差し掛かると冬治は気合いを入れ直す。
家がどんな状態にあろうと自分がブレさえしなければなんとかなる、と言い聞かせる。
少し呼吸が乱れていた。
自分がブレさえしなければなんとかなる。
自分がブレさえしなければなんとかなる。
自分がブレさえしなければなんとかなる。
「大丈夫、大丈夫」
さっき大騒ぎする女の子たちを落ち着かせるために投げ掛けたように、自分の胸を擦って「大丈夫、大丈夫」となだめた。
「大丈夫、大丈夫」
青い瓦屋根とクリーム色の壁の冬治の家が見えてきた。
「これが僕が住む世界だ」
胸が苦しい。
ロウソクが並んだケーキもチキンもジュースも、みんなの笑顔も、嘘だ。まやかしだ。幻想だ。
期待しちゃいけない。
もし、あれが「幸せ」なのだとしたら、まるで僕が「不幸せ」みたいじゃないか。
そんなのみじめすぎる。
「誕生日なんてなければいいのに」
はじめからなければ問題ないんだ。
そんなものがあるから心が乱れてしまうんだ。
「誕生日パーティーなんて知らなければよかったのに!」
いつだったかホームルームの時間が余ったので「幸せの話をしよう」と担任の先生が言い始めたことがあった。
そして「あなたたちひとり一人幸福の形はちがう、それぞれの幸福を見つけなさい」と言った。
何が自分にとって幸せか発表しようということになった。
「ディズニーランドに行くこと!」
「焼き肉!」
「みんなで合唱すること!」
そんな意見が飛び交う中、冬治は黙っていた。
最後まで答えることができなかった。
いくつか思いつくが実現は不可能だ。
どれも邪魔されてしまう。
重くのしかかっているものに身動きが取れずどうにもできない。
強いて言うならばその邪魔なものを取り去ることができたら、それが自分の「幸せ」なのかもしれないと思うことがある。
「僕は罰当たりかもしれない」
「人でなしかもしれない」
坂道の途中の二股から家までは足取りが重いのはいつものことだった。
歩きながら、ここから引き返して家には帰らないという選択肢もあるはずだと思いながらも、そんなことはできずに家に帰ってしまうのはいつものことだった。
扉を開けて家の玄関で小さな声で「ただいま」と言っているのもいつものことだった。
「大丈夫、大丈夫」
胸をおさえる。ゆっくりさすって呼吸を整える。
自分がブレさえしなければなんとかなる。
「ただいま」
と、冬治はもう一回言った。
暗い廊下の先の扉からは何も反応がなかった。
ーおわりー














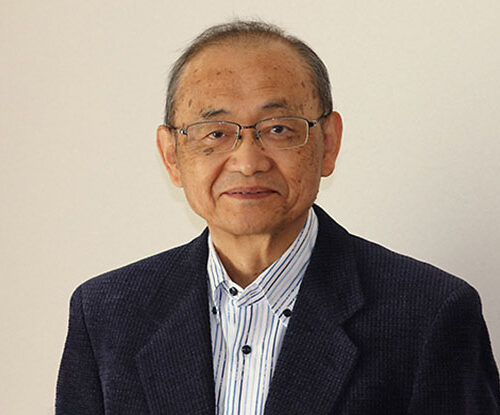




-1.png)




















