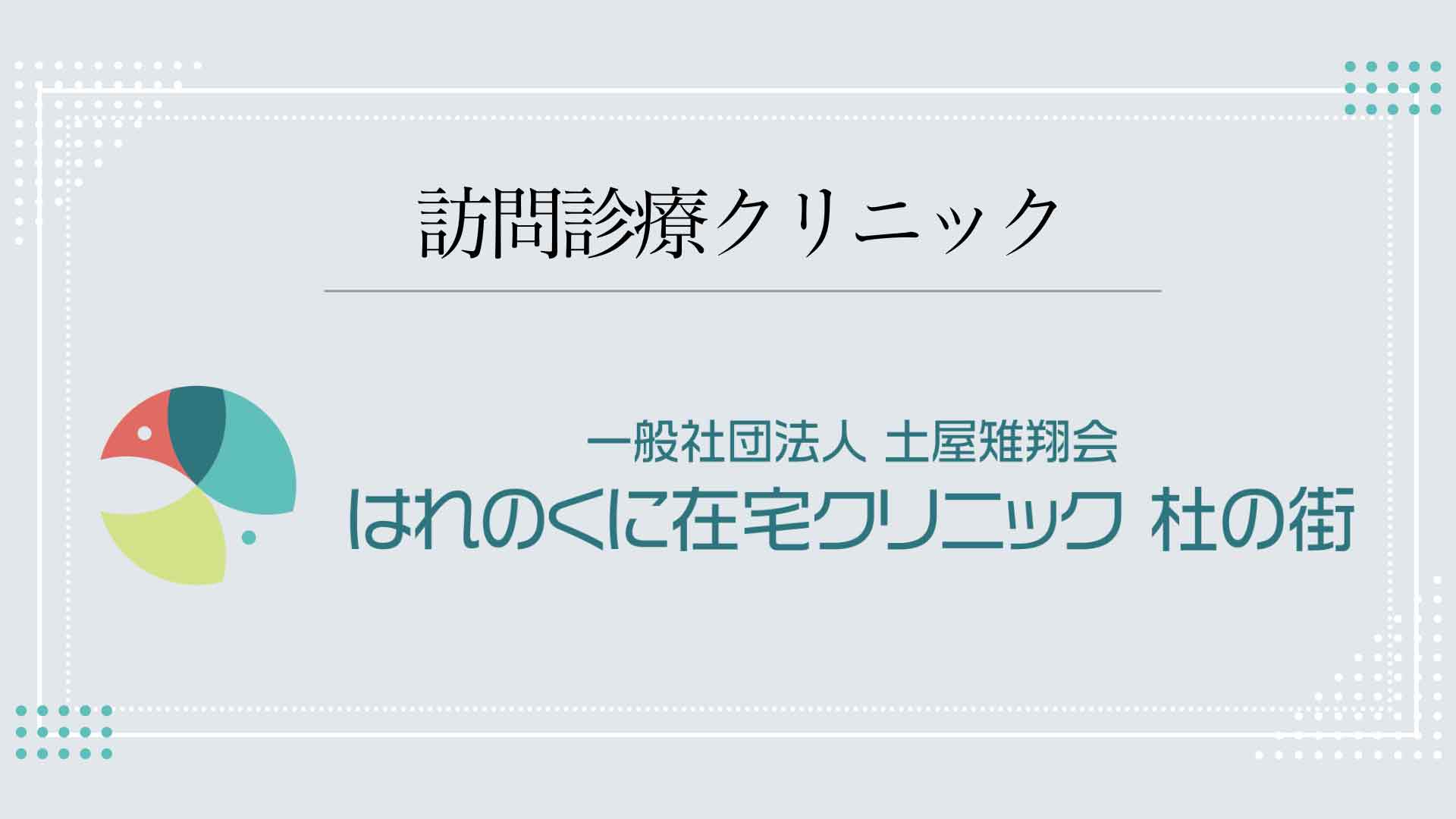土屋ブログ(介護・重度訪問介護・障害福祉サービス)
20 離脱の時②
この自己目的化した数字の追求は、さらに加速していった。この事業に、理解も経験も関心もない人たちが、ビジネスバリューの最大化にだけ興味のある人たちが、一人二人とあらたに私たちの事業に参加するようになった。
プロセスに全く関心のない人たちにとって、数字の最大化は唯一無二の一神教的な神聖さを帯びていた。数字の最大化というプロジェクトに疑念を挟む人や、それに対する貢献が不十分と判断された人に、手厳しい評価が下されていった。事業に興味のない人たちの発言権が高まり、事業に興味があり、その内実を作り発展させてきた人たちの発言権が相対的に低まっていった。
自己欺瞞を続けてきた自分自身の心の内からも、危機感が日増しに高まっていった。事業の本質が得体のしれないウィルスに侵されていくのを感じた。
「新田さんたちから継承したはずのこの事業が、どこに向かってしまっているのだろうか」「介護難民問題を解決するための取り組みが、むしろ介護難民問題を再生産してしまう」と、そんな不安とも恐怖とも思えるような想いがたびたび脳裏を過るようになった。
数字の最大化という私自身が振りかざした錦の御旗の元、売り上げと利益の最大化という神聖なる目的地に向かってみんなが爆走し、プロセスが荒れていった。メンバーの心がささくれ立っていった。
「なんとかして欲しい」
「このままだと会社が壊れてしまう」
「もう限界だ」
「この暴走列車はいつ止まるのですか?」
「私たちを見捨てるのですか?」
「こんなに現場がたいへんなのに、自分たちだけ既得権益に胡坐をかいて、上の奴らはいい気なものだ」
そんな懇願とも悲痛な叫びとも受け取れるような声が、方々から私のもとに届いた。
「見捨てる」という言葉が痛かった。小さな声を「見捨てない」ために、この業界に入ったはずだ。そんな自分が、この事業を作ってきてくれた、クライアントの命と生活を全身全霊で支えてきてくれた、艱難辛苦を乗り越えてきてくれた、そんな仲間たちから、集中砲火のように「見捨てる」という言葉を投げかけられた。彼女たち/彼らの「小さな声」は、私の心に大きく響いた。
小さな頃から「弱さ」を抱え、乗り越えたつもりが本質は何も変わっていない自分自身の繊弱な心は、この言葉の絨毯爆撃に、耐えることができなかった。
途方に暮れ、跪きそうになった。
信頼できる仲間たちと、問題解決について必死で考え、議論した。
「組織変革に本気で取り組もう」そう決断した。2020年7月だった。様々な信頼できるアドバイザーに相談した。回答はみんな同じだった。
「変革は無理、一蓮托生で前進し、悲鳴は見捨て続けるか、それとも去るか、二つに一つです」と。
このまま「見捨て続ける」ことは、自分にはできなかった。私の「弱さ」が、それを許してくれなかった。
0から作ってきた組織を去ることを決断した。新しい道を、志を等しくする仲間とともに、歩み始める決断をした。「見捨て続ける」ということの良心の呵責から解放される、ある意味自分にとっては楽な道を歩むことにした。留まった人たちにとっては、私たちは、彼女たち/彼らを見捨てたという風に映るだろう。その通りだと思う。
私は、「見捨てる」ことによって、「見捨てる」ことから放免された。
「数字」の自己目的化された追求に対して違和感を抱いていたのは、私だけではなかった。一人また一人と、「自分も」といって組織を去ることを決断する人たちが現れてきた。その決断をする人が、日に日に増えていった。多くの人たちが自己欺瞞にはもう耐えられないと思っていたことを知った。
堤防が決壊した。巨大な氾濫が起きた。
「自分なりの正しさ」に向けて、一人また一人と歩みだした。
新しい希望に向けて、事業そのものの本質に向けて、一人また一人と歩みだした。
様々なリスクが推測されたが、多くの人が、留まるリスクよりも、新生に向けて橋を渡るリスクを、我慢するよりも、変化する道を、選んだ。
このようにして、新生土屋、株式会社土屋は2020年8月に、誕生した。
そして今、事業の本質を回復するために、仲間たちと共に試行錯誤しながら歩んでいる。
「留まる」ことを選んだ仲間たちへの微かなる罪悪感を抱きつつも、この間新たな道を歩んだ仲間たちと共にした「稀有な時間」と、そして「忍従」ではなく「変革」を選び取り、それを遂行したことに、ありったけの誇らしさを、私は感じている。
なぜならば、「忍従」ではなく「変革」を選び取ることこそが、障害者運動のリーダーたちから私がリレーされた精神の本質であるから。社会運動家として、社会事業家として、今後も生きていきたいと思う。私をインスパイアーしてくれたメンターの人たちの精神に忠実であれたことに、ありったけの誇らしさを感じている。
介護難民問題の解決に、なんのためらいもなく前進できることに、ありったけの誇らしさを感じている。
「ためらい」のなかで、ある者は「残る」を選び、ある者は「去る」を選んだ。
しかし、どちらも同じ志を抱き、同じ業界の中に身を置き、クライアントの生活を共に支えている。
そんな彼女たち/彼らと共にお仕事をできていることに、ありったけの誇らしさを感じている。
◆プロフィール
高浜 敏之(たかはま としゆき)
株式会社土屋 代表取締役 兼CEO最高経営責任者
慶応義塾大学文学部哲学科卒 美学美術史学専攻。
大学卒業後、介護福祉社会運動の世界へ。自立障害者の介助者、障害者運動、ホームレス支援活動を経て、介護系ベンチャー企業の立ち上げに参加。デイサービスの管理者、事業統括、新規事業の企画立案、エリア開発などを経験。
2020年8月に株式会社土屋を起業。代表取締役CEOに就任。趣味はボクシング、文学、アート、海辺を散策。





















-1.png)