土屋ブログ(介護・重度訪問介護・障害福祉サービス)
今年の春はみなさんどのように過ごしているだろうか。
私は相変わらず休日ともなれば3歳になったばかりの娘と散歩に明け暮れている。
気候が暖かくなり、コートを家に置いて出掛けられるだけで気分も軽くなる。
少しポケットが大きめなシャツでも羽織れば、カバンも持たなくていい。
なおかつ、最近ではクレジットカードでも交通系ICカードでも、カード一枚あれば大抵のお店で買い物もできるから重い財布も持ち歩かなくてよくなった。
身分証明のための免許証とクレジットカード(あるいは交通系ICカード)、家の鍵くらいがあれば手ぶらで気軽に散歩に出掛けることができる。
◇
25歳の春のことだっただろうか。
私が「仕事をする人」になったばかりのころ「手に物を持つ」ということが妙に気になった時期があった。
例えば、業務中に捨てなければならない「ごみ袋」とコピー機の紙が切れたので充填するために運ばなければならない「A4の紙の束」。
その二つを手に持っているということが違和感というのか、特別感というのか、「普通じゃない」感じがしていた。
例えば、利用者の食後にしなければならない「歯ブラシとコップ」と、書かなければならない「連絡帳」と、上司にハンコを押してもらわなければならない「資料」。
例えば、午後の活動のために用意しなければならない「麦茶の袋」と、もうすぐ早退してしまう同僚に渡したい「贈り物」と、事務局に届けてほしいと頼まれていた「保険関係の書類」。
「物を二つ以上同時に手に持つ」ということ。
ふと気づくと、その何でもなさそうなことが妙に意識されて、とらわれてしまう時期があったのだった。
まるで立つことを覚えたばかりの幼児のように、物を持つことを覚えたばかりといった感じに。
不思議なものを見るように私は物を持つ自分の手を見つめていた。
しかし、私はその「不思議」に目を輝かせていたばかりではなかった。
どう感じていたかというと「手が物で埋まっている」と感じていた。
それを面白い現象としてとらえるのではなく、どこか追い詰められるような、プレッシャーすら感じていた。
要するに業務上の荷物を複数持つときに「手が物で埋められている」「物を持たされている」
→「自由を奪われている」と感じていたような気がする。
◇
今思い返せば、あの当時は嵐の時期で、何かとむしゃくしゃしていた。まわりを恨んでいたのかもしれないし、何でも他人のせいにしていた。
それで、お酒を飲んでは暴れていた。
深酒して帰宅の途につくと、月が出ていて…
「自分は一体何をしてるんだ?」
「こんなはずじゃなかったのに」
情けなくて悔しくて涙が溢れた。
ふらふら、千鳥足で泣きながらアパートまで帰った。
たまに実家に帰ると拾ってきた自転車を庭に放り込んだり、鏡餅を蹴り倒したり、お寺のお坊さんにからんで無闇に口論したり、ろくでもないことばかりしていた。
荒れていた。
自分が自分ではなくなってしまうような不安を感じていた。
今だったらそう感じている当時の私に言ってあげることができる。
「それが、成長するということだよ」と。
自分の成長を肌身で感じて嬉しくなったり、力がどんどん湧いてきて強くなっていくと感じることもあるだろうけど、一方で成長することの怖さ、変容していくことへの不安が裏側にはあった。
自分が自分ではなくなる感覚。
青虫は「さなぎ」になることを恐れるだろうか。
「さなぎ」もまた青虫の醜さを嫌悪するだろうか。
過去の小さく弱い自分の否定。
そして変容していく自分への否定。
その二つの否定のせめぎ合いが「成長する」ということのひとつの側面だろう。
恐れるな。
とどまることはない。
だから「迷わず行けよ」
いや、違う。
「迷ってもいいから行けよ」
それも違う。
「迷いに行けよ」
そう、思う。
いつか「迷う」こと自体を楽しめるようになるから。
◇
話を「手」に戻そう。
あの当時はあまり深く分析することなく、
「あっ、また手に物を持っている・・・」
と、何気なく思っていたのだった。
「また、オレ、手に持ってる・・・」
その深層にはもしかしたら、
「何で物を持たなければならないんだ!」
「一体いくつ物を持てばいいんだ!」
→「一体いくつの仕事を同時に抱えればいいんだ!」という駆け出したばかりの青い若者の嘆きがあったのかもしれない。
とはいえ、たいした仕事でもなかったはずである。
床を掃除するとか、切手を買いに行くとか、ゴムボールや縄跳びなどの遊び道具を公園に運ぶとか。
今思えば可愛らしいちょっとした仕事にアップアップしていた。
膝下くらいの浅瀬で溺れかけていたのである。
品川心中みたいに。
『選ばれてあることの恍惚と不安、我に二つあり』
入社したての若者なんてそんなものだろうと、若者一般について述べようとは思わない。そんなこと自分には無理だ。
しかし、社会人一年生と呼ばれたりフレッシュマンと呼ばれ、期待と不安を胸に就職してきた若者は多かれ少なかれそんなふうに仕事を前にしてプレッシャーを感じるのではないだろうか、とは短絡的には思う。
入社したての若者を見ると、この子は庭に自転車を放り込んだりしないだろう、鏡餅を蹴り倒したりしないだろうと思うと私よりはずっとましだ。
何も言うことがない。
みんなしっかりしてそう。荒れてなさそう。
きっと手にいっぱい物を持っても大丈夫なんだろう。
荷物でいっぱいになってうろたえている「手」は、社会に船を漕ぎ出したばかりの不安でいっぱいだった青二才の私の象徴だったのかもしれない。
あるいは成長していくことの不安の象徴だったのかもしれない。












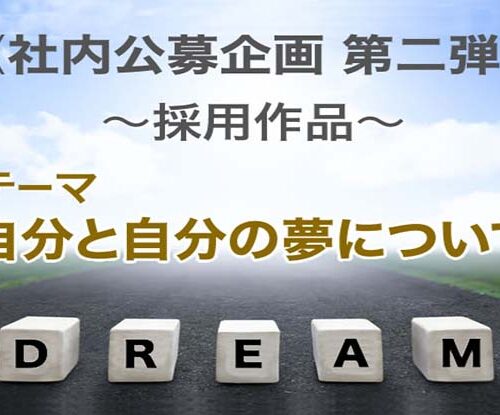






-1.png)




















