地域で生きる/24年目の地域生活奮闘記139~物心ついてからずっと言われてきた親亡き後を迎えて思うこと~ / 渡邊由美子
今年上半期前半は、私にとって、そして日本社会全体にとって明るいとは言い難い現実を目の当たりにさせられるものとなりました。2023年の前半より闘病中だった母親が、力尽きるように2024年初旬にこの世を去りました。また1月1日には能登半島を直撃する大地震が起こり、現在でも生活の復旧がまだまだままならない状況です。これ以上震災関連の被害が広がらないことを願うばかりです。
さて今日の本題に移ります。私の母親がなぜどんなふうにして亡くなったかについては、ごく個人的なことでもありますし、故人のプライバシーに関わることでもあるため、ここに詳細を書くことは控えます。でもあえてこのテーマを選んだ理由は、遺された家族である私の心境を鮮明なうちに書き残しておきたいと考えたからです。あまりあって欲しくはないですが、何かの参考となれば幸いに思います。
まず今回、母親を亡くして一番に感じたことは、次に亡くなることになるのは、年齢の順番から言えば父の可能性が高く、その後は実姉、もしくは私であるということです。否が応でもそれをリアルに感じずにはいられなくなりました。
私は物心ついた頃から再三再四、家族はもとより学校の先生や福祉施設の職員など周囲から、「親が年老いてあなたの介護ができなくなったり、万が一亡くなったりというようなことが起こった際に、どうやって生きていくつもりなのか考えておかないと、いざとなってからうろたえても、他人である周囲の人間は何も手助けできない」といったことを、半ば強迫観念を植え付けられるかのように言われ続けてきました。
その言葉に背中を押され、「親亡き後に備えなければならない」と思い、またその親亡き後は、自分が少しでも望む形の人生となるよう模索しなければと考え、それを実現するべく、障がい者運動にまい進しているのです。
その結果として、重度障がい当事者たちが50年余り血の滲むような思いで作り上げてきた”重度訪問介護”という制度ができあがりました。
言わずもがなですが、この制度は自分で自分のことができなくても、誰かに生活規則を設けられるのではなく、支援をする側の都合ややりやすさにあわせるのでもなく、あくまでも支援を受ける本人の意思を主体とした生活が送れるようつくられたものです。この制度をより良く維持・発展させていこうと、私は日々、障がい者運動に取り組んでいます。
ここでいう本人の意思とは、言葉を介したものだけではありません。自分の意思を言葉で明確に表出できる人もいれば、言葉や文字を介して表現することがむずかしい人もいます。表情や身体全体から醸しだされる声なき声全てを含みます。
この制度ができたことで、どんなに重い障がいをもつ人でも地域で自立した生活を送ることができるようになりつつあります。
その一方で、この制度を作るべく運動を続けてきた先人たちが、まるで共同生活のように介助者と共に暮らす生活の実態は、当事者自身が介護事業所を立ち上げているとか、重度訪問介護の”じゅ”の字もない時代から介護をしてきて、当事者に何があってもその生活を支えるのがこの仕事だと思い、共に運動し共に同じ釜の飯を食べ、入浴介護ではなく一緒に裸になってお風呂に入るみたいな、それこそ制度がなかった時代と同じやり方をしている人たちもいます。
そういった場合には、私がもし最期を迎えるような病気やケガをしたとしても、周りの支援者が看取ってくれることは当然で、何も心配せずとも、骨を拾ってもらうことはできると思います。
しかし仮に今私の生活を支えてくれている人たちに「私の骨を拾うことまでがあなたの仕事だ」と言ったら、何人残ってくれるだろうと考えると、残念ながら皆無に等しいのではないかと思わざるを得ません。
母親の葬儀に立ち会う中で、重度訪問介護という制度は、良くも悪くも、すっかり職業の一種となっていると痛感しました。設立・施行から50年しか経っておらず、いまだ不完全なこの制度を使いながら生活をしている当事者自身が歳を取って、人生の最期を迎える時にはどうしたら良いのかということを考え続けていかなければならないと強く感じたものです。
親亡き後をずっと昔から考え続けてきて、そのときを迎え、ようやく体制が間に合ったのと同じような感覚で、私を含め当事者自身が最期を迎えるときを今から考え、それを想定した制度をつくるべく、運動を続けていかなければと強く思いました。
個人の善意に頼ったり、姪っ子・甥っ子といった遠い家族に負担がいったりすることがないように、重度訪問介護の制度の中に、看取り加算のようなシステムを設け、介護者を派遣する介護事業所が責任を持って、当事者が安心して地域で生き、地域で死んでいけるようにしていかなければとつくづく思います。
母親の告別式で行われた一連のセレモニーの中で、私が自分で出来ないことはいくつもありましたが、若い学生ヘルパーが私の手を取り、健常者となんら変わりなく母親を見送ることができるようサポートしてくれました。
それを経て心の区切りをひとつつけることができ、これからの残された自分の人生と、妻に先立たれ意気消沈している父親を支えていく覚悟ができました。
どうしても感情が先に立ち、書きたいことがまとまりませんが、地域で生きる当事者の最期を介護者一個人に背負わせるのではなく、当事者の最期を支えるシステムが欲しいと思わずにはいられない今日この頃です。そのために何をどう具体的に動いていったらいいのか考え続け、行動していきたいと思いました。
◆プロフィール
渡邉 由美子(わたなべ ゆみこ)
1968年出生
養護学校を卒業後、地域の作業所で働く。その後、2000年より東京に移住し一人暮らしを開始。重度の障害を持つ仲間の一人暮らし支援を精力的に行う。
◎主な社会参加活動
・公的介護保障要求運動
・重度訪問介護を担う介護者の養成活動
・次世代を担う若者たちにボランティアを通じて障がい者の存在を知らしめる活動















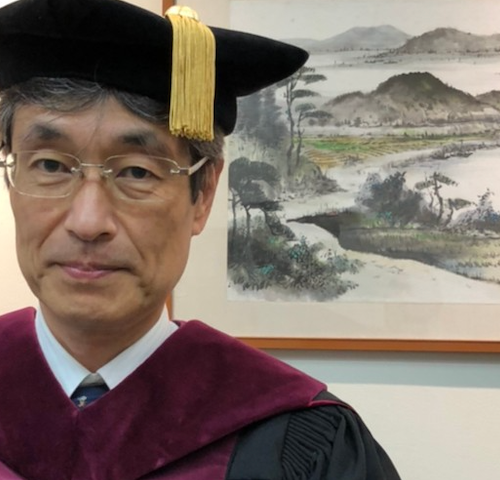



-1.png)




















