
「施設福祉から地域福祉へ」~第1部:施設福祉から地域福祉への移行はいかに実践されたのか~
対談参加者
浅野史郎……土屋総研 特別研究員
司会……宮本 武尊/取締役 兼 CCO最高文化責任者
脱施設活動に向かう、それぞれの思い

本日、第2回目のテーマは「施設福祉から地域福祉へ」とさせていただきます。
浅野先生は宮城県知事時代に「みやぎ知的障害者施設解体宣言」を出されて知的障害者施設の解体に取り組まれていましたが、
「施設福祉から地域福祉へ」とはどのようなことなのでしょうか?

「施設福祉から地域福祉へ」というのは、一つは歴史の流れなんですね。
もともと地域に住んでいる障害のある方に対する施策はほとんどなくて、当時は施設で受け止めるしかない状況でした。
それがずっと続いてきたんですが、これが変わったのが1990年代です。
国が地域福祉に舵を切ったということですね。
趣旨は実に簡単で、「障害者が住むところは施設でしょうか、それとも地域でしょうか」ということです。
障害を持っていない人は地域に住んでいますが、
そういう意味では、障害者にとっても住むべきところは施設ではなく地域であるという“当たり前のこと”です。
この“当たり前のこと”というのがノーマルという意味で、デンマークで始まった“ノーマライゼーション”は実はそこから来ています。
人間が住むところは施設ではなく地域だと。
その人間の中には当然障害者も含まれるということですね。
その当たり前のことに今、近づきつつある。
つまり「施設福祉から地域福祉へ」という流れの出発点は、ノーマライゼーションという考え方なんですね。

高浜代表は最近デンマークに視察に行かれましたが、ノーマライゼーションについて一言お願いします。

ノーマライゼーションが生まれた背景には、生みの親であるバンク・ミケルセンがナチスの強制収容所で暮らした経験があり、
その後、デンマークの地下活動で反ナチス闘争にジャーナリストとして参加したという経緯があります。
そして戦後にデンマークの福祉の担い手といった役割を担う中で、
ある知的障害者施設を視察した時に、そこが「ナチスの収容所とそっくりだった」と言うんですね。
そこで「これはおかしい」と。
知的障害があっても、そうではない方と同じような生活を送れる環境を作るべきだとして運動を展開し、
「1959年法」という有名な法律の立法化につながるわけです。

高浜代表は「施設福祉から地域福祉へ」という流れについて、どのように受け止めていますか?

私は大学卒業後に今まで全く関わりのなかった福祉業界に飛び込んだので、
資格が必要だと思ってヘルパー2級(現 介護職員初任者研修)を取りに行ったんですが、そこでは施設と地域の序列化は特にされていませんでした。
施設というサービスもあり、地域というサービスもあり、
それはある意味で横並びの関係であり、選択するものだという学び方だったんです。
私自身、働く場所として施設か地域かということには特にこだわりもなかったんですが、資格を取得するまでに働ける場所ということで、
障害者介護の木村英子さん(現 参議院議員)の事業所に面接に行った時に、
面接者から最初に言われたのが「ヘルパー2級で勉強したことは全部間違ってるから、全部忘れてくれ」ということでした。
そこで受けた重度訪問介護研修でも、
「いかに施設が極悪非道の人権侵害の場所であるか」「在宅こそが正義だ」というのをひたすら聞かされましたし、
バンク・ミケルセンの存在を初めて知ったのも英子さんの事業所です。
その中で、初任者研修で学んだことや、その価値観は何だったんだという印象は持ちましたね。
もっとも今は、施設は歴史的過程の中で必要な社会資源であったとは思っています。

福祉業界と障害当事者の世界では、施設・福祉に対する考え方に非常に乖離がある中で、
高浜代表は当事者の影響を強く受けていったということですね。

そうですね。
たとえば新田勲さんは「施設なんて人間の生きる場所じゃない。
施設に戻るくらいなら死んだほうがましだ」と言っていましたが、
私もそれを直に聞いて、脱施設の当事者運動を応援しようと思ったわけです。
つまり私自身は理論的な裏付けがあって「施設ではなく地域であるべきだ」と考えたのではなく、
実際に施設に入っていた人たちから「あそこは本当に酷い」という話を聞いて、それを真に受けたわけです。
それが英子さんであり、新田さんであり、安積遊歩ですが、やはり実感が伴っていたんですよね。
それで脱施設運動をし、今は経営者として脱施設を推進する一端を担わせていただいている感じです。

一方、浅野先生は行政の立場から脱施設を推進して来られましたが、
浅野先生はどのような思いで脱施設に取り組まれてきたのでしょうか?

高浜さんが例に挙げた方々は、みなさん喋れるんですよね。
だけど私が主に対象にしていたのは、知的障害や重症心身障害といった喋れない人たちです。
自分の意思を伝えられないので当事者運動は無理です。
誰かが代わりにしなくてはいけない。
たまたま私は行政に身を置いていたので、その誰かの一人に当たると。
だからまず、アプローチが違うんですね。
私は北海道庁で初めて障害福祉の仕事に携わりましたが、
その時は「施設はとんでもないところだ、酷いところだ」とは、実はあんまり思わなかったんです。
ただ、障害福祉課長という名で、生まれて初めて障害福祉の仕事をプロとしてすることになった時に、
何をすればいいのか全く分からなかった。
そこで、「いろんなタイプの障害者が、より幸せになるように」ということで、
行政としてできる施策を実行するところから始めました。
そういう観点からすると、まず「障害者の幸せって何だろう」ということを本人に聞く必要があるんですが、
知的障害者の場合、本人は喋れないんですね。
親が代弁しているわけですが、
その当時から私は「親は代弁してるけど、これは親の立場で言ってるんであって、本人とはちょっと違うな」という感じはしていたんですよ。

では、浅野先生は本人の思いを自分なりに取り込んで施策を実行されていったということでしょうか?

そうとも言えますね。
「施設福祉から地域福祉へ」というのは国の理念としてあったようですが、
私はそうではなくて、障害を持っている本人の幸せを考えることから始めたんです。
そうやって関わる中で改めて自分の仕事を見つめたときに、「施設はおかしい」というよりも、
むしろ「重度の障害の人も、普通の場所で普通の生活をすることを目標とする」というようにだんだん変わっていったんですね。
これがノーマライゼーションだと思っています。
もっとも北海道庁の時はまだぼんやりしていましたが、
その後に厚生省の障害福祉課長になってからはそれが明確になってきて、「そのような場所というのは施設ではなく、地域だ」と。
そこで地域で暮らせる手立てを講じるようになっていきました。
私の場合は徐々に、徐々にです。
ちなみに北海道庁時代も、障害福祉課長になっても、バンク・ミケルセンのことは知らなかったんですよ。
独自に出てきた考えであって、逆に言えばバンク・ミケルセンと発想は同じだなと思いましたね。

先生はよく日本のバンク・ミケルセンと言われてましたからね。

言われてない(笑)

それはバンク・ミケルセンを真似したんじゃなく、先生が経験の中で感じて、
実行に移されたことが、たまたまバンク・ミケルセンと一致したということかもしれないですね。
障害者の「自立」とは

お二人が脱施設を推進する中で、さまざまな壁があったとは思いますが、それについてはいかがでしょうか?

実際に障害者運動に入ると、いろいろと驚くことがありました。
その一つが、当事者がもつ家族会や家族福祉に対する不信感、否定観の激しさなんですね。
当事者運動は「家族とだけは、家族会とだけは連携しない」と訴えてたんですよ。
そういった家族会VS当事者会の平行線がずっとあった中で、
ここ最近、このかつてあった深い溝が埋まりつつあるところを幾度か目撃して、時代の変化を感じています。
その背景として、家族会が当事者会への歩み寄りを進めたのではないかなと。
先生が、当事者と家族の考えが違うことを感じ、当事者に直行便で進んだのは意識として非常に先駆的だったと思いますね。

家族会が変わってきたというのは、一つは地域福祉が進んだからだと思いますね。
「大事なのは当事者の思いだ」ということを家族も分かるようになってきた。
以前は施策がないもんだから、家族が「自分の子どもを守るんだ」という意識が非常に強かった。
ただ敵対だと思ってないんですよね、当然ながら。
だけどここには当事者本位ではなく、
いわゆるパターナリズム(本人の利益を守るために、本人の意志を問わずに本人に干渉・介入すること)という面があって、
当事者にとってそれは実は邪魔になるということを考えなくちゃいけない。
多分それは、「自立」という概念だと思うんですね。
自立というのは、家族からの自立も含んでますからね。
それで敵対ということも起こるんですが、家族側も「自立して、地域に住んで、しっかり生活している障害者もいる」ということが分かって来るにつれて、
「保護する」という家族としての役割を見直すことにつながったんじゃないかと思いますね。

「当事者のことは当事者が決める」という有名な言葉がありますが、障害当事者の「自立」とはどういったことなんでしょうか?

当事者の人たちの「自立」に対する強烈な意思は、
障害をもっていない私たちが考える自立という言葉とは含意が全然違っていて、いろんなことが込められていますよね。
その中の一つが、先生の仰るように「親との関係性」ですね。
私が関わった多くの障害当事者も、親からの束縛というよりも虐待を経験した人たちが多かったので、
「親とは自らの意思で関係を切り離すべき存在だ」というのは大前提としてあるんです。
けれど親を切り離すことで、支援する人を別に代替者として見い出していかなければいけない。
それが初めはボランティアであり、我々がこの業界に入った時は有償のお仕事になりつつありましたが、
今それが確立しつつあるという過程だと思います。

それが重度訪問介護ということですね。

ただ、今度は親の代わりに自分を支援してくれる人との関係構築という新しい仕事が生まれたんですね。
これは非常に難しいテーマです。
他者のサポートを受け続けるというのは巨大な仕事であって、
サポートする側にとっても巨大な仕事だということが実感される中で、障害当事者運動のいう「自立」というのは、
他者との相互依存、他者との関係における葛藤を乗り越えていくことも含まれた自立という点で、
一般的な自立とは違うと感じますね。
そして、そのプロセスの中にはドラマティックなところもあって、
私がこの世界に魅入られて、今こういった事業を経営するに至る出発点になった体験だったと思いますね。

高浜さんは、当事者のもつ「自立」という言葉の強烈な意味が運動として出てきたところに居合わせたというのが大きかったですよね。
大げさに言えば「歴史の転換点」ですよ。
ただ、懸念されるのが、今の重度障害者が「自立」といったことをあんまり感じてないというところですね。
当時は、誰もいない荒野を歩くような、自分たちで作っていかなくちゃいけないという運動の中にあったので、
自立に対する強烈な思いがありましたが、今や自立というのは用意されているもんなんですね。

浅野先生は、「自立」とは一体何だと思われますか?

私は、自分のことは自分で決めるという「自由」だと思いますね。
それを獲得することが、以前の当事者運動の非常に強烈なエネルギーでしたね。
いわば、そういった先駆者が作ってきた道を、後の人は単に享受しているだけになっています。
それはそれでいいのかもしれませんが、ただその先駆者のことも忘れちゃいけないという思いはありますね。

先生が仰るように、私はたまたま新田さん、三井絹子さん、英子さん、遊歩という、
この歴史を切り開いた人たちに偶然最初から出会えたというところは、
この思想の根幹、自立生活主義の根幹に触れた思いはありますね。

今や「自立」というのは用意されているものであり、
現在は重度障害者がそれをあまり感じていないというお話しが浅野先生からありましたが、
高浜代表も事業を運営する中で、それをお感じになりますか?

私は制度がある程度整ってきた後に、現場でサービスを受ける人と関わっていたので、
先生の仰る懸念が2000年初頭に顕在化し始めてきたのを見ているんですね。
自分のことは自分で決めるけれども、それに伴う責任をあまり重く感じずに、ヘルパーをいじめたり、好き勝手する人たちが現れてきたわけです。
それは英子さんや新田さん、遊歩からすると「嘆かわしい事態」であって、ちょうど私が業界に入った頃、
当事者団体の中でも「自分たちが思い描いていた『自立』は、あんなのじゃなかったはずだ。
もう一度『自立』というものを見つめ直さなきゃいけないんじゃないか」という議論がなされていたんですね。
そしてちょうど同じ時期に、
軽度の知的障害を持った人たちから「自分たちも身体障害者の人たちと同じように自立したいんだ」という声が出始めてきました。
ただ、知的ハンディを持った人たちの自立のイメージは、
やはり英子さんたちが作ってきた「自立」のライフスタイルとはちょっと違うわけですよね。
というのも、なんでも自分で決めて、それが特に問題ないというものではなく、
やはり危険なことをしてしまう場合もあるわけです。
そうするとヘルパーさんとの関係性も違ってきて、
その状況を見た身体障害の人たちが「知的障害を持った人たちの自立とはどうあるべきか」といった議論を真面目にし出してですね。
やはり知的障害の人たちの自立のイメージは、
自立生活運動に対する身体障害の人たちのもともとのイメージと大分違いますからね。

確かに自立のイメージ、またはそれに対する行動は、身体障害の人と知的障害の人は大分違いますね。
溶けあわないんじゃないかと思いますね。
だから知的障害福祉をしていく中で、あまり「自立」ということは頭になかったんですね。
「普通の場所で普通の生活を実現しよう」というのであって、出発点からして少し違うんですね。
知的障害の場合、私は「自立」というよりも、こんな言い方をしましたね。
「生きて来てよかったな」ってことを感じられる、そういう状態を「人権」だと。
「自立」という言葉は使わなかったです。

「自立」という概念自体がだんだんと変遷していく過程の中にあるとは思いますが、
サービス提供事業者としては、私たちのサービスを利用されているクライアントの中には、
時に自立生活というより、ケアサービスを消費している消費者というイメージに近かったりと、大分ずれは感じる部分はありますね。
そのずれがいいのか悪いのかという価値判断は簡単にはできないところではありますが、それをリアルに感じることもあるし、
残念な結果としては、カスタマーハラスメント(顧客が、従業員に対して行う嫌がらせや迷惑行為のこと)の深刻化は、
「自立」というイメージがなし崩しになった結果だとも感じます。

やっぱり高浜さんが挙げた歴史に残る人たちは特異です、時代の状況の中で生まれた英雄たちですね。
その人たちに、まず高浜さんがこの世界に入った最初の頃に会ったというのは、高浜さんの運命というか、偶然というか。

偶然ですね。

結果、それはラッキーだと思いますけどね。















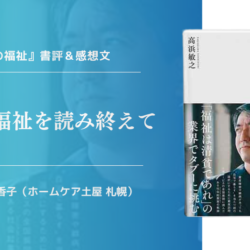
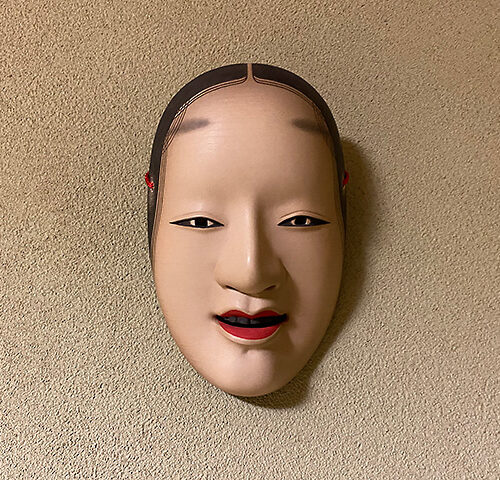

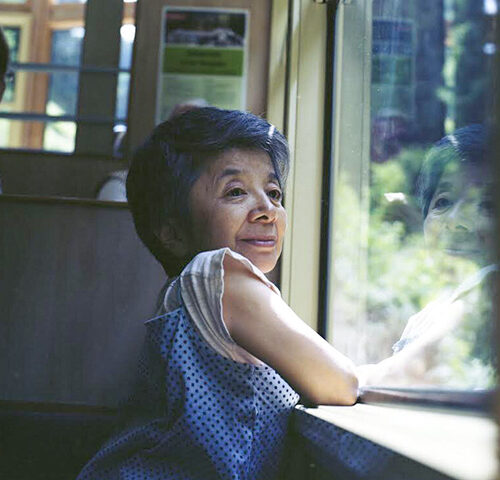


-1.png)




















