
「施設福祉から地域福祉へ」第2部:介護業界の光と影~声なき声を聴きながら~
対談参加者
浅野史郎……土屋総研 特別研究員
司会……宮本 武尊/取締役 兼 CCO最高文化責任者
グループホームの位置づけとは

第一部では、お二人の脱施設にかける思いと、障害当事者の「自立」についてお話しを伺いました。
それに関連して、施設という位置づけにありながら、在宅に近い形でもあるグループホームについてお話しを伺いたいと思っています。
当事者運動の視点からは、グループホームはどう捉えられていたんでしょうか。

当時、身体障害をもつ方々の議論の中で、
知的障害を持った人の自立における論点の一つが「グループホームの是非」だったんです。
やはり、身体障害者自立生活運動の原理主義者の人たちの多くが、
「グループホームなんか地域じゃない。あそこで暮らすなんて自立生活じゃない」と言っていましたね。
やはりそれは、自分たちがかつて生き地獄だと思った施設とグループホームをイメージとして重ねて、
「あそこで生きるのは幸せじゃない」というように決め込んだ議論をしてたんですよね。
施設と地域という二分法の中では、施設というのは、
それを経験した人たちにとってはトラウマ化していて、それを重ねてしまうからとは感じましたね。

当時の当事者運動の中ではグループホームは施設と位置づけられていたということですが、知的障害をお持ちの方でも同じ考えなのでしょうか。

それが違うんですよ。
私はその後に、精神障害や知的障害を持った人の支援活動に入っていって、
それについて彼らに尋ねましたが、ほぼ全員が「在宅よりグループホームのほうがいい」と言っていました。
理由としては「寂しくないから」ということでしたね。
当時グループホームは利用年数に上限があったので、
多くの方がもうすぐグループホームを出なければいけないということにおびえていました。
やはり「当事者のことは当事者で決める」という「自立」が、自己決定とセットであるんだったら、
本人たちが「グループホームのほうがいい」と言うのに対して、
身体障害の人が「あんなのは自立じゃない」と言うのも差し出がましい話で、パターナリズムの一種だと思いますし、
デンマークではグループホームが地域・在宅という括りだと学んだ時に納得もできましたね。

浅野先生が対象とされていたのは、知的障害や重症心身障害といった方々ですが、
浅野先生ご自身はグループホームについてはどのように考えられていましたか?

私は北海道庁の2年の仕事を終えた後に、厚生省の障害福祉課長を拝命したんですが、
その初日から、私の第一の仕事は「グループホームを制度化する」ということだったんですよ。
ずっと「施設は駄目だ」と言ってきましたが、
「施設から出たらどうするの?」という問いにはなかなか答えられなかったんですね。
そのために、対案としてグループホームを出さなくてはいけない立場だったんですけども、
ただその構想を練っている時から、「グループホームは終着駅じゃない」ともよく言ってましたね。
相撲の番付を例に出して、施設入居は幕下、グループホームでやっと十両。
これは半分自立という意味ですね。
でも相撲もそこで終わりじゃなく、横綱を目指すんですよね。つまり地域です。
だから、グループホームが自立か、自立でないかという議論よりも、まさに経過施設としてあると。
ただ、年数を区切っちゃダメなんですよ。
難しいんだけど、次を目指すと。
そのために、グループホームに関わっている人も行政も、共にやっていくべきだと思い定めてこの施策を始めました。

厚生省がトップダウンでそのような設計をされて、私は当事者の声のあるところに身を置いてボトムアップを図るという、
それぞれの意向に基づいた対話が繰り返されながら制度がどんどんアップデートされていったと思います。
まだ20数年ですが、この対話が比較的活発に、特に当事者の声も一定配慮されながら更新されていく中で、徐々に良くなっている印象はあります。
その背景には、当事者が声を発するということと、行政の方々がその声を聞くという、
対話的な環境がしっかりとあったからだと思いますが、今はそれもなくなってきています。
今後、当事者が声を上げなくなり、行政の方々もそれを聞く姿勢や機会がなくなっていくと、
未来が心配という感じはしますね。
声なき声を聴く

当事者の声が小さくなる中で、行政の立場からはこれをどう捉えているのかは気になるところですが、
浅野先生は2004年に「みやぎ知的障害者施設解体宣言」を出されて、知的障害者の地域移行を推進されてきた経緯があります。
どのような意識の下でそれを進められてきたのでしょうか。

まず、知的障害の場合、当事者は声を上げないですからね。
そうすると、行政や他の支援者たちが代弁しなくてはいけない。
これは仕方のないことですが、ただその時に私は「声なき声を聴く姿勢を持とう」と言っていたんですね。
当事者は声に出せなくても思いはあるんです。
身体障害の場合は、声なき声どころか、声ががんがんうるさいくらいなんで、この両者ではそもそもアプローチが違う。
結局は同じなんだけど、形は違いますね。
だから難しいところもありますが、私はこの仕事をやっていて、ある意味面白かったとは思いますね。
行政のやるべきことが沢山あったからですね。

言葉には発されないけど、その裏側にある意図や思いを聞くと、
より深い傾聴を求められるとも思いますし、アドボケーターの役割の重要性も感じますね。
先生とずっと一緒にやってこられた長崎の社会福祉法人「南高愛隣会」理事長の田島良昭さんもそういう役割をされていたんでしょうか。

しかも彼は実践してましたからね。
私と知り合った頃は「コロニー雲仙」という施設を持っていたんですけど、
彼は「施設に入っている利用者をどう幸せにするのか、そのために施設はあるんだ」と言っていました。
障害を持っている当事者の思いを聞いて、そこで「施設を出たい。家族に会いたい」という思いを読み取ったわけですが、
彼はその人たちに「施設を出たいと言ったって、仕事をしなければ食っていけない。だからこそ、まず職業をちゃんと手にする。
8時間労働ができる身体、8時間労働に耐えうる精神、これを鍛えるのがこの施設だ」と言っていたんですね。
最初から全然施設の位置づけが違ったんですよ。
知的障害者施設は、本来は、「知的障害者更生施設」というんですね。
更と生を合わせると「甦る」となりますけど、要するにリハビリテーションなんですよね、本来は。
多くのところでは保護施設になっていますが、そうではなく職業を付けさせて、更生を実現するということです。
それで入居者をどんどん施設から外に出していって、2000年の初頭に「コロニー雲仙」は解体しましたからね。
というように、「声なき声を聴く」ということは、関わる人が聞くべきだし、聞けるんですね。

施設から地域へ、家族からの自立へという動きは、
浅野先生や田島良昭さん、元厚労省事務次官の村木厚子さん、障害当事者運動のリーダーだった中西正司さん、新田勲さん、三井絹子さんといった、
固有名で語られるような人たちの対話によってダイナミックに変化してきたと感じますが、
そういう対話的な環境がだんだんと薄らいできている印象があります。
そこが心配ではありますが、歴史は常に未来に向けて前進させていかなければいけないと思います。
課題はまだまだありますが、そこは先人の思いを継承していくべきだと思いますし、
「声なき声を聴く」というのはその本質だと感じます。
障害福祉、その二つの新しい敵

お二人が「施設から地域へ」の推進を図る中で、現在の障害福祉における課題というのはどういったものかをお聞かせください。

やはり闘うべき相手が変わってきてますね。
その一つは優生思想です。
これは新しい敵ですよね。
「津久井やまゆり園事件」もそうですが、役に立たないものは排除するという思想と闘っていかなくてはいけない。
だから、まさに高浜さんが感知したように、今は歴史の黎明期です。
明治維新の時に居合わせたみたいなもんで、新しい敵がいるんです。
だからこの仕事はある意味で、エキサイティングです。

先生が仰るとおり、優生思想というのは、永遠に戦い続けなければいけない史上最強のラスボスであるとは思うんですが、
同時に日本が批准している障害者権利条約においては、日本の地域移行は進展が遅れていて、
インクルーシブ教育も達成が不十分だと言われています。
まだ施設と地域の壁という日本固有の課題は残っていると思いますね。
そして株式会社の経営者という立場から見ると、新しい敵は飲食業、アパレル業、IT企業などの「他産業」です。
2000年に介護保険制度が施行されて、障害者自立支援法も2006年にできて民間企業の参入が許されたことで、
需要もどんどん拡大してマーケットが拡張しています。
その需要に対して供給が追い付いていない。
少子高齢化で全産業において人手が不足していて、かつインフレの高騰でどんどん他産業の賃金が上がる中で、
この採用マーケットにおいて我々は色んな業界と闘っているんですよね。
こういう新たな敵が生まれたのは、先生方が民間委託したからだと言ってもいいのかもしれませんが、
なぜ国は市場に委ねようと考えられたんでしょうか。

その部分には、私は直接関わってないんですよ。
あれは1990年代ですから、私はその時厚生省にはいなかった。
それはともかく、民間委託にしたのは、
今までなんでもかんでも行政が決めてきたということに対する反省みたいなものがあったんですね。
そこで、そうではない形を作ろうと。
そのほうがケアを必要とする人たちにとってもいいだろうということで、
それを目指して、ある程度は達成しつつあると思いながらも、別な問題が出てきているということはありますね。
民間委託の光と影

介護の民間委託というお話が出ましたが、民間委託によって新たに出てきた問題とはどのようなことでしょうか?

新たな問題は、知的障害者のグループホームを運営するMグループのように、
福祉を金もうけの手段にしている株式会社が出てきたことですね。
民間に任せればいいと言っても、そうはいかない部分があり、
まともな人たちが運営するんでなければ、この障害福祉の仕事はうまくいかないということもあります。
どのようにして悪徳な企業を排除することができるのかが新しい課題ですよ。

この民間委託の光と影は私自身、すごく感じる部分がありますね。光の部分は制度の柔軟性です。
なぜ日本がこれほどしなやかな福祉、多種多様なサービスを生み出せたかと言うと、
先生方が民間委託をして民の力を入れたからです。
公だけでするというのではない方向性を取ったからだと思いましたね。
とういのも、デンマークは福祉が世界で最高の国の一つというイメージがありましたが、
実際に現地を見て、その実践を見て、地域福祉は日本のほうが上だと実感しました。
デンマークでは福祉は公で、ヘルパーも国家公務員ですから。
今の日本の結果は、公だけではできなかったと思うんですが、陰の部分は浅野先生の仰る通り、Mグループのみならず、
儲けることを目的として参入してきた事業者が、それを至上命題にして、
福祉や当事者のことを棚に上げたような運営をした結果、モラルハザード(倫理の欠如)が起きていることです。
地域福祉の推進は民間参入によって一気に加速したというのは確信がありますが、
その民間事業者のモラルハザードというのは地域福祉の新たな敵だと思いますね。

市場原理が働く中で、Mグループのような企業が淘汰されなかったのはなぜなのでしょうか?

ここはですね、需要と供給のバランスです。
介護業界は圧倒的な需要過多で、供給サイドの寡占状態です。
まだ市場も成熟しておらず、施設を出てグループホームで暮らしたいという知的障害者が多くいる中で、
ここに参入する事業者がMグループしかいませんでした。
どんどん参入が増えてくると、良貨ではなく悪貨が駆逐されるという淘汰の原理が働いていくことは起きうると思うんです。
より高い賃金で、よりよいサービスを提供しないと生き残れないような市場原理が働き始めて、外圧的にモラルが働くようになっていくので。
やはり市場原理がきちんと機能すれば、
一定のモラルハザードも神の見えざる手によって排除していける可能性はあるんですが、パイオニア期には非常にリスクがあると思いますし、
Mグループはまさに知的障害者の在宅移行という市場を一気にカバーしていったので、ああいうことになったんですね。
敵がいないのでやりたい放題だったので。
これは地域移行の現在進行形にある巨大な敵だと思いますね。

それに対して、高浜代表はどう向き合っていけばいいとお考えですか?

私は経営者ですし、業界団体の代表でもありますので、多くの事業者に業界団体に参加してもらって、
「モラルハザードはあってはならない」という啓発活動を団体を通じて行うことで、
良貨が悪貨を駆逐するような流れを作っていきたいという強い思いがあります。
ただ、モラルハザードによる行政処分や事業停止によって、
当事者やご家族が大変な思いをするのは間違いないので、事前に予防していく必要性があるとは思います。
行政サイドとして、監査を厳しくする他に、国としてできることや、
我々が期待できることにはどういうことがあるんでしょうか。

障害福祉という業界においては、外からの監査にはあまり期待できないですね。
ないよりはましですけど。
だからそれは、当事者がモノを言える、それが反映できる体制を作ることだと思うんですね。
ついでに言うと、今も大きな問題は精神病院です。
これも施設福祉から地域福祉へと言っていますが、病院がとにかく患者を外に出さないんですよね。
しかもそれは一つや二つの精神病院じゃなくて、全体的にそうだと。
そんな中では、悪質なところをどうするかは課題で、まだ解決がつかないですけどね。
新しい敵ですね、我々にとって。

精神病院は医療法人や財団法人が経営していると思うんですが、どうしても経営という観点から、
病院を維持存続させるためにモラルハザードが起きてしまうこともあるということですよね。
介護では地域移行という観点から民間委託をし、介護保険制度も導入されたことによって地域福祉が一気に拡充したと同時に、
民間委託したことによって、地域福祉がモラルハザードに陥っているという両義性がありますよね。
我々は民間の事業者として、自分自身の自制心を高めて、自分たちのモラルを鍛えていくということはとにかく大事だと思いますが、
そうはいっても国のグランドデザインの枠の中で動いていることは確かなので、
この次の時代を進めるために、どう国がかじ取りをしていくのかという方向性には期待もあるし、不安もありますね。

敵は強力ですよね。
お題目としては、地域福祉で金もうけをするなってことですよね。
でもこれはお題目でね、市場原理の中で淘汰していくということです、究極はね。

ありがとうございました。
今回は、「施設から地域へ」というテーマでお二人の思いや実践、課題についてお伺いしました。


















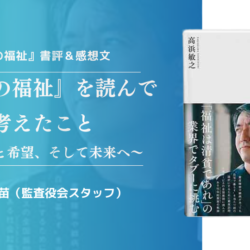


-1.png)




















