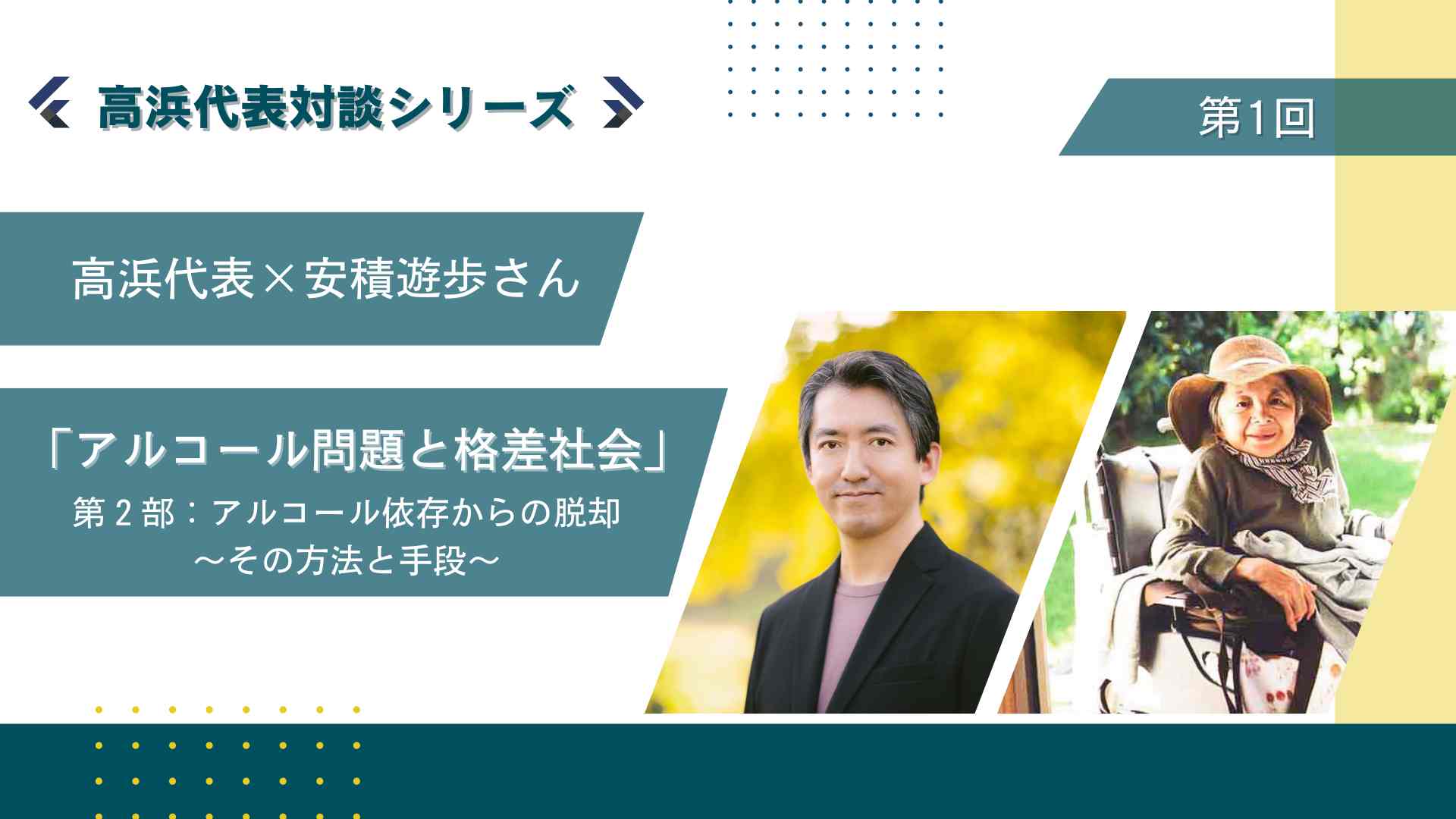
「アルコール問題と格差社会」~第2部:アルコール依存からの脱却『その方法と手段~』~
対談参加者
安積 遊歩……株式会社土屋 顧問
司会……宮本 武尊/取締役 兼 CCO最高文化責任者
アルコールという物質に対する認識について

第2部では、アルコール依存からの具体的な脱却方法についてお話を伺いたいと思いますが、
そもそもアルコールとはなんなんでしょうか。
お二人は今まで関わってきた方々からアルコールがどのようなものだと捉えられていますか?

はまの会社の話の、アルコール依存で迷惑な存在の人たちは、アルコールで自分の心が100%開かれてるから、
大丈夫だって思ってるから離れられないんだと思うけど、それがアルコールという名の物質の作用なのかな。

やっぱり見てて迷惑な人たちは、自分の感情を言語化するのが苦手ですよね、自分もそうであったように。
脳科学的には、人間の感情の爆発を制御する機能が前頭葉にあるわけですけど、
ここが過剰に作動してて、要するにブレーキが利きすぎちゃって、
自分の感情を表現できないから、飲んだ時にその抑圧された感情を爆発させるっていう。
一言で言うと、不器用なんですよね。
で、押さえられたもの爆発させるから、それが過剰になりすぎちゃって、
必ず人間関係とかでトラブル起こすという感じがしますけどね。
やっぱりアルコールは薬物なんです、間違いなく。
良い悪いは置いといて、合法的薬物であることは間違いなくて、
そういう意味では、類型としては覚せい剤、マリファナ、コカイン、アヘンと同じなんです。
体内に摂取することで、脳に変化を与えるというのは全部一緒なんですよ。
そして、これには強度もあって、科学的に証明されてるわけですよ。
アルコールは最高強度です。
薬物の3トップはアルコールと覚せい剤、コカインです。
マリファナとかニコチンの人体への影響なんて、この3トップに比べると、
スズメバチに刺されるのと、蚊に刺されるのくらい違うんです。
ほとんどの人にこの認識はないですよね。
違法か合法かという観点で、コカインのほうがよっぽど恐ろしいに決まってるってみんな思ってるけど、実は互角なんですよ。

だからアルコールはやめるべきだと。

私は遊歩ほどラディカルにアルコール全廃主義ではないので、
「ほどほどに飲める奴は飲んどけばいいじゃないか、めんどくさいから」といった感じですが、
ただ飲めない人たちはやめたほうがいいと思ってます。
だって覚せい剤と一緒なんだから。
それと、ほどほどかどうかは自分じゃ自覚できないんだから、他人に決めてもらいなさいと。
自分の飲み方が適正かどうかは、周りから見て初めて分かるので、周りに「いや、お前の飲み方、異常だ」って言われたら、
自分は「覚せい剤中毒者だ」って言われたのと同じと捉えるべきなんです。
脳科学はそう言ってるんですよ。だけど、そういう捉え方してますかと。
やっぱり世の中のアルコールという物質に対する認識は、実態とずれがあるんじゃないかと思いますね。
私も最近、酒蔵の経営者の友達が増えてるので、あまりアルコール自体を根本から否定したら、また友だち失って、
酒に走ることになってしまうのも嫌なので、そういう気はないんですけども(笑)事実としてはそうですよと。
ズレがあると思いますね。

はまは酒蔵の友達とかできて、利き酒っていうか、試し飲みをしたりとか、最近はしてるの?

するわけないじゃないですか。
「このビールはノンアルコールですよ」って言われても飲まないです。
シャンパンとかビールという名前がついている限り、1滴たりとも体内には入れないという深い決断を持って生きてますよね。
それで不便とかも感じないので。
食事の席でも、「ウーロン茶に変えてくれ」って言えばいいだけですから。

ある意味、めっちゃラディカル禁止論者だよね、はま自身も。置かれた環境の中でそこまで制御できているのはすごい。

自分自身はそうですけど、自分と他人は関係ないので。
他人は好きにしてくれと、自分に迷惑かけない以外はっていうところで。
会社の中では迷惑をかける可能性があるので、好きにしてくれとは言わない。

迷惑をかけられちゃうからね、なるほど。

かけられるんですよ。
なんなら起訴をしたいくらいの(笑)実際、一定役職以上には「私は仕事関係で飲みません」という誓約書を書かせて、
もしこれが虚偽だった場合は1,000万円の損害賠償請求を受け入れてもらうくらいの迷惑ぶりですよ。

書いてほしい、ほんとだね(笑)

それくらい、ほんとにトラブルあるところに酒がありですよ、この会社。
「お酒のないところにトラブルってなんかありましたか?」っていうくらい、
全トラブルの背景にアルコールの香りがしますよね。
それを見ても、アルコールが脳に与えるインパクトは楽観視されてる印象がありますね。

ほんとだよね、楽観視もいいとこだよね。
はまの会社だけじゃなく、政治の場もそうだし。
性暴力、戦争ではアルコールの大量消費が背景にあると思うね。
ありとあらゆる場でアルコールが多大に使われていると思うね。
アルコールがあるからこそ、ありとあらゆる暴力が止まらないという認識を今日ね、
最初の対談で持ちたいなと思ったんですよね。
なぜなら、はまがアルコールをやめなければこの会社は出来なかっただろうし、はまの子どもたちも生まれていなかったよね。
そのくらい、はまがアルコールをやめたことは大きな社会変革だったよ。
みんな簡単に考えてるもんね、アルコールは嗜好品の一つとか。
アルコール健康障害対策基本法って平成25年に厚労省が出してるんだけど、
実に、「この社会のシステムを守るために多大な量のアルコールはやめましょう」ということだけだからね。
知らないだもんね、みんなね。
健康障害のほんとに多くの根底にはアルコールがあるということとか、
うつ病、交通事故とか、ありとあらゆるところにアルコールは破滅的に影響しています。
なぜアルコールに依存するのか

アルコールは危険な物質ということですが、アルコールに依存している人は多くいらっしゃいます。
なぜ依存にまで至っているんでしょうか。

依存全般でいうと、うちの娘も早速YouTubeにはまってます。
家の中で「YouTube見るな」、「見たい」の闘いが毎日のように繰り広げられているんですが、
娘がぱっとYouTubeを手放す瞬間ってあるんです。
それはまず友達と遊ぶ時。それと私と遊ぶ時です。
今のところはですけど。
なので、ほんとに求めるのは「人と触れ合うこと」だとしたら、
依存というのは、それの代替手段かなという感じはするんですよ。
ただ、娘がこれからどういう人生を歩むか分からないですけど、
人生、いいこともあれば嫌なこともある中で、遊歩が経験した障害者差別とか、
かなり深い嫌なことがあった時に―それが傷と言えますけど―世界と自分を分け隔てる壁というか断絶が深まっていく。
そういう経験を繰り返すことで、人と触れ合うことから逃げたいという感覚が必ずやって来ると思うんです。
「あの人と遊んでも嫌な気持ちになるだけだから、それだとYouTube見てたほうがましだ」みたいな。
そういう経験が繰り返されちゃううちに、YouTubeが手から離れなくなるかもしれないし、
そのYouTubeは大人になって、アルコールとか薬物に変化する可能性があるんですよね。

どうそこを乗り越えていけばいいんでしょうか。

実際、嫌なことをなくすなんてありえないわけであって、生きていれば必ず嫌なことがある。
でも嫌なことを経験しても、それを話せる人間関係があれば、その記憶を過去形のものにすることができると思うんですよね。
それは親友だったり、家族だったり、人によってはカウンセラーだったりということになるかもしれませんが、
私はアルコール依存の自助グループだった。
そして、そこで見たものは、より「本質的な飲み会」だったんです。
あそこは、ホームレスの親父とか、失業して生活保護を受けてる親父が、
自分が一番言いたいけど言えなかった感情とか気持ちについて素直に話すことができる場だったんです。
酔っ払ってくだ巻くよりも、より深くて本質的な、より奥のほうから出る言葉がそこで交わされていた。
みんな、実は欲しかったのはアルコールではなくて、アルコールを使って人と触れ合いたかっただけなんだなって。
自分もそうだったんだなって思ったんですよね。よっぽど飲み会より楽しいと思いましたね。

それが自助グループなんですね。

ある種、人工的にできてる場ですよね。
なぜなら、人間関係に伴う、傷ついたり傷つけられたりみたいなコミュニティの危険性は世の中に蔓延してて、
それはうちの会社だって絶対ありますよね。
人といればいいこともあるけど、嫌なこともある。
この嫌な経験が人工的に引き算されている、つまり社会装置として、
心理的安全性が徹底的に保障されてる場として、人工的に設けられてるんですよ。
だからそこでは「言いっぱなし、聞きっぱなし」って言うんですけど、誰かが何か言った時に、
それに対して反論したり、ディスったり、そういうのしちゃ絶対ダメと。
自分が話すときも他人をディスったりしちゃダメ。
「自分を主語にして語れ」っていう、鉄のルールがあるんですよ。それが心理的安全性を保障してたんですよね。
でもそれこそが必要な場だった。
人間はやっぱり人を求める存在だと思うんですよね。
それさえあれば、アルコールや薬物、ギャンブル、YouTubeやゲームを十分超えていける可能性があると思いますね。
それは、うちの7歳と5歳の娘たちにも発見できますよね。

安積さんはいかがですか?

ものすごく思うのは、とにかく、アルコールは私の中では、自分も人も傷つける暴力の装置っていうように見えています。
私はアルコールがあったから今がある、守ってくれてたというふうには言えないし、言いたくないなと思ってます。
なかったら、また何か違うのを見つけたかもしれないけれども、ぎりぎりでよく生き延びたなっていう感じだから、
アルコールが自分の人生にとってある意味良く働いたなとは思えない。
自殺未遂の場にはアルコールがいつもあった。
でもそれになかなか気づけないですよね。
これだけシステムがアルコールを必要としてるから。
自分でも必要としているようにものすごく感じさせられるから。
つらい気持ちを感じないためにアルコールが必要なんだっていうように思っているから。
ほんとに困った薬物だなと思います。

社会的構造として、アルコールが必要とされているとのことですが、そこからどう転換すればいいんでしょうか。

それはやっぱり、はまの言う通り、アルコールなしでもつきあえる、安全な場所を数多く作れるといいなって思いますね。
はまの娘たちが、はまや友達が遊ぼうといえばすぐ飛んでくる、
つまり心を100%全開にしても大丈夫という場所が一つでも二つでもあれば、
アルコールに依存しなくてもいいと思うし、もちろんアルコール以外にもね、自分を開くことができる場所を見つけ出すとか作り出すとか。
人工的にしか今のところ作れないんだったら人工的に作って、努力するに価値のあることだと思いますね。
この社会のアルコールに対する認識が、アルコールにつかまっている人は迷惑な存在で、
ほんとにやめてほしいって思うっていうくらいに自分を傷つけ、
他人を傷つける暴力の巣窟なんだっていうふうに変わっていってほしいなと思ってますね。
アルコール依存から抜け出すための実践的取組み方法

アルコール依存から抜け出すための具体的な実践方法を教えて下さい。

とにかく、はまが何度も言ってくれたカウンセリングですよね。
赤ちゃんとか、言葉がない人たちのコミュニケーションって涙とか笑いとか、みんなそうじゃないですか。
今は言葉で自分の感情を押し隠さなくちゃいけないという教育がすごいけど、そうじゃなくて、
お互いに「泣いていいんだよ」みたいな気持ちで向き合う関係性をいっぱい作ることが大切だよね。
そうなったら子どもたちも幸せになるはずだから。
基本のきの字は、そういう感情に対する、今までとは違った理解・アプローチ。
感情とは押し隠さなきゃいけないものなんだという教育から私たちが自由になって、関係性を作れればいいなって思ってます、いつもいつも。
だからこないだ、あまりコミュニケーションしたくないっていう人としゃべっているうちに、
彼女がすごく泣いたから、「泣いていいよ」って言ったんですが、涙に対する認識が違う世界に生きている。
アルコールに対する認識もそうだよね。
アルコールがコミュニケーションの手段で付き合いに大事なものだというのは私は違っていると思うから、
ぜひアルコールなくても自分の気持ちを、言葉で説明できないんなら涙で表現できるような関係性を、一人一人が持てるといいですよね。
経営者として、そういう人工的な場が会社の中でも必要になっていくんじゃないですかね。
どうですか?

ほんとに仰る通りで、やっぱり「コミュニケーションのスキルを身に付けること」と、
「スキルが低くてもやれるような場に身を寄せること」が大事かなと思いました。
この、スキルが低くても人と仲良くなれる場所が自助グループだったりすると思うんですね。
同じ属性とか同じ悩みを持ってると、スキルが低くても仲良くなれるんです。
だから我々のようにスキルが低いから友達ができない人に、友達を作らせてくれる機会を与える。
マッチングアプリみたいなもんですよね。
それに私自身、我ながらスキルは上がったと思うんですよ。
今や「口がうまい」で有名になったので(笑)昔は口下手だったんで、そう言われるのは感慨深いものがあるんですが、それがなんでかというと、
お酒も使えたっていうのはあるんですけど、一言で言うと、場数を踏めばどんな“へぼ”な奴でも多少は上手くなるという。
やっぱり場数が大事だと思うんです。
特にコミュニケーションスキルの高い人、遊歩なんて達人なわけで、そういう人と一緒にいる時間を持つと、
人ってやっぱり模倣する生き物なので、だんだん上手くなると思うんですね。
だから、スキルを上げつつ、へぼでもいける場を作ると。
で、自助グループとは違う、へぼな人でも簡単にコミュニケーションができるいい場があるんですよ。
それが「共通目標を持てる場所」です。
私にとってはそれが、若い頃はスポーツだったり、大人になってからは社会運動だったんですよね。
同じ社会問題を解決するということで、絶対仲良くならないような、気の合わない奴とも仲良くなれたりするんですよ。
スポーツでもヤンキーと優等生とか絶対合わない奴が親友になったりとかするじゃないですか。
だから共通目標はすごくお勧めですが、とはいえさすがに詐欺行為はお勧めできないですけど。
SDGsを追求するとか、みんなで一緒に目指せる、よりよい目標のほうがいいですよね、社会にとって。
そうしたいい目標を持てる場に入ると、友達ができない人でもできるようになったりすると思うんですよ。
ソーシャルビジネスもそうだと思いますね。
今のうちの役員と、素で友達になれたかっていったら、ほとんど誰もなれなかったんじゃないかくらいの感情が正直ありますけど、
でも今友達じゃないですか、会社の中では一応。一緒になんかやっていこうぜみたいな。
しかもいいことじゃないですか、我々の場合。
こういうのはお勧めです。
だから自助グループと、共通目標持てる場と、達人と接する機会を作るという、この三本柱がいいと思いますよね。

やっぱり、はまはさ、カウンセリングやってて、「お酒やめれない」って言っているうちは、そこに限界を付けてたからさ、なんでも。
自分の中にどっかで限界があると、他のところにも限界がくるけれど、
「やめる」っていう決断の下で限界を突破したからさ、そこから色んなところに限界突破が始まったんじゃない?

ほんとほんと。仰る通り。

身体に出てくれなければさ、もう限界突破はなかったかもしれないくらい、お酒をやめたってことで人間性が花開いたんじゃない。
他者の存在について

では、最後にお二人から総括をお願いします。

アルコール依存ではよく「底つき」って言うじゃないですか。
「自分で気づいて自分でやめなきゃダメなんだ」って。
それはその通りなんですけど、でもやっぱり気付きは他者なんですよ。
遊歩に会うたびに、ずっと「酒やめろ、まだ飲んでんのか」と言われてて、
「うるせえな。めんどくさいから近づくのやめよう」って思ってはいたけど、あれだけ言われたら記憶に残るんですよね、その言葉が。
で、自分がどうしようもなくなったとき、「あの人が言ってたのはこれだったのか」と。
一見無駄ともいえるお説教が、実際に無駄だったかというと、やっぱり無駄じゃなかった。
だから私は、いわゆる海底から上がってくるのが他の人と比べて早かったんですよ。
この上がりの速度を高めるには、他者の存在って大きいと思うんです。人間関係ってほんと大事。

私にも「なんでやめない人に無駄なことを言い続けるの」って言ってくる人もいるわけですよ。
でも今、「記憶に残る」って言ってくれたけど、それがあるのとないのでは全然違うよね。

違うんです、やっぱ。結局違うんです。

だから私は立岩(立岩真也:社会学者、故人)にもそういう存在でいたいって思ったけど、ちょっと間に合わなかったね。
立岩の家に泊まってんのに、私を拒否してさ。
夜飲みたい時間になると、もう部屋の扉、開けてくれなかったからね。
それでも家には行けてたから、もうちょっと間に合えばよかったなあ。
だから、はまには間に合ってよかったってしみじみ思ってるよ。
とにかく、うるさがられようと何しようと、愛情をもって関わるというのは、コミュニケーションの基本のきの字ですね。

やっぱり妙薬口に苦し。
人に言われて嫌なことは、実は後々役立つ面もあるっていうのを、飲む側は自覚していることが大事。
「飲むな」って言われるより、「飲みっぷり最高ですね」とかのほうが気持ちいいに決まってんだけど、
でもやっぱり時にネガティブなことも言ったほうがいい。
ゆとり教育は大賛成ですけどね。
逆にいいことばっかり言うのって嫌われたくないからだけで、
自己中心的なんじゃないかっていう見方もあり得るじゃないですか。
やっぱり『嫌われる勇気』っていうベストセラーの本もありますけど、必要な面があると思いますけどね。

そうだそうだ。
特にアルコールに関しては、嫌われる勇気、大事です。

ま、長女にめっちゃ嫌われてますけど。
全く身に覚えはないけど。
良いことばっか言ってるのに、「素晴らしい」とかしか言ってないのに嫌われてます。

(笑)大丈夫、それは大好き。
7歳でちゃんとそこまで表現できるってすごいじゃないですか。
子どもとの関係がどうかっていうのもほんと大事だよね、言葉を我慢させてないかっていうのは。
嫌われる勇気、障害を持つ仲間にいっぱい言いたいな。
ほんとに、嫌われないようにしようとする人が結構多くなってきてるから。

本日はありがとうございました。
勇気がキーワードだったかなと。
いろんな勇気があると思いますが、勇気と共に感謝の気持ちもすごく重要なんだなと。
アルコールという切り口から人生全般の大切なことを教えていただいた感じがします。












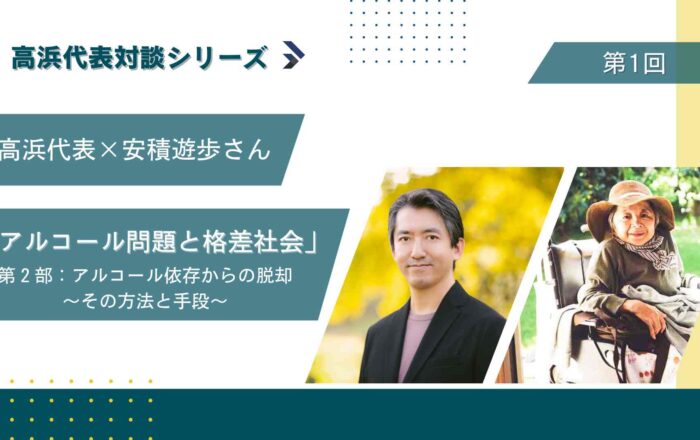







-1.png)




















