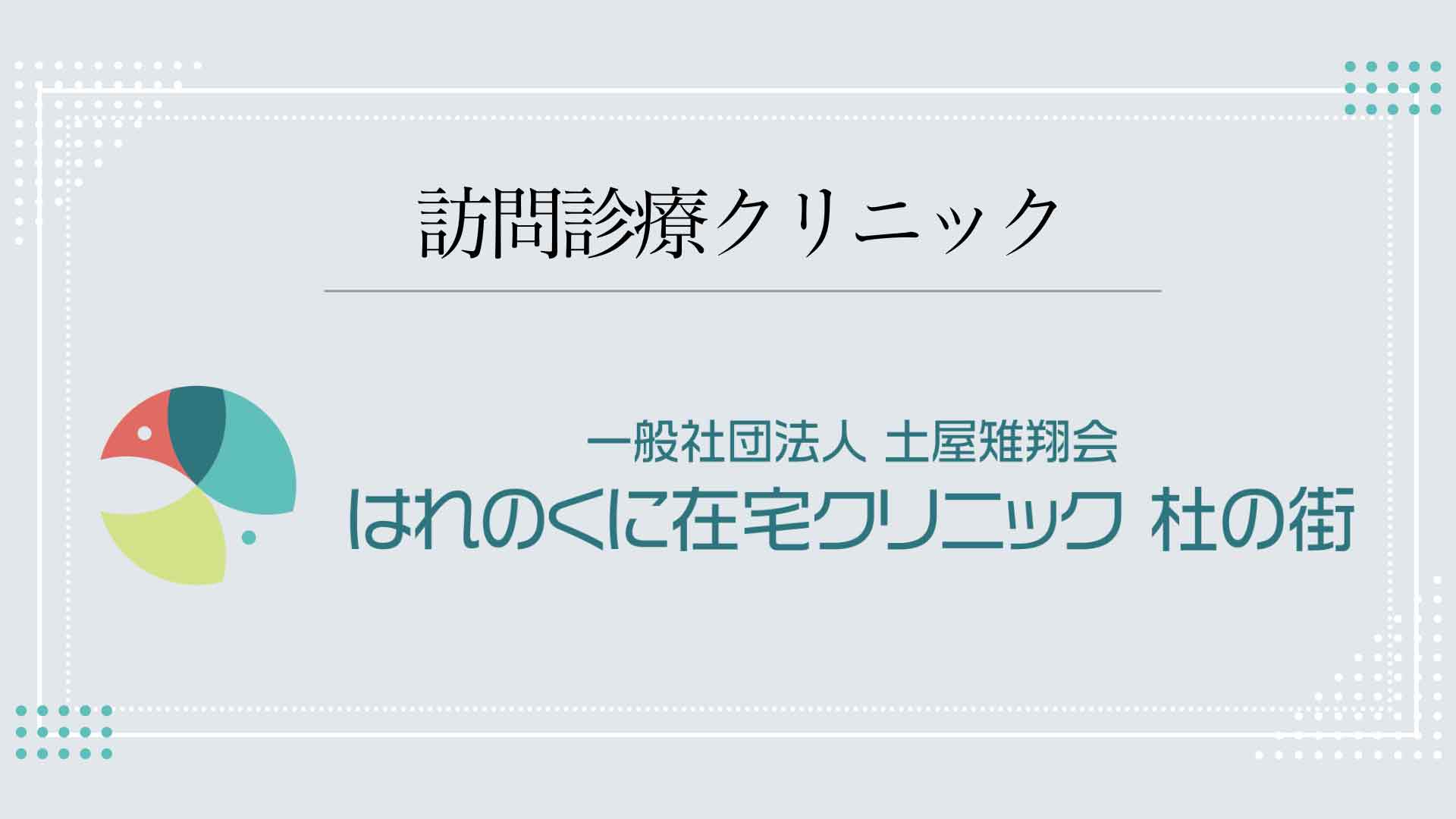役割とは / 豊田幸歩(本社管理部)
全てを読み終わったとき、一貫して「ひと」との関わりや経験が転機となる事を感じた。
介護保険だとか支援区分だとか決まった制度はあるが、その先にいるのは、「ひと」であり、考え、他者と関わり合い、それぞれが「自らのすすむ道」をつくりあげていく。
それはクライアントやアテンダントなど、どんな立ち位置でも関係なく皆がおこなう営みとしてある。
我々が提供する主なサービスである重度訪問介護はクライアントが「自らのすすむ道」の道標を探し、えらび、切り拓き、つくりあげていくためのひとつの手立てである。
だがその「手立て」となるアテンダントも「ひと」である。考え、関わり合いながら「道標」を得て「自らのすすむ道」をつくりあげていく。
当著書を通して、私は従業員として土屋にいる事について考えた。
誰しも働いているうちにやりがいや達成感の他に、「道標」となり得ないような理不尽な思いや経験をすることがある。その様々な経験が「すすむ道」の彩りとなる。
しかし、彩りの陰りは減らしていけるように、私が担える役割とはなにか模索したい。
役割は必ずしもはじめに決められるものではなく、経過していく時間の中でふいに気づくものや、負の体験、無駄だと思えた経験すら「役割」に昇華していけるものもある。
そしてそこからまたそれを新たな彩りとして、「道」を拓いていけるのではないだろうか。
ヤングケアラーの現状の項で「家庭のことというのは、ある意味で密室」であるとの言葉があった。生まれたときから、その「家庭」にいればそこにあるものが自身の普通として生きていく。
その密室の窓を開く機会がなければ、外に違った景色が広がっていることにすら気付きにくい。知らない景色に手を伸ばすのには勇気を必要とする事も多い。
そういった密室にいる人に外から手を差し伸べたり、窓から入り込む涼やかな風を吹かせたりすること、その人に関わって違った景色を目の前に拓くためには、手を差し伸べるひと自身が自慈心を大切にすることも必要と感じた。
自慈心をもたずして、手を伸ばし続けると損耗していくのはそのひと自身である。
少なくとも私と関わるひとが自慈心を持てる環境とはなにか、日々問答し、意識を研鑽していきたい。
当著書内でも障害者福祉関連法の変遷において触れられていたように、現実に求められているものと制度との間には多くのアンティノミーをはらんでいる。
これは様々なことに当てはまり、国や地域、延いては今所属している学校や会社など多くの「ひと」が関わるところ全てで起こりえる問題である。
私はいま、労働基準法をはじめとした、労働する上での法を学んでいる。
「やりがい」や「おもしろみ」などを得られる事は働く上で大切なものである。
ただし、もらうべきもの、享受すべきものを労働者が当然として得られることが、正しく「働く」ということであると私は考えている。
私はこれを学ぶことに「おもしろみ」を感じている。この「おもしろみ」を社会の中に混在するアンティノミーの解決の糸口として変換していけるよう尽力したい。
また、縁が繋がって入社した従業員の満足度をあげることは、本社管理部の責務である。
私個人にできる事はそう多くはない。
けれど歴史上の文化がそうであったように、ひとりの「小さな声」が土屋の文化を紡ぐ一本の糸であり、誰かに届き、重なり合い、縁やきっかけとなり結びつきが生まれ、道となる。
私が感じた事や発信したことが、振り返ったときに小さくとも何かの役割となれればいい。
当著書を手に取った事は、いまの私が社会のなかで暮らしながら担っていける役割について立ち返る1つの基点となったことには間違いない。
「株式会社 土屋」という窓を通して社会を見ることで今まで見えなかった社会問題も見えた。見えればつくりあげていく道の選択肢も増やすことが出来る。
大きな社会問題を紐解いていくためには1つの手法だけではなく様々な方向からのアプローチが必要だが、個々が抱える意思や悩みが糸口となり、たとえ小さくともその問題に対しての一手となることを祈る。



















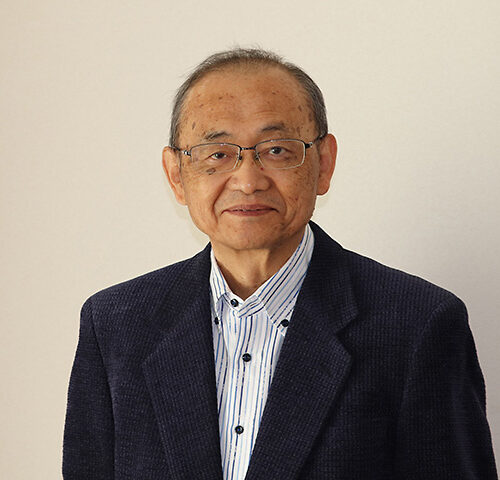

-1.png)