「なんで足、ちゃんと前に出して、サッササッサ歩けへんのや!あんたなぁ、あれだけモスクワの施設で訓練させて来たのに…。情けない、ほんま情けないわ・・・。あんた、普通の人みたいに歩けるようになろ思てへんやろ?!あんたみたいな怠けモン、知らん!!」
「歩けるようにならんと、普通の生活でけへんで。どこへも行かれへん、何の仕事にも就かれへんわ。そうなったら死ぬしかないんやで。歩けるようになりたいやろ?!」
と母が怒鳴り散らす。
私はすかさず、
「うん、なりたい!」
と答える。
親も子もこの時点で涙と鼻水で顔がグチャグチャになっていた。
これは、私が10才か11才の頃、毎朝繰り広げられたファミリー劇場の殺気だったワンシーンだ。
私は当時、足先から腰までの補装具を付けて杖をついて歩けていた。いや、正確に言えば、ソロリソロリと移動することができた、という程度だ。
確かに私は、5年間に渡る、モスクワの障害児施設での生活の中で足の手術と機能訓練を受けた。そしてその時は体幹がしっかりしていたし、脳性麻痺特有の不随意運動やツッパリもある程度抑えられていた。しかし、その状態が維持できていたのは、毎日の筋肉弛緩剤注射や数時間にも及ぶマッサージといったメンテナンスのおかげだった。
日本に帰ってから、メンテナンスの無い状況下であの比較的良好な状態を維持し続けるのは、そもそも無理な話だったのだが、施設にいた私に会いに来るのが2か月に1回、しかも長くて1時間余りの面会時間では、母がそんな「裏」があることに気づく由もなく、私の脳性麻痺が着実に治っていっているのだと考えていたのだろう。
だから母は帰国後、「普通」に戻っていない私を目の当たりにして、大きな落胆と焦燥感が渦巻く一種のショック状態に陥ったのでは、と思う。そして始まったのが冒頭のシーンで、私を激烈に叱咤することで何とかしようとしたのではないだろうか。当然のこと、そんなことをいくらやったところで、いつまでたっても私がスタスタと歩けるようになるはずもなく、成長して体重が増した私は余計に身体の動きが悪くなっていった。
毎朝繰り返される冒頭のシーンのラストは、必ず私の頬が平手打ちされる弾けたような音と鋭い痛み、そして「歩かれへんのは、あんたにやる気が無いからや!」という罵声だった。
が、この罵声は半分正しかった。意外かもしれないが、そもそも生まれつき歩けない私は、「普通の人のようにスタスタと歩けるようになりたい」などと自分から思ったことは一度も無いからだ。逆に、膝立ちで歩いたり四つん這いでいざったりする方がよっぽど早く移動できた私にとって、二本の足で歩くことはしんどいだけで、どこにどんなメリットが有るのか理解できなかったのだ。
「歩けるようになりとうないんか?」との母の問いかけに、当時の私がいつも間髪入れずに「うん、なりたい」と答えていたのは、そうしないと罵倒される時間が延び、またひっぱたかれる回数が増えるからだった。私が歩けるようになりたかったのではなく、母が私を歩けるようにしたかっただけなのだ。そう、普通の人のように〇〇ができる私を作りたかったのだろう。「普通」と「できる」ことに憑りつかれていたのだ。
話は変わるが、子供の頃から大人になってからも、頻繁に他者から投げかけられてきた言葉がある。それは、「障害があるのだから普通の人と同じように生きたければ、3倍も4倍も努力しないと駄目だ」というものだ。また、「何もできない障害者は、一般社会のお荷物にならない為にも謙虚の上にも謙虚になって目立たないところに身を置くべきだ」という言葉も何回も聞いたことがある。
養護学校の中等部に通っていた頃、毎年、冬の感冒シーズンになると、症状の進んだ筋ジストロフィー、重度脳性麻痺の子たちが肺炎で命を落とすことがかなりの頻度であった。その子たちの通夜と葬儀で耳にした、悲しみに暮れる親を慰める決まり文句がこうだった。
「これでいいのよ。この子が何もできないまま大人になるまで生きたとして、あなた、そんな子をこの世に残して死ねる?死んでも死にきれないでしょう。親孝行してくれたのよ。」
このようなことを口にすることが多かったのは、特に養護学校の教師や医療関係者、障害者の就職、生活上の相談を受け付ける職業の方々だったように記憶している。
もちろん、何の努力もいらないとは私は言わない。しかし、3倍、4倍はいかにも多すぎるだろう。しかも、できない、能力がないことが、どうして死に直結するのか、どうして死んで良かった、となるのか。社会の不備がそう言わせている面が大きいのだろう。しかし、果たしてそれだけだろうか。
去る7月26日は、5年前に相模原やまゆり園事件が起こった日だ。
あれから私はずっと考えてきた。私の聞いてきた残酷な言葉や私の悲痛な経験と、あの事件とは同じ線の上にある、ということを。
「(障害がある子は)親より先に死んでよかったんだよ」を癒し慰める言葉として口に出してしまう人たち、普通の人のように私が歩けるようになることにこだわった私の母、そしてやまゆり園で46人もの重度障害者を殺傷した、元同施設職員の植松死刑囚。これら三者に共通するのは、「障害を持っていても何かを普通の人のようにできること」にこだわり、そこに生の価値を結び付ける、という価値観だ。もっと端的に言うならば、これら三者は、障害者に最も近い立ち位置を占めながら、優生思想(何もできず役に立たない者は無価値だという考え方)を内包してしまって、それが正しいと信じて疑わない人達であるということだ。
もちろん、三者がその罪の深さにおいて、残忍さにおいて全く同じだ、などと言うつもりは毛頭無い。それでも、内なる優生思想に気づき、それを克服しない限り、誰もが私の親のようにもなり得るし、さらに言えば植松死刑囚にもなり得ることを肝に銘じるべきだ。
やまゆり園事件を起こした植松死刑囚は言ってのけた、「意思疎通できない障害者には生きる価値がない」と。彼の示したこの言葉に対する私たちの正しい抗弁は、「いや、この人達も意思疎通できているかもしれない」では決してなく、「意思疎通ができる・できないことと生の価値との間には何の関係もない」であるべきなのだ。前者と後者では、意味する内容が全く違う。ここを絶対に取り違えてはいけない。
きれいごとだと言われようと、どんな誹りを投げつけられようと、私は、全ての生に価値があり、また生の意味に何ら条件も付けられるべきではない、という信念を曲げないだろう。もっとも、日々の生活の中で常に「生産性」やら「効率性」やらの人間性を無視した物差しで優劣を判定され続けるこの社会では、私もついその信念を見失いそうになるのだが・・・。それでも、これだけは言っておきたい ー そのきれいごとが意味を失くした社会では、もはや誰も生きることを許されなくなるだろう。誰も、だ。なぜならば、なんでも「できる」人はほとんどおらず、何かしら「できない」を抱える人の方が圧倒的に多いからだ。
7月26日という日を忘れまじ。
◆プロフィール
古本 聡(こもと さとし)
1957年生まれ
脳性麻痺による四肢障害。車いすユーザー。 旧ソ連で約10年間生活。内幼少期5年間を現地の障害児収容施設で過ごす。
早稲田大学商学部卒。
18~24歳の間、障害者運動に加わり、障害者自立生活のサポート役としてボランティア、 介助者の勧誘・コーディネートを行う。大学卒業後、翻訳会社を設立、2019年まで運営。
2016年より介護従事者向け講座、学習会・研修会等の講師、コラム執筆を主に担当。













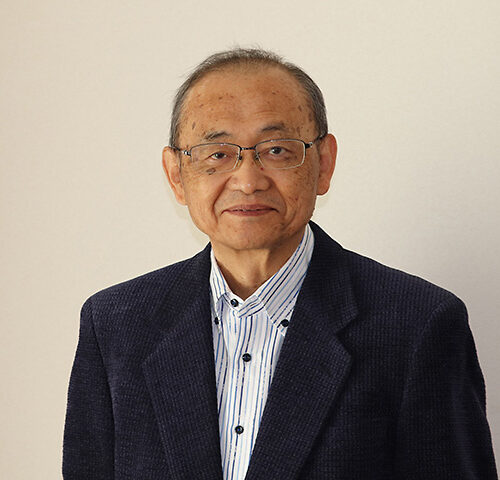

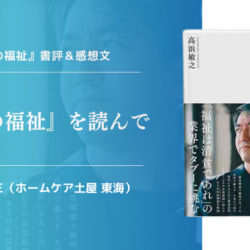




-1.png)




















