土屋ブログ(介護・重度訪問介護・障害福祉サービス)
深夜午前2時7分
「それで近所の人が言うには、笑い声が止んで急に何かガラスの割れる音がして、その後壁を叩く音や床に何かを叩きつける音が聞こえたって言うんだけどどうしてそうなったの?」
と、峰田は質問を投げ掛けてきた。
ワイングラスを壁に投げつけたり、フライパンを振り回して部屋中を滅茶苦茶にするのにはそこに至るまでのそれなりの理由がある。この大人はそう考えている、と冬治は思った。
物事には原因と結果があって、それは理路整然と説明可能だとこの女は考えている。
幸せ者だ。
理由なんかない、という世界を知らない。
冬治が答えないでいると峰田は肩をすくめて話を先に進めた。
「そこから怒鳴り声が聞こえた」
「いつもです」
「叫び声も続いた」
「日常です」冬治は答えた。
「どうしてお母さんは怒鳴ったの?」
峰田の質問に冬治は睨んで返す。
「峰田さんはどうして呼吸するんですか?」
「何?呼吸?する理由?」
「そう、どうして息するの?」
「生きるために体が自然にしてるのよ」
「じゃあ母が怒鳴る理由も同じです」
深夜、暗いロビーはいっそう静まり返っていた。
峰田は指をおでこにあててしばらく考え込んでいた。
うっすらとシャンプーの香りがする。
お風呂に入ったあと、(もしかすると子どももいて一緒にお風呂に入ったあと)緊急の呼び出しでうちに駆けつけてくれたのかもしれない。
それを考えると忍びない。
この人の幸せな家族の時間を邪魔してしまったのかもしれない。
迷惑をかけてしまった。
息をして、動いて、何かをしゃべると、誰かの幸せを壊してしまう。
誰かの希望や欲望を奪い、破壊してしまう。
母とは一体何者なんだろう?
世界を破壊し、誰かを不幸にするために生まれてきたのだろうか?
そいつから生まれ落ちた僕は一体何者だろう?と、冬治は時々考えるのであった。
◇
その日は朝から不気味だった。
台風が過ぎ去って本格的な秋を告げる空が広がっていた。昨夜までの雨で庭の木々は濡れ、しっとりとした落ち葉の匂いが冬治のベッドルームまで漂ってきた。
キッチンで物音がする。
冬治が恐る恐る階段を降りていくとキッチンで働く母の姿が見えた。胸騒ぎがした。
いつもなら母が冬治より先に起きていることなんてありえない。ましてやキッチンで何かをしていることなんてこれまでなかった。廊下の奥の部屋に閉じこもり、カーテンを締め切って横になっていることが多かった。
普段冬治は自分で朝食の支度をして食べ終えると、母を起こさないように扉をひっそり閉めて学校に出掛けた。部屋の掃除も皿洗いも洗濯も冬治が行っていた。
家事は慣れているので苦でもなんでもない。ただ、問題はそれを音をたてずに行わなければならない辛さだった。
これがかなり苦しい。
お皿の音をたてずに皿を洗う。水流の音もなるべくさせない。食器籠にそっと置く。
アクセルとブレーキを同時に踏まなければならないようなかなりのストレスがかかるのだ。
音がうるさくて眠れないと怒鳴られてからそこに気を遣わなければならなくなった。
音をたてないようにそもそも家事をやらなければいいとは思うが、やらないとあとで暴れられるのは目に見えているのでやらなければならない。
やらなければならないが音をたててはいけない。
夕方、学校から帰っても母はまだ部屋に閉じ籠もったままのことが多かった。そのまま朝まで部屋から出てこないことも稀ではなかった。
出てくるのはお腹が空いたとき、シャワー、トイレ、そして冷蔵庫の酒を注ぎにくるときだけだった。
冬治にとっても母が部屋の中にいてくれることはありがたいことだった。
母の部屋の扉が開く音を聞く度に胸がドキッとする。
緊張が走る。出てきてもろくなことがない。
ほとんど酒で酩酊していた。
文句を言ったり怒鳴ったり暴れたり、ネガティブなシャワーを冬治に浴びせかけるのだった。
だからそっとして、なるべく起こさないように息を潜めて冬治は暮らしていた。
ところがその日の朝は、台風一過の爽やかな光が溢れるキッチンで料理する母の鼻歌が聞こえてきた。
トントントンと包丁で何かを切る軽やかな音が聞こえた。
油の匂いがした。
やかんのお湯が沸いている。
キッチンの入り口に立つと母は背中を向けて料理していた。
「おはよう・・・」
と、冬治が声をかけると、
「あら、起きてきたの?おはよう!」
母は振り返って満面の笑みで冬治を迎えた。
手にはハムのサンドイッチを持っていて、それをお弁当箱にきれいに並べはじめた。
フライパンで焼いていたのは卵だった。卵が焼きあがるとまな板にうつして半分に切り、もう一つのお弁当箱に盛り付けた。
何をしてるんだろう?と怖くなったが聞くことができない。
「サンドイッチはいくつ食べたい?」母が聞いてきた。
「いくつ?」
質問に答えるときは慎重にならなければいけない。例えば「三つ」と答えてサンドイッチが二つしかない場合、あと一つ作ることになってしまっては困るのだ。その一つを作る間に何かが起こって気分が崩れてしまうことがある。そのとき、サンドイッチをもっと作れって言ったあんたのせいだと怒りの矛先は間違いなく自分に向かってくる。
だから新たにサンドイッチを母が作らなくてもよい数を答えなければならないのだが、それがいくつなのか、少なめを言っておくにこしたことない。
「二つかな・・・」
「それだけでいいの?作り過ぎちゃったかな?」
しまった。気分を害してしまっただろうか。冷や汗が出る。
「じゃあ、三つ・・・」
「余らせてももったいないから四つ食べなさいよ」
はじめから四つと決まっていたように母は言った。だったらいくつ食べたいか聞いてくる必要はないのに、と冬治は嫌な気持ちになる。
それでも地雷を踏まずに済んでホッとした。
「お弁当作ってるんだね・・・」
「そうよ。なんか気分がよくて、体が動くのよね今日は。だからバスに久しぶりに乗ってピクニックにでも行こうかと思って」
「ピクニック・・・」
「昔はよく行ったじゃない。小さなあんたを連れて。懐かしくなっちゃって。昔みたいに。お弁当持って、昔よく行った場所に行ってみましょうよ」
母とのピクニック。
昔よく行っていたのだろうか。あまり記憶がない。ここ最近は母と外に出ることなんて救急車で運ばれるときぐらいしかなかった。どこかに出掛けることがないばかりか、まともに家の中で一緒に過ごすこともなかった。一緒に食卓を囲む、食後の団欒をする、隣の布団で眠る、そんな時間の共有がなかった。
これが冬治の「家族の時間」なのである。
冬治は生まれてこのかた家族と一緒に時間を過ごしたことがないので、はじめからイメージがない。だから求めようとも思わない。
今の状態が当たり前だと思っている。
なんなら他の家族も同じように過ごしていると思っているところがあった。
普段では決してありえない「家族のピクニック」というものに冬治は動揺していた。アニメや映画の世界ではなんとなく休みの日に親子でピクニックに出掛けるのを観たことがあるが、いざ自分が行くとなるとまったくどういう展開になるのか分からない。
どう振る舞えばよいのかも分からない。
しかし今日一日の自分の「任務」は了解できた。
無事に帰って来られるだろうか。
鼻歌を歌いながら楽しそうにお弁当箱をトートバッグに詰めている母の後姿をキッチンの入り口から冬治は見つめていたのであった。
【後編】につづく











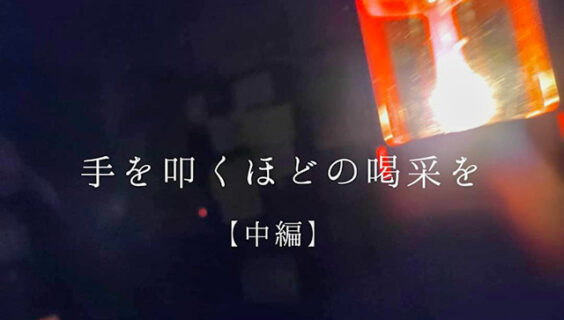







-1.png)




















