土屋ブログ(介護・重度訪問介護・障害福祉サービス)
2月16日、誕生日を迎えて、66歳になった。66歳は、母が逝った歳だから、私にとって特別な歳だ。母が逝った時私は38歳。母の反対していた政治家への立候補を決め、そのためにチラシを撒いた日でもあった。そのチラシ作りが忙しくて、亡くなる前日に電話をくれた母に「忙しいから後にして。何か急用?」と聞いたら、「いや、何もないけど…」と言われ、「じゃあまた後で」と、そのままになってしまった。
一体そのとき母は、何を私に告げたかったのか。とにかく母に対しては何でも言えたし、母と同じように私を応援してくれるのはいつだって妹だけだと思ってきた。甘えていると言えば、その通りだったろう。しかし、どこかに母を軽蔑していた気持ちがあって、こんなにも大好きなのに軽蔑し続ける事はなかなかに辛かった。だからピアカウンセリングに出会ってからは、母を心の底から誇りに思い、愛したいということに取り組んだ。ところが、ピアカウンセリングで話すたびに、医療トラウマの原因が全部母にあるとの思い込みに気づき、そこから出るために女性解放を学んだ。
母は2歳年下の妹を産んだとき、「自分と私を助けてくれる子を産みたくて産んだのだ」と、ポロっと言ったことがある。妹と私はその言葉を別々に聞いたのか一緒に聞いたのか覚えていないけれど、それぞれに「ちょっと酷いよ」と思ってしまった。私にとっては真実ではあったが、妹にとっては自分の命が自分のものではなく「お姉ちゃんのために産まれさせられたのだ」と思ったかもしれないと考えて。妹はもちろんそう思って、そこで苦しみもした。
しかしそれ以上に、私が医療からされている酷い治療であまりに苦しんでいたので、母の言う通り、思い通りに私を助け続けてくれた。しかし、先述した母のひとことは、妹を妊娠することで私に0歳からされていた男性ホルモンの投与を止めたかったということなのではないだろうかと今は思っている。つまり、妹にヤングケアラーと呼ばれるような役割を意図して産んだとは全く思えないのだ。
母は祖父母が小作農で寺男(お寺の雑事をするために雇われている人)をしていた貧しい家庭に育った。7人兄弟の上から3番目で、下の妹とは双子だった。その双子の妹とは、兄弟の中でももちろん1番の仲良しだった。しかし、その妹は母の結婚後、粟粒結核で、1週間で亡くなった。貧しさゆえに薬が買えず、酷い家父長制の中、大好きな妹が死の床にいるにも関わらず、結婚を急がされた。優しい母は、1人でも小姑がいなくなれば、当時結婚したばかりの兄の嫁、義姉が楽になるかもしれないと考えたのだろう。それとプロポーズしてきた人、私の父が既に満州で両親を亡くしていたので、そこに気を使う必要もないのだからと、家族親戚に説得されて結婚した。
そのために、私が生まれた時には、私に対してなされている治療が、命に別状がないものであったにも関わらず、医者の激しい脅かしの中、男性ホルモンの投与を2年間続けた。1日おきに打たれる注射のたびに泣き叫ぶ私を抱きしめ、見守った。どんなに泣き叫んでも母からは1度も涙を止められたことはない。
2歳までの注射は記憶にはないが、体の中には無茶苦茶な医療に対する怒りと不信が残った。そして13歳の時には自分で病院に併設された養護学校や施設の医者たちに激しく抗議をしてそこを出た。それからは、今後一切西洋近代医学の整形外科医にはかからないと決めた。母は一度として自分からは医者に治療の抗議ができなくても、私を止めることはしなかった。私が「ヤブ医者でてけ」と叫んでも、私の代わりに頭を下げて涙した。
そして私の言論の自由と抗議の意思を守り続けてくれた。医者は、時に私を庇う母に酷い言葉を投げつけた。その時でも、母は小さくなって医者に謝り、ポロポロと私と一緒に泣いた。
思い起こせば母と私の人生は、ありとあらゆる社会問題を濃縮して生きてきた。つまり、母は12歳で進学を諦め、児童労働で東京に出た。高等尋常小学校卒業で働かざるを得なかったのは、60人学級の中たった2人だけだったという。
ここにもあまりの経済格差と児童労働という社会問題がある。母は、小学校6年間、時に妹や弟を背負いながら通学したにも関わらず、勉強がよくできたので、副学級長もしていたという。にも関わらず勉強を続けられないほどの貧しさで、祖父に連れられて東京に出た。祖父もまた非常に優しい人で、勉強を続けさせてあげれない状況が不憫で母を東京まで見送ってくれたらしい。母の家は常に貧しさに追い詰められてはいたが、祖父母を中心に愛情いっぱいの家族であった。
私がなぜ宇宙をこの世に迎えられたのかというと、この母の優生思想とは無縁に生きていた姿があったからだと、今更ながら気付く。母は、私に公教育はとにかく卒業させたいと願い、学校に通い続けてくれた。片道1.5㎞の道をおんぶをして、授業中は、保健室や図書室で待ち続け、誰とでも仲良くした人だった。小柄な母だったから、私をおぶり、重い教科書を下げて通うのはどんなに辛かったことだろう。
戦争に負けたことによって、露骨な天皇制教育は影を潜めた。しかしその代わりに、今度は経済至上主義を貫徹するための人づくりに移行した。だから生産性のない障害児は養護学校に隔離、分離していくことになった。
私は小学校5年になるときに、その養護学校に好奇心に突き動かされて行くことにした。ほとんどの子供たちは、親や医者の勧めでそこにきていたのだが、私だけは母が涙まじりに止めてくれたにも関わらず、そこに2年8ヶ月を過ごした。差別を植え込む隔離分離教育は私から将来の夢を奪い、その後の1978年には養護学校義務化の法令さえ通された。
その法律が通る前の1969年、私は中学一年で、もう一度地域の学校に戻ってこようとした。しかし今度は校長から露骨な差別を受け、中学1年の3学期は就学権を奪われて不登校を強制された。その時にも母は、パートの仕事に出る前に、毎朝学校に通い、私が通えるよう学校に頼み続けてくれた。その諦めのなさと、父が教育委員会に働きかけてくれたことが実って、私は中学2年からは地域の学校に通えることになった。
もう一度繰り返すが、私の人生は親とその家族を追い詰め続けた家父長制度や天皇制教育、そして小作農制度や貧困、貧しさによる進学不可等々の社会問題、今回は書いていないが、父の戦争トラウマによるアルコール依存や暴力、そして私が障害を持ったことで受け続けた様々な差別。医療の横暴や教育からもたらされる差別等々を味わい、たくさんの不正義の中を生き抜いてきた。
しかしそこには、常に母の愛と涙に満ちた優しさがあった。その愛は語るには深すぎて、一見しただけではまるで全貌が見えない。しかし、母の存在、そして戦いこそが優生思想とは無縁に、私を抱きしめ続けて自由で平和で穏やかな喜びを志向し続けていたのだった。私が娘に無条件の愛情を注げるのも、この母のロールモデルがあったからこそなのだ。
◆プロフィール
安積 遊歩(あさか ゆうほ)
1956年、福島県福島市 生まれ
骨が弱いという特徴を持って生まれた。22歳の時に、親元から自立。アメリカのバークレー自立生活センターで研修後、ピアカウンセリングを日本に紹介する活動を開始。障害者の自立生活運動をはじめ、現在も様々な分野で当事者として発信を行なっている。
著書には、『癒しのセクシー・トリップーわたしは車イスの私が好き!』(太郎次郎社)、『車イスからの宣戦布告ー私がしあわせであるために私は政治的になる』(太郎次郎社)、『共生する身体ーセクシュアリティを肯定すること』(東京大学出版会)、『いのちに贈る超自立論ーすべてのからだは百点満点』(太郎次郎エディタタス)、『多様性のレッスン』(ミツイパブリッシング)、『自分がきらいなあなたへ』(ミツイパブリッシング)等がある。
2019年7月にはNHKハートネットTVに娘である安積宇宙とともに出演。好評で再放送もされた。

















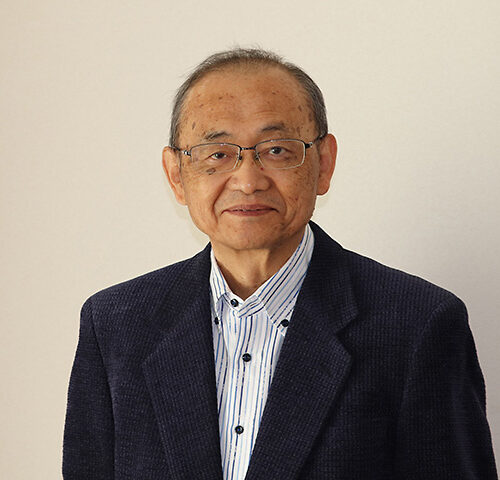


-1.png)




















