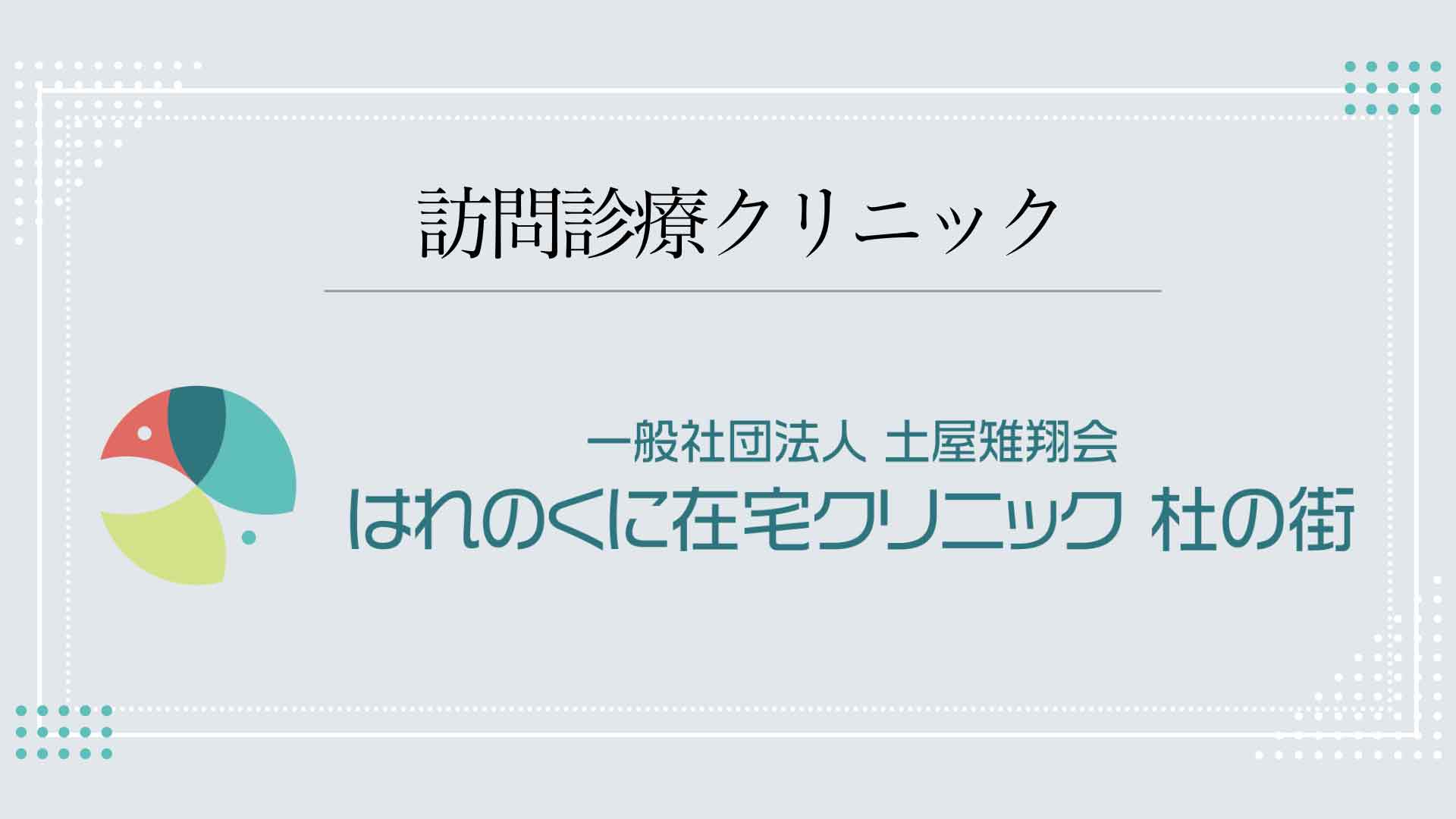土屋ブログ(介護・重度訪問介護・障害福祉サービス)
18 私の前史:貧しさと共に①
東京郊外の横田基地に隣接する小さな街で生まれた。父は長崎の漁師町出身で、母は西東京の魚屋を営む兼業農家の出だった。家は4畳半と6畳の部屋、風呂無しの古いアパートで、そこに両親と私と4歳下の弟の4人家族で住んでいた。部屋が狭くて布団は三枚しか敷けなかったので、弟は父と母と私の布団をたらいまわしにされていた。
歩いて10分くらいのところに銭湯があったので、父が仕事から帰ると毎日家族でお風呂屋さんに通っていた。当時はお風呂屋さんにいくとお客さんの中には必ず一人や二人背中に絵が描いてある人がいた。友達もみんな相対的貧困層だった。当時にしては珍しくシングルマザーの家庭もちらほら見受けられた。
父は生まれてすぐに家族が全員他界し、孤児となった。彼が生まれたころはまだ村の相互扶助機能が高く、父は年老いた祖母を中心とした親族の家々をたらいまわしにされながらコミュニティーに育てられた。児童養護施設は存在しなかったし、その必要もなかった。
短距離走者で県大会に出場したが、そのたびに「コメがもったいないから勝つな!」と言われたという。戦後間もない頃で、まだまだ貧しかった。不良少年だったようだが中学時代に勉学に目覚めて町の魚市場で働きながら定時制高校に通った。その後挫折し、高校を中退して上京した。
村に帰ることはなかった。漁師にはなりたくないという理由と、もう一つは、孤児の彼には安心できる居場所を故郷に発見できなかったようだ。リソースが限られた時代に、家族のいない彼のもとに食料や衣類が届くのはいつも最後だった。
「あまりもの」で生き延びた。どうしても腹が減ったときは、海に飛び込んで魚を銛でついて食べた。いつも空腹を抱えながら、優先順位で最後尾に置かれた。そんな故郷に帰りたいとは思わなかったようだ。
東京に来ると、そこは戦後の焼け野原から復興したとは言い難い状況だった。牛乳配達の仕事をしながらプロボクサーを目指した。日本チャンピオンを目指した。栄養失調もその要因の一つだったようだが、結核を患い、夢は潰えた。3年間の結核療養所での隔離生活を経て、地域に戻った。
なにもかもうまくいかず、家族のサポートもえられず、孤独と疎外に苛まれ、自暴自棄の生活に陥った。酒や暴力に依存し、一時は留置所生活も経験したようだ。
母は5人兄弟の長女で、幼少期から家業の魚屋を手伝った。少女時代は忙しい両親の代わりに小さな弟や妹の子育てをしつつ農作業に勤しんだ。勉強は好きだったようだが、学校は中学までで十分というのが当時の常識だった。高校には行っていない。戦中戦後の最も貧しい時代にお米を食べることができたということが彼女の誇りでもあった。
毎日泥にまみれて仕事をするなか、会社に就職した仲間が華やいだ姿で村に帰ってくる姿が羨ましかったようで、両親に懇願して会社勤めを許可された。が、就職した繊維会社で大きな事故に合い、20台のほとんどを病院で過ごした。
私が少年時代もたびたび体を壊し、病弱そのものだった。彼女が倒れると、母に育てられた彼女の妹たちが助けにきてくれた。私は主に母のマッサージをする係だった。
そんな貧困と病を生き延びた中卒の両親に私たちは育てられた。私の誕生とともに父は牛乳配達業から不動産業に転じた。立ち上げた会社が3年で倒産し、多額の負債を負うことになった。
当時はヤケ酒を煽ることが多く、普段は落ち着いた父が酒を飲むと異様な気配を纏った。自分の人生や境遇を呪う言葉を発し、そのことに怯え、かといって逃げ込む個室もなく、布団に隠れていた幼い頃の記憶がある。
トイレ以外独りになる場所が全く存在しない我が家で寂しさという感情を抱くことはほとんどなかった。小学校で「お前の家は風呂もない。貧乏人!」などと同級生から揶揄されるまでは、自分の家が相対的に貧しいという認識もなかった。
しかし、物心がつくとともに、友達が持っているものを自分だけ持っていないという事実に直面することが多くなり、親戚から夢を聞かれると「金持ちになってお風呂のついている家を建てたい!」と語ったことを覚えている。
同級生が持っていたおもちゃがどうしても欲しくて、ズボンの中に隠して盗んで帰ったこともある。塾に通っている仲間が、進研ゼミで学んでいる仲間が、ファミコンで遊ぶことができる仲間が、心底羨ましかった。嫉妬と羨望を深く感じた。
典型的なワーキングクラスの家族だった。同級生の友達と同じように、お風呂がついていて、自分の部屋がある、ふつうのミドルクラスの生活をしたいというのが子供時分のささやかな目標だった。
とても気の弱い少年だった。母からはたびたび「男の子でしょ!すぐ泣くんじゃないの!」と怒られた。体の弱い母は、気概だけで生きていた。気の弱い私が許せなかった。何とかして心の強い男の子に育てようと必死だった。
悪さをするとよくソロバンで顔面を殴打され、そのソロバンが砕け散った。痛くて泣くと、また殴られた。般若面のようだった。当然だが、当時それを虐待と名づけることは、私にも母にもできなかった。
よく友達に叩かれたり悪口を言われたりいじめられたりして、泣きながら家に帰った。すると「情けない、やり返すまで帰ってくるんじゃない!」と言われてドアを閉められた。助けを求めて帰ったのに、そのニーズが満たされることなく、エントランスがぴしゃりと閉められた瞬間の悲しみは、いまでも心の底に流れているように思う。
泣きながらやり返すために友達たちのいる場所に戻って手を振り回した。友達も泣いた。家に帰って、やり返した、と報告すると、やっとドアを開けてもらえた。家に入ることができた。
両親は病と貧困を強い心をもって生き延びてきた人たちだった。生き延びるためには心の強さが必要だという信念があった。その心の強さを、心の弱い私にも求めた。両親が期待する自分と、あるがままの自分にギャップがあることを、人生の比較的早い段階で自覚した。
そのギャップが心の歯ぎしりとなって、自分の人生に緊張を与えた。このギャップを埋めること、すなわち期待される自分に現実の自分を一致させていくことに労を費やした。弱い自分を脱して、強い自分にならなければならないと思った。この強い自分とは、男らしさと呼ばれた。
まずは涙を捨てなければならない。痛いとき、悲しいとき、辛いとき、泣くのではない、湧き上がる涙を殺し、それを怒りに転換し、その怒りを外に放出し、自分に痛みや悲しみを与えた他者を傷つけなければならない、それが男らしいということだ、そのような教えを受けた。
中学校に入学したころには涙を踏みにじり、抹殺することができた。私が受けた暴力を、こんどは周囲にリレーしていくことになった。涙を流す代わりに、拳を握った。涙を流す代わりに、自分の身体や誇りを傷つけた他者に暴力を振るうようになった。
虐待の連鎖のバリエーションといえるかもしれない。顔面がはれ上がり、拳もはれ上がった。はれ上がった拳や流された血にこそ誇りを感じた。通信簿についていた4や5の評価などは、自尊心を満たすにはささやかな効力しかなかった。他者を傷つけ、強さを表現することによって、はじめて幼いころに感じた心の歯ぎしりから解放された。
あるべき自分とあるがままの自分を一致させるために必死だった。他者の痛みに想像力を馳せるほどのゆとりがなかった。涙を抹殺すると同時に、想像力も枯渇した。いわゆる「男らしさの病」に完全に罹患してしまった。
数多くの人たちを傷つけ、私自身も中学校を卒業するころにはほとんど前歯を失ってしまった。同じような境遇を生きた仲間たちが、ぽつりぽつりと、いわゆる反社会的組織に飲み込まれていった。
自分も強さを表現できる仕事をしたいと思った。かつて父がそうであったように、ボクサーに憧れた。プロボクサーになりたいと思った。
◆プロフィール
高浜 敏之(たかはま としゆき)
株式会社土屋 代表取締役 兼CEO最高経営責任者
慶応義塾大学文学部哲学科卒 美学美術史学専攻。
大学卒業後、介護福祉社会運動の世界へ。自立障害者の介助者、障害者運動、ホームレス支援活動を経て、介護系ベンチャー企業の立ち上げに参加。デイサービスの管理者、事業統括、新規事業の企画立案、エリア開発などを経験。
2020年8月に株式会社土屋を起業。代表取締役CEOに就任。趣味はボクシング、文学、アート、海辺を散策。





















-1.png)