土屋ブログ(介護・重度訪問介護・障害福祉サービス)
18 私の前史 貧しさと共に③
2回目のキャンパスライフが始まった。落ち着いた生活を取り戻した。父の事業も安定し、平穏な環境で学業に専念できる日々を享受することができた。とてつもなく安全な感じがした。哲学や文学を学び、語り合う友人ができた。妻もその一人だった。
彼女たち/彼らは、私がそれまでの人生で全く出会うことのなかった言葉や思考様式や書物を知っていた。遅ればせの大学生で周囲にいる人はみな4~5歳年下だったが、心からリスペクトできた。彼女たち/彼らから多くのものを吸収したいと心から思った。
しかし、そんな落ち着いた生活を自ら崩していくかのように、アディクションが深まり、過量飲酒によってブラックアウトに到り、問題行動を起こしていった。
少年時代に暴力の中をサバイブしたが、ボクシングを経験することにより加害行為はなくなった。しかし、傷にアディクトするかのように、被害経験は繰り返された。心の中のトラウマは、落ち着いた平穏な時間が送られることを許すことはなかった。意識は平和な日々を愛したが、無意識の破壊衝動が日常を転覆していった。
不安定な情緒と足並みをそろえるように、生活そのものも、詩人アルチュール・ランボーが描いた「酔いどれ船」に乗るかのように落ち着きがなかった。
泥酔して集団暴行を受け、血だらけになって路上に倒れていたのを病院に搬送されたことがある。目を覚ました時、目の前にお医者さんと看護師さんがいた。
「生きているのが奇跡だと思ったほうがいい。何をやっているの?」
懇々とお説教を受けた。
フランスの文学哲学者であるジョルジュ・バタイユの「エロティシズムとは、死に至る生の称揚だ」という有名なフレーズがお気に入りだった。三島由紀夫や中上健二の作品に登場する人物たち、生の苛烈さの中で死にゆく者たちへの憧れがあった。「愚かさ」から逃れるすべを見出すことができなかった。
傷は死に向かう緩慢な流れを作り出した。いま思えば、青臭い思春期病からの卒業が遅れたかのようにも思える。ありふれた日常を生きるということへの希望を発見することができなかった。薄っすらとした希死念慮が通奏低音のように気分の地下水脈を流れていたようにも思える。
ある日、父が悪性リンパ腫を罹患したことが分かった。全身に転移していた。立ち上げたばかりの会社が倒産した。安定した生活は束の間の出来事だった。
病気がちで長年専業主婦だった母が還暦を過ぎてパートの仕事を始めた。弟が夜間大学に通いながらアルバイトをして家計を支えた。独り暮らしをしていた私も大学を休学し、実家を経済的にサポートするつもりで営業の仕事などについたが、アディクションが深まり十分な戦力にはなれなかった。
またしても貧困に回帰していった。静かに学業に専念するという夢は潰えた。混乱した日々が再開した。
しかし、なんとか今回の大学は卒業したかった。新聞奨学生として働き始めた。新聞専売所の寮で暮らし、朝刊と夕刊を配りながら、その合間を大学に通ったりアルバイトをしたりして過ごした。
慶應義塾大学三田キャンパスの近くの朝日新聞の専売所に2年間在籍した。専売所には慶応義塾に在籍する人は私しかいなかった。いろんなバックグラウンドを持つ仲間たちがいた。借金を抱える人、司法試験浪人、ミュージシャン、ボクサー、学生、外国人、などなど、様々な人たちと共に働き、共に過ごした。
雨の日も、風の日も、雪の日も、台風の日も、変わらず、毎日毎日新聞を配った。芝浦のオフィスビルの谷間を駆け回った。日の出ふ頭で落日を眺めながら一服するのが楽しみだった。
様々なバックグラウンドを持つ仲間たちと時に飲み、語り合った。飲みすぎて、朝刊配達の時間に寝坊し、所長さんたちにご迷惑をかけることもしばしばあった。諍いもあった。新聞専売所の寮の壁はあちこちに穴が開いていた。時には殴り合いの仲裁に入ることもあった。
みんな貧しかった。貧しさの中で、それぞれが希望や目標を持っていた。希望や目標を持たず、ただ生きる、という佇まいの人もいた。とにかくいろんな人たちがいて、バックグラウンドや趣味や性格や価値観が全く異なる人たちが一つ屋根の下で生き、働き、争い、存在していた。
あの新聞専売所での日々は、他者と共に生きるとは、他者を歓待するとは、どういうことなのか、について深く考えさせられる時間だった。いま思えば、障害福祉のお仕事をさせていただく心の準備があそこできたかもしれない。
ある日、朝刊を配る準備をするため、自室から作業場に降りて行った。作業場には誰もいない。様子がおかしい。事務室から叫び声が聞こえてくる。そちらに足を運んでみた。仲間たちがみんなテレビモニターにくぎ付けになっている。私も覗き込んでみた。
飛行機がビルに突入していく様子が映し出されていた。映画の一場面かと思えた。現実とは思えなかった。みんな戸惑っていた。2001年9月11日に起きたアメリカ同時多発テロ事件が報道されていた。イスラム過激派テロリスト集団アルカイダによる犯行だった。
アルカイダの指導者であるオサマ・ビン・ラディンが犯行声明を語っていた。異様な印象を受けた。その事件を目にしたアラブ諸国の国民の熱狂する姿にも驚いた。約3000人の命が失われた。たいへんな事件が起きてしまった、そう思った。
その後、アメリカをはじめとした先進国では熱狂的なナショナリズムが立ち上がり、復讐の炎に包まれた。アルカイダを支援するタリバン政権が支配するアフガニスタンを多国籍軍が攻撃する反テロ戦争へと突入していく。テロで亡くなった命の数をはるかにしのぐ数の命が失われていった。
毎朝毎夕配る新聞を眺めながら、世界がたいへんな時代に突入していっていることを知った。
2002年の元旦も夕刊を配っていた。新聞配達夫にはお盆も正月もなかった。一面に、あるメッセージが掲載されていた。気になったので、立ち止まって読んでみた。
「好ましいグローバリゼーション?それはハリウッド的な大音量のスピーカーによる支配ではなく、世界の小さな声にお互いに耳を傾けあえることでしょう」
韓国の映画監督イ・チャンドンの言葉が、朝日新聞の夕刊で紹介されていた。とても気に入った。夕刊を配り終え寮に戻ると一部を部屋に持ち帰り、そのメッセージの部分を切り取って財布に入れた。
私たちは新聞専売所で語り合い、耳を傾けあった。しかし、世界には、その小さな声を聞き届けられることなく、悲嘆に暮れ絶望している人たちがいる。テロとはそんな絶望した人たちの最後の表現手段だ。
そんな絶望の叫びを多国籍軍がモグラ叩きのように一つ一つ潰していき、新しい絶望を生み出す。止むことのない復讐の無限連鎖が始まり、世界はテロと戦争の時代へと突入する。犠牲になるのは兵士だけではない。子供やお年寄りや女性たちが命を失う情景が、毎日のように新聞で、テレビで、報じられた。
どうしたらこの負のスパイラルを止めることができるのか?当時を生きた誰しもがそんな思いに駆られた。
小さな声に耳を傾けあう。
誰にも聞き届けられることのない小さな声、貧しい人、差別される人、抑圧される人、無視される人、病に苦しむ人、そんな人たちの小さな声に真摯に向き合うこと、それこそがテロと戦争の時代に終止符を打つ、遠回りのようで実は最短距離の道、そう思った。
「福祉の仕事をしてみようかな。」新聞専売所の仲間に相談してみた。
「意外とあっているかもしれないね。いいと思うよ。」私の話に耳を傾けてくれた人がそう言ってくれた。
新聞配達をしながら、無事大学を卒業することができた。卒業後は、いままで全く興味のなかった福祉の仕事をすることに決めた。貧しい人、差別される人、抑圧される人、無視される人、病に苦しむ人、そんな人たちの「小さな声」に耳を傾けるお仕事をしたい、そう思った。
それは、孤児として貧しさを生き延びた父に、原因不明の病で若かりし日のほとんどを病院で過ごした母に、差別と貧困に絶望しテロ組織に吸収されていった若者たちに、恵まれない環境に生まれやがて反社会的組織に飲み込まれていった幼い頃の仲間たちに、そして精神的にも身体的にも傷だらけになってしまい、そんな傷の痛みをごまかすためにアディクトにならざるをえなかった自分自身に、出会う航路でもあった。
大学を卒業してまもなく、自立生活をする障害者の介助のお仕事と出会った。障害者の権利を回復する公的介護保障運動と出会った。
◆プロフィール
高浜 敏之(たかはま としゆき)
株式会社土屋 代表取締役 兼CEO最高経営責任者
慶応義塾大学文学部哲学科卒 美学美術史学専攻。
大学卒業後、介護福祉社会運動の世界へ。自立障害者の介助者、障害者運動、ホームレス支援活動を経て、介護系ベンチャー企業の立ち上げに参加。デイサービスの管理者、事業統括、新規事業の企画立案、エリア開発などを経験。
2020年8月に株式会社土屋を起業。代表取締役CEOに就任。趣味はボクシング、文学、アート、海辺を散策。













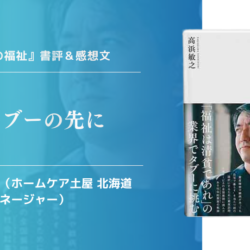

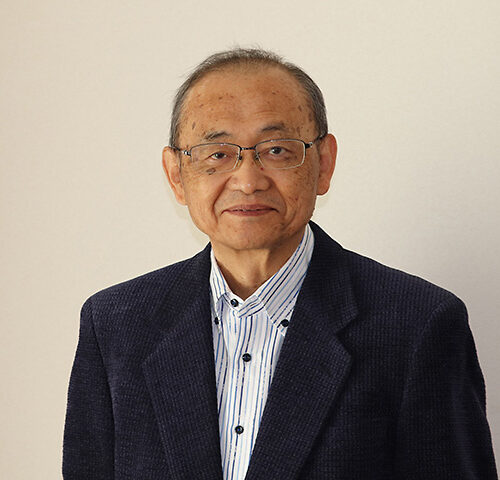




-1.png)




















