土屋ブログ(介護・重度訪問介護・障害福祉サービス)
ピクニック
ピクニック。大概の人はこの言葉を聞くと、爽やかな自然の中で戯れ、走り回る子供たちや草地の上にシートを広げ食べる美味しいお弁当、人によってはバーベキュー、酒盛りを思い浮かべるだろう。ともかく楽しいイメージの言葉だ。
しかし、そんな爽やかで幸せそうな連想は、あのモスクワ郊外にあった障害児収容施設に入っていた子供たちにとっては全く縁のないものだった。ピクニックという言葉はロシア語にもある。辞書では、第一義はもちろん日本語と同じで、自然の中で遊んだり、食事を楽しんだりすることなのだが、この言葉の項目の最後の方に載っている意味は『強盗犯や窃盗犯が使う「ひと仕事」』 となっている。
入所児にとってピクニックとは、施設建物を取り囲むようにあった森に入って行き、食べられるものを片っ端から採取することだった。どんぐりや野生のクルミ、日本語でスカンボ(ガッポン)と言われる酸っぱい草、キノコ類、ラズベリーや木いちご等の木の実、野生のリンゴ、白樺の皮や樹液、果てはロシア独特の茶色い蟻、蛙、野ネズミ、リス、野バト、大きいところでは野兎、ともかく食べられるものは全て採取し、皆で分けあって食べた。
このピクニックに参加するには一定の基準を満たさなければならなかった。それは第一に、這ってでも転がってでも良いから自分で動けること。第二に、採取場所を他の者に漏らさない口の堅さを持っていること。そして第三に、ピクニック隊と呼ばれていたグループ内の序列と秩序を守ることだった。
グループの構成は、上は15歳から下は8歳までの男子5~6人。隊長と副長には、上半身に障害がなく力が強い子がなるのが決まり。初めてピクニックに誘われた時、私は最年少の8歳。割と素早く這って移動ができたことと、身体が小さく軽かったことが選ばれた理由だった。ピクニック隊に入れることは、入所児の間では非常に名誉なことで、あの嬉しい気持ちを今でもはっきりと憶えている。それに、空腹の時間を減らせることが何よりも幸せなことに思えた。
私達入所児にとってこのピクニックはまさに仕事だった。絶対にしなければいけない仕事。以前にも書いたが、施設で出されていた食事は、質的にも量的にもこれ以上酷いものはなく、大地が雪に覆われない、この5月から10月の初めまでの期間にできたピクニックという一大イベントは、常に腹を空かしていた私たちにとっては絶対不可欠なものだったのだ。
季節によっては、特に6月ごろ、このピクニックは、森を抜けたところにあった広大なコルホーズ(旧ソ連の協同組合式集団農場)のジャガイモ畑から芋を盗み取るという大仕事にもなった。森を抜けるのには大体1時間ぐらいかかった。今から考えてみれば、グループ全員が這うか、あるいは足を引きずって移動するのだから、その速度は2km以下だっただろう。それでも1時間程度で抜けられたのだから、あの森は実際の所あまり大きくなかったのかもしれない。それでも私たちにとっては大冒険だった。
畑につくとそこには高さ1mぐらいの木の板を打ち付けただけの柵があり、そこを乗り越えるのが私の役目。力の強い隊長と副長がいとも簡単に、体が小さく軽い私を持ち上げて柵を乗り越えさせてくれた。この先頭を切って行くということが名誉で、勇気があって誇らしいとされていた。そしてほかの子たちは私が安全を確認するや否や柵の一部を壊して畑に入り込むのだった。
そこからが勝負だ。見回りの農夫たちが来るまでに、ろくな手入れもされず作られる小ぶりの芋を、持てる限り掘り出さなければならないのだ。先ずは柵の近くから、徐々に奥へと進むのだが奥へ行けば行くほど見つかった時の恐怖が大きくなる。見回り農夫たちは必ず散弾銃を持っていたからだ。
彼らからしてみれば私たちは子供であってもただの泥棒だ。しかも当時のロシアの一般的な見方では、どうせ障害児なのだから人間の内に入らない、というのもあり、遠慮容赦なく私たちに向けてその銃を撃って来た。幸いだったのはその銃の威力が弱かったことだ。
ところで、ピクニック隊の隊長と副長だけではなく、12歳を過ぎたくらいの男子はほぼ全員ナイフを持っていた。ナイフと言っても日本で言うところの切り出しナイフ程度の大きさのもの。鉄製のベッドのつなぎのプレートを取って削って作る、お手製が主流だった。施設全体にはごく稀に、折り畳み式ナイフを持っている年長男子もいて、皆の羨望の的となっていた。
そのナイフで器用に小動物をとらえる罠を作り、掛かった獲物をさばき、肉にし、焼いてガツガツと食らう。至福の時だった。骨の髄まで吸い取って食べた。これを読む人は、テレビのサバイバル番組を思い出すだろうが、私達は必死にそれをやっていた。私の思い出の中で、初めて捕ったウサギの肉の味は今でも忘れられないくらい最高に旨かった。因みに、コンロも鍋も年長者の手作りだった。
そのコンロの着火用燃料は薬用アルコールが使われていた。薬用アルコールが収納されていた棚の錠前は常に開いていたので年上の子が持ってくるのだ。鍵が開いているのには深い訳があった。病院や施設関係者は特権として薬用アルコールを手に入れることができたのだが、ワインやウォッカ、コニャックなどの人気酒類が欠乏していた当時、そのアルコールを薄めて飲んでいたのだ。
ところが在庫調査は役人が来て行われるので、鍵がかかった棚からアルコ―ル残量が減っていると職員による盗み飲みがばれる。そこでわざと鍵を開けて置けば、誰がいつ盗んだか分からなくなり、誰も責任を問われなくなる。そういうコントのような現実が当時のあの国にはあったのだ。それで通るのが不思議だと思われるかもしれないが、悪く言えばいいかげん、良く言えば大らかな、ロシア人をよく知っている私としては十分に納得できる話なのだ。
◆プロフィール
古本 聡(こもと さとし)
1957年生まれ
脳性麻痺による四肢障害。車いすユーザー。 旧ソ連で約10年間生活。内幼少期5年間を現地の障害児収容施設で過ごす。
早稲田大学商学部卒。
18~24歳の間、障害者運動に加わり、障害者自立生活のサポート役としてボランティア、 介助者の勧誘・コーディネートを行う。大学卒業後、翻訳会社を設立、2019年まで運営。
2016年より介護従事者向け講座、学習会・研修会等の講師、コラム執筆を主に担当。














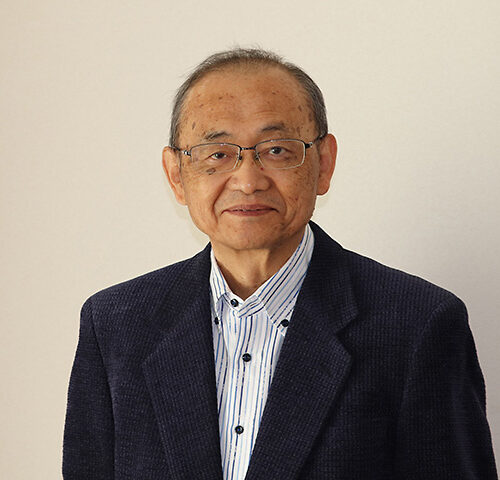




-1.png)




















