土屋ブログ(介護・重度訪問介護・障害福祉サービス)
初めての夜
頭の中で「バチッ」という音がして急に目が覚めた。強烈な違和感と重い気怠さの中、我に返った、という感じだった。おそるおそる目を開いていくと、目の焦点が合い始め、私が最初に認識したのは、やけに遠いところ、いや正確に言えば随分高いところにある真っ白で広い平面だ。
それは天井だった。その周囲は真っ黒な闇に包まれていて、自分が一体全体何処にいるのか、どんな位置に置かれているのか。把握するのに相当な時間が掛かった。
その暗闇の中で、何処からか微かな風の音と、ピタンッ、ピタンッという、何か柔らかいものが固いものに当たって崩れていくような音がしていた。
意識がはっきりしてくるのと同時に、目も大分暗がりに慣れて周囲の様子が分かってきた。私はベッドに寝かされていたのだ。寝たままゆっくりと頭を動かして辺りを見回してみた。がらんとした大きく広い空間で、そこはまるで、1か月半前、モスクワに到着する直前にコペンハーゲンで1泊した、19世紀半ばに建てられた古びたホテルの玄関ホールのようだった。
ベッドの左側は壁、そして顔を右に向けてみると、10メートルくらい先に大きな窓が3つ連なって並んでいた。カーテンも何もなく。しばらくして、まだ身体に力があまり入らなかったが、何とかゆっくりとベッドの上で起き上がることができた。その時、泣き叫び過ぎたせいか、はたまた注射のせいだったのだろうか、頭の芯がキーンと痛かったのを今でも思い出す。
起き上がった私は、何故だかもう一度窓の方を見た。驚いたのはその窓の高さだった。下辺は概ねベッドの高さと同じなのが見て取れたが、天辺は天井のすぐ近くまで届いていたのだ。そして、どの窓の外を見ても、漆黒のビロードのような闇があるだけだった。次に視線を下に向けた。暗い中でも、窓が縦横の枠木の影を落としていた床は、全面に10センチ角のベージュ色のタイルが敷き詰められていたのだが、所々タイルが割れたり欠けたりでギザギザの断面がむき出しになっていて、見るからに酷く痛そうだった。
後になって知ったことだが、あの障害児収容施設の建物は、1829年に当時の貴族の屋敷として建設された、とのこと。1890年にモスクワ州に売り渡され孤児院になり、その後、不治病者療養所に転用。1904年~1955年の期間は日露戦争、第1次世界大戦、革命後のロシア内戦、スペイン内戦出兵、第2次世界大戦で負傷した帝政ロシア軍・ソ連赤軍将兵の治療院兼保養所として使われ、1950年代末頃から肢体不自由児収容施設となったそうだ。
建てられてから私が入所するまでの約130年間、そしてそれから1991年のソ連崩壊までの歳月に、あの建物はどれほど多くの人生ドラマを、そして人の生き死にを見てきたのだろうか。
天井から長さ5メートルほどもある鎖に吊り下げられ、すっかり錆だらけの骨組だけになっていた大きなシャンデリアらしき物体が印象的だった、吹き抜けのフォイアから2階へと続く幅の広い螺旋階段を、いったいどれくらいの傷ついた人々が上り下りしたのだろうか。ある者は松葉杖をつき、またある者は這いずりながら。
玄関を入ってすぐ左横にあった談話室の、金箔が殆ど剥がれ落ち、表生地が擦り切れていた猫足式長椅子やカウチに、どんな人物が腰を下ろして、どんな想いに浸ったのだろうか。
それを考えると、60歳を過ぎた今、幼少期の5年足らずとは言え、自分があの国の正に激動の歴史に触れながら生きていたのだ、と実に感慨深い思いに打たれる。
横行100~120メートル、奥行35~40メートル、高さ25メートル超の、半地下階を含め4階建て(2、3階の床から天井までの高さは、少なくとも5mはあった)のこの元貴族の屋敷は、かなり頑丈に建てられ、そして細部にわたり丁寧に造り込まれていた。ただ、社会主義時代に、特に第2次大戦以後に施された補修や増築は、子供の目にもどうしようもなく仕事が雑で、醜悪なものに映った。
しばらくの間、下を向いたままボーっと床を眺めていたが、突然、その日の朝からあったことが全て脳裡に蘇ってきた。
最後に見た時に両親が浮かべていた愛想笑い、毛布でぐるぐる巻きにされ運ばれていった時の困惑、混乱、狼狽、そして苦しさ、入浴室で受けた屈辱的な扱いを思い出したのだ。それと同時に、気が付いたら眠らされていた自分への不甲斐なさの他に、「なんで、ぼくだけが、こんなところに置いて行かれたのか」という理不尽への悔しさ、怒りが頂点に達した。私の心に強烈な悲しみ、寂しさ、心細さ、恐怖、恥ずかしさ、悔しさが一気に押し寄せてきた、という感じだった。
すると、ついに我慢できなくなった。そして目からは涙が止め処なく溢れだし、それまで自分自身でも聞いたこともなかった、ゥヴォー・ゥヴォーという、大人の男のように野太く、とてつもなく大きな声が勝手に喉の奥の方から響き始めて止まらなくなった。それに加え、ベッドの鉄柵を力一杯ガタガタと揺さぶった。当時の私の力は弱かったかもしれないが、それにしてもかなりの騒音だったことは間違いないだろう。それらの音がだだっ広い空間に轟き渡っていた。
>赤國幼年記6につづく
◆プロフィール
古本聡(こもとさとし)
1957年生まれ。
脳性麻痺による四肢障害。車いすユーザー。 旧ソ連で約10年間生活。内幼少期5年間を現地の障害児収容施設で過ごす。
早稲田大学商学部卒。
18~24歳の間、障害者運動に加わり、障害者自立生活のサポート役としてボランティア、 介助者の勧誘・コーディネートを行う。大学卒業後、翻訳会社を設立、2019年まで運営。
2016年より介護従事者向け講座、学習会・研修会等の講師、コラム執筆を主に担当。















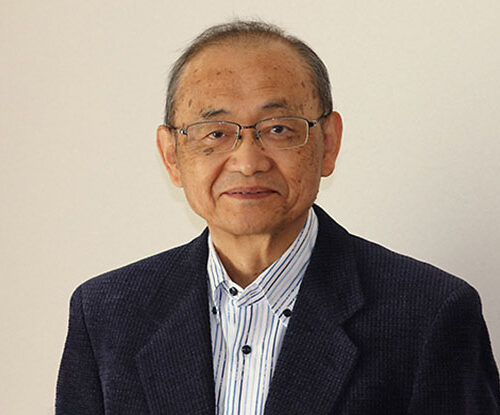




-1.png)




















