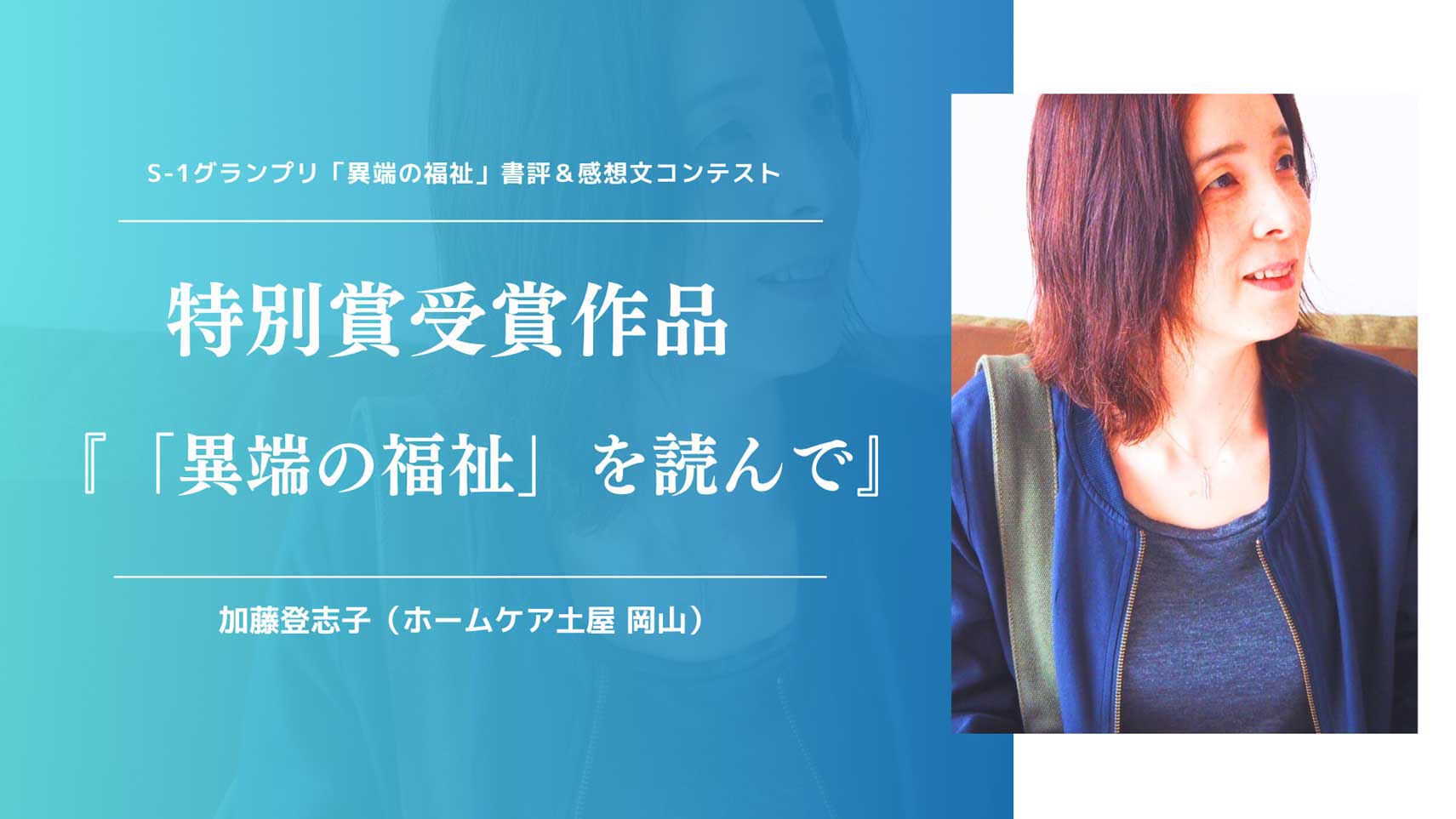
『異端の福祉』を読んで / 加藤登志子(ホームケア土屋 岡山)
福祉、介護をビジネスにすると言い切った人がこれまでにいただろうか。介護と言えばボランティア、善意、薄給といったイメージが付きものだ。しかも重度訪問介護なんて大変そうに聞こえる。それをビジネスに繋げようと公言した人がいただろうか。
どこか怪しいにおいがする。うさんくささが漂う。そんな疑いの気持ちはこの本を手に取り、読み進めていくにつれて晴れていく。読み終えると、澄んだ晴天の下で爽やかな風が吹き、誇らしげな気持ちに包まれていく自分に出逢う。そんな本だ。
私が高浜代表に出会ったのは4年前だ。難病のALSだった母を見送った1年後だった。母の介護のため、実家に戻って母と過ごした2年間は色濃く、愛おしい時間となった。ただ、2年の間、睡眠不足とALSが投げかけてくる難題に私の体は悲鳴をあげていた。
重度訪問という制度がありながら、まだまだ地域格差もあり、使える制度にはなっていないのを目の当たりにした。そんな私は母を見送ってからは、同じようなつらさを抱えている当人と家族の力になりたい、障害者支援のサポートができないかと、ボランティアや仕事を探した。
家族にゆっくり寝てほしいという気持ちから夜勤の仕事を探した。だが、探しても探しても見つからなかった。探し始めて1年後、やっと出会ったのが著書にも記してある介護系ベンチャー企業の重度訪問介護事業所だった。
私は、怪しい事業所ではないか?大丈夫か?といった不安の中、まずは研修会場に向かった。その時に高浜代表に初めて出会う。講義が始まり、30分でその不安は興奮に変わっていた。
障害者福祉のこれまでを、こんなに正確に静かに熱く語れる人に出会ったことはない。20年以上、介護を仕事としてきた私だが、この時の興奮は今も忘れない。2020年8月に高浜代表が岡山の地で重度訪問介護事業の会社を設立した際に、信じて付いていく決断をしたのは言うまでもない。
重度障害者はこれまで施設や病院で暮らすことが当たり前とされてきた時代を経て、やっと家で暮らせるようになっても、家族が看るのが当たり前、制度をしっかり使って自立したいと思うのはわがままではないかと捉える考えが根強くある。世の中もまだまだそうで、家族であった私もまたそうだった。
私が休みの日はリハビリと看護のスタッフが2時間半ほど来てくれていた。その間、私はスーパーで食料の買い出しをして、駐車場に停めた車の中でおにぎりを頬張り、30分熟睡するのが心身を休める最高の時間だった。
ヘルパーさんで埋めてくれた平日に有給休暇を取り、カフェで珈琲を飲んだときは、なんとも言えない罪悪感にさいなまれた。体が動かなくなり辛い思いをしている母を思うと、母が待つ家に帰る足どりも重く、悪いことをした気持ちになったものだ。
福祉、介護をビジネスにする真意を、この本を手に取り読んで知っていただきたい。福祉の精神と情熱だけでは近い将来、息切れしてしまう。いや、してしまっているかもしれない。
すべての人がその人らしい暮らしを実現するという、疑いようのないニーズに応え続けようと歩み続ける1人の人間と仲間の歴史、そして福祉の歴史を知ってほしい。
そして私も歩み続けようと思う。
















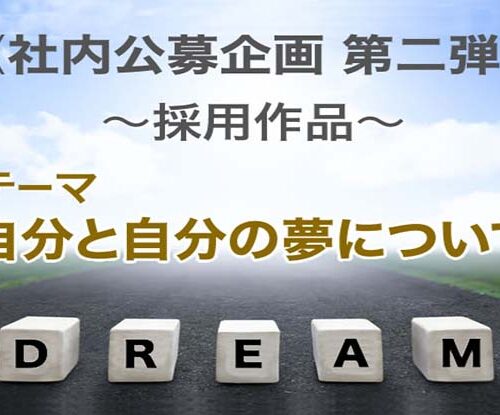


-1.png)




















