
福祉の異端者が打つ次なる一手 / 山根 健(有限会社のがわ)
オメラスを知っているだろうか?
アーシュラ・K・ル・グィンの書いた小説に出てくる、とある理想郷のことだ。オメラスは自然に恵まれ、独裁者もいなければ、身分制度もなく、飢餓も戦争もない。ところが、その街のどこかに、固く閉ざされた地下室があった。その地下室には、一人の子どもが、ずっと鎖につながれ、閉じ込められている。
実は、その子の存在を、オメラスの『住人』たちは全員知っていた。だが、誰も助けようとしなかった。オメラスという理想郷が保たれる条件が、その子を閉じ込めておくということを皆が知っていたからだ。たった一人の子どもを地下室に閉じ込めておくことで、他の全ての人々が幸せに暮らせるならと、『住人』たちは、見て見ぬふりをしているのだ。
今回の書評では、この子どもは障害者を示すと考え、私たち『住人』は一体、何を感じるのかを考えたい。
この本「異端の福祉」は、今年1月に、全国47都道府県に重度障害者を24時間在宅支援する重度訪問事業所「ホームケア土屋」(株式会社土屋)の現 代表取締役兼CEOの高浜敏之氏が、世間に広く重度訪問を知ってもらい、現状ある課題を解決するため、多くの人の理解と協力を得たいという思いから綴ったものである。
本章は5章で構成されている。
第1章、第2章では、著者の重度障害者の介護の出会いと障害福祉の歴史的歩み、日本に根強い、介護は家族がするものという重圧と重度障害者自身の自分の家族には介護をさせたくないという葛藤、重度障害者の受け皿と働き手不足について書かれている。
第3章では、著者の重度訪問介護事業の立ち上げ、土屋が解決しようとしている社会課題。シンクタンク部門「土屋総研」により見えてきた更なる実態と課題。さらには、3名のクライアントの重度訪問介護を利用した実生活での声が書かれている。
続く第4章では、土屋の追求するビジネスモデルと、6名の社員(異業種から未経験で重度訪問介護の世界に飛び込んできた社員も)の重度訪問、土屋にかける思いが書かれている。
そして、最終章第5章では、会社を成長させることが社会課題を解決すると信じて進む現在の姿が書かれている。
では、私が疑問に思うことである。
著者は、誰が悪いと責任追及するのではなく、社会全体で議論を深め、課題解決していくことが大事であると述べている。しかし、これは、なかなか難しいのではないかと思う。
誰が悪いかはっきりさせ、責任追及を求めているわけではない。社会全体での議論という点だ。社会全体での議論の前段階、もしくは全く違う何かが必要ではないだろうか。
私は、社会の重度障害者についての理解は、まだまだ少なく、偏見も多いと感じている。偏見とまで言わずとも、実際、目の前にすると、何をしていいのか分からない、声をかけたらかえって迷惑になるのではと思い、声をかけることが出来ないということもあるだろう。
以前、友人と話している時、ALSについて知らないと言っていたことに、驚いた記憶がある。しかし、かく言う私も高齢者介護とは言え、同じ介護業界にいたにも関わらず、大した知識はなかった。
さらに、家族に障害者がいる方と話をした際、こんなことを言っていた。
「よく、障害を持っている人が家族なんて大変でしょうと言われる」と。中には、「可哀そう」とまで。だけど、「私たちは、不幸でも何でもないです。幸せだって感じています。」と。
これには、そこにいた他の、家族に障害をもった方がいる方も、共感していた。
また、障害を持つ当事者の方からは、こんな話を聞いた。
ヘルパーさんに同行して外出した際、立ち寄った店で、「私(障害を持つ当事者の方)に話をするのでなく、ヘルパーさんに何でも聞いて、話をするんです。私だって、ここにいるのに、私に聞いて欲しかった。」と。
つまり、介護業界にいる人も理解できていない、また、障害を持つ方を家族とする方、障害を持つ当事者の方の話からは、社会は、世間は障害について、まだまだよく分かっていない、知られていないことが分かる。
これは、直接的ではないにせよ、偏見につながっている可能性があると感じる。議論をするには、社会があまりに知らないことが多く、積極的関心が低いのだ。
ソクラテスはこんなことを言っている。
「無知は罪なり、知は空虚なり、英知を持つもの英雄なり」
「知」とは知識や情報のこと、「無知」とはあることについての知識や情報を知らないこと、「空虚」とは、知っているだけでは、何の役にも立たないこと。そして「英知」だが、これは、いろいろ見解はあるだろうが、「知を活かした経験」だと私は考える。
つまりである。現在、重度訪問介護事業を展開している土屋は、知識も情報も経験も有している。さらに、その事業所は、全国47都道府県に進出を果たし、今も空白地域をゼロにすべく活動を継続しており、更なる英知の獲得が期待出来るのだ。
冒頭のオメラスの話では、理想郷が保たれる条件が、子どもを閉じこめておくことであるが、当然、この世の中にそんな条件は存在しない。また、このオメラスの話には、理想郷であるオメラスの存在の条件である犠牲者の存在を知り、さらに助けることが出来ないと知った時、私たち『住人』は、何をするのかという倫理的問いがある。
私の答えは「何もできない」だろう。たとえ出来たとして、声もかけられず、無言で立ち去るが精一杯であろう。
だが、土屋は、オメラスの子どもを助けること、もしくは、助けるすべを考え出す、次なる一手を見出しているかもしれない。本著では書かれていない何かがあるはずである。そんなことを感じさせる一冊である。














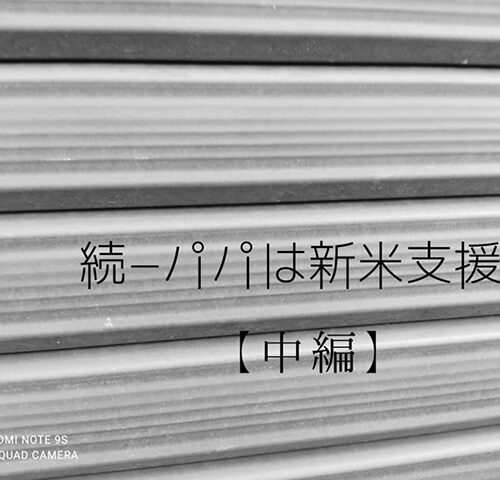

-1.png)















