土屋ブログ(介護・重度訪問介護・障害福祉サービス)
レポートを書き終えた虎吉は涼しい職員室の奥の席に座ったまま、しばらくぼんやりしていた。
するとそこに新人の湯山香苗が入ってきた。
香苗は静かに畑山主任のところに行き「お疲れ様です」と声をかけた。畑山はパソコンから目を離さないまま、ちょっと待っててと言った。
香苗は一歩下がって、少し斜め上を見て待っていた。
開け放たれた窓から入ってくる風に香苗の細い髪が揺れていた。
その様子を虎吉は奥の席から見ていた。
後ろめたいものは何もないのだが、少し身をかがめるようにしてノートパソコンのモニターに隠れて、時々香苗の様子をちらちらと眺めた。
今年新卒で入ったばかりの香苗は虎吉とは違うフロアにある活動室に配属された。同じ施設で働いているが、フロアが違うのであまり接点がなく、ほとんど話をしたことがなかった。
歳の差を考えれば娘であっても(ぎりぎり)おかしくはない年齢だ。例え話す機会があってもどんな話をしていいのかさっぱり分からない。
香苗はぼんやりと職員室を見回して、奥にいる虎吉と目が合った。二人とも気まずい感じになって目を背けた。
虎吉は身を低くして仕事をしているふりを続けた。
「湯山さん、座って」
畑山が言った。
「働きはじめて3ヶ月、仕事はどうですか?」
「えぇ………」香苗は心弱くうなずく。
仕事がうまくいっていないという話を聞いたわけではなかった。仕事で悩んでいるという話を聞いたわけでもなかった。
ただし、仕事がうまくいっているという話も聞いたことがなかったし、仕事で悩んではいないという話も聞いたことがなかった。
要するに何を考えて何を思っているのかよく分からなかった。
業務中に何か辛そうな表情をしていることがあったそうで、グループのリーダーが後で確認したら「辛いことはない」「仕事を覚えるのに一生懸命だ」と言っていた。
逆に平気な顔で過ごしているのかと思っていると「支援のことで不明な点があった」とか「疑問に思っていたことがあったけど言い出せなかった」とか「自分の意見なんて恥ずかしいものだから言えない」とか、そんなことを考えていたのだということがずっとずっと後になって風のうわさで漏れ伝わってくる。
本人から直接聞いたわけではない。
どこからともなく伝わってくるのである。
そこで確かめようとして本人を呼び出して質問してもよく分からない。
ガードを固めながら、うやむやにする濃い霧でも放っているかのように煙に巻かれて香苗の考えていることが誰にも分からないのであった。
仕事は優秀にこなす。
指示したことはすぐに飲み込み、期日までに確実に終わらせる。その正確さは他の職員よりも優れているのかもしれない。
まだ3ヶ月目なので仕事は限られているが、これからもっと経験を積めば正確さとスピード感が必要な仕事は信頼して任せられるようになるだろう。
ところがその仕事に対してどう思っているのかということを聞いた途端、答えが返ってこなくなる。
また、対人支援においてそのとき相手がどう思っていたと感じましたか?という質問にも動きが止まってしまう。
なので支援ができないかというとそうでもない。いつも心弱く微笑んでいる香苗の周りには不思議とご利用者たちが集まって来るのである。
全く捉えどころがない。
畑山は悩んでいた。
香苗にアドバイスをしようとしている自分が何か間違っているのかもしれないと思うこともあるほどだ。
時代が変わったんだ、と時代のせいにすることも。
スマホのせいだとか、ユーチューブのせいだとか、何か悪者を探してこの不安から逃れたいような気にもなってくる。
そこでとにかく研修に参加してもらおうということになった。
「アサーティブって知ってますか?」
「知りません」
「アサーティブっていうのは簡単に言うと思っていることを他人に上手に伝えるための技術のことです」
そう言って畑山は研修のチラシを香苗の目の前に差し出した。そしてそこに書かれていた研修概要を読み上げた。
『自分の気持ちを率直に伝えたり、自分の考えをきちんと伝えることはなかなか難しいですよね。
また言いすぎてしまった、もっとはっきりものが言えたらいいのに、上手に断れるようになりたい、攻撃的な言い方をやめたい、自信をもって人と接することができるようになりたい…。
でも、どうやったらそんなふうにコミュニケーションすることができるのでしょうか。
その道しるべとなってくれるのが「アサーティブ(自己主張)」です。
でも、アサーティブであることは、自分の意見を押し通すことではありません。
自分の気持ちや意見を、相手の気持ちも尊重しながら、誠実に、率直に、そして対等に表現することを意味します。』
「どうですか?受けてみませんか?」
「分かりました」
と、香苗は答えた。
そして静かに畑山の目の奥を見つめた。
無言の時間が流れた。
職員室の奥には心配そうな目で二人を見守る虎吉の姿があった。
香苗は畑山の目の奥をじっと見ていた。
数分にも感じられた無言の時間に耐えきれなくなったところに、ちょうど天の助けか内線電話が入った。畑山は電話が終わると、事務局からの呼び出しだと言って席を立った。
「湯山さん、申込みはするから研修の予定だけ入れといてね」と言って職員室から出て行った。
香苗は研修のチラシに目を落とした。
虎吉が座っている奥からでも横顔は見えるのだが、その表情が表しているものはよく分からない。
見ようによっては悲しいような、つまらないような、でもリラックスしているようにも見える。Tシャツから伸びた白くて細い腕は脱力しているようだったが、手はきれいに膝の上で揃えられていた。かしこまっているようでもある。
「変なやつだぜ」
と、虎吉は思った。
20歳そこそこなのに若者っぽくない。
かと言って老成しているわけでもない。
自分と比べてみると不思議な存在としか言えない。
虎吉はこの知的障害者支援の仕事をしてから自分を振り返ってみることが多くなった。
何故だろう?
これまでも深夜のコンビニでアルバイトをしていて年下の人間と付き合うことはあった。
しかし自分を振り返ろうとは思わなかった。
この仕事をはじめて、ここにいる変わった奴らと付き合ったり、この仕事に携わる人々と関わるようになってから何故だか過去を振り返ってしまう。
自分が香苗と同じ年齢のときやっていたことは何だろう?
高田馬場の路上で眠ったり、郵便局の職員専用の浴場を無断で使って怒られたり、ボーリング場の店員と喧嘩したり、自転車を庭に投げ込んで迷惑をかけたり、決して自慢できることではないけれど何かに衝き動かされるように無駄に暴れてしまっていた。
「香苗さんも暴れたくなることないの?」
という質問が口から出そうになったが一回飲み込んだ。
静かに座っている香苗には何か聞きたくなってくる。
【後編】につづく












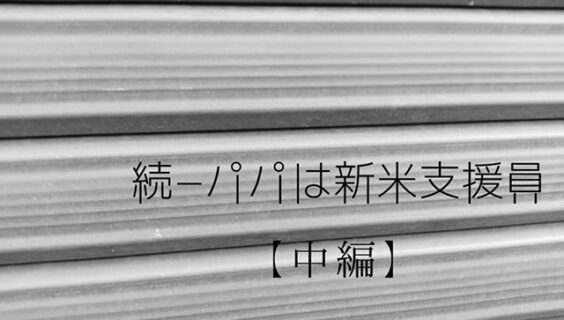
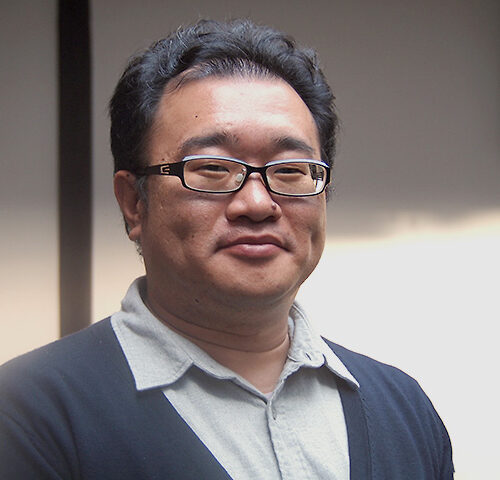






-1.png)




















