土屋ブログ(介護・重度訪問介護・障害福祉サービス)
深夜2時38分
外灯に照らされた窓の外の大きな棕櫚の木の影が、児童相談所の暗いロビーの壁に揺れていた。鋭い葉っぱの影はまるで細い爪のように見えた。
掛け時計の長針は真下を指し、針の先にあしらわれたおどけたピエロの人形は逆さまになって逃げる格好になっていた。盤面に描かれた動物たちがそのピエロの滑稽さを笑っていた。
ピエロは一体何から逃げ惑っているのか。
動物たちが檻から解放され、サーカス小屋がパニックになっている様を表現しているのかもしれない。そのパニックに慌てふためくピエロの姿を虐げられたものである動物たちがここぞとばかりに嘲笑っているのかもしれないと思った。
峰田はクリップボードに挟んだ白紙にペンを走らせつつ、時折おでこに指を当てて何かを考えている風に冬治に視線を向けた。指には薄いピンク色のマニキュアをしていた。ロビーの暗がりでは目立たないが、外灯の光に照らされたときだけ指先の色づきがかろうじて分かった。
ポケットから取り出した布製の細いペンケースにボールペンをしまうと、
「さて、移動するよ、冬治くん。ついてきてもらう」
と、言った。
「どこに?」
「しばらく家を離れて生活するのよ」
荷物など何も用意してないと言うと、全部揃っているから大丈夫だと峰田は言った。
「お迎えが来たみたい」スマホをチラチラ見ていた。
「お母さんにはあなたを育てていくのが今は難しいから、しばらくの間保護します」
そう言って冬治に立つように求めた。ここから車で移動すると告げた。
冬治は力なくうつむいていた。峰田に脇を持たれ、身を預けるように立ち上がるとそのまま児童相談所の裏口へ誘われ、外に止まっていた白いワゴン車に乗り込んだ。
◇
所々塗装が剥げてサビが目立つ古い型のハイエースはけたたましい音を立てていた。エンジンも古いので、音ばかり立てて発車に手間取るあいだ、峰田は運転してきた男性に一言二言言葉を交わし、男性が言った冗談に笑っていた。
車は四方向を山に囲まれた広大な盆地の底を走った。
深夜、街は寝静まり信号の光とオレンジの外灯だけが車の後方に流れていった。冬治の目は灯を消した低い家並の間に徐々に夜空を広げる車の前窓へ、まっすぐ向けられていた。
これからどうなるのだろう。
冬治は何を手がかりにしてこの先のことを予測すればよいのか分からず焦っていた。母と離れるということが自分にとってよいことなのだろうか。もちろん息の詰まる生活を送ってきたのは事実だ。しかし、その生活から離れるということが一体何を意味するのだろうか?自分は何者になってしまうのだろう。
これまでの生活が冬治の血と骨を形成している。それは事実だ。その生活はあまりにも激しく、あまりに過酷ではあったが、冬治をこの世界に規定しているのもまたその生活なのであった。冬治を冬治たらしめるものだった。
分別のついた大人ならば切り離して冷静に見ることもできるかもしれない。
パンがなければケーキを食べればいい、というようにそんなどうしようもない生活ならば捨てればいい、と。
しかし冬治には自分の生活以外の経験が少なすぎた。母との生活がすなわち自分なのである。それが当たり前すぎて逃れようという意識を持つことすらできない。
「怖い」思わず後部座席でつぶやく。
「なんて言ったの?」峰田は振り返って聞き返した。
「・・・」言えない。
このまま家から離れたら自分が空洞になってしまう、と思うが、それをうまく言葉にできない。
もちろん、これまで何もやりたいことができず、嫌な思いばかりさせられてきた。
幸せについて考えようとしても母の存在が目の前を塞いでしまう。
あんなことがしたい、こんなことがしたい・・・他の子どもと同じように「したいこと」が浮かばないわけではない。
想像しても、それが叶うわけがないと諦めるしかないから想像しただけ苦しくなるのだ。
思いつかなければいいのに、と自分を責めさえしてしまう。
母がいなければ自分はどんなに楽だろう、そう考えたことが何度あっただろうか。
呪詛の言葉を心のうちに吐いて、その後悔恨の思いで身を引き裂かれそうになったことも決して少なくはなかった。なんて自分は悪いやつだ、と思った。人に対していなくなればいいと願う最低の人間だ。修羅だ。悪魔だ。
道徳?僕にはない。正義?僕には資格がない。冬治はずっと日陰を、薄暗がりを歩くしかないと思っていた。陽の光の下に出てはいけない人間だと思っていた。
ああ、その全てが自分だ!
もし、家から離れ、母から離れたら自分は空洞になってしまう。何もなくなってしまう。空虚。
うまく言葉にできない。
◇
深夜ラジオが低いボリュームでかかっていた。天気予報が終わると曲が流れた。
曲は日本のヒップホップだった。
冬治はラジオの音声には気を止めていなかったが、ふと歌詞が耳に入りようやく音楽が流れていることに気づいた。
『クソなことばっかりのため息で
曇るフロントガラスの熱はamor
リバーサイド走る俺のmy way
景気づけに太いやつを巻いて』
冬治の乗っているハイエースのフロントガラスは曇っていなかったが、クソなことばっかり起こっている今の状況にピッタリだと思った。
『悲しみの後には幸せを
手を叩くほどの喝采を
汗にまみれてエイエイオー
悲しみの後には幸せを
手を叩くほどの喝采を
汗にまみれてエイエイオー
大嫌いな夜に
大好きな歌を
大嫌いな夜に
大好きな歌を
大嫌いな夜に
大好きな歌を
大嫌いな夜に
大好きな歌を』
ヒップホップなのだがどこか演歌でもあるようなその変わった曲が終わり、ラジオのDJがこの曲は岡山県津山出身のラッパー「紅桜」の『悲しみの後』だと紹介した。
『悲しみの後には幸せを
手を叩くほどの喝采を
汗にまみれてエイエイオー』
曲が終わっても歌詞が冬治の心の中でループしていた。
悲しみの後には、本当に幸せがくるのだろうか?
手を叩くほどの喝采が訪れるのだろうか?
後部座席で揺られながら冬治はひとり考えるのである。
しかし、全然理路整然とは考えられない。
言葉にもならない。
矛盾だらけ。
混乱している。
胸にひとつの感情が噴き出て、すぐにそれを否定するような反対の感情が噴き出る。
その激しい感情のぶつかり合いに翻弄されていると、冬治自身も驚いてしまったが、今まで考えたこともない感情が胸に激しく噴き出る。
母が愛おしい。
母との生活が大事だ。母が大事だ。
そう思い、しかし慌てて否定する。あんだけ苦しめられてきたのに・・・。いなくなればいい。殺してしまいたいと考えたことだって何度もある。そしてまたやっぱり母が大好きなのだと思う。首を振って大好きなわけがないと否定する。母がいたら幸せになれない。僕の幸せを奪う。みんなの幸せを奪う。いなくなれ!死んでしまえ!いや、そんなことじゃない。
じゃあ一体どうしたいんだ?
おまえはどうしたいんだ?自問自答する。
どうしたい?
どうしたい?
母と「一緒に」幸せになりたい。
本当は母と「一緒に」幸せになりたい。
母の病気が治ればいい。母が変わってくれて、朗らかになって、元気になって、いつでも笑っていてほしい。
母に「幸せ」でいてほしい。
それが僕の「幸せ」だ、と冬治は思う。
その日の午前中に出掛けたピクニックで感じたような儚い幸せが、もう少しだけ長く続けばいい。
時よ止まれ!
時よ止まれ!
時よ止まれ!
母と「一緒に」幸せになりたい。
(・・・でも、そんなの絶対に無理だ)
路上にはまったく人影がなかった。
車は市役所の前を通って左折し、消防署の宿直の明かりがほの見えるところで右折して歌詞にあったように河沿いの道に出た。
堤防の上にできた広い道は河の流れよりも随分高いところを走っていた。眼下に流れる河は弱く光を反射させていた。夜空を映しているのだろうか、と思い今度は空を見上げる。
台風が空気中の塵を一掃したおかげか普段ではたえて見られない豪奢な星空だった。異様なほどに大気が澄んでいた。
その星空の下に冬治が住んでいる山上の地区が見えた。盆地の縁、みんながアクロポリスと呼んでいる小高い丘になっている部分の中腹に冬治の家はあるはずだった。
しかし、今は暗くて家を探すことができない。
悲しみの後には、本当に幸せがくるのだろうか?
手を叩くほどの喝采が訪れるのだろうか?
家があるあたりの暗闇を凝視しながら、もう一度冬治は考えた。
―おわり―












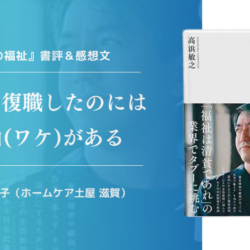






-1.png)




















