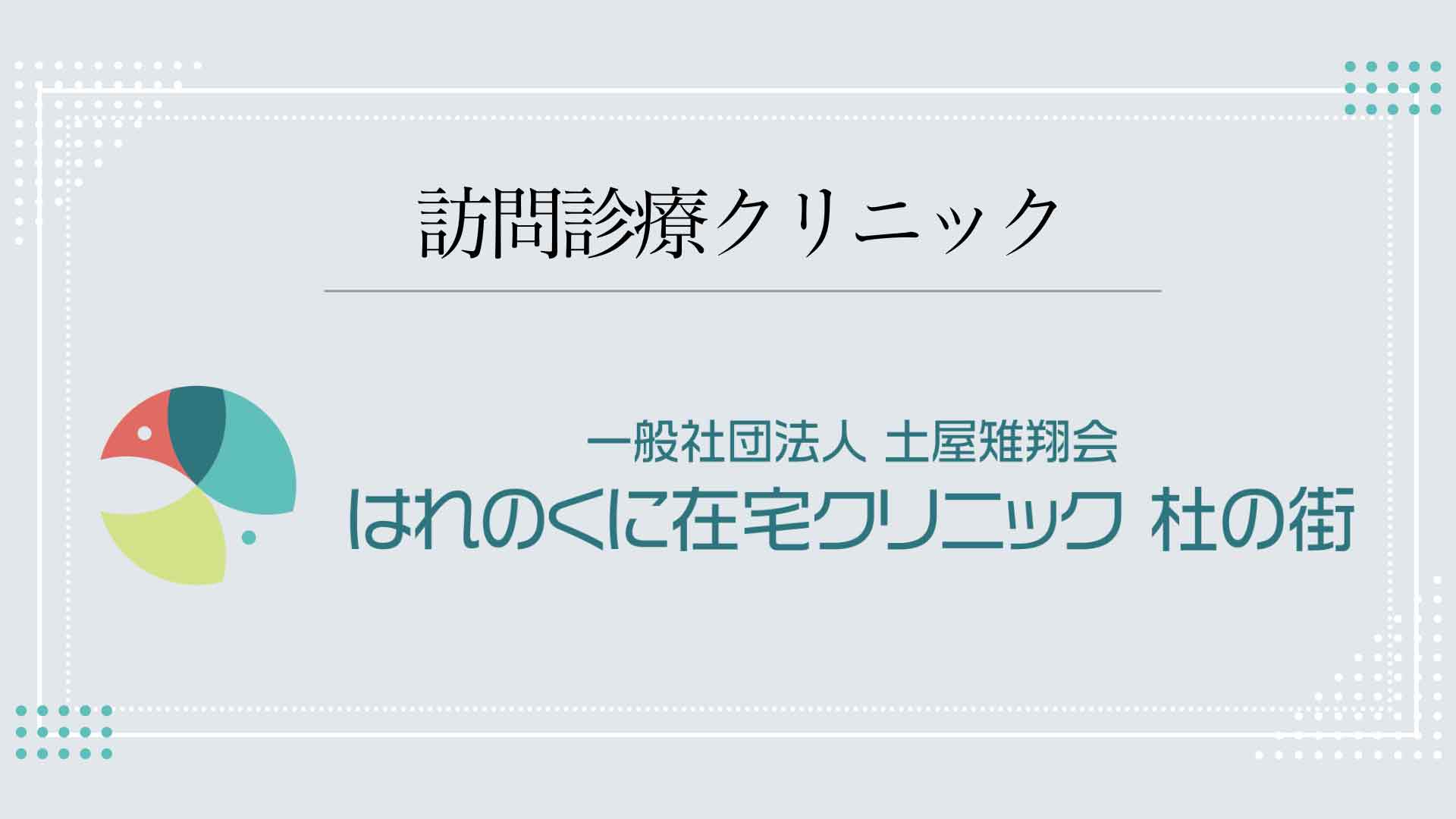土屋ブログ(介護・重度訪問介護・障害福祉サービス)
なんでや、なんでぼくだけが・・・
酷い悪臭を放つ毛布にグルグル巻きにされて連れて来られた場所が入浴室であることは、塩素くさい硬水の蒸気が窓ガラスをビショビショに濡らしていたので、6歳の私にもすぐに分かった。服を脱がされながら、私はもうあの怪力には敵うはずがないと観念して抗うことはしなかったが、やっと声が出せたので精一杯泣き喚いていた。
「マーマー、パーパー!」
と語尾を上げながら懸命に訴えた。
「パ-パ、マーマ、ダモーイ。」(パパ、ママ、おうち、帰っちゃったよ)
と、周囲の皆が代わる代わる、わざと外国人風の片言で答えるだけだった。
入浴・・・。あの施設で私を含め収容児たちに、1週間に1度、ないしは10日間に1度行われていたあの衛生管理作業が果たして「入浴」という心地良い日本語に該当するだろうか・・・。38年間翻訳を生業にしてきた私としては、言葉には正確を期さなければならないと思う。あれは決して「入浴」などではない。あれは正に「洗浄」だった。
おそらく、どの国の、どの同じような施設でも多かれ少なかれ、「入浴」は「洗浄」という一連の機械的な、無慈悲な作業なのだろう。少なくともあの頃は。
あの日、モスクワ郊外にあった障害児施設に放り込まれた私は早速、その「洗浄」という衛生管理作業の洗礼を受けた。
大好きだった余所行き着をすべて剥ぎ取られ、素っ裸にされた私は、バスタブが10基ほど据え付けられただだっ広い浴室に移された。ゴム製の前掛けを着けた大声のおばさんたちが、煙草をくわえながら、まず3方向から、当たると痛いくらいの思いっきり強いシャワーを浴びせてきた。顔だろうが頭だろうが、はたまた腹部だろうが、尻だろうが股間部だろうがお構いなしだった。
ようやくシャワー攻撃がやや弱まったかと思いきや、今度は、シャワー部隊とは別のおばさんたち2人による石鹸擦り付け攻撃が始まった。
ところで、ここを読んで下さっている皆さんは、石鹸と言えば、あの白くて、手の平に収まる程度の大きさで、いい香りのする、そしてある程度濡らして擦れば泡立つものを思い浮かべるだろう。私も、実は、あの日まではそうだった。しかし、私は間違っていたのだ。
プロレタリアートの国で使われていた石鹸とは、色は茶色で、大きさはレンガよりやや大きめ、そして何よりもとてつもなく重く、異常に固く、5、6回擦り付けてようやくヌルっとしてくるものだった。また、身体は、石鹸を付けたタオルやスポンジを使ってではなく、皮膚が真っ赤に荒れるくらい硬い毛が植わったブラシで洗うものだ、ということも合わせて知ったのだ。
身体中に直接石鹸を擦り付けられている間、私は、酔っぱらった父に殴られている時のように、ひたすら身体を縮めて、歯を食いしばって耐えていたのだが、そこにブラシによる垢すりが加わった時には、ついに大声をあげて泣き出すしかなかった。痛かったからだけではない。無性に屈辱的だったのだ。
おばさんたちは、まるで楽しんでいるかのように、私の顔、尻、そして股間を繰り返し、繰り返しブラシでこすりまくり、笑いどおしだった。私が手で股間を隠そうとしても、それはいとも簡単に阻止された。そんなサディスティックな作業の後、シャワー攻撃が再開された。大声で泣き叫んでいる私の口の中に容赦なく水がザバザバと流れ込んできて、「溺れてしまう!」と感じたのを覚えている。もう頭の中はパニックだった。「なんで、ぼくが・・・」、「なんでや、なんでぼくだけが・・・」という言葉しか思い浮かばなかった。
歯がガチガチ鳴りだし、体中がブルブル震え始め、目の前が薄暗くぼやけ始めたころ、シャワー攻撃が止んだ。もうクタクタで力が入らなくなっていた。少しホッとした次の瞬間、私は、以前にも何回か経験したことのあるチクッという一瞬の鋭い痛みと、それに続く、筋肉繊維の間に何か冷えたものが送り込まれていくときの、やや長めの鈍痛を臀部の上の方に感じとった。それは注射だった。
薄目を開けてみると、急に周囲の景色が回り始め、逆様になり暗くなっていった。
その日の明るいうちの記憶はそこまでだった。
赤國幼年記5につづく
◆プロフィール
古本聡(こもとさとし)
1957年生まれ。
脳性麻痺による四肢障害。車いすユーザー。 旧ソ連で約10年間生活。内幼少期5年間を現地の障害児収容施設で過ごす。 早稲田大学商学部卒。 18~24歳の間、障害者運動に加わり、障害者自立生活のサポート役としてボランティア、 介助者の勧誘・コーディネートを行う。大学卒業後、翻訳会社を設立、2019年まで運営。
2016年より介護従事者向け講座、学習会・研修会等の講師、コラム執筆を主に担当。



















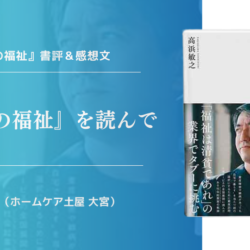

-1.png)