土屋ブログ(介護・重度訪問介護・障害福祉サービス)
「LIVE をすることに決めました!」
まずは宣言してから、慌てて私は楽器を習い出したのだった。
今になって思えば、まったく向こう見ずである。
音楽を人前で演奏した経験がなかったばかりか、そもそも楽器すらもできない。
それなのに、LIVEの日程だけは決まっていた。
もちろん、誰かに命令されて強制されたわけではない。
自分で勝手に申し込んで、自分で勝手に追い詰められているのであった。
時々発作的に訪れる自分を未開の地へ放り投げる行為。
私はそれを「無茶修行」と呼んでいる。
とにかく、迫りくるLIVEに向けて急いで楽器を習わなければならなかった。
選んだのはカホンという南米の打楽器。
コンパクトで持ち運びがしやすく、バス、スネアなど多彩な表現ができるので、ドラムセットに代わってストリートではよく使用される楽器だった。
インターネットでカホンを教えてくれる先生を探し出して月に2回のレッスンが始まった(LIVEまで3ヶ月!)。
子どものころから不器用で、料理も工作も楽器もうまくできなかった。
苦手意識があり、そういうものからずっと逃げてきたようなところがあった。
大人になっても不器用さはあまり変わらず、レッスンが始まって先生がカホンを叩くのを見様見真似でやろうとしても手が全然ついていかず、回を重ねてもなかなか上達しなかった。
8ビート、16ビート、3連符。頭では分かったつもりになっている。
しかし、思うように体を動かすことができない。
それがとても、もどかしい。
カホンを習いはじめて気づいたのだが、私は基本的に教えられたことはその場ではできない。
子どもの頃習わされた(最初は自分から習いたいと言ったはずなのだが)水泳教室でもそうだったことをこの歳になって思い出したのである。
少年の私は「できない、できない」と、ずっと焦りと恥ずかしい気持ちを抱えて、時間が早く過ぎることを祈っていた。
多分緊張が強いのかもしれない。
「うまくやらなきゃ」と、焦ってしまう。
焦れば焦るほどできなくなっていく。
家に帰ってから、ダンボールで自作した音の出ないカホンで練習を繰り返した。
仕事が休みの日には川原や公園で練習したこともある。
それでもなかなか上達はしなかった。
◇
「できない!」
と、私が嘆いていると
「嘆くことないですよ」
と、先生は言ってくれた。
「大丈夫、大丈夫!」
Tシャツに短パン、サンダルをつっかけていつも身軽な格好で先生はレッスンに現れる。
服装だけではなく「まあ、とりあえずやってみましょう!」というノリがあり、私はそのよい意味での「軽さ」にあこがれさえ感じていたのだった。
比べてしまうと、自分のなんと重く硬いことか。
先生のように軽やかに生きられたらどんなに素敵だろう!
先生は仲間から「K」と呼ばれていた。
いくつかのロックバンドから声がかかると飛んでいってドラムを叩く。
その合間にドラムやカホンなど打楽器の個人レッスンをしていた。
フリーで世の中を渡っていくのは至難の技だ。
身軽さだけでなく、同時にバランス感覚と処世していく力強さ、賢さもまた必要である。
ある日のこと、練習が終わってスタジオのロビーで次のレッスンの日程を決めたあと、先生は煙草を吸って、なんとなく他愛もない世間話になった。
雑談が終わると思い出したように撮影したレッスンの動画をLINEで送ってくれた。
何度挑戦してもなかなかできなかったパートの動画だった。
「できないと悔しいでしょ?」
と、先生が微笑みながら言った。
「情けなかったり、悲しかったりしませんか?」
「そうですねー」私は頷いた。
「でも、その悔しさがいいじゃないですか。自分の足りないところを味わうのって捨てたもんじゃないですよ」
「そうですかねー」心弱く笑った。
「自分の足りなさを味わえる人は本当に強い人ですよ」
「どういうことですか?」
私は先生の言葉の意味が飲み込めず、詳しく聞いてみたいと思った。
「つながるかどうか分かりませんが僕の師匠から聞いた話をしましょうか」
そう言って先生は二本目の煙草に火をつけて煙をふかしてから、自分にドラムを教えてくれた現在80歳になるらしい「師匠」という人物の話を始めた。
◇
僕の師匠は世界的に有名なドラマーでした。
今はもうスターウォーズの「ヨーダ」みたいな妖怪レベルの見た目なんですけどね・・・、不思議と叩く音がつやつやしていて色鮮やかなんです。
力を入れてないんだけどパワフルだし、繊細だし、アンニュイだけど輪郭もくっきりしているような、とにかく圧倒的にすごい人なんです。
海外では生きる伝説扱いされてリスペクトされてますよ。国内ではそれほど知られてはいないかもしれません。
その師匠がまだ若かったとき、ある親子にドラムを教えることがあったそうなんです。
お父さんの頼みで、息子、確か敬介くんって呼んでたかな、その子がドラムのコンクールに挑戦しようとしているんだけど、今のままだと全然駄目なので、さらにうまくできるように特訓してほしいという願いだったそうです。
そのお父さんもまた、若い頃はバンドを組み、ミュージシャンを目指していたのですが志半ばで夢破れ、それでもその夢が捨てきれず、それを敬介くんに託して親子二人三脚で頑張ってきました。
二人の夢を力強く語る熱血なお父さんのかげで、敬介くんは静かにたたずんでいました。
時折、不安そうにお父さんの顔を見上げていたそうです。
息子さんの才能を信じながら、それでもうまくいかないときはイライラし、何でできないんだ?と帰りの車の中であたり散らしてしまうことも一度や二度のことではなかったそうです。
その思いに応えようと敬介くんは長時間の練習でも休まず必死で頑張っていました。
師匠は普段あまりレッスンの依頼を受けることはしません。
しかし、そのときは演奏を聞いたあと敬介くんの表情を見て、引き受けることにしたみたいです。
どうして引き受けたのか、最初は周囲のみんなは謎だったそうですが、あとになってその理由は分かりました。
師匠のレッスンによって、敬介くんはどんどん上達しました。
練習の甲斐あってコンクールの準決勝まで進みました。お父さんはたいそう喜んだそうです。
◇
決勝が三日後に控えた日の夜のことでした。
師匠がお父さんだけをスタジオに呼び出しました。
お父さんは会って開口一番お礼を伝えました。
「先生のおかげです。ありがとうございます。このまま気を抜かず、決勝も頑張りたいです。やっぱり敬介はあれでいて本番には強いかもしれませんね。でもまだまだリズムが跳ねるのが不自然でぎこちないんだよなー。もっと楽しくやれって言うんですけどね。駄目駄目です。どうしたらいいですか?」
「今日はね、お父さんに伝えておきたいことがあって来てもらいました」
「何でしょうか?」
師匠はしばらく沈黙しました。
どこからどう伝えようか探しあぐねているように。ふっとお父さんの目を見てから話はじめたそうです。
「お父さん、もし敬介くんに何かが起こってドラムが叩けなくなったとしたらどうしますか?」
「えっ!どういう意味ですか?」
お父さんは師匠の投げかけを最初は了解できず、しばらく唖然としていたそうです。
「ドラムが叩けなくても敬介くんを息子でいさせてくれますか?」
「?!」
お父さんは徐々に苛立ちを感じ始め、信じられないというように視線がきつくなりました。
「当たり前じゃないか!」お父さんはついに怒り出しました。
それでも師匠は話し続けました。
「私はお二人を初めて見たときに感じていました。敬介くんは言葉にはしていませんが、ずっとあなたに向けてこう言ってますよ『僕を見て!』」
淡々とお父さんに伝えたそうです。
「あなたは確かに四六時中敬介くんと一緒にいて、ドラムを叩く姿を見ている。
だけど敬介くんはドラムを叩く自分ではなくその奥にある『本当の僕を見てほしい』『ありのままの僕を分かってほしい』って言ってますよ。
あなたが見ているのは夢に見る理想の敬介くんです。
そうではなく、お父さんの思いに必死で応えようとしながら不安でいっぱいになっている、そこにいる敬介くんそのものの姿を見てあげてほしいんです」
「・・・」
「敬介くんは確かにうまい。才能があると思います。それはこれまでのお父さんの訓練の賜物だと思います。苦労も多かったと思います。本当にお二人の努力はすごいです。それは演奏を聞いて分かりました」
師匠がレッスンを引き受けたのは演奏のうまさが基本にはありました。
しかし、それだけではなく演奏を聞いて敬介くんの不安に揺れる気持ちがよく分かったからなんだそうです。
敬介くんの目を見ていたらそれをお父さんに伝える役割を頼まれた気がしたそうで、引き受けざるを得ませんでした。
「お父さん、大切なことを話しますから聞いてください。
敬介くんのドラムは確かにうまいですが、この先さらにうまい人はたくさんいるでしょう。その中でさらに抜きに出ないといけません。
もしかしたらこの先、敬介くんはどこかで挫折するかもしれない。心が折れるときがくるかもしれない。
『できない』ということにぶち当たるときがきっとくるでしょう。
そのときに、自分はドラムがなくても大丈夫、何もできなくても大丈夫、また立ち上がって自分の道を歩もうとする、自分を信じられる力を今のうちに育んであげてほしいんです」
「自分を信じられる力?」
「そうですよ。自分を認めてくれる人がいる。困ったときに手を差し伸べてくれる人がいる。ありのままの自分を見てくれる人がいる。
その積み重ねが人を信じることにつながり、やがてそれは自分を信じる力に変わるんですよ。
それを教えることができるのはお父さん、あなただと思います」
お父さんの心は揺れてました。
「敬介くんはいつも不安に思ってますよ。もしドラムができなくなったら、自分の存在価値はなくなるのではないかって。
お父さんの子どもでいさせてもらえなくなるんじゃないかって。
今度のコンクールで優勝することを心からお祈りしてます。
だけど、もし優勝することができなくても敬介くんを認めてあげてください。ありのままの敬介くんを受け止めてあげてください」
師匠は優しく微笑みました。
お父さんは力弱く頷き、かすれる声でそうだったのかと何度も反芻するように言いました。
そしてそのうちにわっと泣き崩れたそうです。
「決勝の前にこれだけは伝えておきたかったのです。お父さんや敬介くんの頑張りを幸せにつなげてほしいからです」
師匠はお父さんの肩をさすって慰めました。
◇
どうですか?
これが僕の師匠から聞いた話です。
もうだいぶ昔の話なんだそうですよ。
「ね、強引にまとめると楽しく叩けばいいんです!」
先生は朗らかに笑って言った。
「それが一番!」
私もつられて笑ってしまった。
「それから敬介くんとお父さんはどうなったんですか?」
「結局、ドラムコンクールで優勝はできなかったそうです。優勝はできませんでしたが、二人は幸せになりましたよ。敬はやがてプロになりました」
煙草の煙を吐き出して、目を細めた。
「さて、喋ったらビール飲みたくなったなー」
先生は唐突に言った。
「飲みに行きませんか?」
「えっ!いいんですか?」ちょっと驚きつつ私は頷いた。
「もちろん!いいお店知ってるんですよー!」
こんな風に軽く生きてみたいものだと改めて感じながら我々はスタジオの外に出た。
外は爽やかな初夏の空が広がっていて、確かにビールを飲むにはもってこいの一日だった。
おわり













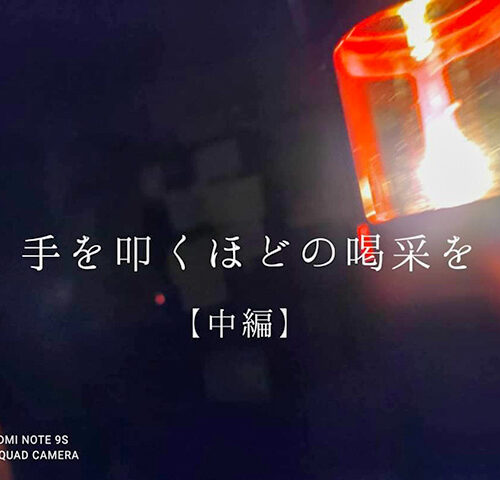





-1.png)




















