土屋ブログ(介護・重度訪問介護・障害福祉サービス)
ヒーローか赤土の盛墓か
特に人間としての扱いに大いに問題があったと、今でも思われるのは2階の子供たちだった。憐れとしか言い表しようがない。私たち3階の住人たちは2階の子たちと敢えて交流を持とうとはしなかったのだが、その一番大きな理由は、2階の子たちが「死」に最も近い存在だったからである。子供であっても死は恐ろしいものであり、悲しいものだ。
2階の子とせっかく友達になって仲良く過ごしていても、ある日突然、全く何の前触れもなくその子は消え失せてしまう。そして同時に、施設敷地内にあった墓地に新しい盛土を発見してしまうのだ。あれほどのショックと恐怖、あれほどの深い悲しみはない。今でもそう思う。自分もいつああなるのか、と心底私はそう怯えていた。
2階の子供たちは親のいない子たちだったのだ。もっと正確に言うと、親が自分から見捨てた子たち、ないしはこの世に生を受けた直後に医者の権限により親から引き離され、出生届も出されぬまま、人里離れた場所に設けられていた孤児収容所に送致された子たちだった。
そうなった理由は、その子たちに目に見える障害があったこと、そして、ただでさえも労働力が不足していたあの国において、そういう子供を親元に置いておくと親が普通よりも重い育児に力を削がれ、労働力としてフルに活動できなくなることを防ぐことにあった。それは国策だった。
日本人の一部、特に私よりも10~15歳ほど上の世代の中には、障害児を新生児の段階から親から取り上げて収容所送致してしまう、あのソ連の政策について、大事な国民を障害児の成育という大変な苦行から解放し、自由で明るい市民生活を保障するための最善の方法だったと、何の疑いもなく褒め称える人たちが今でもいる。いわゆる戦中派、と呼ばれる世代に多い。
そういう人の話を聞いたりすると、私は言い知れようもなく強い憤りを感じる。そして、現実を知らない、事実を見ようとしないことが如何に愚かなことか、と私は思ってしまう。戦後の左翼化風潮にミーハー的に乗っかって、マルクシズム・レニニズムの何たるかも碌に勉強もせず、いやその前に、先代から受け継いだ己の封建主義・人間性無視の思想に凝り固まった脳を洗い直すという基本的なことすらもせず、頭のてっぺんだけ赤く染まった連中。
そういう連中に限って、社会人になってから様々な差別的行動や言動を世の中に広げてきたのだ。悲しいことに、私自身の親もそういう部類に入る。
2階の子供たちには正式な氏名がなかった。男子ならサーシャ、ワーシャ、ワーニャ、女子ならレーナ、ガーリャ、マリーナといった、施設の職員が適当に付けた極ありきたりの愛称で呼ばれていた。それは当然のことだった。あの子たちは、出生届が出されていないのだから。氏名どころか、出生地も生年月日も分からなくなっていたのだ。
あの子たちの存在を証明した唯一の公的文書と言えば、生まれた直後に産院の医師が発行した、「〇歳の年齢を迎えるまで生きることはない」と記された診断書だった。
2階の子たちの6割くらいは、その「実験動物」としての短い一生をあの施設で終え、一部が、「治療の価値なし」と判断され、何処か他の施設に移されていき、そしてごく少数が施設の年齢制限の18歳を迎えた後、劣悪な環境の一般市民向け老人ホームに送られるのであった。ソ連時代から今に至るまで、ロシアでは、貧困層向け高齢者収容施設は重度成人障害者収容施設を兼ねているのが通常なのだ。
そんな人生から抜け出すには、非常に強い運に恵まれた上に、様々な苦しみ、痛み、屈辱に耐え抜き、ソ連医学界発展の証となる必要があった。ヒーローだ。ヒーローになるほか生き延びる方法はなかったのだ。
けれども、大概の子供は強運の持ち主でもヒーローでも、はたまた偉人でも鉄人でもなかった。だから、その命は簡単に力尽きた。コロコロ死んでいった。そして死んでしまうと、施設内墓地の盛土の一つになった。墓標も何もないただの赤土の盛土に。なぜならば、彼らの氏名も生年月日ももう分らなくなっていたからだ。
>赤國幼年記13につづく
◆プロフィール
古本 聡(こもと さとし)
1957年生まれ。
脳性麻痺による四肢障害。車いすユーザー。 旧ソ連で約10年間生活。内幼少期5年間を現地の障害児収容施設で過ごす。
早稲田大学商学部卒。
18~24歳の間、障害者運動に加わり、障害者自立生活のサポート役としてボランティア、 介助者の勧誘・コーディネートを行う。大学卒業後、翻訳会社を設立、2019年まで運営。
2016年より介護従事者向け講座、学習会・研修会等の講師、コラム執筆を主に担当。














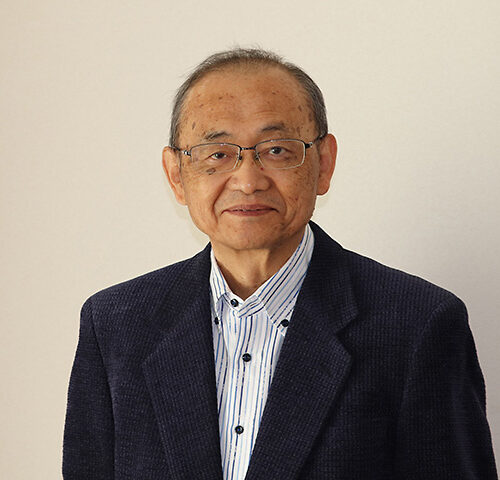


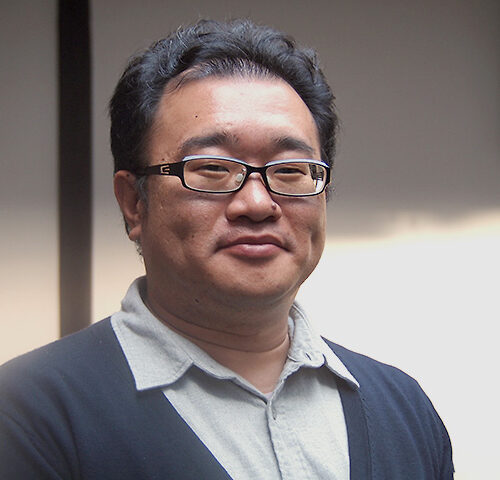


-1.png)




















