土屋ブログ(介護・重度訪問介護・障害福祉サービス)
12 私が出会った障害者運動の先駆者たち② 『新田勲さん その2』
国の新しい施策や方針は社会保障審議会障害者部会というところで議論される。新田さんはその部会の議事録なども欠かさず目を通した。その中で新田さんが気に留めたことから問題意識が喚起され、議論をすることが多かった。
正直に告白しよう。私も新田さんに倣って審議会の議事録に目を通したが、専門用語が多すぎてほとんど理解できなかった。大学に合計8年間も通い、法律と哲学を学び、それなりに文字言語に触れることには慣れているはずの私がほとんど理解できない文章を、公教育をほとんど受けることのなかった新田さんが読解し、批判的に考察する姿を見て、例のごとく驚きを感じた。
ある日、新田さんに聞いてみた。どうやって言葉を学んだのかと。新田さんは足文字でこう答えた。
「じ しょ よ ん だ の」
え、と思った。
しかも、新田さんがことばを覚えるための主目的は、なんとラブレターを書くためだったのだ。公的介護保障運動を展開するための武器である新田さんの言葉の由来は、恋の成就にあったのだ。
「け っ きょ く これ で しょ」
爆笑しながら新田さんが小指を立てて足文字で語った
エロスに由来することばの強度が公教育で上からべたべた張り付けられた言語と同じなわけがない。新田さんにとって言葉は生きるため、生を成就するためにあり、受験競争を勝ち抜くためでも、資格取得試験に合格するためでも、観念的な言葉の遊びに戯れるためでもなかった。言葉の根源に触れるような感覚に包まれた。
新田さん宅にいくと必ずと言っていいほど夕食をご馳走になった。新田さんは自身で料理された。足文字で介助者に細かく指示を出しながら調理された。いくらでも食べていいよという感じでしきりにお替りを勧められた。いかにも昭和の親分という感じだった。
新田スペシャルというメニューがあった。詳しくは知らないが、魚を醤油にどぶどぶにつけてその中に大量のニンニクを入れて煮たのだと思う。新田家でしか食べられない味だった。それを食べるとやたらと元気になった。帰りの電車のなかで、周囲にいる人たちが離れていった。
毎日のように新田スペシャルを食べていた新田さんは、異様なまでに元気だった。60半ばに差し掛かろうとしている初老の男性と一緒にいるという感じが全くしなかった。
歴史を作る人物はやはり違うな、常軌を逸しているな、心からそう思った。その生きるエネルギーの塊のような新田勲という人物が巻き起こす嵐に、私をはじめ多くの人たちが巻き込まれていった。
体調を壊して1か月で体重が10キロ近く減ったことがある。介護の仕事をしながら障害者運動にも参加し、ガンを発病して療養に専念する父とアルバイトをする母の生活をサポートするために清掃や塾講師などの副業もこなす日々を送っていたが、無理がたたってしまった。そんな私をみて、会議が終わったあと新田さんに呼ばれた。
「た か は ま く ん や せ た ね ど う し た の?」
「すみません、ちょっと体調壊してしまいました。」
そう答えると、
「め し だ った ら い く ら で も く わ せ る か ら う ち に ま い に ち で も あ そ び に き て よ お た が い さ ま で しょ」
足文字を書き終えた新田さんの顔を見ると、涙が溢れていた。
「ありがとうございます。」
そう答えながら、心身とも限界にきてしまっていた私はその場で跪きそうだった。涙が溢れるのを抑えるのに必死だった。
重度全身性障害者として社会からやってくる差別や偏見や抑圧と闘い続けた人が、30台半ばで体調を壊して体重を減らした神経症的な青年の姿をみてコンパッションを抱いて涙するという情景に当事者ながら不思議な感覚を覚えた。
新田さんは事業所という存在に常に懐疑的だった。スウェーデンやカナダのパーソナルアシスタンス制度に賛同し、障害者と介護者はあくまで1対1の関係であるべきであり、第三項的存在である事業所があることにより、双方ともお互いの命や生活に対して無責任になる、そう考えた。
また、介護者の生活保障に対しても強いこだわりと取り組みをしてきた新田さんにとっては、事業所という存在があることによりリソースが横に流れて介護者の所得保障にマイナスインパクトしかない、そう考えた。
私はそうは思わなかった。誰しもが新田さんのように自分で介護者を見つけ、育て、関係を持続できるわけではない。障害当事者全員がパーソナルアシスタンス、日本でいうところの自薦ヘルパー制度に馴染めるわけでも使いこなせるわけでもない。誰しもが必要なケアを受けられるようになるためには、公平平等の観点からも事業所の存在は必須だ。そう思った。
このテーマについて、つまり事業所の存在価値の是か非かについて、厚労省との交渉の帰り道に有楽町の飲み屋に行って夕方からお酒を飲みながら新田さんと議論になったことがある。結局議論は折り合わず、新田さんもいささかご機嫌斜めになって有楽町駅で別れた。そのあと新田さんは大好きな秋原場でショッピングをして鬱憤晴らしをしたかもしれない。
新田さんはもはやこの世の人ではない。新田さんの死に際して、私はしばらく離れていた障害福祉の世界に回帰し、土屋訪問という事業所を仲間と共に立ち上げてその全国展開の一端を担わせていただいた。
わが師、新田勲の意に反して、事業所をどんどんと立ち上げ、いまや株式会社土屋という新田さんたちが作った重度訪問介護というサービスを全国で展開する業界最王手の一つの代表取締役をさせていただいている。
反ビジネス、反事業所、の新田さんにあの世からこっぴどく叱責を受けそうだ。足文字で叫ばれるかもしれない。しかし、もしそうだとしたら、新田さんにこう伝えたい。
「新田さんが命がけで創り守った重度訪問介護と命を見守る時間を、全身全霊で守り、広げ、誰もが共に生きられる社会の創造に寄与し、新田さんが貫いてきた社会的弱者の命の保障をしっかりと継承させていただきます。
その目的のために、最も有効な手段を選択していきます。新田さんが私たちに伝えてくれたメンセージの本質を裏切ることは絶対にありません。
それが私がやせ細って頽れそうなときに全身で共感を表現してくれながら、飯ならいくらでも食わせるから毎日うちに来い!といってくれた新田さんへの感謝の私なりの表現です。」と。
新田勲という稀代の人物との出会いは私の運命を変えた。
新田さんが恋文を書くために言葉を学んだように、私たちは新田さんのメンセージの本質を実現するために新しい言葉を紡いでいきたい。
◆プロフィール
高浜敏之(たかはまとしゆき)
株式会社土屋 代表取締役 兼CEO最高経営責任者
慶応義塾大学文学部哲学科卒 美学美術史学専攻。
大学卒業後、介護福祉社会運動の世界へ。自立障害者の介助者、障害者運動、ホームレス支援活動を経て、介護系ベンチャー企業の立ち上げに参加。デイサービスの管理者、事業統括、新規事業の企画立案、エリア開発などを経験。
2020年8月に株式会社土屋を起業。代表取締役CEOに就任。趣味はボクシング、文学、アート、海辺を散策。















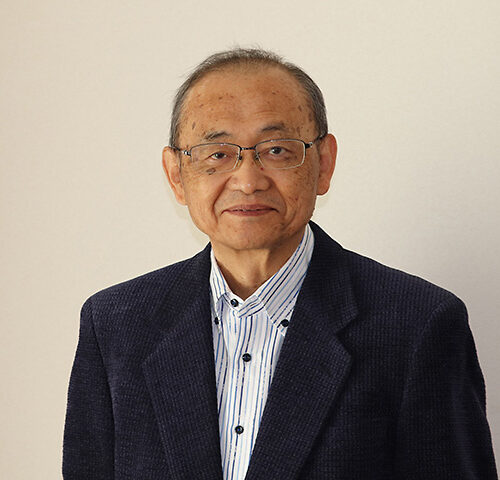





-1.png)




















