土屋ブログ(介護・重度訪問介護・障害福祉サービス)
アーニャについて(つづき)
アーニャたち家族が当時のソ連に残留したのは、同民族の先達者たちとはやや違った理由からだった。
1905年に終結した日露戦争の結果、樺太の南半分が日本に割譲された。そんな樺太にアーニャのお父さんが渡ったのは太平洋戦争が始まる5年程前で、その後間もなく、やはり本土から来たお母さんと結婚したとのことだった。それ以前の経緯としては、その数年前にお父さんはまず、当時日本統治下にあった朝鮮から大阪の大学に入り、土木建築を学んだ。そして卒業後、日本企業の鉱山土木技師として樺太に派遣されたとのこと。
今考えると、日本の大学に入れて、しかも、強制的に樺太に連れていかれ使い捨ての労働力として働かされた他の大勢の朝鮮半島出身者とは、彼女のお父さんは、家柄や元々の社会的地位が違っていて、所謂「良家の出」だったのかもしれない。
そして、この朝鮮半島出身家族の生活は、終戦の年の夏までは比較的平穏だったようだ。アーニャは彼女のご両親が、まだ彼女がこの世に生を受けていなかった頃の樺太での暮らしぶりを、時々懐かしそうに語っていたことを私に話してくれた。
朝鮮出身家族のそんな暮らしが激変したのは1945年8月11日。ソ連軍が突如として、樺太を南北に分けていた北緯50度の境界線を越えて南部になだれ込んできた日だ。多くの日本人、朝鮮半島出身者が、北海道に渡ろうと、樺太島の南端を目指して逃げたことだろう。しかし、様々な歴史資料を読むと、ソ連軍の勢いはもの凄かったらしい。
そしてあの島で戦闘が止んだのは同年の8月23日、終戦は、翌月9月2日となった。
あの南北に細長い島に当時、最盛期には40万人以上の日本人と朝鮮半島出身者が住んでいた。1945年8月15日前後から日本人住民の本土への引き揚げが始まってはいたが、ソ連軍が島南端に来るまでに北海道へ逃れられたのは約11万人。残された約29万人の日本人の大部分も、翌21年の「米ソ引き揚げ協定」によって順次、帰国が叶った、と歴史資料には記されている。
しかし、朝鮮半島出身者は別だった。1945年8月25日までに、日本人と共に本土に逃れられたのは、2万~4万人(ネットのデータには大きなばらつきがある)いた内の数千人だとも言われている。こうして彼らは後に「在樺コリアン」と呼ばれるようになったのだ。そして、アーニャの一家もソ連軍の命令で樺太に留め置かれることになった。
アーニャは私に優しく接してくれた。日本人的あるいはアジア人的な丁寧さと細やかさをもって、と言った方が良いだろう。常に怒鳴り散らし乱暴に、粗野に仕事をしていた他のロシア人スタッフとはその点、まるっきり違っていた。上記のような自分の家族の歴史についても、当時のモスクワでの学生としての自分の生活についても、何もかも話してくれた。
声の調子も穏やかで静か。その様子はまるで、自分たちのことを。当時たった8歳だった私に言い含めて記憶に残そうとしているかのようだった。もちろん、私がこのような感想を持つに至ったのは、年齢的に大分後になってからになるのだが。
アーニャ一家は終戦後2年間、樺太で他の在樺コリアン、在樺邦人、そして終戦間もなく入植してきたロシア系住民と混合コミュニティで暮らしていたが、1947年の春、ちょうどアーニャがお母さんのお腹にいた時に、突然、日本人と関りを持っていた在樺コリアンたちに強制移住命令が出され、その2日後にはウズベキスタンへの7000キロに及ぶ、一家の長く辛い旅路が始まったそうだ。貨物列車に揺られながら。
そんなアーニャからも、怒りというよりも静かな、内に押し殺した憤りが伝わってくることがあった。それは主に、私が学校の宿題を、何とかして小ズルくサボろうとしたときと、アーニャ一家が「親父さん」と呼んで慕っていた会社の日本人上司が、彼らに何も告げることなく樺太から去り、結果的に置き去りにされた、という話を聞かせてくれたときだった。
そして、3か月の研修期間が終わると、アーニャは突然来なくなり、それ以来二度と会うことはなかった。
時代がいきなり飛ぶが、2004年の夏に私は車でサハリンを訪れて1週間ほど逗留したことがある。今では稚内からサハリンのコルサコフ港(旧大泊)まで5時間。その近さには驚かされたが、海峡のおよそ真ん中あたりで携帯電話の電波がプツッと途切れた時には、国境という国と国との間に立ちはだかる大きく動かしようのない隔壁を感じざるを得なかった。
サハリンに上陸した後、宿を2、3回替えながらひたすら北を目指して走った。2軒目の宿で、そこは普通のアパートだったのだが、住人のおばあさんが終戦間もない頃の状況を色々話してくれた。
日本人に対しては大いに好意を持ってくれていたようで、一緒の小学校で机を並べたという「のりこ」という人について懐かしそうに、時折涙を浮かべながら、一緒に遊んだことやお互いの家を行き来したこと、そして最後の引き揚げ船に乗った「のりこ」を見送った話などが次々と飛び出してきた。
さらに北上を続けると、実に不思議な光景に出くわした。
そこは海岸から30メートルくらいのところに道路が通っていて、左側は見渡す限り草が生い茂り、樹木は、低木さえ一本も生えていなかった。そこここに錆に覆われて、指でつついただけでもハラハラと崩れ落ちるかと思われるような、旧日本軍の大砲やら戦車が打ち捨てられていた。また右側は、ごつごつとした岩が砂から顔を出している浜辺だったのだが、その向こう側に見えたものがこれまた異様であった。
そこは入り江になっていて、入り江の真ん中あたりで大きな船が船首を海底に突っ込んだ形で、10階建てのビルの高さほどの船尾を空に向かって突き出していた。同行していたガイドに「あれは何だ」と尋ねると、「あんたの同胞たちが終戦時にこの島を脱出しようとして海軍に魚雷で沈められたんだよ」という答えが返ってきた。
目を凝らして見てみると、船体には白い塗料と赤い塗料の痕跡がまだ所々に残っていた。不思議だと思ったのはその船の黄銅色のスクリューだった。少しも錆びていないのだ。少しも、だ。
その日は、空には黒い重みを感じさせる雨雲が厚く低く垂れ込み、今にも激しい雷雨が襲ってきそうだったのだが、私はその場所で車を止めてしばらくその船を眺めていた。すると、その分厚い雨雲が突然裂けて一筋の太陽光が差し込んだ。その光が船のスクリューに当たり、まるで灯台のように周囲を明るく照らし始め、私の顔にも当たった。
60年近くも錆びずに光るスクリュー。私は霊的なものは信じない方なのだが、あの時はそういうものを感じ、大勢の誰かに語りかけられたかのような気がした。それと同時に、あのモスクワの障害児収容施設で会ったアーニャのお父さん・お母さんたちも、当時この景色を見たのかもしれないと思った。
私はしばらくその場で首(こうべ)を垂れて黙祷をささげた。
◆プロフィール
古本 聡(こもと さとし)
1957年生まれ
脳性麻痺による四肢障害。車いすユーザー。 旧ソ連で約10年間生活。内幼少期5年間を現地の障害児収容施設で過ごす。
早稲田大学商学部卒。
18~24歳の間、障害者運動に加わり、障害者自立生活のサポート役としてボランティア、 介助者の勧誘・コーディネートを行う。大学卒業後、翻訳会社を設立、2019年まで運営。
2016年より介護従事者向け講座、学習会・研修会等の講師、コラム執筆を主に担当。














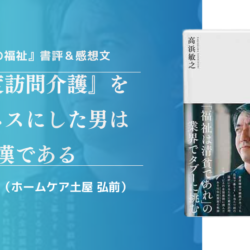


-1.png)















