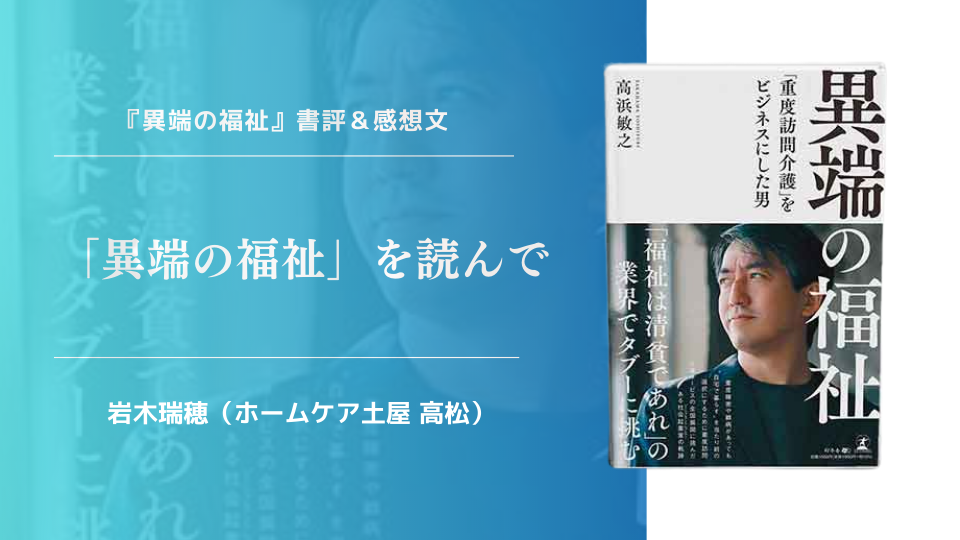
「異端の福祉」を読んで / 岩木瑞穂(ホームケア土屋 高松)
コンビニでコーヒーの順番を待つ間、手に取った求人雑誌の中から目に留まったのが「土屋」だった。重度訪問介護に興味が湧いたし、22時スタートなら本業に差し支えないし、ギャラも魅力に思えた。
しかし50歳手前で応募するには勇気がいった。新しいことを覚えられるだろうか、体力は持つだろうか。2週間程悩み、恐る恐る担当者に電話したのが1年前だ。そこからの展開は早く、採用が決まったかと思うと、あっという間に研修スケジュールが組まれた。
この最初の研修で古本聡氏と安積遊歩氏に驚いた。驚いたのは存在感だ。講師として障害を持つ者の不遇な歴史を語る二人は、ピンと張った糸を弾くように、「痛み」を魂に訴えた。こんな人たちがメンバーにいる土屋ってどんな会社だ、高浜代表って何者なんだ。その答えが本書にあった。
高浜が福祉業界に身を置いたのは30歳の時だ。かつてプロボクサーを目指し、大学で哲学を学んだ高浜が「実利ではなく、意味を実感できるような仕事」として選んだのが障害者訪問介護だった。この時、障害者が社会から置き去りにされている現状を目の当たりにし、翌年には重度障害者が地域で普通に暮らせるように活動を始めた。
元々がボクサー志願で哲学科卒の若者だ。凄まじい集中力と勤勉さを発揮させ、「人間とは何なのか」という問いかけをしながら活動に邁進したことは想像に難くない。20年後には日本全国に重度訪問介護事業所を設立する大企業の経営者となった。本書を読み進めていると、意外なことに、自分との共通点がいくつか見つかった。
私は香川県で生まれ、18歳で芸術家に憧れて東京の大学へ進学した。大学付属の寮には海外からの留学生や全盲や脳性麻痺の人が自然に共同生活を営んでいた。自治寮だったので管理人ではなく、学生たちが選挙で寮長と役員を選び、お互いが平和に暮らせるよう話し合って決めていた。
寮生の中にはストリッパーや漫画家、占い師等個性豊かな人たちがいて、田舎から出てきたばかりの自分は、一つしか色がない世界から極彩色の世界へ迷い込んだようなショックを受けた。小劇場に入り芝居に夢中になって過ごし、気付いたら大学4年になっていたが、周囲を見渡しても就職活動をしている者はおらず(私の学科で就職したのは2人だけだった)、何となくみんな卒業していった。
大人になり切れないまま社会に出て、派遣で小銭を稼いでは物価の安い東南アジアを周遊して、このままではまずいかなぁと焦りだしたのが28歳。香川に戻り、やることもないので海辺にレストラン&バーを開き、それなりに楽しんだ後4年で廃業した。そして私は自分を見失った。
やりたいことが何もないのである。いつしか朝から酒を飲み、寝ては飲む生活になった。もうとっくに30歳を超えていて、派遣の仕事でさえ採用されなくなっていた。ある人の勧めで断酒会に繋がり、頭の整理ができてきた頃、認知症対応型グループホームで介護の職を得た。
これが自分の天職だった。もっと深く学びたいと、働きながら通信教育で社会福祉士と精神保健福祉士の受験資格を取得し、40歳の時ダブル受験で合格した。ようやく人生が始まったという実感があった。そこから10年、精神科病院でソーシャルワーカーとして働かさせてもらっている。
障害者を取り巻く環境は変わっただろうか。病院には退院したくてもできない人たちがいる。職がなく、保証人になってくれる身寄りのない者にとって、アパート一つ借りるのも至難の業だ。苦労して住む所を決め退院できても、再入院することは珍しくない。
誰かが言っていた。「治療して病気が良くなっても、戻る社会は変わらない」と。ここに土屋の存在意義がある。ともにいる。それだけで救われる人がどれ程いるだろう。学生の頃、寮に帰れば誰かがいた。暗い夜道、遠くに寮の灯りが見えて、ホッとしたのを思い出す。
毎週土曜日の深夜に私は支援に入っている。クライアントと二人でいる空間はまるで即興劇のようだ。その日の天気や温度、空気の匂い、クライアントと私のコンデション等々で構成される舞台で、私はどうすればクライアントが心地よく過ごせるかを考える。
目を見て、呼吸する音を聞きながら。土屋で働く人が増えるということは、こんな創造的な仕事をする人が増えるということだ。社会を変える小さな力になるだろう。












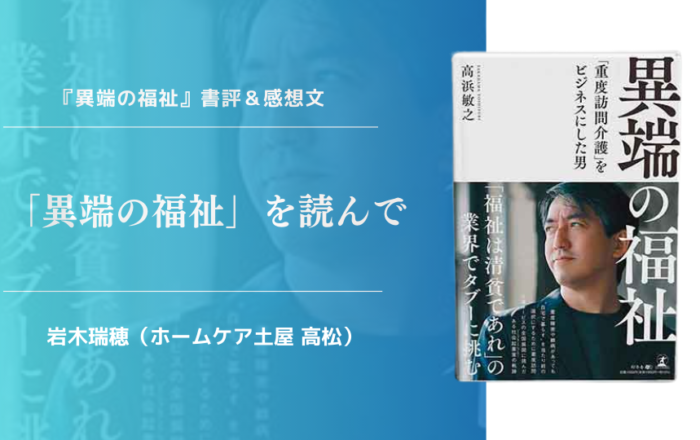







-1.png)




















