土屋ブログ(介護・重度訪問介護・障害福祉サービス)
捨てられたんや・・・
どれくらいの間、そんな状態が続いたのか、もう分らなくなっていた。どんなに声を上げようとも、どんなに暴れて音を立てようとも、そしてどんなに時間が経とうとも、その夜、私のベッドに誰かが近づいてくる気配は一切なかった。
ところで、あの夜、泣き喚き、暴れている間、私の頭の中では、その朝からのことが何回も何回も、エンドレスビデオ映像のように繰り返し流れていたのだが、その映像の所々に現れる一コマがあった。それは、私が施設内に運び込まれる際にチラッと見た、玄関ドアの真横に植えられていたナナカマドの細い木にたわわに成った、真っ赤な実だった。
その色は、建物の暗灰色、木肌の真っ黒な色、そして枝の上に凍り付いた真っ白な雪とで、余りにも鮮烈なコントラストを織り成していた。それが私の目と記憶に焼き付けられたのだろう。
ナナカマドの実は、初冬の寒気に晒されるたびに、その赤い色は鮮やかさを増していき、それと同時に味も甘さを凝縮させていく。次の冬が到来する頃には、まさか自分が、その実が真っ赤に熟していくのをワクワクしながら心待ちにするようになるとは、あの時は予想だにしていなかった。
時系列が今ではもう判然としないが、その夜、強烈な尿意に襲われたのを憶えている。考えてみれば、トイレには、その日の朝に行ったきりだった。しかしながら、自分が何処にいるのかさえ分かっていなかったのだから、トイレの在りかなど知りようもなかった。にもかかわらず、私は、「ぜったい、トイレ行かなあかん!」、という必死の思いで、何とかしてベッドから降りる方法を考えたのだ。
ベッドの高さは、横柵の分を入れると優に1メートルを超えていた。一方私は、当時身長があまりなく、なんと100センチメートルもないくらいだった。高さが凄く怖かった。そこで思いついた、「そや、落ちたらええんや。柵から手を離さんかったら・・・」と。そして、落ちた。どうやって落ちたかはもう忘れてしまったが、私の背中が、ゴンッと鈍い音を立てて固い床に当たった時の衝撃と痛みは、何となく憶えている。
また、落ちた時のショックでオシッコを漏らしてしまったこと、それが、焦れば焦るほど止まらなかったこと、そして、昼間、入浴後に着せられたみすぼらしくやけに薄い生地のパジャマのズボンを脱いで、その痕跡を残すまいと、ベソをかきながら懸命に拭きとったことは、はっきりと記憶に残っている。
その後も大声で長い間泣き続けた。そうするしかなかったのだ。
やがて、自分が疲れ果てていくのが分かった。徐々に声の大きさは下がっていき、暴れる気力も失せて行った。「捨てられたんや・・・。」、と不意に思った。父はよく、施設に放り込んでやるだの、捨ててやるだの、機嫌が悪い時や酒に酔った時などに普段から私に言っていたのだ。「とうとう、そうなったんか・・・」。自然にそう思えた。疲れてしまうにはもう一つ理由があった。
泣き叫んでいる時の激しい嗚咽で大量に吐いてしまったのだ。殆どが胃液だけの吐しゃ物は床の上に飛び散っていて、強い酸臭が漂い、口の中が苦く、喉の奥がヒリヒリしていた。諦めの気持ちが強くなってきても涙だけは止まらなかった。そしてひどく頭が痛みだし、眩暈も感じ始めた私は、そのまま冷たい床に突っ伏して目を閉じた。意地でも眠る気はなかった。が、身体中の力がどんどん抜けて行った・・・。
>赤國幼年記7につづく
◆プロフィール
古本聡(こもとさとし)
1957年生まれ。
脳性麻痺による四肢障害。車いすユーザー。 旧ソ連で約10年間生活。内幼少期5年間を現地の障害児収容施設で過ごす。
早稲田大学商学部卒。
18~24歳の間、障害者運動に加わり、障害者自立生活のサポート役としてボランティア、 介助者の勧誘・コーディネートを行う。大学卒業後、翻訳会社を設立、2019年まで運営。
2016年より介護従事者向け講座、学習会・研修会等の講師、コラム執筆を主に担当。
















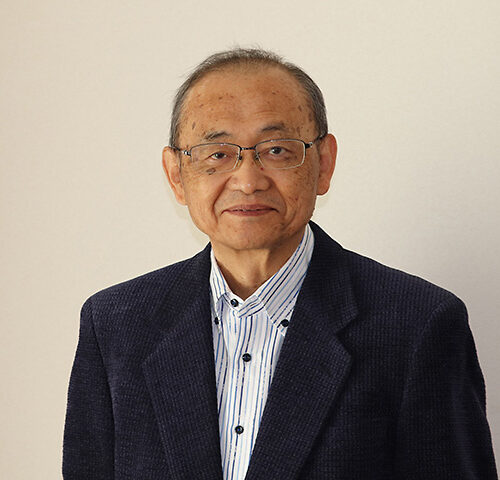


-1.png)




















